 2004年10月発行
2004年10月発行江戸詰めのまま、藩から召し放しとなった夫を探し、陸奥国からはるばる江戸までやって来た、妻のなみと総八郎が帰藩を願いながら、裏店の人々の情に振れ逞しく生きる下町人情物語。
「桜花を見た」に収録されている「夷酋列像」に繋がる松前藩物である。
憂き世店
文化4年、陸奥国伊達郡梁川へと移封になった蝦夷松前藩。石高を減らされた事から、家臣を召し放しとした。江戸詰めの相田総八郎もそのひとりであった。
国許で相田家から追い出され、実家では嫂にいじめられ、宛もなく総八郎を捜しに江戸に出た妻のなみは、運良く総八郎と巡り会い、慣れない長屋暮らしに入るのだった。
女三界に家はなしの例え通りに、居場所を失ったなみが、総八郎を捜す為に江戸に出た辺りまでは、臨場感たっぷりだったが、浅草寺門前で偶然にも出会うシーンは、出来過ぎと感じざるを得ない。だが、読み進めるうちに、宇江佐さんが言いたい事はやはり松前藩の移封問題と、その犠牲になった藩士たちの生き様である事が分かると、出会いの場面は飽くまでも過程でありあっさりと流してしまうのも頷ける。
酔いどれ鳶
日々、内職に励む総八郎が、酒粕を食べて酔った鳶を連れ帰った。徳兵衛店の面々は珍しい鳶をひと目見ようと…。
余り話の筋とは関わりのない項のように思えたが、元藩の鷹部屋席だった総八郎が、日々内職に勤しむ浪人に身をやつしても、その神髄ではお務めを忘れていないと伝えたかったのか。または、なみに関わる人々の人間性をここで紹介したかったのか。何れにしても、先に述べたように、本筋とは違う話を持ってきて、読者にこんな想像力を膨らませさせている。
露草の悲
子を身籠ったなみは、現状を踏まえ子を諦めようと中條流を訪れる。
やはり長屋暮らしの浪人の悲哀を、こういった形で現したかと思った。
そして、長屋のつま弾き者であるおもんと、馬鹿にされている風のあるとん七ではあるが、この二人の本当の優しさを通し、人を上辺だけで語る事は出来ない。真実困った時に手を差し伸べてくれるのは、意外な人物なのかも知れないと考えさせられる。
箒星
総八郎は世情に疎くならないようにと、召し放しになった朋輩たちと勉強会を開く。
総八郎の朋輩である牧田兵庫助を通し、幾度となく時代の情勢を織り交ぜてあったが、ここにきて本格的に維新の風と、それに翻弄される当時の徳川体制、松前藩を出してきた。やはり、宇江佐さんの狙いはこれかと思う。
話は、総八郎、なみに娘友江が産まれ、相反しておもんが逝く。生と死の悲哀を感じさせる。
望郷
十歳になった友江は、紅屋の手伝いに通う事もあったが、ある日を境に嫌がるようになった。
そんなある日、友江を庇ったとん七が他界する。
これは悲しい話である。冒頭から総八郎、なみを慕う心優しき男としてとん七は関わってきたが、いずれは何か事件に巻き込まれるだろうと予想していても、死なせてしまわれたのは残念でならない。それは物語をドラマチックに盛り上げる効果はある。無論胸が詰まるエピソードである。
彩雲
帰藩が適った総八郎となみは、江戸で産まれた友江を伴い、陸奥国伊達郡梁川へと戻るのだった。
一項ごとに数年を経た設定になり、目まぐるしい時の移り変わりをみせていたのは、やはり最終的な結末を出す為だった。
念願成就の帰藩ではあるが、その夢が叶った時…人は失ったものを知る。ラスト2ページが総八郎の心中を見事に現して、ファンタスティックな終わり方となっている。「あの場所に帰りたい。あの愛しい日々に戻りたい。そこで自分がどれほど幸福であったかに総八郎は気づいた」。
見事な締め文句である。だが、ここで終わらないのが宇江佐さん。
「下谷に帰る足取りは重かった。総八郎は自分の人生がもはや終わりに近いと感じた」。
この一文があるかないかで、総八郎の思いの深さが大きく違ってきた事だろう。
余談ではあるが、宇江佐さんは本当に蠣崎波響が好きなんだなあと感じる。こ物語中一度も姿を現していない、蠣崎波響を大ラスの2行に持ってきているのだ。この2行に関しては些か疑問を抱く。
主要登場人物
相田総八郎...元蝦夷松前藩鷹部屋席
なみ...総八郎の妻
友江...総八郎、なみの娘
牧田兵庫助...元蝦夷松前藩作事奉行所所属、総八郎の朋輩
小野寺十蔵...元蝦夷松前藩徒士、現手習師匠
千蔵...三河町一膳めし屋千福主
とん七(藤七)...三河町小間物屋紅屋
お藤...とん七の姉
安吉...お藤の亭主
お富...とん七の母親
お米...三河町徳兵衛店住人
お松...徳兵衛店住人、大工竹蔵の妻
お駒...徳兵衛店住人、ひとり者
お房...徳兵衛店住人、花屋の棒手振りの妻
お菊...徳兵衛店住人、菓子屋奉公人の妻
おさち...徳兵衛店住人、お米の姪
おもん...徳兵衛店住人、夜鷹










 2004年7月発行
2004年7月発行 2004年6月発行
2004年6月発行 2003年9月発行
2003年9月発行 2003年05月発行
2003年05月発行 2003年4月発行
2003年4月発行 2003年3月発行
2003年3月発行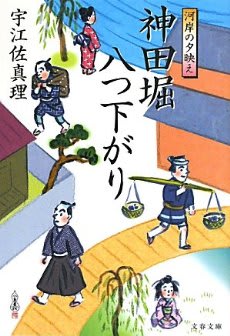 2003年2月発行
2003年2月発行 2002年5月発行
2002年5月発行 2002年3月発行
2002年3月発行 2002年1月発行
2002年1月発行  2001年11月発行
2001年11月発行 2001年11月発行
2001年11月発行 2000年12月発行
2000年12月発行 2000年9月発行
2000年9月発行