'13年に読んだ感想積み残し第三弾。
これで'12年の積み残しは終わり、ということで昨年最後に読んだ本です。
細かい活字で10ページから始まり778ページまで本文の続く大作。
読み終わるまで15日間かかりました。
「所有せざる人々」でも書きましたが、本作を読むと'12年ローカス誌SF長編オールタイムベスト2位~16位まで既読になるため入手して読み出しました。
ブックオフで見つからなかったためamazonで新品を購入1,600円。
本屋にはあまり並んでいないようなので品薄なのでしょうか?

ということで本作、'12年ローカス誌長編オールタイムベスト11位。
ハインラインの作品のなかでは最上位です、1961年発刊。
ヒューゴー賞受賞。
ハインラインが意図したかしないか謎ですが本作は60年代後半にヒッピーの聖書とされていたようです。
ということでwikipediaによると
ブライアン・アッシュの『SF百科事典』によれば、「SF界で最も有名な、というよりおそらくは最も悪名高い作品の一つに急速にのし上がってしまった長編」。
と書かれています。
「宇宙の戦士」の2年後、「月は無慈悲な夜の女王」5年前の作品ですがハインラインの中でも特殊な位置を占める作品といえそうです。
(私がそんなにハインラインを知っているわけではありませんが....。)
内容(裏表紙記載)
宇宙船ヴィクトリア号で帰った”火星から来た男”は、第一次火星探検船で火星で生まれ、ただひとり生き残った地球人だった。 世界連邦の法律によると、火星は彼のものである。 この宇宙の孤児をめぐって政治の波が押し寄せた。 だが”火星から来た男”には地球人とは異なる思考があり、地球人にはない力があったのだ。 巨匠ハインラインがその思想と情熱のかぎりを注ぎ込んだ超大作。
とりあえずの感想、「とにかく長い」と「小説=物語としては破綻しているなぁ」ということ。
SF的アイディアはそれなりに詰め込まれているので巨匠ハインラインであればもっと話を膨らませて面白くできそうなものですが、意図的なのかブツブツ切っていて薀蓄話にあふれていて面白くならない。
それが延々750ページ以上書かれている。
かなり読むのに苦労しました。
前段の火星から来た男マイクの権利を確保する辺りまで(第二部まで)は、ハインラインの知識のひけらかすための人物的な老学者ジュバル・ハーショーの超人性が鼻につき、いささか雑な展開ですがSF小説していますが、(ジュバルはハインラインの分身的人物設定らしいです)後半は小説の形を借りた宗教論的展開になってきます。
思想をストーリーに昇華させないで登場人物に語らせる、しかも作者の分身的人物に....。
なんとも鼻もちならない感があるのですが、なんだかんだ読んでしまうと印象には残ってしまう(笑)内容にはなっています。
作中何度も出てくる火星語「グロク」=「認識」が頭の中にこびりついて来て、本作を読んでいる最中に「グロクした」とかうっかりいいそうになったりしました。
あとトンデモ的展開として平井和正の「幻魔大戦」のこが頭に浮かびました、崩れかたは「幻魔大戦」の方が上かと思いますが...。
ハインラインがどこまで本気で登場人物に語らせているかは「?」ですが、宗教について何か語りたかったんでしょうね。
あとは異なる前提を持つものどうしが分かり合えるか=グロクできるか?ということがテーマでしょうか。
この辺を思いっきりストレートに書いています。
宗教については「所有」と「愛」、「宗教」が並存できるかどうか?というテーマを書いているのかなぁと感じました。
この辺端的にでているのがジュバル・ハーショーが新聞記者ベン・カクストンに最後の方で語った「愛とは、他人の幸福が自分自身にとって欠くことのできない状態」、愛とは嫉妬と相いれない感情としています。
この辺「所有」の概念をグロクできない火星から来た男マイクのことばを借りて突っこまさせています。
モーゼの十戒の「汝姦淫するなかれ」「汝盗むなかれ」も「所有」という概念がなければ成り立ちませんしねぇ。
(私は成り立たないような気がするですが...宗教は詳しくないです)
他、異なる存在どうしのグロクについてもいろいろ書いています。
この辺でフリーセックス的な表現も多く出てきますね。
まぁ両者とも壮大な問いなので答えが出るはずもなく、あの世=天国的存在を戯画的に書いたりして答えを濁してはいます。
なんとも印象に残る作品ではありますが、エンターテインメントという感じでもなく、芸術的作品とも違う気がする、なんとも微妙な位置の作品ですね。
ハインラインの「薀蓄小説」とでもいうのが一番合うような...。
この作品がオールタイムベストの11位にランクされているのは私的には「???」ですが、アメリカ社会では前述のように「悪名」でインパクトがあった作品のようですのでその辺が評価されているのと、アメリカ人はマッチョなハインラインが好きなんだろうなぁ。
「月は無慈悲な夜の女王」も「革命」やら「政体」やら薀蓄たっぷりな作品だったような気もしますし(これも老学者=ハインラインの分身? が重要な役割果たしていた)、「宇宙の戦士」「暴力」に対する薀蓄がかなり含まれている作品なので60年代以降のハインラインはそういう傾向だったんでしょうかねぇ。
でも本作は上記二作ち比べてもはるかに「小説度」が薄い作品になっています。
ハインラインの長編は他に「夏への扉」(1957年'12年ローカス誌67位)しか読んでいないのでなんともいえませんが...。
(これは薀蓄小説ではなかったと思います)
よく「夏への扉」の評価が日本で高くアメリカでそれほど高くないことが日本人の未熟さ的に言われていますが、私的にはローカス誌オールタイムベストで上位にある「異星の客」「月は無慈悲な夜の女王」「宇宙の戦士」を読んでみて、やはり「夏への扉」の方が好きですねぇ。
アメリカ人の感性を批判するわけではないですが、日本人的感性があってもいいんじゃないかと思います。
ということで年の終わりに巨匠ハインラインの作品ということで楽しみに読んだ作品ですが、残念ながら「凄い楽しい」読書ではありませんでした。
でもまぁ「小説」という形態としてはかなり外れた作品のような気がしますがインパクトはありました。
「SF」いろんな作品がありますねー。
今年(14年)も海外SF読んでいきたいと思っています。
薀蓄はどうもという方も、グロクしたという方も。
↓よろしければクリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。
 にほんブログ村
にほんブログ村
これで'12年の積み残しは終わり、ということで昨年最後に読んだ本です。
細かい活字で10ページから始まり778ページまで本文の続く大作。
読み終わるまで15日間かかりました。
「所有せざる人々」でも書きましたが、本作を読むと'12年ローカス誌SF長編オールタイムベスト2位~16位まで既読になるため入手して読み出しました。
ブックオフで見つからなかったためamazonで新品を購入1,600円。
本屋にはあまり並んでいないようなので品薄なのでしょうか?

ということで本作、'12年ローカス誌長編オールタイムベスト11位。
ハインラインの作品のなかでは最上位です、1961年発刊。
ヒューゴー賞受賞。
ハインラインが意図したかしないか謎ですが本作は60年代後半にヒッピーの聖書とされていたようです。
ということでwikipediaによると
ブライアン・アッシュの『SF百科事典』によれば、「SF界で最も有名な、というよりおそらくは最も悪名高い作品の一つに急速にのし上がってしまった長編」。
と書かれています。
「宇宙の戦士」の2年後、「月は無慈悲な夜の女王」5年前の作品ですがハインラインの中でも特殊な位置を占める作品といえそうです。
(私がそんなにハインラインを知っているわけではありませんが....。)
内容(裏表紙記載)
宇宙船ヴィクトリア号で帰った”火星から来た男”は、第一次火星探検船で火星で生まれ、ただひとり生き残った地球人だった。 世界連邦の法律によると、火星は彼のものである。 この宇宙の孤児をめぐって政治の波が押し寄せた。 だが”火星から来た男”には地球人とは異なる思考があり、地球人にはない力があったのだ。 巨匠ハインラインがその思想と情熱のかぎりを注ぎ込んだ超大作。
とりあえずの感想、「とにかく長い」と「小説=物語としては破綻しているなぁ」ということ。
SF的アイディアはそれなりに詰め込まれているので巨匠ハインラインであればもっと話を膨らませて面白くできそうなものですが、意図的なのかブツブツ切っていて薀蓄話にあふれていて面白くならない。
それが延々750ページ以上書かれている。
かなり読むのに苦労しました。
前段の火星から来た男マイクの権利を確保する辺りまで(第二部まで)は、ハインラインの知識のひけらかすための人物的な老学者ジュバル・ハーショーの超人性が鼻につき、いささか雑な展開ですがSF小説していますが、(ジュバルはハインラインの分身的人物設定らしいです)後半は小説の形を借りた宗教論的展開になってきます。
思想をストーリーに昇華させないで登場人物に語らせる、しかも作者の分身的人物に....。
なんとも鼻もちならない感があるのですが、なんだかんだ読んでしまうと印象には残ってしまう(笑)内容にはなっています。
作中何度も出てくる火星語「グロク」=「認識」が頭の中にこびりついて来て、本作を読んでいる最中に「グロクした」とかうっかりいいそうになったりしました。
あとトンデモ的展開として平井和正の「幻魔大戦」のこが頭に浮かびました、崩れかたは「幻魔大戦」の方が上かと思いますが...。
ハインラインがどこまで本気で登場人物に語らせているかは「?」ですが、宗教について何か語りたかったんでしょうね。
あとは異なる前提を持つものどうしが分かり合えるか=グロクできるか?ということがテーマでしょうか。
この辺を思いっきりストレートに書いています。
宗教については「所有」と「愛」、「宗教」が並存できるかどうか?というテーマを書いているのかなぁと感じました。
この辺端的にでているのがジュバル・ハーショーが新聞記者ベン・カクストンに最後の方で語った「愛とは、他人の幸福が自分自身にとって欠くことのできない状態」、愛とは嫉妬と相いれない感情としています。
この辺「所有」の概念をグロクできない火星から来た男マイクのことばを借りて突っこまさせています。
モーゼの十戒の「汝姦淫するなかれ」「汝盗むなかれ」も「所有」という概念がなければ成り立ちませんしねぇ。
(私は成り立たないような気がするですが...宗教は詳しくないです)
他、異なる存在どうしのグロクについてもいろいろ書いています。
この辺でフリーセックス的な表現も多く出てきますね。
まぁ両者とも壮大な問いなので答えが出るはずもなく、あの世=天国的存在を戯画的に書いたりして答えを濁してはいます。
なんとも印象に残る作品ではありますが、エンターテインメントという感じでもなく、芸術的作品とも違う気がする、なんとも微妙な位置の作品ですね。
ハインラインの「薀蓄小説」とでもいうのが一番合うような...。
この作品がオールタイムベストの11位にランクされているのは私的には「???」ですが、アメリカ社会では前述のように「悪名」でインパクトがあった作品のようですのでその辺が評価されているのと、アメリカ人はマッチョなハインラインが好きなんだろうなぁ。
「月は無慈悲な夜の女王」も「革命」やら「政体」やら薀蓄たっぷりな作品だったような気もしますし(これも老学者=ハインラインの分身? が重要な役割果たしていた)、「宇宙の戦士」「暴力」に対する薀蓄がかなり含まれている作品なので60年代以降のハインラインはそういう傾向だったんでしょうかねぇ。
でも本作は上記二作ち比べてもはるかに「小説度」が薄い作品になっています。
ハインラインの長編は他に「夏への扉」(1957年'12年ローカス誌67位)しか読んでいないのでなんともいえませんが...。
(これは薀蓄小説ではなかったと思います)
よく「夏への扉」の評価が日本で高くアメリカでそれほど高くないことが日本人の未熟さ的に言われていますが、私的にはローカス誌オールタイムベストで上位にある「異星の客」「月は無慈悲な夜の女王」「宇宙の戦士」を読んでみて、やはり「夏への扉」の方が好きですねぇ。
アメリカ人の感性を批判するわけではないですが、日本人的感性があってもいいんじゃないかと思います。
ということで年の終わりに巨匠ハインラインの作品ということで楽しみに読んだ作品ですが、残念ながら「凄い楽しい」読書ではありませんでした。
でもまぁ「小説」という形態としてはかなり外れた作品のような気がしますがインパクトはありました。
「SF」いろんな作品がありますねー。
今年(14年)も海外SF読んでいきたいと思っています。
薀蓄はどうもという方も、グロクしたという方も。
↓よろしければクリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。










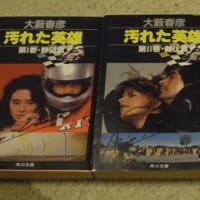
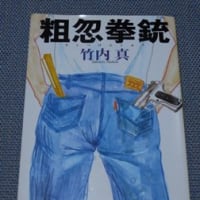
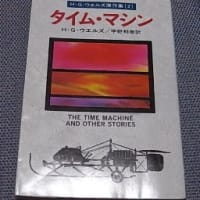
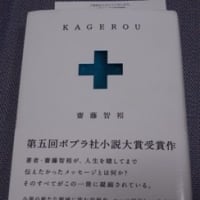
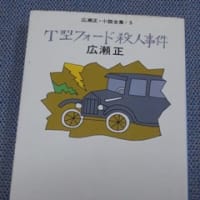
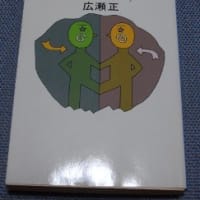


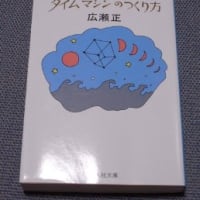
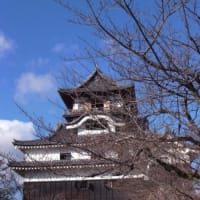






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます