各地で個々に闘う15原発訴訟団,全国で団結共同して闘おう、9600人、2016年02月13日 | thinklive
*規模は力なのだ、1つの統合的な訴訟に纏めるげきだ、その次に訴訟の世界化へ持ってゆくべきであろう、世界の弁護士に集まってもらうことも有効であろう、
福島第1原発事故で遠方に避難するなどし、国や東京電力に損害賠償を求めて各地の裁判所に提訴した原告団が13日、東京都豊島区のホールで全国連絡会の結成集会を開き、「団結して闘おう」とアピールした。
連絡会に加わったのは15地裁・地裁支部で係争中の計約9600人。避難区域への裁判官の視察や十分な本人尋問などを、足並みをそろえて各裁判所に求めていくほか、国会議員に支援を働き掛ける。
福島地裁訴訟の原告団長で、連絡会共同代表の中島孝さん(60)は「事故から間もなく5年だが、避難者の苦しみは増している。苦しみや困難を声にして国や東電にぶつかろう」と呼び掛けた。〔共同〕
|
蓮池透氏が安倍首相の“逆ギレ”国会答弁に堂々反論!「安倍さんは議員バッジより先にブルーリボンを外すべきだ」 |
日銀総裁、デフレ心理払拭へ「断固たる決意で行動」 2016/1/12 22:23
<form id="JSID_formKIJIToolTop" class="cmn-form_area JSID_optForm_utoken" action="/async/usync.do/?sv=NX" method="post">日銀は12日、フランス銀行(中央銀行)などが開いたシンポジウムでの黒田東彦総裁の講演原稿を公表した。物価2%目標の達成は「依然として道半ば」としたうえで、デフレ心理の払拭に向けて「誰かが断固たる決意を持って行動しなければならない」と指摘。「その役割を果たすのは中央銀行だ」と強調した。</form>総裁は同日のシンポジウムに出席できなかったが、主催者が参加者に原稿を配布した。総裁は量的・質的金融緩和の成果として、生鮮食品とエネルギーを除いた消費者物価指数(CPI)上昇率が1.2%まで高まったことや、失業率が完全雇用状態の水準まで下がったことをあげた。特にベースアップ復活が「強調に値する」とした。
【衆院予算委員会】安倍首相マジ切れ! 民主議員「拉致を政治利用したのか」との質問に「私が言っていることが真実だとバッジをかけて言う」とも 
産経新聞
安倍晋三首相は12日午前の衆院予算委員会で、北朝鮮による日本人拉致問題をめぐり、民主党の緒方林太郎氏から「拉致を使ってのし上がったのか」と問われ、「議論する気すら起きない。そういう質問をすること自体、この問題を政治利用している」と切り捨てた。また、この問題を巡る自身の発言について「真実だ。バッジをかける。言っていることが違っていたら、国会議員を辞める」と覚悟を示した。
首相は冒頭、北朝鮮の核実験が拉致問題に与える影響について「厳しい圧力をかけながら、対話の窓口を閉ざすことなく解決に向けて全力を尽くす」と述べた。
すると緒方氏は、拉致被害者の蓮池薫さんの兄、蓮池透さんによる著書『拉致被害者たちを見殺しにした安倍晋三と冷血な面々』(講談社)に「拉致問題はこれでもかというほど政治利用されてきた。その典型例は安倍首相だ」などとする一説があるとして、首相に認識を尋ねた。
首相は「いちいちコメントするつもりはない。家族会にもその本に強い批判がある。大切なことは北朝鮮に対して一致結束し、すべての被害者を奪還するために全力を尽くすことだ」と述べた。
緒方氏が「首相は拉致を使ってのしあがったのか」と重ねて質問すると、首相は「議論する気すら起きない。その質問をすること自体がこの問題を政治利用しているとしか思えない」と真っ向から否定した。
また、緒方氏は、本の中に、平成14年に拉致被害者5人が日本に帰国した際、官房副長官だった首相が5人の北朝鮮帰国を止めようとせず、5人が日本に残る意思が覆らないため結果的に日本に残るため尽力したとする趣旨の記述があることを紹介し、真偽をただした。
首相は「当時は5人の被害者を北朝鮮に戻すという流れだったが、私は断固として反対した。これをどう覆すか大変だった。他の拉致被害者本人に聞いてもらえればわかる」と否定した。
緒方氏が「蓮池氏がウソをついているのか」と続けると、首相は「誰かを落とすことは言いたくない。私が言っていることが真実だとバッジをかけて言う。違っていたら私は国会議員を辞める」と断言した。
さらに緒方氏は、一昨年の衆院選の新潟2区で、拉致被害者の親族が活動していたとして「政治利用ではないか」と迫った。
すると首相は「本の引用だけで独自の取材を全くせず、私の名誉を傷つけようとしている。極めて不愉快だ。何の意味があるのか。20年前、私たちが一生懸命拉致問題をやっていたときにあなたは何をしていたのか」と色をなした。
その上で「あなたが批判することが北朝鮮の思うつぼだ。そういう工作が今までもあったというのは事実だ。常にマスコミを2分し、国論を二分し、この問題で戦う力を落とそうとしてきたのが今までの歴史だ。大切なことは、すべての拉致被害者奪還のために、一致協力して全力を尽すことだ」と緒方氏を批判した。
最後に首相は「政治利用」との指摘に対し、「こんな質問で、大切な時間を使って答えるのは本当に残念だ。1人の方の本だけで誹謗中傷をするのは、少し無責任ではないか」と述べ、怒りがさめやらぬ様子だった。
記事THE PAGE/2015年12月25日
三菱航空機MRJ初納入1年延期 機体の強度向上図るため

[写真]3度目のMRJ飛行試験のようす(2015年11月27日、三菱航空機提供)
三菱航空機(愛知県豊山町)は24日、開発を進める国産初の小型ジェット旅客機MRJ(三菱リージョナルジェット)の第1号機納入時期を、当初予定の2017年4~6月から1年程度延期し、18年半ばにすると発表した。機体の強度向上や試験項目の見直しを図るため。納期延期は4度目となる。
岸副社長「想定に甘いところがあった」

[写真]納期延期の説明会のようす(愛知県春日井市で)
同社の森本浩道社長らが春日井市で記者会見し、納入延期に関して説明した。初納入先となる全日本空輸(ANA)にも納期延期を知らせ、「残念」という反応があったことを明かした。25機の受注契約については、キャンセルはないという。
機体の強度については、通常の飛行では「問題ない」とした。開発責任者の岸信夫副社長によると、通常飛行で考えられる最大の負荷を100%とした場合、100%には耐えられるが、それ以上の150%になると、主翼の付け根部分に問題が出る恐れがあるという。
国土交通省が安全性を認証する「型式証明」を取得するためにも強度向上は不可欠。岸副社長は、強度を上げつつ軽量化も追求する現状を踏まえ「50年ぶりの旅客機開発で、想定に甘いところがあった」と、正直な胸の内を明かした。
同社では、15年10月以降に行った走行・飛行試験に関しては「良好」の結果として、そこで得られたデータを改修に利用している。これまでの受注は国内外の航空会社から計407機あり、契約キャンセルなどは出ていない。特に11月の飛行試験以降は、引き合いが増加しているという。
同社は開発作業の加速や、北米での飛行試験実施に向けて、三菱航空機本社やアメリカのシアトルエンジニアリングセンターとモーゼスレイクテストセンターの、3拠点の役割や体制を整える。MRJの部品供給や、機体受注も多いアメリカの拠点には、航空宇宙関連の経験者を送りこむ。
リージョナル(地域間輸送)ジェットの競合他社は、ブラジルのエンブラエル社やカナダのボンバルディア社があり、この2社が世界市場のほとんどを占めている。この市場に挑戦するMRJは、燃費や環境性能の良さ、客室の快適性などを売りに受注数を増やしてきた。開発計画の延期は6度目となり、今後の受注の推移に注目が集まる。
森本社長は「市場に食い込むには開発を加速させる」と意気込み、「安全安心で完成度の高い機体を目指す」と力を込めた。
(斉藤理/MOTIVA)
米国利上げで浮上する世界経済の失速リスク
 © diamond 12月16日、FOMC後の記者会見時のイエレンFRB議長 Photo:federalreserve
© diamond 12月16日、FOMC後の記者会見時のイエレンFRB議長 Photo:federalreserve
12月16日、米国FRBは9年半ぶりに政策金利を引上げ、7年に及ぶゼロ金利政策を解除した。
今回のFRBの決定は大きなイベントであったが、それによって世界経済が抱える問題が解決されたわけではない。むしろ、多くの問題が詰まった箱=“パンドラの箱”のふたを開けてしまったと考えた方がよい。
金融緩和策によって、今まで箱の中に押し込めていた問題が逃げ出し、徐々に問題点が顕在化する可能性が高いからだ。今、世界経済が抱える問題を数え上げると、それこそ枚挙に暇がない。
まず、懸念されるのは米国経済だ。ドル高や原油価格の下落などの問題を考えると、米国経済の行方は必ずしも順調というわけではない。2009年7月以降、回復してきた米国経済には、そろそろ陰りの兆候が見え始めている。今後、住宅や自動車のローン金利が上がると、堅調な消費活動が落ち込む可能性もある。
また、わが国やEUが金融緩和を継続する中で、米国が金利を引き上げて金融政策の正常化に動き出した。主要国間の金利格差などを通して、世界の投資マネーが米国に引き寄せられることも想定される。
さらに、新興国、特に多額の債務を抱えた諸国の経済は心配だ。既に金融市場では、トルコなど一部の新興国に信用不安の懸念が生じている。そうした問題がさらに拡大すると、世界経済の足を引っ張ることは避けられない。
重要なポイントは、金融政策が変更される中で、米国経済が世界を牽引するパワーを維持できるか否かだ。それができないと、世界経済は再び下降トレンドに落ち込む可能性が高くなる。
今回のFRBの決定は大きなイベントであったが、それによって世界経済が抱える問題が解決されたわけではない。むしろ、多くの問題が詰まった箱=“パンドラの箱”のふたを開けてしまったと考えた方がよい。
金融緩和策によって、今まで箱の中に押し込めていた問題が逃げ出し、徐々に問題点が顕在化する可能性が高いからだ。今、世界経済が抱える問題を数え上げると、それこそ枚挙に暇がない。
まず、懸念されるのは米国経済だ。ドル高や原油価格の下落などの問題を考えると、米国経済の行方は必ずしも順調というわけではない。2009年7月以降、回復してきた米国経済には、そろそろ陰りの兆候が見え始めている。今後、住宅や自動車のローン金利が上がると、堅調な消費活動が落ち込む可能性もある。
また、わが国やEUが金融緩和を継続する中で、米国が金利を引き上げて金融政策の正常化に動き出した。主要国間の金利格差などを通して、世界の投資マネーが米国に引き寄せられることも想定される。
さらに、新興国、特に多額の債務を抱えた諸国の経済は心配だ。既に金融市場では、トルコなど一部の新興国に信用不安の懸念が生じている。そうした問題がさらに拡大すると、世界経済の足を引っ張ることは避けられない。
重要なポイントは、金融政策が変更される中で、米国経済が世界を牽引するパワーを維持できるか否かだ。それができないと、世界経済は再び下降トレンドに落ち込む可能性が高くなる。
ドル高、原油下落、ジャンク債──最大のリスクは米国経済の先行き
今後の世界経済が抱える、最も大きなリスク要因は米国経済の落ち込みだ。世界を牽引しているのは間違いなく米国経済であり、その減速が鮮明化すると世界全体にマイナスの影響が及ぶことは避けられない。
FRBの政策変更によって、今後、ローン金利が上昇すると、足元で堅調な住宅や自動車の販売にマイナスの影響が出る。それが現実のものになると、米国の消費活動全般に頭打ち傾向が出て景気の先行きに不透明感が強まる。
また、米国経済は三つのリスク要因を抱えている。一つ目はドル高だ。自国通貨が強含むことは輸出企業にとって大きなマイナス要因となる。足元の米国の輸出実績を見ても、悪影響が徐々に顕在化している。
しかも、今回のFRB利上げによって、わが国や欧米、さらには新興国との金利差が拡大する可能性が高い。金利策の拡大がさらに進むと、一段のドル高傾向が考えられる。それは、米国の輸出企業には大きな痛手になる。
二つ目は、原油価格の下落だ。現在、シェールオイルの開発で、米国は世界最大の産油国になっている。原油価格の落ち込みは、米国の企業業績全般にもマイナスの影響を与える。
また、中小のエネルギー関連企業が、低格付けの社債=いわゆる“ジャンク債”で資金調達をしていることを考えると、ジャンク債市場の落ち込みは金融市場全般にも無視できないマイナスインパクトがある。
そして三つ目は、循環的要因だ。2009年の年央から本格的回復に入った米国経済は、既に6年を超える上昇過程を歩んでいる。米国経済とて永久に上昇することはできない。そろそろピークを迎えることも想定される。
今回のFRBの金利引き上げが、最も大きなマイナスの影響を与えるのは新興国だ。ドル金利が上昇すると、多額の債務を抱える新興国には金利支払い負担が一段と重くなる。
少し長い目で見ると、新興国の中には負担増に耐えられない国が出てくるだろう。既に金融市場では、トルコなど一部の国の信用状態に対する懸念が出ている。
米国金利の上昇によって、投資資金が一部の新興国から米国に回帰する=リパトリエーションが本格化する可能性もある。投資資金の流出で、経済活動に悪影響が及ぶことが懸念される。
また、新興国通貨が下落する場合には、当該国の輸入物価が上昇してインフレ率が高まることも予想される。そうした弊害を食い止めるため、メキシコやチリなどはFRBの金利引き上げに伴って自国の金利を引き上げた。
これらの国の景気は必ずしも良好なわけではない。むしろ、仕方なく政策金利を引き上げざるを得なかった。ただ、金利を引き上げると、当該国の経済にはブレーキがかかり景気をさらに冷え込ませることも考えられる。
今回のFRBの利上げで、ドルと自国通貨を連動させているサウジアラビアや香港など、ドルペッグ制度の諸国も金利の引き上げを行なわざるを得なくなっている。特に、中東諸国は原油安の影響で一段と財政状況の悪化が懸念される。
今後、ブラジルやコロンビアなど、中南米諸国もFRB利上げに追随する可能性がある。こうした動きがさらに拡大すると、新興国の経済は一段と下落傾向を辿ることになる。新興国経済の落ち込みは、原油など資源価格の下落などを通じて世界経済をさらに下押しすることになるはずだ。
米国と並んで、景気の先行きに大きなリスクを抱える国を忘れてはならない。それは中国だ。中国経済の減速懸念はやや低下しているものの、来年以降も景気の緩やかな減速は避けられないだろう。
最近の共産党政権の方針は、成長率の鈍化よりも経済構造の変革を優先する姿勢が見える。李克強首相は、機能が低下したゾンビ企業を淘汰して、経済全体が抱える過剰設備を整理することを明言している。その方針には合理性はあるものの、短期的には景気の下押し材料になる。
中国政府が本気で経済構造の改革を断行すると、成長率はさらに鈍化して輸入にさらにブレーキがかかる。中国向けの輸出比率の高いブラジルやオーストラリアなどの資源国、IT関連部品の輸出が多い台湾や韓国などには痛手になるはずだ。
世界経済が抱えるリスク要因を考えると、それらを顕在化させずに順調な景気回復の過程を辿ることは難しくなるだろう。今までわが国やEUをはじめ多くの諸国が、経済活動を支えるために思い切った金融緩和策を取ってきた。
しかし、わが国やECB(欧州中央銀行)の緩和策にもそろそろ限界が見え始めている。その証拠に、12月3日のECBドラギ総裁の追加緩和策、同18日の日銀黒田総裁の補完策の効果はかなり限定的になっている。
それらの政策対応に対して、金融市場はむしろ“期待外れ”として失望感を表明している。今回のFRBの金利引き上げについても、これから米国経済がピークを打って、下落局面に入った時の政策余地を作ることが目的との指摘もある。
いずれにしても、今後の世界経済は米国次第で、米国景気の回復が続く間は、それなりの堅調さを維持することは可能だろう。逆に、その命綱が切れた時には、世界経済はかなり厳しい状況に追い込まれる可能性がある。その時は、わが国経済も例外ではありえない。
NYダウ大幅下落、309ドル安 原油安による影響懸念 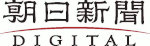
11日のニューヨーク株式市場は、大企業で構成するダウ工業株平均が大幅に下落し、前日より309・54ドル(1・76%)安い1万7265・21ドルで取引を終えた。 原油の先物価格の下落に歯止めがかからず、米石油大手などエネルギー関連を中心に幅広い銘柄に売り注文が入った。原油安による世界経済に対する悪影響も懸念され、投資のリスクを避けるための売りが一段と拡大した。 ハイテク株が中心のナスダック市場の総合指数は、前日より111・70ポイント(2・21%)低い4933・47で取引を終えた。(ニューヨーク=畑中徹)
世界の石油市場、2016年末まで供給過剰続く=IEA
来週は日米金融政策の行方に注目、FRBイエレン議長、日銀黒田総裁我々は、それまでは手が出ない、 1$120.81~来週は?
急激な利上げは景気腰折れ=「日本が教訓」―米FRB議長 時事通信
【ワシントン時事】米連邦準備制度理事会(FRB)のイエレン議長は23日公開した書簡で、急激に利上げを進めれば景気を腰折れさせ、低金利に戻らざるを得なくなると指摘した。その上で「他の国々は後戻りによって重い代償を支払っている。(長年)ゼロ状態の金利が続いている日本が教訓だ」と述べた。
議長はこれまで12月に利上げに踏み切る可能性に言及している。書簡では「景気が予想通りに回復すれば利上げを開始するのが適切」と説明。その後、金利は徐々に引き上げるとの見通しを示した。
書簡は、超低金利の持続により預金者が不利益を受けているとの消費者問題活動家ラルフ・ネーダー氏らの訴えに対する回答。議長は不満に理解を示した上で「低金利は景気回復と雇用創出を下支えした」と反論した。
認知症の介護苦に無理心中か 三女を逮捕
NHKニュース&スポーツ 利根川で74歳と81歳の夫婦が川の中で死亡しているのが見つかり、警察は、47歳の三女が認知症の母親の介護を苦に無理心中を図ったとして殺人と自殺ほう助の疑いで逮捕しました。 ・・・一言、逮捕?法律とは言えおかしいだろう! ”まず保護が先だ” 悲しい日本の実態・実に悲しい、AO
出生、育児支援への尊敬が日本の社会的通念には欠落、低出生社会への恐怖が男性に欠落、 | thinklive
*日本の貧困率は先進国ではアメリカに次いで2番目に高い国、特に母子家庭の貧困率が7割?
*スエーデンの婚外子の割合は54.7%、日本は2.1%、日本は異常に低い、婚外子への社会的な制裁感覚がいまだに存在している!
*日本では怖くて1人でこどもなんか産めないのが現実、中絶件数が20万件以上?中絶は無くせない?婦人会の医師がいなくなっちゃう!
フランスは1993年には1.6%付近まで下降していた出生率を回復させ、人口維持に必要な出生率20%を維持している数少ない先進国。そして、女性が最も働きやすい国と、声をそろえて称賛される国でもあります。
子育てと仕事を両立し、女性が自信をもって生きていくフランス。「恋愛大国」というイメージも強いかと思いますが、恋愛中だけでなく結婚後にも輝いているから、フランスの女性はとても魅力的に映るのかもしれませんね。
*フランスの出生率は2%
子供を持つ女性が働きにくい日本の原因は・・・
・保育園などの子供を預けられる施設や制度が足りない
・核家庭が増え、祖父母から保育のサポートを受けられない
・公的な休暇が少なく、仕事の休みが取りにくい
・経済的に子供を育てる余裕がない、就業の市場が狭く、賃金が低い、
*母子世帯への公的支援が極めて低い、
・子供ができたら家庭に入るものという社会風潮?
*出産する女性への尊敬が社会通念に存在しない?
フランスの子供達が通う学校には、バカンス・スコレールと呼ばれる長い期間の休暇があります。日本にも夏休みはありますが、フランスの夏休みは丸々2ヵ月。親も子供の休みにあわせて5週間もの有給休暇をとるのです。
フランス人にとっては「有休取得は国民の権利ではなく、義務」1年間に5週間与えられた有給休暇の消費率は、男女ともにほぼ100%だといわれています。
世界各国の婚外子の割合は急増している
先日、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を、結婚している両親の子ども「嫡出子」と同等にする改正民法がありました。
世界各国、特に欧米諸国では、1980年と比較して2008年では婚外子の割合が急増しています。
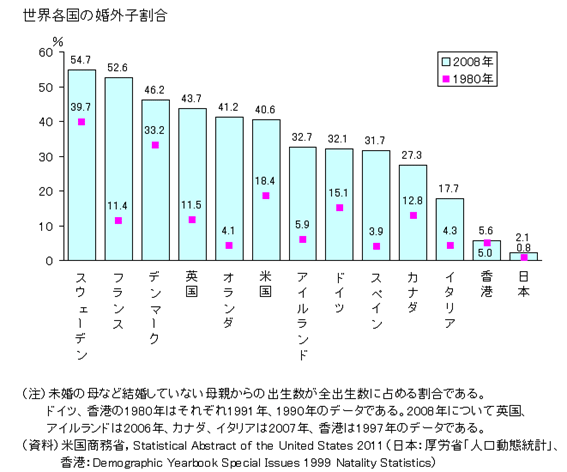
- 13日に署から不明に 熊谷4人変死 13日に署から不明に 熊谷4人変死
ペルー人の男、署に同行後行方不明に
捜査に落ち度はなかったのか。埼玉県熊谷市で16日、連続して84歳の女性と母子3人とみられる4人が死亡した事件。県警は13日に、住居侵入容疑で逮捕状を取ったペルー人(30)とみられる男を熊谷署に同行していたが、所在不明になり、その後立て続けに事件が起きていた。
13日の同行の経緯はこうだ。消防から連絡を受けた熊谷署員は通訳を手配するため署に男を同行。男が「たばこを吸いたい」と言ったため、玄関脇で吸わせていた。付き添いの警察官は1人だった。
すると、男は国道を強引に横断し、走り去った。午後3時半ごろだった。警察官は追わなかったが、県警の阿波拓洋(たくよう)刑事部長は16日夜の記者会見でその理由について「(この時点で)容疑者でも保護対象者でもなかった」と述べた。
午後5時5分ごろには、ペルー人の男が熊谷市石原の民家に侵入した。県警はペルー人の男と同行した男を同一とみている。
熊谷市見晴町の田崎稔さん(55)と妻の美佐枝さん(53)が自宅で殺害されたのは14日午後の可能性が高いという。県警は足跡などからペルー人の男が関与した疑いがあるとみている。
県警が13日以降、男の姿を捕捉したのは16日になってから。熊谷市石原の白石和代さん(84)とみられる女性が自宅で血を流して倒れているのが見つかり、周辺を捜索したところ、近くの加藤美和子さん(41)宅の2階にいるのを見つけた。
男は窓から顔を出し、窓枠に足をかけるように座っていた。捜査員の説得に応じず、自分の腕を刃物で切りつけて刃物を下に落とし、自らも落下した。加藤さんと娘2人とみられる3人が血を流して倒れているのが見つかり、その後死亡が確認された。
捜査関係者によると、男は平成17年に来日。横浜市や埼玉県鴻巣市、同県所沢市、群馬県伊勢崎市などを転々と移り住み、現在は住所不定だった。
県警の新井共実捜査1課長は会見で、報道陣から捜査に落ち度はあったかと問われ「必要な捜査をした」と否定した。
<モミの木>福島で生育異常が増加…線量高い場所ほど多発 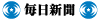
東京電力福島第1原発事故に伴う福島県の帰還困難区域内で、2012年以降にモミの木の生育異常が増加しているとの調査結果を、放射線医学総合研究所の渡辺嘉人主任研究員らが28日、英科学誌サイエンティフィックリポーツに発表した。放射線量が高い場所ほど異常な木の割合が高く、放射線の影響の可能性がある。チームは「放射線との因果関係やメカニズムを解明するにはさらに研究が必要だ」としている。
◇幹の先端、芽が出ず
チームは大熊町と浪江町の計3カ所と、比較対象として茨城県北茨城市でそれぞれ111〜202本のモミの木を調べた。その結果、放射線量が最も高い大熊町の調査地(毎時33.9マイクロシーベルト)では97.6%で、幹の先端の「主幹」と呼ばれる芽がなかった。主幹がないと生育が止まる。放射線量が同19・6マイクロシーベルトと同6.85マイクロシーベルトの浪江町の2カ所の調査地では、それぞれ43.5%と27%に異常が見られた。一方、北茨城市(同0.13マイクロシーベルト)では5.8%にとどまった。
環境省が11年度から実施している野生動植物調査では、約80種を調べた結果、モミ以外で異常は見られないという。針葉樹は放射線の影響を受けやすいことが知られており、旧ソ連・チェルノブイリ原発事故後には、ヨーロッパアカマツなどで異常が出たという報告がある。メカニズムは分かっていない。
チェルノブイリ事故の環境影響に詳しい笠井篤・元日本原子力研究所研究室長は「チェルノブイリで木に影響が出た地域の線量は今回の調査地点よりけた違いに高い。気象条件など自然環境要因も考慮し、慎重に原因を調べる必要がある」と指摘する。【渡辺諒】
火山大国日本での暴挙・噴火、地震の中、原発稼働「日本が危ない」
自然災害に逆らう大バカ者、此のまま行けば日本が”危ない”観光立国日本! AO
川内原発、原子炉起動へ 原発ゼロ、2年で幕 朝日新聞デジタル
 © 朝日新聞 川内原発(薩摩川内市)の地図
© 朝日新聞 川内原発(薩摩川内市)の地図
九電は11日午前10時半に原子炉を起動し、半日後の午後11時ごろ、核分裂反応が連続的に起こる「臨界」となる見通し。14日に発電と送電を始めて、9月上旬に営業運転に移る。
東日本大震災で東京電力福島第一原発が事故を起こし、その後国内の全原発は停止。電力不足で関西電力大飯原発3、4号機(福井県)が12年7月に一時的に再稼働したが、13年9月に停止し、その後は「原発ゼロ」が続いた。
福島第一原発事故を受けて、地震や津波の想定を厳しくした新規制基準ができ、川内原発は、新基準で初の再稼働となる。このため、九電は原子力規制委員会への対応に手間取るなどして手続きは遅れたが、審査を申請してから2年以上をへて再稼働する。
九電は川内2号機も10月中旬の再稼働をめざしている。他の電力会社では、関電高浜原発3、4号機(福井県)と、四国電力伊方原発3号機(愛媛県)も新基準を満たすと認められ、再稼働への手続きが進む。ただ、高浜原発については、福井地裁が4月、再稼働を禁じる仮処分を出し、再稼働できるかは不透明だ。
安倍晋三首相は10日の参院予算委員会で再稼働を進める責任を問われ、「安全神話に陥ることなく、事業者と規制当局が安全性を不断に追求していくことが大事だ」と電力会社や原子力規制委員会の責任を強調した。そのうえで「世界最高水準の新基準で認められた原発から再稼働していく」と述べた。
今年7月に決めた2030年度の電源構成で、原発の割合を約2割とするなど、政権は再稼働の「地ならし」を着々と進めてきた。だが、再稼働への世論の反発は根強い。安全保障関連法案の審議などで支持率が低迷する政権にとって、再稼働問題で「国が前面に立つ」ことをかわしたいのが本音だ。菅長官も10日の記者会見で「稼働するかどうかは事業者の判断」などと繰り返した。
一方、原発や福岡市の九電本店の周辺では、脱原発を訴える市民らが反対の声を上げた。(長崎潤一郎、星野典久)
東電元会長ら3人強制起訴へ 原発事故で検察審査会議決 2015/7/31 14:16
東京電力福島第1原子力発電所事故をめぐり、東京第5検察審査会は業務上過失致死傷などの容疑で告訴され、東京地検が不起訴とした東電の勝俣恒久元会長(75)ら旧経営陣3人について「起訴相当」とする議決をしたことが31日、関係者の話でわかった。
検察審が3人を起訴すべきだと議決したのは昨年7月に続き2度目。今後、東京地裁が指定する検察官役の弁護士が3人を起訴し、刑事裁判が始まる。東日本大震災後の津波で発生した未曽有の原発事故について、東電旧経営陣の刑事責任が法廷で争われることになる。
業務上過失致死傷罪で起訴相当とされたのは勝俣元会長のほか、武藤栄元副社長(65)と武黒一郎元フェロー(69)。















