朝8時半頃、道路に近い和室から外を見ながら女房が私を呼んだ。
「ちょっと来てみて、あの家の荷物片付けているよ」
「えっ、なに?」
私はトーストを食べ終わり、コーヒーを飲んでいた。
和室に行って女房の隣に立ち、道路のほうを見てみた。
道路側の窓から男が、トラックの荷台に向かって家具や荷物を投げていた。
どう見ても、引越しという感じではなかった。
家の中のものを廃棄するために、トラックの荷台に放り投げていた。
この家は、私の家から2軒前の道路を挟んだ隣の家です。
今年の1月の頃、この家の郵便受けの入り口にガムテープが張ってあった。
ということは、この家には人が住んでいないということか、と思った。
しかし、駐車場には白い車が停めてあった。
ガムテープでふさがれた郵便受けと白い車に、違和感を感じた。
私はこの家に住んでいる人を知らない。
この家のまわりに住む人たちの顔を、女房は知っているという。
この家の住人は、75歳ぐらいの男の人だったという。
9時半に私は女房を車で職場に送っていった。
そのときにその家の話をした。
「やはり亡くなったのかな?」と女房がいう。
「そうだろうね。もしおれが死んだら、おれのものは全部捨てていいからね」
「大丈夫、まちがいなく***くんのものは全部捨てます」
なぜか女房は、5歳年上の私を「くん」づけして呼ぶ。
私は自分の部屋に、20代の頃から書いてきた小説の原稿用紙が2つの段ボール箱にある。
その頃録音したカセットテープも何本もある。
昔のパソコン通信の記録を保存したフロッピーディスクもかなりある。
これまで読んだ小説が本箱にある。
壊れて見られない8ミリフィルムの映写機がある。
30代のときに住んでいたところの、市民吹奏楽団に入ったときに吹いていたトロンボーンがある。
ケーナは数本、サンポーニャ、尺八は各1、ブルースハープが5・6本あり、ギターは2本ある。
昔、陶芸サークルで焼いた焼き物もかなりある。
それらも私が死んだら何の意味もない。
しかし、あのように私の〝生きて残したもの〟が廃棄されるのは見たくない。
でも、私以外の人には、なんの意味もないガラクタだろう。
捨てられるしかない。
おそらくあの家は空き家になるだろうか?
うまいこと売却されて、新しい人が住んでくれればいいのだが・・・。





















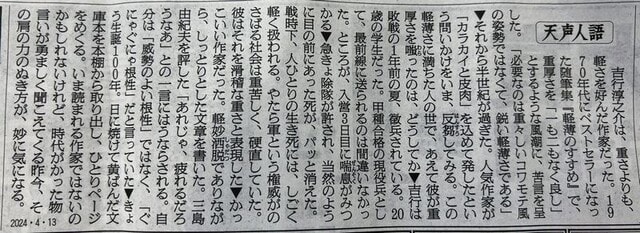
 2024年
2024年 2023年
2023年




