先日、電車の中でスマホで書いた記事を、大幅に加筆しました。
■ 日銀統計の家計保有分とされていた投資信託33兆円が、ゆうちょ銀行保有だった ■
日銀の統計で家計が保有しているとされていた投資信託33兆円が、実は「ゆうちょ銀行」保有だったと発表されています。家計保有分の投資信託は、実は減少していた。
「ゆうちょ銀行」は最近、投資信託の保有額を急増させていたのです。
■ 世界最大で最低の投資銀行であるゆうちょ銀行 ■
ゆうちょ銀行は法律で一般的な融資や住宅ローンの貸し出しを禁じられている為、ゼロ金利下で利益を上げる為には、多少リスクの有る投資も仕方無いのですが、ゴールドマンサックスの元日本支社長が運用部門を率いるなど、金融マフィアの「お財布」にされている可能性が高い。
それでもリスクの低い米国債投資ならいざ知らず、危機が発生すると価値が大きく毀損する投資信託を大量保有しているのだから、かなりリスクテイクな運用だと言えます。
日銀は郵貯銀行の投資信託33兆円をゆうちょ銀行保有の外債としてカウントしていたので、資産がその他金融機関のゆうちょ銀行と家計とでダブルカウントもされていた事になります。家計保有の投資信託の算出は、投資信託全体の保有額から金融機関保有分を差し引いて算出していたからです。
■ 巨大な機関投資家としてのゆうちょ銀行 ■
銀行とは名ばかりで、実体は投資銀行というよりも、「巨大機関投資家」と言える「ゆうちょ銀行」。
元々、国相手に財政投融資としてお金を貸すか、国債を買うだけの運用しかした事の無い組織でしたから、運用ノウハウや投資ノウハウを持つ社員は皆無でした。外部からヘッドハントして運用を任している訳ですが、彼らが「獅子身中の虫」や「トロイの木馬」で無い事を祈るばかり。
巨大な資金を運用する一方で、運用利益率が他のメガバンクに見劣りするのは、国債保有額が未だに巨大な事に起因していると思いますが、一方でかなりリスクも取っている様です。オルタナティブファンドにも手を付けています。
一方で「ゆうちょ銀行」独自の優位性も有ります。
1) 自己資本比率が22%と非常に高い事
2) 長期的な預金(貯金)が多いく、他己資金が一般の銀行より安定している
3) 預金者の多くは、「ゆうちょの貯金は国が保証してくれる」と思い込んでいる
これらの特殊性により「ゆうちょ銀行」は多少投資に失敗しても債務超過になる危険性が少ない。ただ、これは言い換えれば、ストレステストの基準が甘くなる事と同義かと。
「自己資本比率が高い=リスク許容度が高い=リスクの高い資産を大量に保有」
ここら辺に「ゆうちょ銀行の見えないリスク」が隠れていると、私は妄想します。
■ 個人の資金が直接リスクに晒される時代 ■
日銀統計が故意かミスかは藪の中ですが、預金から投資への掛け声とは裏腹に、家計は投資信託の保有額を減らしていた事には驚きました。リスクの実体が素人には分かり難く、金融庁も警鐘を鳴らしていた投資信託ですが、少し勉強された方ならば手数料が高くて儲からない事に気づくでしょう。
一方で「積立nisaやってる」という様な会話が当たり前になりつつある昨今。「銀行に預けても利息が付かない」時代、国民の資産はジリジリと元金が保証されないリスク運用に追い込まれています。
様々な会社が社員向けの投資講座を開くなど、資産運用は本格手にに「預金から投資」の時代に変わりつつあります。これは銀行を介した間接金融から、個人が直接投資銘柄や商品を選ぶ時代なった事を意味します。
ジャンク債などプロならばリスクを意識しがちな投資でも、「ハイイールド債投資信託」などに加工して個人相手に売れば、儲かります。こうして、リスクの認識の甘い個人がカモになっているのが現在の世界の実体。これは日本に限った事ではありません。
個人は金利に目が行きがちですから、国内投資よりも海外投資が増えますが、為替リスクなどを正確に理解されている方は少ないでしょう。さらに、投資される金融商品の中身を把握されている方は一握りに過ぎません。
世界的金融危機が間近に迫っているとするならば、今こそリスク性の投資を手仕舞いして、預金に資金を移すべきだと私は考えています。最悪の事態を考慮して、多少の現金も手元に置く事もお勧めします。
ただ・・・資金の置き場として「ゆうちょ銀行」を選ぶかどうかは・・・。











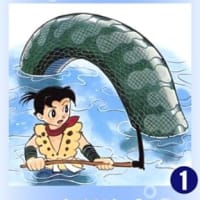
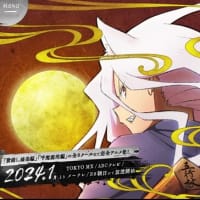







というか、こういった混沌状態は生物としての人間にと
って大事だと思います。
自分の持つ資産の価値が不変だったりすると永久に格差
が固定化すると思います。
自分が必死に(卑怯なことや人道に外れた事もして)頑
張った結果の財産が大きく変動すれば良い面もきっとあ
ると思います。
私個人としてはガラガラポンは世代間格差や、資産格差の解消に有効で、富の偏在がもたらす成長力の低下の最大の解消方法だと考えています。
本来、政府が所得再配分を最適化する事で、成長力を維持すべきですが、現在はこの機能が崩壊しています。
す
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33691680R00C18A8E
N2000/
日銀の異次元緩和の本当に目的は、財政ファイナンスなので、インフレが本当に起きてしまうと日銀は困った事になります。だから、インフレ率が高まりそうになったら消費税増税で消費を抑制します。ただ、市場が冷え切ってしまうのも困るので、金利変動が許容できる範囲で空売り用の国債も貸し出すのでしょう。
日本国債市場は日銀が金利を支配する形で、既に市場の体を成していませんし、国内の金融機関が国債を一斉に手放さない限り、金利の急上昇も起こりません。これは一見無税国家が成立している様に見えますが、このバランスが崩れるとすれば、海外発の金融危機によって各国の国債の信用不安が高まる時だと私は妄想しています。
こうして、国内で誰も責任を負う事も無く、ソフトなガラガラポンが達成される事こそが最終目標なのでは無いか・・・。
池田信夫氏などは、財政インフレによって、金利上昇が起きると予測されている様ですが、拡大が続く年金や福祉分野でバラまかれたお金が、銀行預金に停滞している事が先の投資信託の集計ミスで明らかになっています。
老人と国と日銀の間でお金がやり取りされる今の日本では、簡単には財政インフレも起こす事は出来ないのでは?