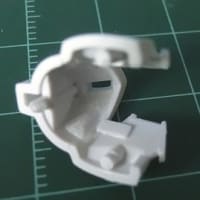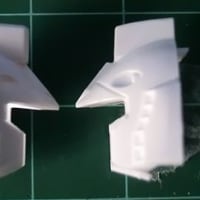昨日・今日と大きな用事があったので、クロスボーンの作業は進みませんでした(泣)。仕方がないので昔のお話をお送りします(汗)。
「これ塗るのん、無理やわ~」
……昔のガンプラは、塗装するのが前提になっていて、ほとんどの1/144スケールキットは単色成型でした。なおかつパーツ分割も今ほど細かくなかったので、塗りにくい部分が多くありました。
特に旧1/144ガンダムの顔は、その小ささと、顔面がヘルメット部分と一体成型であるために小学生の技術ではどうしても……(泣)。ガンダムの顔って、白・黒・黄・赤が隣り合わせになっているので、極めて塗りにくいんですよねぇ。当時の同級生は「針で塗ったで!」と言っていました。細筆でも塗り分けは困難でしたからねぇ。
実は筆者は旧1/144ガンダムを手に入れたことがなかったので、HGUCガンダムの顔を塗装した時も「おお、塗りやすい!」ぐらいの感想でしかなかったのですが、旧1/144ガンダムを苦労して塗った人なら、言いようのない感動を味わったのではないかと思います(HGUCガンダムの顔は、1/144スケールのガンダムタイプMSのキットの中でも群を抜いて塗りやすいと思います)。
以前も記事に書きましたが、昔(いや、「逆襲のシャア」ぐらいまででしたっけ?)のガンプラの説明書の塗装見本には、ランナーに部品がつながった状態で塗装された写真がありました(MSV:モビルスーツ・バリエーションのシリーズは現在と同様の構成でしたが)。パーツリストも兼ねているんですねぇ。この方式だと、どのパーツをどう塗り分けたらよいのかが分かりやすいというメリットがありました。
しかし、ランナーにつながった状態でパーツを塗装すると、組み立て時に合わせ目を消すことが出来ません。旧ガンプラの箱や説明書の完成写真も、合わせ目が残ったままでした。「MSV」以降は、合わせ目が消えていましたが……。
塗料の配合の指示もおおらかでした。「ミディアムブルー:40%」みたいな感じではなく、「黒にグレーを少し混ぜる」みたいな書かれ方が多かったような気がします。これがなかなか良い色にならない!
そういえば、当時はツヤ消しにする風習はなかったようで、完成写真のガンプラはみんなツヤありでした。「フラットベース」が登場するのは「MSV」以降になります。
スミ入れについては、実は「1/144ザク」で「油性の極細ペン」を使うように書かれていました。ちょっと意外!
余談ですが、「○○%」と書かれるようになった後で、水性ホビーカラーで指示通りの配合にしたら、似ても似つかない色になったことがありました(コバルトブルーをメインに混ぜていました)。どうやらキットの配合指示は油性の「Mr.カラー」を元にしたものらしく、色によっては「Mr.カラー」と「水性ホビーカラー」の同名の色に違いがあるため、このような事態になったのだと思います。
また、塗装の指示の中には、色の指定が書かれていないものがありました。しかも、メインの色が! ガンプラを作り始めてしばらくのうちは、「ガンダムカラー(旧)」の存在を知らなかったので、「いちばん多く使う色やのに、なんで書いてないのん?」と、不思議に思ったものでした。
旧ガンダムカラーも、現在のものと同じく基本色3色のセットになっていました。メーカーはグンゼ産業(現:GSIクレオス)だったと思います。実物を手に入れたことがなかったので、詳しいことは分かりませんが、タミヤのエナメル塗料のような小さいビンに入っていたかと思います。ビンのフタは金属製だったような…。
この旧ガンダムカラーもガンプラ同様、入手は困難でした。模型屋さんのレジの奥に置いてあるのは「ジオング用」とか「ガンタンク用」ばっかりで、筆者には縁遠いものでした。グフとザクが好きだったもので…。
1/60スケールおよび1/100スケールの中には、成型色が3色ぐらい使われていて、ほとんど塗らなくても良いものがありました。今の多色成型の前身ともいえますが、使用色の少ないジオン系のキットばかりだったような…。
当時の小学生のお小遣いでは1/100キットには手が出せず、だいたいは1/144キットを無塗装か、筆塗りするしかありませんでした。
そこに衝撃のアイテムが! 「いろプラ」シリーズの登場です。1/250という小スケールで、パーツごとに色分けされていて(ザク・グフはほとんど塗装不要)、しかもフル可動(ザクなんかは1/144でもなしえなかった足首可動も)! おまけに200円という低価格でした。
しかしこの「いろプラ」、生産数が少なかったのか、店で売ってるのを見たことがありませんでした。友達が持っているのをうらやましがっていた記憶があります。それ以降も見たことがありません。
ガンプラの絶版品は初代「HGガンダム」だけという話を聞くことがありますが、この1/250「いろプラ」も絶版といってもよい状態だと思います。
絶版といえばもう一つ、今から15年ほど前に、旧ガンプラの塗装済みキットが発売されました。確か「FCM(フルカラーモデル?)」というシリーズ名だったと思いますが、ランナーにパーツがつながった状態で、きれいに塗装されていました。箱のフタの一部が透明になっていて、そこから塗装済みのパーツが見えるようになっていたような記憶が……。
300円クラスのキットが500円ぐらいで、自分で塗装することを考えると割安な価格設定でした。もちろん、合わせ目を消すことはできませんが……。このシリーズも絶版といってもいいでしょう。
機体解説として、当時最新の解釈(MSVや「Zガンダム」以降、「ポケットの中の戦争」シリーズまでの内容を踏まえたもの)が説明書に載っていて、それだけでも魅力があったんですけどねぇ。
筆者が小学生の時代に話は戻ります。ガンプラが入手困難ではなくなってきた頃、初代ガンプラの後を受けて登場したMSVシリーズの完成写真に、筆者はカルチャーショックを受けることになるのでした。続きはまた次回に…!
――子供がシンナーを使うという危険性から、最初は一緒になって作ってくれた筆者の父は、ガンプラをはじめプラモデル作りを禁止するようになりました。まあ、それでも筆者はこっそり隠れてしつこく作り続けましたけどね(笑)。この「隠れて作る」が、当ブログのタイトルの原点になっているんです。
今はHGクラス以上のキットなら、ほとんど基本塗装をしなくても設定色に近い完成品を手に入れることができます。こだわらなければ十分です。ホンマに良い時代になりましたねぇ…(しみじみ)。
「これ塗るのん、無理やわ~」
……昔のガンプラは、塗装するのが前提になっていて、ほとんどの1/144スケールキットは単色成型でした。なおかつパーツ分割も今ほど細かくなかったので、塗りにくい部分が多くありました。
特に旧1/144ガンダムの顔は、その小ささと、顔面がヘルメット部分と一体成型であるために小学生の技術ではどうしても……(泣)。ガンダムの顔って、白・黒・黄・赤が隣り合わせになっているので、極めて塗りにくいんですよねぇ。当時の同級生は「針で塗ったで!」と言っていました。細筆でも塗り分けは困難でしたからねぇ。
実は筆者は旧1/144ガンダムを手に入れたことがなかったので、HGUCガンダムの顔を塗装した時も「おお、塗りやすい!」ぐらいの感想でしかなかったのですが、旧1/144ガンダムを苦労して塗った人なら、言いようのない感動を味わったのではないかと思います(HGUCガンダムの顔は、1/144スケールのガンダムタイプMSのキットの中でも群を抜いて塗りやすいと思います)。
以前も記事に書きましたが、昔(いや、「逆襲のシャア」ぐらいまででしたっけ?)のガンプラの説明書の塗装見本には、ランナーに部品がつながった状態で塗装された写真がありました(MSV:モビルスーツ・バリエーションのシリーズは現在と同様の構成でしたが)。パーツリストも兼ねているんですねぇ。この方式だと、どのパーツをどう塗り分けたらよいのかが分かりやすいというメリットがありました。
しかし、ランナーにつながった状態でパーツを塗装すると、組み立て時に合わせ目を消すことが出来ません。旧ガンプラの箱や説明書の完成写真も、合わせ目が残ったままでした。「MSV」以降は、合わせ目が消えていましたが……。
塗料の配合の指示もおおらかでした。「ミディアムブルー:40%」みたいな感じではなく、「黒にグレーを少し混ぜる」みたいな書かれ方が多かったような気がします。これがなかなか良い色にならない!
そういえば、当時はツヤ消しにする風習はなかったようで、完成写真のガンプラはみんなツヤありでした。「フラットベース」が登場するのは「MSV」以降になります。
スミ入れについては、実は「1/144ザク」で「油性の極細ペン」を使うように書かれていました。ちょっと意外!
余談ですが、「○○%」と書かれるようになった後で、水性ホビーカラーで指示通りの配合にしたら、似ても似つかない色になったことがありました(コバルトブルーをメインに混ぜていました)。どうやらキットの配合指示は油性の「Mr.カラー」を元にしたものらしく、色によっては「Mr.カラー」と「水性ホビーカラー」の同名の色に違いがあるため、このような事態になったのだと思います。
また、塗装の指示の中には、色の指定が書かれていないものがありました。しかも、メインの色が! ガンプラを作り始めてしばらくのうちは、「ガンダムカラー(旧)」の存在を知らなかったので、「いちばん多く使う色やのに、なんで書いてないのん?」と、不思議に思ったものでした。
旧ガンダムカラーも、現在のものと同じく基本色3色のセットになっていました。メーカーはグンゼ産業(現:GSIクレオス)だったと思います。実物を手に入れたことがなかったので、詳しいことは分かりませんが、タミヤのエナメル塗料のような小さいビンに入っていたかと思います。ビンのフタは金属製だったような…。
この旧ガンダムカラーもガンプラ同様、入手は困難でした。模型屋さんのレジの奥に置いてあるのは「ジオング用」とか「ガンタンク用」ばっかりで、筆者には縁遠いものでした。グフとザクが好きだったもので…。
1/60スケールおよび1/100スケールの中には、成型色が3色ぐらい使われていて、ほとんど塗らなくても良いものがありました。今の多色成型の前身ともいえますが、使用色の少ないジオン系のキットばかりだったような…。
当時の小学生のお小遣いでは1/100キットには手が出せず、だいたいは1/144キットを無塗装か、筆塗りするしかありませんでした。
そこに衝撃のアイテムが! 「いろプラ」シリーズの登場です。1/250という小スケールで、パーツごとに色分けされていて(ザク・グフはほとんど塗装不要)、しかもフル可動(ザクなんかは1/144でもなしえなかった足首可動も)! おまけに200円という低価格でした。
しかしこの「いろプラ」、生産数が少なかったのか、店で売ってるのを見たことがありませんでした。友達が持っているのをうらやましがっていた記憶があります。それ以降も見たことがありません。
ガンプラの絶版品は初代「HGガンダム」だけという話を聞くことがありますが、この1/250「いろプラ」も絶版といってもよい状態だと思います。
絶版といえばもう一つ、今から15年ほど前に、旧ガンプラの塗装済みキットが発売されました。確か「FCM(フルカラーモデル?)」というシリーズ名だったと思いますが、ランナーにパーツがつながった状態で、きれいに塗装されていました。箱のフタの一部が透明になっていて、そこから塗装済みのパーツが見えるようになっていたような記憶が……。
300円クラスのキットが500円ぐらいで、自分で塗装することを考えると割安な価格設定でした。もちろん、合わせ目を消すことはできませんが……。このシリーズも絶版といってもいいでしょう。
機体解説として、当時最新の解釈(MSVや「Zガンダム」以降、「ポケットの中の戦争」シリーズまでの内容を踏まえたもの)が説明書に載っていて、それだけでも魅力があったんですけどねぇ。
筆者が小学生の時代に話は戻ります。ガンプラが入手困難ではなくなってきた頃、初代ガンプラの後を受けて登場したMSVシリーズの完成写真に、筆者はカルチャーショックを受けることになるのでした。続きはまた次回に…!
――子供がシンナーを使うという危険性から、最初は一緒になって作ってくれた筆者の父は、ガンプラをはじめプラモデル作りを禁止するようになりました。まあ、それでも筆者はこっそり隠れてしつこく作り続けましたけどね(笑)。この「隠れて作る」が、当ブログのタイトルの原点になっているんです。
今はHGクラス以上のキットなら、ほとんど基本塗装をしなくても設定色に近い完成品を手に入れることができます。こだわらなければ十分です。ホンマに良い時代になりましたねぇ…(しみじみ)。