今年の総括をするには早過ぎるが、もう年内には観能の機会がなさそうなので一応まとめてみた。
今年は1月の喜多流「久留米座能」から始まった。20数年前久留米に住んでいたが、この新しいホールへ入るのは初めて。立派な特設能舞台が組まれ、素晴らしい雰囲気だ。番組では狩野了一さんがシテを務める能「船弁慶」は迫力十分。義経を務めた子方の石田大雅君が凛々しかった。
4月には大倉源次郎さんを中心とする囃子方をフィーチャーした「音と舞」。熊本震災復興祈念として行われ、各流派合同の公演となった。なかでも観世流・菊本澄代・美貴姉妹の相舞による舞囃子「小袖曽我」は見ごたえがあった。そしてこの公演が平成最後の観能になった。
8月は毎夏恒例の出水神社薪能。今年は第60回記念ということで十四世茂山千五郎さん演じる狂言「彦一ばなし」。金春流・本田光洋さんの「羽衣 替ノ型」というスペシャルな番組が組まれた。お二人とも堂々たる風格を感じさせる舞台だった。
9月は毎年恒例の藤崎八旛宮例大祭御能組。喜多流・金春流が交互の番組だが、今年特に印象に残ったのは、喜多流・狩野祐一さんの半能「熊坂」だった。23歳の若手らしい長刀振り回しながらの「飛び返り」はダイナミックだった。
そして10月は、3年ぶりの開催となった熊本城薪能。大いに期待したのだが、最後の金春流「半蔀」が残念な結果となった。ただ、救いは観世流・菊本澄代さんの舞囃子「経正」の気迫のこもった舞を観ることができたことだ。
さて、来年はどんな能を観ることが出来るだろうか。

出水神社薪能 金春流 能「羽衣 替ノ型」(シテ:本田光洋)
今年は1月の喜多流「久留米座能」から始まった。20数年前久留米に住んでいたが、この新しいホールへ入るのは初めて。立派な特設能舞台が組まれ、素晴らしい雰囲気だ。番組では狩野了一さんがシテを務める能「船弁慶」は迫力十分。義経を務めた子方の石田大雅君が凛々しかった。
4月には大倉源次郎さんを中心とする囃子方をフィーチャーした「音と舞」。熊本震災復興祈念として行われ、各流派合同の公演となった。なかでも観世流・菊本澄代・美貴姉妹の相舞による舞囃子「小袖曽我」は見ごたえがあった。そしてこの公演が平成最後の観能になった。
8月は毎夏恒例の出水神社薪能。今年は第60回記念ということで十四世茂山千五郎さん演じる狂言「彦一ばなし」。金春流・本田光洋さんの「羽衣 替ノ型」というスペシャルな番組が組まれた。お二人とも堂々たる風格を感じさせる舞台だった。
9月は毎年恒例の藤崎八旛宮例大祭御能組。喜多流・金春流が交互の番組だが、今年特に印象に残ったのは、喜多流・狩野祐一さんの半能「熊坂」だった。23歳の若手らしい長刀振り回しながらの「飛び返り」はダイナミックだった。
そして10月は、3年ぶりの開催となった熊本城薪能。大いに期待したのだが、最後の金春流「半蔀」が残念な結果となった。ただ、救いは観世流・菊本澄代さんの舞囃子「経正」の気迫のこもった舞を観ることができたことだ。
さて、来年はどんな能を観ることが出来るだろうか。

出水神社薪能 金春流 能「羽衣 替ノ型」(シテ:本田光洋)












 天皇、皇后両陛下の祝賀パレードに沸いた一日。オープンカーからにこやかに手を振られる両陛下を見ながら、ふと、宇野哲人先生もきっとお喜びにちがいないと思った。宇野先生とは「浩宮徳仁」(天皇陛下)の名付親でもあり、少年浩宮の教育にも携わった漢学者。明治8年、旧熊本藩士の四男として内坪井町に生まれ、済々黌、五高で学び、明治33年、東京帝大漢学科を恩賜の銀時計を拝受して卒業した秀才。永年にわたり後進の指導と学術の振興に尽力し、昭和49年、99歳の長寿を全うした。僕の高校の大先輩でもあり、在学時から卒業生の中でも特別な存在として認識していた。
天皇、皇后両陛下の祝賀パレードに沸いた一日。オープンカーからにこやかに手を振られる両陛下を見ながら、ふと、宇野哲人先生もきっとお喜びにちがいないと思った。宇野先生とは「浩宮徳仁」(天皇陛下)の名付親でもあり、少年浩宮の教育にも携わった漢学者。明治8年、旧熊本藩士の四男として内坪井町に生まれ、済々黌、五高で学び、明治33年、東京帝大漢学科を恩賜の銀時計を拝受して卒業した秀才。永年にわたり後進の指導と学術の振興に尽力し、昭和49年、99歳の長寿を全うした。僕の高校の大先輩でもあり、在学時から卒業生の中でも特別な存在として認識していた。




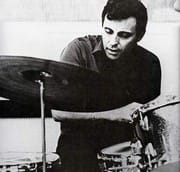 今年3月、90歳で世を去った名ドラマー、ハル・ブレインを追悼するニューヨークタイムズのWeb記事の中に次のような一節があった。
今年3月、90歳で世を去った名ドラマー、ハル・ブレインを追悼するニューヨークタイムズのWeb記事の中に次のような一節があった。
