さてさて。
それでは、「十二支にはなぜ龍が存在するのか~月氏(がちし)との邂逅~」。
十二支にはなぜ龍が存在するのか~謹賀新年~の続きです。
「月氏(がちし)ってなぁに? 」
」
 ひよこさん。「月氏」。一度こんな記事に登場していますよ。
ひよこさん。「月氏」。一度こんな記事に登場していますよ。
のんきの宗教観~外伝。
ガンダーラ王国そのものは、紀元前6世紀ころから存在したらしく、ガンダーラが最も繁栄
するのは、イラン系遊牧民族の「月氏(がちし)」がインドに築いた王朝、「クシャーナ朝」
の時代。「月氏」が漢字表記になっていることからもわかるように、月氏とは、始皇帝の時
代の中国史にも登場する民族です。
中国と月氏との出会いはというと・・・。
時代は紀元前2世紀。漢の時代。武帝という皇帝が、張騫(ちょうけん)という人物を同盟を結ぶために、この「月氏」のもとへと派遣したことがそのきっかけ。
当時の月氏は、「匈奴(きょうど)」という民族と敵対していて、この匈奴に敗れた月氏は、北のほうに逃れていました。中国では、このころの月氏のことを、
「大月氏」と呼んでいました。
漢はこの「匈奴」を挟み撃ちにするためにこの月氏に張騫を派遣したのです。
さて。この月氏という民族。いわゆる「遊牧騎馬民族」で、実に八尺(2m40cm)を超える身丈の馬を駆使していたのだとか。
当時の中国で利用されていた馬は、「蒙古馬」という種類だったのだそうです。蒙古馬。日本の在来馬もルーツは蒙古馬にあるそうですから、こんな感じでしょうか。

一方、月氏の馬はこんな感じでしょうか。

さて。この月氏の馬を見た漢人たちの驚きたるや、なかったかのではないでしょうか。
そしてさらに、月氏の言葉で言う「馬」の発音と、漢語の「龍」の発音は、とてもよく似ていたのだといいます。
このことから、漢人たちの間で、「西方に龍を駆使する民族がいる」といううわさが瞬く間に広まります。
そして、このころから、中国では「龍」を描くとき、それまで「蟲」をモチーフとした「龍」から、月氏たちの駆使する「大形の馬」をモチーフとした龍に、
その描かれる姿は大きく変化するようになりました。

さて。改めて見てみると、ちょいと「馬」っぽくないですかね。
やがて、月氏は再び匈奴に追われ、西方へと遠ざかっていきます。漢人たちはあの大形馬接触することはなくなり、やがて大形馬をモチーフとしたまま、
漢民族の中で、「龍」は独自の発展を遂げていきます。より大きく、より煌びやかな姿へと・・・。
さて。それでは改めてタイトルにある設問。
「十二支にはなぜ龍が存在するのか」
これは、つまるところ、華夏族の有していた「トーテム信仰」がそのルーツとなっているのではないかと思います。
「龍」だけではありません。古代中国では、「猪」「鳥」「蛇」「羊」「虎」「牛」もすべて神聖な生き物として崇拝され、また生活に根差した存在でした。
「龍」はそういった神聖な動物たちの象徴。伏羲によって、「人間が喜ぶ生き物」として「馬、蛇、鳥」のキメラとして生み出された「龍」。
さて。シリーズ、「十二支にはなぜ龍が存在するのか」。いかがだったでしょうか。
改めまして、本年一年が、何よりもこの国に住むすべての皆様にとって素敵な一年となりますよう、心よりお祈りいたします。
日本の未来は明るい!!
は日本を明るくする!!










帰りしにクリックを・・・
あなたの1票が、のんきのブログを沢山の方に知っていただく力になります^^

それでは、「十二支にはなぜ龍が存在するのか~月氏(がちし)との邂逅~」。
十二支にはなぜ龍が存在するのか~謹賀新年~の続きです。

「月氏(がちし)ってなぁに?
 」
」 ひよこさん。「月氏」。一度こんな記事に登場していますよ。
ひよこさん。「月氏」。一度こんな記事に登場していますよ。
のんきの宗教観~外伝。
ガンダーラ王国そのものは、紀元前6世紀ころから存在したらしく、ガンダーラが最も繁栄
するのは、イラン系遊牧民族の「月氏(がちし)」がインドに築いた王朝、「クシャーナ朝」
の時代。「月氏」が漢字表記になっていることからもわかるように、月氏とは、始皇帝の時
代の中国史にも登場する民族です。
中国と月氏との出会いはというと・・・。
時代は紀元前2世紀。漢の時代。武帝という皇帝が、張騫(ちょうけん)という人物を同盟を結ぶために、この「月氏」のもとへと派遣したことがそのきっかけ。
当時の月氏は、「匈奴(きょうど)」という民族と敵対していて、この匈奴に敗れた月氏は、北のほうに逃れていました。中国では、このころの月氏のことを、
「大月氏」と呼んでいました。
漢はこの「匈奴」を挟み撃ちにするためにこの月氏に張騫を派遣したのです。
さて。この月氏という民族。いわゆる「遊牧騎馬民族」で、実に八尺(2m40cm)を超える身丈の馬を駆使していたのだとか。
当時の中国で利用されていた馬は、「蒙古馬」という種類だったのだそうです。蒙古馬。日本の在来馬もルーツは蒙古馬にあるそうですから、こんな感じでしょうか。

一方、月氏の馬はこんな感じでしょうか。

さて。この月氏の馬を見た漢人たちの驚きたるや、なかったかのではないでしょうか。
そしてさらに、月氏の言葉で言う「馬」の発音と、漢語の「龍」の発音は、とてもよく似ていたのだといいます。
このことから、漢人たちの間で、「西方に龍を駆使する民族がいる」といううわさが瞬く間に広まります。
そして、このころから、中国では「龍」を描くとき、それまで「蟲」をモチーフとした「龍」から、月氏たちの駆使する「大形の馬」をモチーフとした龍に、
その描かれる姿は大きく変化するようになりました。

さて。改めて見てみると、ちょいと「馬」っぽくないですかね。

やがて、月氏は再び匈奴に追われ、西方へと遠ざかっていきます。漢人たちはあの大形馬接触することはなくなり、やがて大形馬をモチーフとしたまま、
漢民族の中で、「龍」は独自の発展を遂げていきます。より大きく、より煌びやかな姿へと・・・。
さて。それでは改めてタイトルにある設問。
「十二支にはなぜ龍が存在するのか」
これは、つまるところ、華夏族の有していた「トーテム信仰」がそのルーツとなっているのではないかと思います。
「龍」だけではありません。古代中国では、「猪」「鳥」「蛇」「羊」「虎」「牛」もすべて神聖な生き物として崇拝され、また生活に根差した存在でした。
「龍」はそういった神聖な動物たちの象徴。伏羲によって、「人間が喜ぶ生き物」として「馬、蛇、鳥」のキメラとして生み出された「龍」。
さて。シリーズ、「十二支にはなぜ龍が存在するのか」。いかがだったでしょうか。
改めまして、本年一年が、何よりもこの国に住むすべての皆様にとって素敵な一年となりますよう、心よりお祈りいたします。
日本の未来は明るい!!
 |









帰りしにクリックを・・・

あなたの1票が、のんきのブログを沢山の方に知っていただく力になります^^














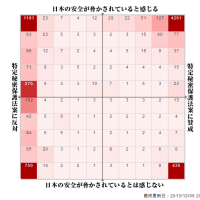

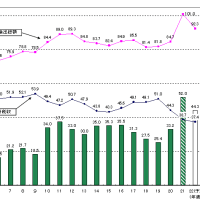
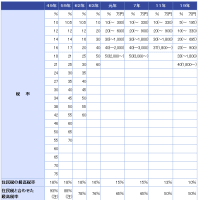
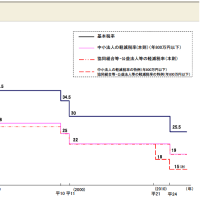
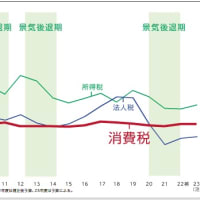
ごあいさつが遅れましたすみません。
今年もよろしくお願いいたします。
龍の記事(過去記事も含めて)興味深く読まさせていただきました。
私は龍の元は「わに」だったという説を聞いたことがあります。
昔は日本や中国にもワニが生息していたそうです。なんか、証拠の品が出ているようです。
因幡の白兎に出てくる「フカ」も、実はワニだったそうです。
でも、顔がワニ、は馬より納得しませんか?
ます。
なるほど。「龍」もベースは爬虫類っぽい
ですから、ワニのほうがしっくりきますね^^
証明しようのない古代の出来事だけに、
いろんな考え方があると、夢が広がって
面白いですね。