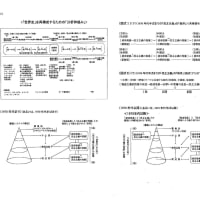「在沖米軍基地」の中に、あるいはその背後に「覇権システム」の存在をどれだけ感じられるか、想像できるか、それが肝心な問題である。
前回は久しぶりに昔の私を思い出し、いろいろなことが脳裏をよぎり、オーバーに言えば、私がたたかってきた、格闘してきた「相手」の姿がまた眼前に現れ、そのためか少し熱が入ってしまった。とにかく「壁」は厚く、「そんなものにやられてしまうか」とずっと歯を食いしばり書き続けてきたこれまでの私を思い出した次第だ。
三谷太一郎(以下、敬称略)の「ワシントン体制」と「日本外交」の関係を考察した論文にも端的に伺われるのだが、篠原一や猪口邦子の著作もそうだったように、彼らは「覇権システム」を論じながら、それもすぐその横の、あるいは前後のくだりで「民主主義」に関しても言及しながら、何故か不思議なことに両者の結び付きについては、まったく触れることなく、論を展開していたことを思い出した。(以下の段落は後からの追加)
それはわかりやすく言い表せば、よく時代劇に出てくるように、一方ではやくざの親分でありながら、他方では庶民の暮らしを守る十手持ちを演じるといった二律背反的な仕事を同時にこなしているという構図である。覇権国の親分が力に任せて他の子分の動きを監督・統制しながら、同時にまた覇権システムという「組」の構成員たちの自由や平等、人権、法の支配、平和といった普遍的価値の実現に関わるといった具合だ。本来ならばおかしな話だが、これがおかしくならない、おかしくさせない何かが働いている空間に私たちは生きているのだから、やはりおかしいことではあるまいか。ところがそうでもないのだ。〈「大英帝国」下の「デモクラシー」〉という小見出しで両者の関係をそのまま受容しながら、何のためらいもなくイギリス政治史を語る研究者は大勢いるのだ。先の篠原もその一人だ。藤原の以前紹介した著作のタイトルは『デモクラシーの帝国』であったが、こうした点は一体、何を物語っているのかを是非とも想像してほしいところだ。
さらに覇権システムを論じた際も、淡々とその概要に触れるだけで、それが抱え続けてきた「衣食足りて(足りず)礼節を知る(知らず)」の営為の関係に見られる世界的な差別と排除の関係(構造)と、そこから導き出される不条理な世界の有り様、すなわちもっとわかりやすい今日的表現を使うとすれば、それはまさに「イジメ」の関係であろうが、そうした問題には、さほどの興味もないかのような通り一遍の語り方であったことを再確認したのだ。付言すれば、そうした態度はどこか似ているのだ。いじめに苦しんでいる力の弱い人間達が抱えている生活上の苦悩に関して、嘘でもいいから思いやるそぶりさえ感じられない現代の支配層のエリートたちを連想してしまうのだ。
私はいまだにそれが、そうした態度が解せないのである。なぜもっと掘り下げた分析を試みないのか。中心ー半周辺ー周辺から成る関係からつくり出される数々の問題を、すなわち差別や排除の関係から導き出される問題を、自分自身も自分の周りの他人との間でそうした関係に巻き込まれ巻き込みながら、苦しい思いをしながら生きている、生きていかざるを得ない一人の人間としての生き方とその辛さや惨めさを、何故もっと「想像」できないのか、と彼らの著作を介して何度も感じた次第だ。
そんな昔の思いを噛みしめるとき、やはり悲しいと言うか、辛くなるのだ。なんでこんなたわいのない(おっと失礼、私も世間様からは同じように思われていることは自覚している。改めて言うことではないが、念のため。)著作がさももっともらしく読まれるのだろうか、と。同時に、逆に改めて普遍的価値の「(社会的・文化的)ヘゲモニー」の強固さ、強大さに圧倒されてしまうのである。そうした普遍的価値とそれをつくり出すシステムとその関係の歩みを、何ら疑うことなく受容させ続ける著作物の前に、私はただ無力を感じるばかりだが、それだけではやはり終われないと思うのだ。普遍的価値とそれが抱える「宿あ」を、批判的に考察できる地点まで到達させない、辿り着くのを妨げるように、私たちの思考上の「煙幕」として、理想主義や現実主義に関する議論が交わされてきたのではないか、と私はこれまで考えてきたのだ。
E・H・カーは大英帝国の外交官であったし、W・チャーチルは、大英帝国の英国の首相であった。それゆえ、彼らの著作や発言に接する場合には、相当に注意しながら、突き放せる距離を保ちながら付き合うことが必要だろう。
私たちは第2次世界大戦に至る一つの大きな流れとして、第1次世界大戦後の理想主義外交をやり玉に挙げるが、不思議なことにその時期の矛盾に満ちた不合理、不条理な世界の仕組みというか関係を、例えば大英帝国という存在に象徴される帝国主義関係としての覇権システムの世界と資本主義世界と民主主義世界の関係がつくり出す差別と排除の関係から、戦争へと至る歩みを考察しようとは試みなかった。つまりそうした舞台に生きているという問題それ自体を不問に付した格好であった。それを例えて言えば、海洋に浮かぶ氷山の海面上の姿だけを捉えて、やれ理想主義外交が世界を戦争の渦に巻き込んでいった、現実主義外交であったら結果は異なっていたかもしれない云々、と述べたのである。
同様に、「冷戦」崩壊後に誕生した米国のクリントン大統領政権下での理想主義外交の展開が、米国それ自身の国力を低下させることで、世界の警察官としての米国の威信を低下させ、そこからまた世界各地の紛争や地域戦争が導かれることとなり、それが結局は世界を混乱に巻き込んでいったとの見方が論壇やマスコミにおいて支持を得たが、ここでも1970年代以降における世界とそれが抱える問題を直視するまでには至らなかった。逆に冷戦時代の現実主義外交の方が、世界の「平和」と「安定」に貢献していたとする見方が常識的だとされたのである。こうした見方は、第1次世界大戦前の時期を「百年にも及ぶヨーロッパの平和」として、第1次世界大戦から第2次世界大戦へと至る両戦間期に見られた不安定な世界と武力的衝突として顕在化した世界大戦の時代と比較しながら、そうした「平和」の背後に国力や国益とか勢力均衡の原則を重視した現実主義外交の展開を肯定的に評価する声が支持を得たのである。
これらの理想主義や現実主義を論じる中で、私が何度も述べてきたように、それこそ「平和な民主主義」社会の実現のために「勝ち(負け)続けなきゃならない」世界をつくり出す帝国主義的覇権システムを前提とした「衣食足りて(足りず)礼節を知る(知らず)」の世界的営為の関係に見られる差別と排除の仕組み(構造)を俎上に載せることはなかったのである。換言すれば、1970年代までの{[A]→(×)[B]→×[C]}、70年代以降の{[B]→(×)[C]→×[A]}のモデルで描かれるシステムとその関係の歩みが抱え続けてきた「宿あ」を真正面から考察することはなかったのである。
本来ならば、こうしたシステムとその関係の歩みの中で、それこそ勢力均衡の原則とかヨーロッパの百年にも及ぶ長い平和」や「安定」といった問題を捉え直すべきなのだ。これに関連して言えば、藤原の「レター」記事で提起されていた問題は、システムとその関係の歩みとしてのセカイの歴史を舞台として、その枠の中で、それを前提として考察されなければならないのだ。私たちが生きている、生かされている歴史の制約性を何ら認識しないままで、理想主義や現実主義に関する論点を提示したとしても、ほとんど意味のない話で終わってしまう、と私は考えるのだ。
また前置きが長くなったが、これらの点を踏まえた上で在沖米軍基地問題に、もう一度戻ってみたい。すぐ上で紹介したモデルを念頭に置いて話すならば、モデルで描いた関係の中に、在沖米軍基地を置き直してほしいのだ。あのA、B、Cの、またB、C、Aの関係の中に、である。ここで注意しなければならないのは、「在沖米軍基地」というとき、そこには、米国が含まれているということだ。つまり、70年代以前の米国は、覇権国家としての米国でもある。戦後の日本は、敗戦後しばらくはGHQの占領下にあったので、Cに位置していたが、サンフランシスコ平和条約以降は、Bに、そして65年以降はAにそれぞれ位置付けられる。沖縄は72年に復帰するまでは米国の施政権下に置かれている。
70年代以降の米国はシステムとその関係の歩みの中で次第にその地位を低下させていくが、日本の位置も同じように低下していく。すなわちB、C、Aの関係の中で在沖米軍基地、覇権国であった米国と次期覇権国として台頭するBグループの国家との関係を見なければならない。いずれにしても、在沖米軍基地は、その「基地」の中に、あるいはその背後に覇権システムを抱え込んでしまうことにならざるを得ないことを、銘記しておかなければならないのである。このくだりは、少し違和感を覚えられても仕方のない物言いである。というのも、覇権システムの中に沖縄米軍基地があるという見方は、おそらくわかりやすいかもしれないが、それにもかかわらず、米軍基地を抱えるということは、基地を介して直接基地の中に主権国家、国民国家としての米国と、覇権国家としての米国とその世界戦略を抱えるということを意味している。また覇権国家の米国を抱えることは同時に、覇権国としての米国の指導・監督の下に、米国を先頭として、その他の中心国、半周辺国、周辺国から構成される覇権システムを、基地が抱えてしまうということを同時に意味しているということなのだ。
それゆえ、基地問題を語るということは、沖縄、日本、米国の問題と同時に、覇権システムを考えなければならないということにもなるのである。そのことは、ただ単に基地を沖縄から移転すればそれで済むということを意味しないということなのだ。逆に、基地を米国の意向に沿うままに、沖縄に据え置いておけばそれで済むという話にもならないということなのだ。ところが、私たちの基地問題を巡る議論は、覇権システムの問題を俎上に載せるまでには至らないままに、今もそうなのである。本当に悲しい話だが、サンゴ礁とか杭打ちとかその地盤がどうだとかの、なんの罪もないサンゴ(礁)には悪いのだが、二の次、三の次の話でお茶を濁すことに終始しているのだから。そこに暮らしている人間を守れないのに、どうしてサンゴ礁や環境保全の話題を口にできるのだろうか。(この個所のくだりは少しおかしな論理の展開がみられる。やはり人間中心史観だ。別に自然は人間が存在しなくてもそれなりに自然を維持していくだろうし、むしろ人間存在により自然の破壊の方が問題だというのはこれまでも私たちが経験したことである。それは確かにそうなのだが、一度破壊された自然を「回復」するには人間の力が必要だということにならざるを得ない。その再生なり保全を試みる人間は「自然を守れ」と自然を破壊した人間に向かって抗議しても、それは有効な抗弁にはなり得ない、と私は考える。それゆえ、舌足らずであったが、先の記事ではそのような趣旨を述べたつもりだった。それをここで断っておきたい。)これはまた、憲法や第9条の話にも関連している。私たちの生存を確保できないような空間で憲法や人権がどうのといってもおかしいだろう。飯が食えない人間を前にして、法の支配とか立憲主義を説いても駄目だろう。まず腹を満たして、命の生存が保証されて、初めてそこから先の話となるのではないか。国会議員の先生は十分にみの安定が、生活が保障されているから分からないのだろうが。またつまらない話をしてしまった。
覇権システムを前提にして基地問題を語るならば、そこから「衣食足りて(足りず)」の営為における世界資本主義システム関係に、また「礼節を知る(知らず)」の営為における世界民主主義システム関係に、さらにそうした三つの下位システムから成る一つのシステムとその関係の歩みに、私たちは在沖米軍基地問題を介してたどり着けていたはずではあるまいか。もしそうであったならば、おそらく私たちはもう少しだけ賢い議論ができていたはずだ。ごめんなさい、また上から目線で。今回はここまで。前回の続きにいけないままで残念。