さて、アルフィーの名誉卒業式ご招待に当たらなかった私だが、
当たらなかったけど、当日同じ時間に明治学院に行ってしまおうかな~、と思いつき、
大学サークルの後輩、コムに相談してみたところ、もうちょっと考えてみてね、と言われて、即刻思いとどまった、
という話を前回書いた。
それで、その代わりに、思いついた 「別のいいこと」 というのは、卒業式とは別の日に、明治学院大学に行ってみよう

つまりは、“聖地巡礼” である。
そのことについて触れる前に、ちょっと寄り道ではあるが、自分の人生にとって大切なひと駒について書いておきたいと思う。
ちょー、ナガイです・汗。 スミマセン・・・ お覚悟を。


前回にも書いたが、明治学院というのは THE ALFEE のメンバーだけでなく、我が郷土 「K谷」 が生んだ作家、島崎藤村の母校でもある。
島崎藤村は、K出身の作家であるというただそれだけで、子供のころから尊敬していたが (小学校の時の遠足で、今は岐阜県N市になってしまったが、M宿にある 「島崎藤村の生家=藤村記念館」 にも行ったことがある)
子どもでも読める童話や詩くらいしか読んだことがなく、
ちゃんとした小説を読んだのは、高校の現国の教科書に載っていた 『桜の実の熟する時』 が最初である。
確か、高校2年生くらいだったと思うが、とても感動して続きが読みたくなった。
その後、『春』、『新生』へと続く、藤村の自伝的小説・青春三部作を、
そして『家』、『ある女の生涯』 などK谷を舞台とした小説を、大学にかけて読んだように思う。
『桜の実の熟する時』 は、自分の藤村文学への入り口の作品でもあり、
当時、まさに伸びていこうとしてもがいている主人公の気持ちが痛いほどよくわかったので、青春の象徴であるかのような美しいタイトルとも相まって、忘れならない小説なのである。
その後、島崎藤村という作家の、私生活、血筋などを知るうちにちょっと驚いたりはするのだが、
そして、普通だと、作品が良ければ人間性や私生活は別物 (どうでもいい) という人もいる中、私はそうは思えないタチの人間なのだが (人間的にも素晴らしい人でなければ尊敬できない)
藤村だけは、それを許そう (エラそうですみません) と思える人物である。
それだけ、作品に傾倒している (とりわけK谷のことを書いたものは身につまされる) ことや、多分にK出身、ということに対する肩入れであると思うが。
話を戻すが、その、『桜の実の熟する時』 は、
10歳で兄と郷里Kを後にし上京した藤村が、泰明小学校卒業後、三田英学校、共立学校などを経て、16歳で明治学院普通部本科(明治学院高校の前身)に入学。
同じクラスだった戸川秋骨、馬場孤蝶らとの交流や、のちに北村透谷から強く受けた刺激など、次第に文学を目指すようになって行く頃の、青春のみずみずしさに満ち溢れている。
本書には文学を志すことへの苦悩と青春の憂鬱、恋愛への憧れと挫折なども書かれているが、自分自身は読んだのが高校のころだったので、その辺のところはあまり覚えていない部分もある。
さて、アルコンに復帰し始めて間もなくの2009年、マニアから届いたアルフィーの57枚目のシングル発売 (その年の5月13日) のお知らせを見て驚いた。
タイトルが 『桜の実の熟する時』 だったのである。
アルフィーのメンバーの母校が明治学院大学であることも、高見沢が同じ明学出身の島崎藤村のことを尊敬していて好きな作家であると言っていたことも知ってはいたが、
まさかその藤村作品の中でも、最も自分が好きである 『桜の実-』 と同名の曲を作ってくれるなど夢にも思わなかったので、それを見た途端、胸がきゅうん、となった。
そして、発売を心待ちにしていたものだが、
テレビ朝日木曜ミステリー 『京都地検の女』 第5シリーズ主題歌である同曲が、だいぶ自分の思っていた 『桜の実-』 とは歌詞の雰囲気が違うような気がして、最初はちょっとがっかりした。 (きゃータカミーごめんなさい)
のちに、マニアの会報か何かで読んだのだと思うが、この曲は、高見沢がまず小説のタイトルに惹かれて、いつか曲にしたいと思っていたこと、
そして小説の中に出てくる明治学院の周りの風景などが自分にも思い当たることがあったので、それが強く印象に残っている、というようなことを語っていたと思う。
もっとも自分の読んだのは高校のころで、この中に描かれている恋愛のことなどについてはよくわかっていなかったと思うし、自分が感銘を受けた青春のみずみずしさや、延びていきたい思いなどは、曲にするのは難しいだろうと思う。
また、文学に限らないが、作品というのは読んだり見たり聞く人によって、その人の感じ方でどのようにとらえてもいいので、こうであるというものは全くない。
そう思って自分のイメージを抜きに聞いてみると、桜の花びらが舞い落ちるがごとく、一片の小説や詩の断片であるかのような歌詞が、しみじみと人生を思わせる美しい曲であり、大好きになった。
ミステリーというのは結局のところ、人間の哀しい運命を背負っているので (事情があって人を殺してしまったりするので、そこに主人公の哀しい過去を見るので) ミステリーの主題歌にも似つかわしい。
何より、自分の大好きだった青春の書と同じタイトルで、同じ小説からイメージされた曲であるということ、
タカミーも、曲にしたいほどこの小説が好きだった、ということほど嬉しいことはない。
* * * * * * * * * * * * * * *
もうひとつ、高見沢の作ったというよりアレンジした曲で衝撃を受けたものについても書いておこうと思う。
2010年に、前の年2009年に行った 「Takamiyソロコンサート」 のDVDを見て、ソロTakamiyにすっかりホレ込んでしまった自分が、
2007年、2008年とさかのぼってソロコンサートのDVDを見てみたこと、
そしてついにその年の8月26日、Takamiy ソロコンサート・デビューをした、ということは以前書いたが
( 【 百聞は一見にしかず ~ 『高見沢俊彦・Fantasia(ファンタジア)』 】 2010年08月28日 | THE ALFEE & Takamiy カテゴリー 参照 )
その、TakamiyソロDVDを見ていた時、それは起こった。
それは2008年のコンサートの時のもので、タカミーがMCで、
「映画や小説など色んなものにインスパイアされてできる曲がある。この曲は、僕が大好きな詩を “メタル” にアレンジしてみました。」
タカミーの好きな詩というと、ハイネとかリルケとか、よく知らないけど、とにかく外国の詩人のものなんだろうなー。とっさに思った。
「あの曲がこうなるのかってね、・・・もちろん、本人には許可を取ってあります・笑。」
 ええっ
ええっ  そんな詩人が、いま生きてるワケが・・・
そんな詩人が、いま生きてるワケが・・・と思っていると、
イントロを聞いて体中に電流が走った。

だってそれは、大好きな曲だったから。
もう何年も聞いていなかったけど、イントロだけですぐにわかった。
さだまさしさんの 『まほろば』。
あとはもう、涙、なみだ。












タカミーとさだまさしというのは、全然イメージが付かなかったので、まさか、という思いと、
さだまさしさんは、アルフィーに出逢う前、高校3年くらいから、大学にかけて大好きで、グレープ時代 (さかのぼってだが) から81年の 「うつろひ」 までの9枚、全アルバムを出るたびに買い求め、カセットに録音しては繰り返し聞くほど傾倒していたアーティストだった (特に、古典文学や漢詩を思わせるような詞の世界観が大好きだった(注:1) ので・・・
それほど好きだったアーティストの、その中でも上位に入るくらい好きな曲を、タカミーも大好きだったという驚きと衝撃。
そして感動にも似た喜び。
「まほろば」 は、
シンガーソングライターさだまさしのソロ4枚目のオリジナル・アルバム 『夢供養』(ゆめくよう)(1979年4月10日発表) の中に収められている。
歌の舞台は奈良の春日野で、万葉集をモチーフに男女の心のすれ違いを描いているが、
自分の当時大好きだった奈良の情景と、古典文学的な言葉の言い回し、そしてさだの詞に多く描かれている人の世のむなしさや切なさを無情なまでに見事に切り取っている世界観、曲の持つ美しさと、さだの冴えわたる月のような、また突き抜ける青空のような、澄み切った美しい声が無常観を駆り立て、圧巻の一曲。
ちなみに、猫田は大学で国文学を専攻し、日本の児童文学の自主ゼミを作り、最終的に日本の児童文学を卒論のテーマとして選んでいるが、実は 『万葉集』 ゼミにも2年間入っていた。
万葉集が大好きで、ゼミ旅行で奈良、飛鳥地方を訪ねてもいる。
大学を選ぶとき、奈良の方の大学へ進んで、史跡を訪ねたり研究しながら4年間を過ごしてみたい、という思いもあったくらい、奈良が大好きで、その当時の歴史や古典文学にのめりこんでいた。
ついでながら、受験する大学を決める時、大好きな、あこがれのさだまさしさんが行っていた (中退で、実際はほとんど行ってなかったそうだが)、 という理由だけで 「國學院大學」 もいいなぁと思っていた。(ちなみにさだは、高校は國學院高校を卒業している。)
大学の特色がどうだったかは忘れたが、なんとなく国文学が盛んで、日本色も強いように思えたというのもある。(字も旧仮名遣いだし)
また、「二松學舎大學」 にも似たような理由からちょっと惹かれていた。
それで、両大学の大学見学にも行ってみたことがある。
もっとも、当時は今のような入学希望者のための見学や説明会などを含めた 「オープン・キャンパス」 なんてないから、自分で勝手に行っただけで、
その時、埼玉の某女子大では、守衛さんに見学の由を告げると、学校内部を少し見せてくれたりしたが、國學院と二松學舎は、大学の建っている場所まで行って、遠目に眺めて、あれがそうなんだな、と確認しただけで帰ってきた。
大学の建っている場所があまりに都会の真ん中のビルの中 (渋谷区と千代田区) という気がして、こんなゴミゴミしたところで勉強するのはやだなぁーと思ったせいもある。 (もっとも、自分の出た大学に初めて面接に行ったとき、建っているのがあまりにも田舎で、せっかく東京に出てくるのに、こんな田舎に通うのはやだなぁーとも思ったものだが。我がまま(笑))
だが本当のことを言うと、自分は推薦入学で大学に入ろうと思っていたので、「受験」 では無理だとあきらめていたのが一番大きな理由で、これらの大学には推薦入試制度はなかった。
このように、高校から大学にかけて、島崎藤村とさだまさしさんが大好きで傾倒していた私だが、
そういえば島崎藤村が出たという理由で、明治学院大学 (当時は高校で藤村は第一期卒業生) にも憧れていて、行ってみたいなという気持ちはなくもなかった。
だが先ほども書いたように、自分はあくまでも推薦入試でしか大学には入れないとあきらめていたので (レベルがちょっと低い高校だったので、自分のようなものでもいい成績が取れた。その高校を選んだ理由は多々あったが、推薦入学も狙っての高校撰びであったし、そのため3年間勉強は、生涯の中で最高と言ってもいいくらいめちゃくちゃやっていた) 明治学院も入れるわけはないわなぁーと思っていたのと、
自分、國學院とか明治学院、青山学院とかの 「学院」 という響きへの憧れや、ミッションスクールに対する憧れが全くなかったわけではなかったが、
どちらかというと、仏教や神道の方に興味があって、仏教系や神道の大学もいいなぁーと思っていた (注:2) ので、キリスト教にはほとんど興味がなかった。
国文学、古典、日本史、漢詩、仏教、神道などの日本的なものが好きだったのである。
ちなみに、当時は尊敬する島崎藤村の母校だったので明治学院というものに興味をひかれたが、
せっかくアルフィーが自分が中学2年のころデビューしていたのに、大学受験のころはまだ存在を知らなかったので、アルフィーの母校だから明学に興味があった、ということは全然なかったのが、今思うと非常に残念である。
余談ついでに、最近知った新事実
 で、タカミーがNHK・FMラジオ 『終わらない夢』 で桜井さんと、なぜ明治学院高校を選んだかについて話したことがあって、
で、タカミーがNHK・FMラジオ 『終わらない夢』 で桜井さんと、なぜ明治学院高校を選んだかについて話したことがあって、タカミーが中学の部活で夢中になってやり、そうとう入れ込んでいた 「バスケットボール」 で、中3の時の大会で大きな挫折を味わい、
その後の人生を大きく変えたことは、メンバーやファンならだれでも知っていてつとに有名なことだが(後述)
その挫折があったからこそ、高校で音楽にのめりこんだというのと、
もうバスケットはやらない、高校は、自分がバスケットをやっていたことなど誰も知らない、どこか遠くへ行こう、と決め、
「実は國學院にも興味があったんだよ、国語が好きだったから。でも、子供だったんだよね。 (高校のあったのが) 品川だったから、家 (埼玉県蕨市) から、できるだけ遠くへ行きたかったんだ。」
( のちに、さだまさしさんとの対談で、國學院高校を受験し合格していた、とまでおっしゃってましたので、ホントの話だったんだぁ~とビックリしましたっけ・笑。 )
と、明治学院を選択したということだった。
ここでまた、びっくり。


大学ではなく高校ではあるが、タカミーも國學院がいいと思っていたなんて、初耳であった。
そして、自分が強く行きたいと思ったことのある学校にタカミーも行きたかっただなんて、何だか妙に嬉しかったものである。


(まさかタカミーも “学院” てつくのに憧れてたりしてね・笑)
が、しかし、日本史が大好きで国語も好きだった (本人弁。ちなみに中学の校長だったタカミーのお父様は国語の先生で 『万葉集』 をこよなく愛していたという。なので家には難しい本や辞書などが沢山あり、幼少より本好きだった高見沢の将来の夢は、父親と同じ教師か作家や漫画家であったともいう ← ここでまた、共通の箇所を多々発見して喜ぶ自分・笑) というのに、
タカミーよ、ナゼに大学で英文科を選ぶか



 のちに知ったことであるが、明学の文学部は、英文とフランス文学だけで、 「国文科」 というものがなかったのだった。
のちに知ったことであるが、明学の文学部は、英文とフランス文学だけで、 「国文科」 というものがなかったのだった。  びっきゅり
びっきゅり 
文学部に国文ないトコがあるなんてね、国文(日文)なんて、どこでも必ずあると思ってたよ。さすがはミッションスクール

ま、タカミーは高校時代ロックに傾倒していたので、当然のことイギリスやアメリカに対する憧れはあったと思うし、
中、高とあまり英語は好きでなかった自分でさえも、当時好きだった映画音楽やレターメンというグループの歌う曲の歌詞などをノートに書き写しては、辞書を引きひき、一生懸命日本語訳を自分なりに書いてみたりしたくらいだから、
大好きな曲の意味を知りたい、というのは誰にでもあるかもしれないし、
また当時は英米文化に対する憧れというものが、国民全体的に流れていたと思うので、そんなこともあってかもしれない。
 と、ゆーのは、あくまでこの記事を最初に書いた当時、私が勝手に想像していたことで、
と、ゆーのは、あくまでこの記事を最初に書いた当時、私が勝手に想像していたことで、のちにご本人がラジオで語っていたところによると、自分は英語がちょっと得意だったということ、それから当時はまだ珍しかった社会学部の社会福祉科というのにも興味が引かれたが、進路指導か何かの先生に、もしも将来教師になるのなら、英文科の方がいいぞ、(社会福祉科では)つぶしがきかないぞと言われ英文科に決めたと言ってました。
なんだ、意外とフツーの理由・笑。
それでも面白いのは、作詞家としてのデビューがアルフィーに提供した曲だった (1981.10.21 『言葉にしたくない天気』) ことから、それ以来の付き合いだという、今を時めく作詞家の秋元康いわく、
「高見沢さんはロッカーなのに厄落としに神社に行くような可愛いところがある・笑。」 らしい。
キリスト教も含めた西洋音楽と西洋文化に強い憧れと興味を持っている (ゆえに、知識もすごい) のに、日本史や仏像も大好きだ (中でも大好きな 「阿修羅像」 を歌った曲も作っているほど)、
西洋も日本古来のものもどちらも大好きで、どちらも似合う、という面白さを持っているのが高見沢俊彦であると思う。
ちなみに、私に至っては、日本の文化、歴史、言葉、仏教、名所などは大好きだが、
西洋のものは、ごく幼少期を除いては、言葉も文化も宗教も場所も、ほぼ今も昔も興味がほとんどない・笑。
( 高校のころは、将来は社会科の先生になりたいと思うほど、実は国語よりも社会科全般の方が好きだったので、世界史も世界の地理も、そして倫社に出てくる西洋の思想も好きではあったが、興味があったのはその当時だけだったようだ。今では、語学が堪能になりたいとか、外国旅行に行ってみたいなどという興味がほぼ皆無である。 )
なんだか話がまとまらなくなってきたが (アンタの興味のことなんてどーでもいいってか!? ごもっともで・笑
 )
)話のついでに、自分、高校の時に将来なりたい職業が二つあり、一つは高校の日本史を主に教える社会科の先生と、童話作家であった。
なので、受験する大学を決めるときに、史学部にするか文学部にするか、相当悩んだ。( 受験する時には、何学部の何学科まで決めて受験しないとならないため。大学によっては専攻まで決めるのかどうかわからないが、自分の出たW大は専攻は入学後に決めていい仕組みになっていた。 )
それで、やはり子供のころからの夢だった 「物を書く人になりたい」 という方が大変不確かな夢ながら勝ったので、文学部の方を選んだ (厳密にいうとW大は人文学部) のである。
もしも、先に書いた大好きな奈良の大学の史学部を選んでいたら、自分の人生は全く違うものになっていたかもなぁーと思う。
でも、東京にも憧れが強かった (といってもファッションや流行や遊びという方ではなく、
東京は日本の学術文化が最も高い水準にある
 と信じていたからで、そういうところで勉強がしたかったのだ、
と信じていたからで、そういうところで勉強がしたかったのだ、と大卒後だいぶ経ってから、当時を振り返って言ったら、東京生まれの文学仲間にそれ
 は言いすぎだと思うなー、と笑われたが、この田舎者の気持ち、東京の人にはわからないと思う) ので、
は言いすぎだと思うなー、と笑われたが、この田舎者の気持ち、東京の人にはわからないと思う) ので、結局最後には東京が勝ったのだ・笑。
というわけで、いささか余談が過ぎたが、私が島崎藤村とさだまさしさんにいかに傾倒していたか、
また、現在最も尊敬していて大好きなタカミーとの共通点を、単に色々と揚げてみたかっただけであるが、

そういう下地を踏まえておいていただいて・・・、
次回はいょいょ、聖地巡礼、いざ出発編です。




きゃー、 ここまで来るのに、ちょー長すぎるワ








【 補足 】
というより、蛇足
 (上の「注:1、2」をまとめて書きます)
(上の「注:1、2」をまとめて書きます) 自分が仏教に興味があったのは、幼稚園がお寺の経営するところだったので、通った3年間、毎日お弁当の前に 『延命十句観音経(えんめいじっくかんのんきょう)』 をみんなで唱え、合掌して 「いただきます」 と言っていたことや、お釈迦様の誕生日の花祭り (4月8日) を祝うなどして、仏教が身近であったこと (園長先生もそのお寺の住職さんだったし)、
自分が仏教に興味があったのは、幼稚園がお寺の経営するところだったので、通った3年間、毎日お弁当の前に 『延命十句観音経(えんめいじっくかんのんきょう)』 をみんなで唱え、合掌して 「いただきます」 と言っていたことや、お釈迦様の誕生日の花祭り (4月8日) を祝うなどして、仏教が身近であったこと (園長先生もそのお寺の住職さんだったし)、確か幼稚園の頃だったと思うが、家に 広隆寺の『弥勒菩薩』の仏頭(お顔の部分)像が来て、以来2階の自分の部屋の隣の柱にずっと飾ってあったので、 「広隆寺の弥勒菩薩さま」 をいつか見に行きたいものだ、とずっと思って育ったというのもある。
長くなるので、別項目にていつか詳しく書きますが、知り合いの美術教師が作った? ものを譲り受けたということだったので、親がほんとに欲しくて手に入れたものかどうかはわかりませんが、身近に仏像があり眺めて育ったというのは大きいかも。
それから中学の時、K郡内の禅宗のお寺が主催している 『少年禅道会』 という、夏休みに2泊3日でお寺に寝泊まりして、座禅を組んだり写経をしたり、お経を読んだり説法を聞いたり、禅にのっとった食事をしたりする行事に、
最初は母の 「あんたは怒りっぽくて修行が足りんから、禅道会でも行って修行してきなさい。」 という勧めに、それは言えてるかも、と割と素直に行く気になったのだけど (ちょっとおもしろそうだったし)、
参加してみたら、3日目の最後に “3年間皆勤で出席すると座禅の時に肩や背中を打つのに使う 「警策(けいさく)」 という棒のミニチュアがご褒美にもらえる” らしいとわかり、それ欲しさに頑張って3年間通ったこと、
あとは、中学、高校の修学旅行で仏像について勉強し、実際にお寺を見て周りながら仏像に触れ、寺や仏像が一層好きになったこと、などの理由による。
また、中学3年からNHKの大河ドラマにのめりこんだことから日本史好きになり、日本史と仏教やお寺は深くかかわっていたことにもよると思う。
その後社会人になってから、全くの偶然であるが、知り合いの児童文学評論家で、全国同人誌連絡会事務局を兼ねていた大岡秀明さん(故人)がたまたま寺の住職で、彼の家であるお寺の寺務員 (早く言えばお手伝いのようなもの) として、家業を除く自分の過去の勤務史上最も長い4年間、そのお寺に勤務していたこともあるので、縁というものは不思議なものである。
 神道に興味を持ったのは、高1の時の大河ドラマ 『花神(かしん)』(司馬良太郎作 『花神』、『世に棲(す)む日々』 などの5作品が原作) の影響で、吉田松陰に傾倒するあまりに、意味もよく理解しないままに 「尊王攘夷」(そんのうじょうい・天皇を敬い外国を俳する) の思想にかぶれたため、天皇は神であると一時期本気で信じたことがあったため。 (あー、不覚だわ)
神道に興味を持ったのは、高1の時の大河ドラマ 『花神(かしん)』(司馬良太郎作 『花神』、『世に棲(す)む日々』 などの5作品が原作) の影響で、吉田松陰に傾倒するあまりに、意味もよく理解しないままに 「尊王攘夷」(そんのうじょうい・天皇を敬い外国を俳する) の思想にかぶれたため、天皇は神であると一時期本気で信じたことがあったため。 (あー、不覚だわ)それが大学で全く逆の思想に影響されることとなるので、今思うと、この、何でものめりこむタチというのは、空恐ろしい。
当時は、神道を学ぶ大学というのは神主の子息が行く、神主を育てるための大学であることさえも、よくは知らなかった。
 タカミーが、実はさだまさし好きだっという話は、2013年3月のNHKテレビの 『今夜も生でさだまさしスペシャル~朝まで生で音楽会』 という、さだまさしさんの取り仕切る、深夜から明け方にかけての5時間にも及ぶ超ロング・トーク音楽会にアルフィーがゲストで出たときに言っていた。
タカミーが、実はさだまさし好きだっという話は、2013年3月のNHKテレビの 『今夜も生でさだまさしスペシャル~朝まで生で音楽会』 という、さだまさしさんの取り仕切る、深夜から明け方にかけての5時間にも及ぶ超ロング・トーク音楽会にアルフィーがゲストで出たときに言っていた。それまでもアルフィーとさだとの交流は深かったが、
『まほろば』 をメタルアレンジにしてTakamiyソロコンサートで単独演奏したり (2008年8月17日、私がDVDで見たもの)、
さだまさしのデビュー35周年を記念して製作されたトリビュート・アルバム 『さだまさしトリビュート さだのうた』(2008年10月22日、ユーキャン、販売はユニバーサルミュージック) に、 「まほろば」 を高見沢アレンジ、歌 THE ALFEE として参加しているなどしていたことから、
アルフィーのメンバーたちより2年先輩で、2012年4月10日に60歳を迎えた、さだまさしの誕生日を祝う記念コンサート 「60人のまさしくんWORLD」(於:さいたまスーパーアリーナ) 第一部のトリとして、高見沢が 「高まさし」 としてゲスト出演、さだと 『まほろば』 をセッションしている。
この年はさだまさしの還暦でもありデビュー40周年でもあった (あらまぁ、どっかのグループとおんなじ・笑) ので、2012年6月に長崎ブリックホールから始まり、2013年1月28,29日の東京国際フォーラムでの追加公演を含む 『さだまさし デビュー40周年記念コンサート・ツアー さだまつり 』(東京国際フォーラム、ホールAでのファイナルは、なんと歌わずにほぼしゃべってるだけの 「しゃべるDAY=前夜祭」 と 「うたうDAY=後夜祭」 とがあったという、前代未聞のさだまさしらしいコンサート企画である) も行ったというので、ぶったまげるのだが (本人いわく、大変だからもう二度とやらないコンサートと言っているらしいが、そりゃそうだ・笑)
そんなこんなで、その直後の 通称 『生さだ』 にアルフィーが生出演した際、「まほろば」 をさだとアルフィーとでセッションした。
その時のトークで、さだが、タカミーのことを彼のニックネームの王子と呼び、
さだ 「王子は、なんかこの曲を気に入ってソロコンサートでやってくれたんだよね。」(中略)
高 「・・・レッドツェッペリンの次に聞いていたのがさださんです。」
坂崎 「ほんとですよ。ツェッペリン、ディープパープル、クリムゾンのレコードに混じって、さだまさし 『帰去来(ききょらい)』 があったもん。」
などと言って半分笑いを取っていたが、
このとき高見沢は、 「まほろばの詞は尋常じゃあないです。」 と感心し褒め称えていた。
( このときも、かつて大好きで尊敬していた人と、たった今大好きで尊敬している人とがお互いをリスペクトしあいながらセッションしているのだと思うと、曲自体が好きなだけでなく、心から感動して、泣けて泣けて仕方がなかった。 )
実は 「60人のまさしくんWORLD」 の出演を終え楽屋に戻ってきた高見沢のもとに、8つ年上の実の兄から 「お前が出てるなんて知らなかったよ、しかも第一部のトリじゃないか。びっくりしたよー。」 とメールが入り、 「えー、兄貴が見に来てたなんて知らなかったよー」 とこちらもびっくりして返信したタカミーだったらしいが (ラジオ 「高見沢俊彦のロックばん」談)、
60周年バースディコンサートに来るくらいなので、兄は相当さだまさしファンなのではないかと思う。
さだまさし好きというのは、かつての兄の影響だったのではあるまいか。
そして、幼い頃からずっと背中を追いかけてきた、8つも上で優秀だった憧れであり自慢の兄が、自分のことを驚いて感心してくれたのは、
高見沢にとってもちょっと鼻が高く、くすぐったくもあり嬉しかったに違いない。
ちなみに、ネコタがさだまさしさんを好きになったのは、
高2の時、所属していた体操部の一つ上の先輩が大ファンだったらしく、部室で着替えながら、
「この間さださんが松本に来てくれて、コンサート聞きに行ったんだけど、もー、さださん、すごい素敵だったぁ~!!」 などと興奮してしゃべっているのを聞くともなしに聞いていて、
大変失礼ながら、えー、あんなうらなりびょうたんみたいな人のどこがいいのかしら? などと思って注目しているうちに、気づいたら自分が好きになっていてびっくりした。

初めは友人などが、もしかして好きなのかなぁー、あんな人のどこがいいのかしら、と不思議に思って観察しているうちに、気が付いたら自分が好きになっちゃっててびっくりした、という人は今までの人生の中で実は3回もあって、小6の時2つ上の合唱団の先輩であり団長さんだった人、さだまさしさん、そして何を隠そう現在夫になっている人物である。
さださんも、はじめは青白くて病弱で神経質そうで暗い人、と思っていたのが、
もともとワイルダーな方よりも、色白でナイーブな文学青年タイプ、お坊ちゃんタイプ (何しろ彼はデビューの時ヴァイオリンを弾いていたのだから! そして当時の歌謡界でそんな人はいなかったので相当なお坊ちゃんに見えた) の方のほうがどちらかというと好きだったので、
さださんも好きになってみたら、ちょっと憂いを含んだ繊細そうな文学青年みたい、素敵!



になったのだから、面白い。
( でも、実際は高校で 「落研」 (おちけん、落語研究会のこと) に入るほど明るくて面白い人だったというのが、彼の作る “面白い方の曲” や、明るく楽しいトークからもよくわかるのですが・笑 )
さださん、今でこそ少し貫禄が出られましたけど、若いころはそりゃあ素敵でした。
何年か前、さださんの実息である佐田大陸くん(さだ・たいりく、クラッシックユニットTUKEMENメンバー、ヴァイオリニスト) をテレビで初めて見たとき、ちょっとドキッとしましたね。
だって、若いころのお父さんそっくりだったから。
( もちろん、一番好きだったのは御本人の外見とかよりも、曲の素晴らしさ、特に詞の持つ世界観に強く惹かれて、そして、声の美しさに、ですけどね。 )
ちなみに、タカミーも、今でこそあんなに派手派手で、TV『新堂本兄弟』 とか見てると、明るくて面白いというかお茶目な可愛らしい感じで、そしてそんなお姿がとっても大好きですけど (すごく、いい風に年を重ねられて、変化された、または自然に自分を出せるようになった感じと言ったら生意気でしょうか)、
存在を知った頃は、TVではあまりしゃべらなかったし、もっとおとなしそうで地味?な感じでした。
でも、まるで少女漫画から抜け出してきたかのような美しくてカッコいいルックスに一目惚れ、
ちょっと憂いを含んだ繊細そうな文学青年風な、ちょっと暗い?というか、とんがってる感じのところまで素敵だと思いました。
( 自分でも若い頃は決して明るいタイプではなかったので、明るくておしゃべりでひょうきんな人より、無口で繊細な感じの人の方がどちらかというと好きだったので )
さだまさしさん、今ではすっかり聞かなくなってしまいましたが、当時の曲は今でも好きです。
当時は 「精霊流し」、 「追伸」 や 「パンプキンパイとシナモンティー」 「関白宣言」 などという言葉が社会現象になるほど一世を風靡してましたが、私は世間的に流行った曲よりも、どちらかというとマイナーな方が好きでした。
線香花火、胡桃の日、つゆのあとさき、晩鐘、風の篝火(かがりび)、まほろば、空蝉(うつせみ)、鳥辺野(とりべの)、邪馬臺(やまたい)など、漢字を多用するタイトルや歌詞、小説と同名の曲や古典文学的な詩、文学的な世界観などが大好きでした。
ちょっと流行った曲では、無縁坂、飛梅(とびうめ)、檸檬(れもん)、主人公なども好きでした。
とりわけ 「歌詞」 にこだわり、自分の書くのは 「詞」 ではなく 「詩」 であると言ったり、
小説も書けるさだまさしさんは、言葉の天才だと思います。
 THE ALFEE 名誉卒業と聖地巡礼の旅 ~ 本編2. いよいよ聖地巡礼・その1 ~ へと続く。
THE ALFEE 名誉卒業と聖地巡礼の旅 ~ 本編2. いよいよ聖地巡礼・その1 ~ へと続く。










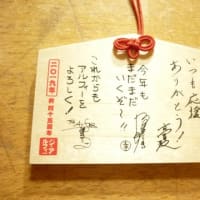

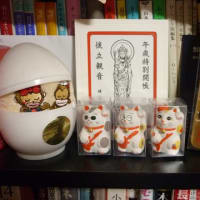

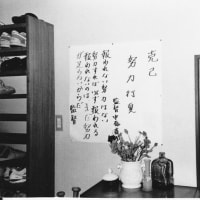




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます