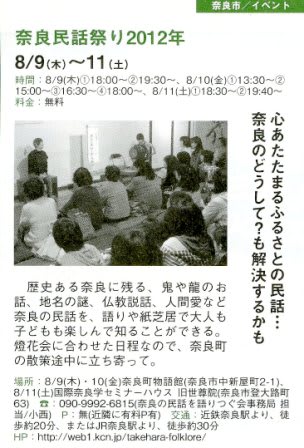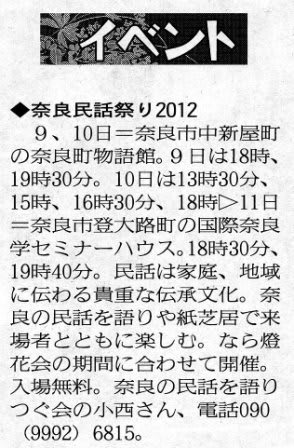応募多数につき、「2012年度 語りの入門講座Ⅱ」の申込を締め切りました!
詳しくは、ここをクリックしてみてください。
定員に達しましたので、一般の方からの応募は締め切りました。
奈良教育大学の学生・院生からの応募は引き続き募集いたします。
9月26日朝10時30分までにお申し込みいただけた方は全員参加いただけますので
講座の初回、10月9日(火)午後2時までに104教室にお集まりください。
奈良教育大学への道順については交通アクセスをご覧ください。
--------------------------------
「奈良・語りの文化研究所」のHPを更新しました!
とくに、■イベント情報をご覧ください。
私の関係する、秋からの公開講座などを紹介しています。
1.奈子連40周年記念講演会:グリム童話初版編者所持本に隠された秘密 ―「いばら姫」の語り手の素顔に迫る― 10月18日 はぐくみセンター1F NEW 申込受付中!
2・東洋大学創立125周年・『グリム童話』刊行200年記念国際シンポジウム 10月20日 東洋大学白山キャンパス5号館「井上円了ホール」 NEW
3・グリム童話刊行200年記念 シンポジウム 10月28日 武庫川女子大学 マルチメディアホール NEW
4・講演会:グリムまつり: グリム童話の世界へようこそ! 11月17日 LICはびきの2F NEW
5.佐保川まちづくり塾C:グリム童話と奈良の民話 12月8日・22日 奈良県立図書情報館1F交流ホール NEW 申込受付中!
6.講演:昔話とメディア ―「いばら姫」をめぐって ― 11月20日 あすのす平群 NEW 企画中!
特に、2.3.は、ドイツ・カッセルのグリム兄弟博物館のラウアー博士を迎えて、
グリム童話刊行200年を記念して国際シンポジウムがありますので、
東洋大学か、武庫川女子大学にぜひお出でください。
本日のブログは、秋の講演のご案内でした。
詳しくは、ここをクリックしてみてください。
定員に達しましたので、一般の方からの応募は締め切りました。
奈良教育大学の学生・院生からの応募は引き続き募集いたします。
9月26日朝10時30分までにお申し込みいただけた方は全員参加いただけますので
講座の初回、10月9日(火)午後2時までに104教室にお集まりください。
奈良教育大学への道順については交通アクセスをご覧ください。
--------------------------------
「奈良・語りの文化研究所」のHPを更新しました!
とくに、■イベント情報をご覧ください。
私の関係する、秋からの公開講座などを紹介しています。
1.奈子連40周年記念講演会:グリム童話初版編者所持本に隠された秘密 ―「いばら姫」の語り手の素顔に迫る― 10月18日 はぐくみセンター1F NEW 申込受付中!
2・東洋大学創立125周年・『グリム童話』刊行200年記念国際シンポジウム 10月20日 東洋大学白山キャンパス5号館「井上円了ホール」 NEW
3・グリム童話刊行200年記念 シンポジウム 10月28日 武庫川女子大学 マルチメディアホール NEW
4・講演会:グリムまつり: グリム童話の世界へようこそ! 11月17日 LICはびきの2F NEW
5.佐保川まちづくり塾C:グリム童話と奈良の民話 12月8日・22日 奈良県立図書情報館1F交流ホール NEW 申込受付中!
6.講演:昔話とメディア ―「いばら姫」をめぐって ― 11月20日 あすのす平群 NEW 企画中!
特に、2.3.は、ドイツ・カッセルのグリム兄弟博物館のラウアー博士を迎えて、
グリム童話刊行200年を記念して国際シンポジウムがありますので、
東洋大学か、武庫川女子大学にぜひお出でください。
本日のブログは、秋の講演のご案内でした。