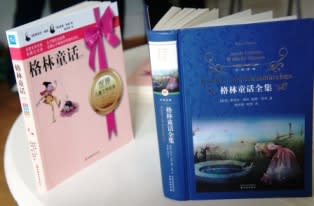みなさん、お正月はいかがでしたか?
お餅とお雑煮の食べすぎで、「正月太り」の方はいらっしいませんか?
私は七草粥でお腹(なか)の調整をしました。
近くのスーパーで「春の七草」を買ったら、こんなチラシが入っていました。

■春の七草
芹(セリ) セリ科
薺(ナズナ) 別名:ぺんぺん草 アブラナ科
御形(ゴギョウ) キク科
繁縷(ハコベラ) ナデシコ科
仏の座(ホトケノザ)キク科
菘(スズナ) アブラナ科
蘿蔔(スズシロ) (今の大根)アブラナ科
頭の体操のため、7草の名前を唱えてみました。
「せりなづな 御形はこべら 仏の座 すずなすずしろ これぞ七草」
平安時代には、このように詠んで、覚えたそうですよ。
それではもう一度
「せりなづな 御形はこべら 仏の座 すずなすずしろ これぞ七草」
もう、ちゅうで言えますか?
■七草囃子
正月の六日の夜から七日の早朝にかけて、まな板の上に七つの道具をそろえて七草を
49回(7×7)叩き刻みます。
このときに唱える言葉が囃子歌となって七草囃子として各地に伝えられています。
七草ナズナ、
唐土の鳥が日本の土地に渡らぬ先に、
セリこらたたきのタラたたき
七草ナズナ、
唐土の鳥が日本の土地に渡らぬ先に、
トントンバタリ トンバタリ
七草なずな
唐土の鳥と 日本の鳥と 渡らぬ先に
七草なずな
手につみ入れて あみばし とろき ひつき ちりこ
げにげにさりげなきようにて 物の大事は侍りけり
という鳥追い歌が一般的です。
七草粥は現代風にいえば、「鳥インフルエンザ対策」です。
「大陸から渡ってくる鳥の翼にはいろいろな害虫や病気があるので、
日本に渡って来る前に七草かゆを食べて厄を落とし、元気で1年間を過ごそう」
というのが、この囃子の由来だそうです。
みなさま、この一年もお互い、元気に過ごしましょう!
お餅とお雑煮の食べすぎで、「正月太り」の方はいらっしいませんか?
私は七草粥でお腹(なか)の調整をしました。
近くのスーパーで「春の七草」を買ったら、こんなチラシが入っていました。

■春の七草
芹(セリ) セリ科
薺(ナズナ) 別名:ぺんぺん草 アブラナ科
御形(ゴギョウ) キク科
繁縷(ハコベラ) ナデシコ科
仏の座(ホトケノザ)キク科
菘(スズナ) アブラナ科
蘿蔔(スズシロ) (今の大根)アブラナ科
頭の体操のため、7草の名前を唱えてみました。
「せりなづな 御形はこべら 仏の座 すずなすずしろ これぞ七草」
平安時代には、このように詠んで、覚えたそうですよ。
それではもう一度
「せりなづな 御形はこべら 仏の座 すずなすずしろ これぞ七草」
もう、ちゅうで言えますか?
■七草囃子
正月の六日の夜から七日の早朝にかけて、まな板の上に七つの道具をそろえて七草を
49回(7×7)叩き刻みます。
このときに唱える言葉が囃子歌となって七草囃子として各地に伝えられています。
七草ナズナ、
唐土の鳥が日本の土地に渡らぬ先に、
セリこらたたきのタラたたき
七草ナズナ、
唐土の鳥が日本の土地に渡らぬ先に、
トントンバタリ トンバタリ
七草なずな
唐土の鳥と 日本の鳥と 渡らぬ先に
七草なずな
手につみ入れて あみばし とろき ひつき ちりこ
げにげにさりげなきようにて 物の大事は侍りけり
という鳥追い歌が一般的です。
七草粥は現代風にいえば、「鳥インフルエンザ対策」です。
「大陸から渡ってくる鳥の翼にはいろいろな害虫や病気があるので、
日本に渡って来る前に七草かゆを食べて厄を落とし、元気で1年間を過ごそう」
というのが、この囃子の由来だそうです。
みなさま、この一年もお互い、元気に過ごしましょう!