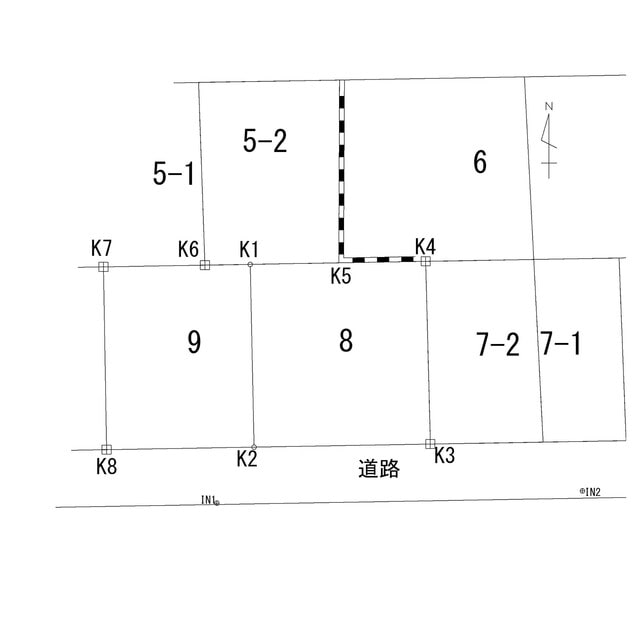日調連から全国各会に「土地家屋調査士業務取扱要領」案への意見募集が求められた、ということです。「土地家屋調査士業務取扱要領」案を見て、思ったことを書きます。
まず初めに「前置き」的なことを言っておくと、私は、この「土地家屋調査士業務取扱要領」案というものについて、そもそも賛成しがたいものだと思っています。
それは、この「業務取扱要領」というものが、これまでのように、日調連で作成した「調査測量実施要領」について、全国各会が検討を加えたうえで「会の定める要領」としてきたことを止めにして「全国統一」のものとして作成することにした経緯そのものがおかしい、と思うからです。
それは、土地家屋調査士法の改正がなされて、土地家屋調査士に対する懲戒権者が、それまでの(地方)法務局長から法務大臣に変わったことを受けて、調査士が守るべきものとされている「要領」も全国統一にする必要がある、という形で説明されているものです。
なぜそうなるのか?何の必然性もない話です。
調査士が業務を行うにあたって拠らなければならないものとされているのは、まず「法令」であり、これは全国共通のものです。その上で「本会の制定する要領」に拠るものとして「調査測量実施要領」を定めていた(り、いなかったり)わけで、何もこれが全国共通でないと進められない、というわけではありません。現に、法務大臣の懲戒に関する事務は、各(地方)法務局に委任されて行われることになっているわけで、これまでどおりの形態で不都合が生じるというものではないはずです。
むしろ、「各会が検討して制定する」という自主的な姿をなくしてしまう方が弊害が多い、と言うべきでしょう。(こういうところから今回の意見照会も、108条207頁もあるものに対してわずか1週間の期限、というアリバイ的なものになっています。「検討」するべきものではなく「与えられるもの」になってしまっているのです。)
そしてそれは、具体的な内容へも影響を与えます。
「業務取扱要領」というものが、「懲戒」への対応を主要動機として考えられているので、それは「懲戒に引っかからないように作っておこう」という方向で考えられるようになります。ここから、従来の「義務規定」を「努力規定」に変えちゃおう、というようないじましいことがなされたりもするわけです。情けないことです。
・・・というわけで言いたいことはいっぱいあるのですが、一つだけ、看過しがたいと思うことに絞って本題に入ります。
この「業務取扱要領」は「調査士法改正を受けて」なされているそうですから、「懲戒」に関することだけではなく、第一条の「筆界を明らかにする業務の専門家」として位置づけられたことを受けて、その「筆界を明らかにする業務」の「取扱要領」を明らかにする方向で検討・策定を行うべきものとしてあるのか、と私は思っていました。「第1条 使命」が規定されたわけですから、それを具体化する「業務取扱要領」を作って行こう、と考えるのは、当然の思考回路なのかと思ったからです。しかし、そのような問題意識はおよそ持たれていないようです。不思議なことです。前を向いて考えればいい(「調査士の使命」を果たすこと)のに、後ろ(「懲戒」に引っかからないように!)ばっかり見ているようで、情けないことです。
その「筆界を明らかにする業務」に関係すると思われるのは、次の条項です。
正直言って全体として何を言っているのかよく理解できないのですが(その意味で「要領」としての役割を果たしているとは言えないと思いますが)、理解しえた範囲で思ったことを書きます。
この「筆界位置の判断」に関する内容には、「筆界を明らかにする業務の専門家」として考える、という姿勢がまったく感じられません。
それを端的に示しているのは、(1)(2)(3)の各項が立てられているわけですが、それがどのようなことで区別されているものとして別項にしているのか、ということが考えられていないことです。
すなわち、それぞれが「どのような場合」のことを考えているのか?ということが問題になるわけですが、(1)も(2)も「現地において境界標等により土地の区画が明らかな場合」のことを言っているようになっています。
このように、同じ「場合」を考えるのであれば、項を分けずに同じ項にまとめる、というのが論理的な考え方だと言えるでしょう。
さらに、この「場合」の上で、(1)は、「地図、地積測量図又はその他の数値資料が存」する「場合」のことを、(2)は「地図、地積測量図又はその他の数値資料が存」しない「場合」のことを考える、という構造になっています。
この初めに来る「場合」と次に来る「場合」とは逆転しても問題がないようです。すなわち、(1)では、「地図、地積測量図又はその他の数値資料が存する場合」において「現地において境界標等により土地の区画が明らかな場合」にはどうか?というように考えるのでもいいようです。むしろ、このように考えた方が(2)「数値資料が存しない場合」との区別がはっきりとついて、わかりやすくなる、と言えるでしょう。そのようなものとして、従来の「調測要領」では、「既存の地積の測量図、登記所備付けの地図及びその他の数値資料が存する場合・・・」(39条(1))、「前項の資料が存しない場合・・・」(同(2))とされて、異なる「場合」に応じて項が立てられていたのでした。(従来の「調測要領」39条の全文は末尾に掲載)
それをわざわざひっくり返しているわけですが、これは「改正」ではなくて「改悪」だと言うべきです。なぜなら、このように規定することは、「筆界の位置の判断」をするときに、まず考えるべきこと(初めの「場合))を「現地において境界標等により土地の区画が明らか」かどうか?ということに置くことにしていることになるからです。これは間違いです。「筆界の公的性格」ということから、公的な資料から「筆界が明らかである」と認められるかどうか、ということをまず第一に考えるべきです。それが、「筆界を明らかにする業務の専門家」としての見方であり、「土地の区画が明らか」かどうか?という現況を考えてしまう、というのは「現況主義」的な「素人の見方」への後退になってしまいます。「筆界を明らかにする業務の専門家」としての「業務取扱要領」を考えるべき時に行うべきことではありません。(もっとも、従来の調測要領では「当事者間でそれらの境界標等を土地の境界として認めているときは」という限定規定を置いていたのを除いていますので、その面では「改正」と言ってもいいのかと思いますが。)
初めの「場合」と次の「場合」をひっくり返した方がいい、というのは(2)でも明らかです。
すなわち、「地図、地積測量図又はその他の数値資料が存」しない場合でも、「現地において境界標等により土地の区画が明らかな場合」にはどうなのか?というように問題は立てられるべきでしょう。その方が論理的につながるからです。
そのようにせずに、最初に「現地において境界標等により土地の区画が明らかな場合」を置いたので、その次は「地図、地積測量図又はその他の数値資料が存せず、地図に準ずる図面、関係者の証言等により対象地の位置、形状、周辺地との関係が矛盾なく確認された場合」というように、否定的な「場合」(数値資料が存在しない)と肯定的な「場合」(矛盾なく確認できた)を並列的に置く、というアクロバチックな形になってしまい、それは一体どういう「場合」なのか?ということがわからなくなってしまっています。
こうしてみてみると、この「案」を作って人たちがどこまで考えてこのようにしたのかはわかりませんが、この条項が示しているのは、「筆界位置の判断」に当たって最も重要なことは「現地において境界標等により土地の区画が明らか」なのかどうなのか?ということなのだ、ということであり、「現地において境界標等により土地の区画が明らか」な場合には、(何を意味するのかよくわからない条件を付けながら結局のところ)「筆界と判断することができる」という結論に結びつく、としている、ということです。これは、「筆界と普段関係しない一般の人々」に理解しやすいことなのかもしれませんが、それは「専門家」が専門分野をわかりやすく説明する、ということではなく、「素人」のレベルにまで落ちて行ってしまう、ということに過ぎません。本当に「専門家」なの?と疑問に思われてしまうところです。
(なお、(3)については、本当に意味不明で、言うべきことがありません。いろいろと推測をめぐらしたのですが、本当にわからん!)
さて、以上「文句ばっかり言ってる!」と思われるかもしれないので、原文の雰囲気を残したままで作り変えるとしたらどうなるだろう?と考えたものを書いておくことにします。あまり出来のいいものではありませんが、この辺のところにしておけば、その後の具体的な展開を期待できるのではないか、と思います。
従来の「調測要領」の規定は次のようなものでした。この規定も、少なくとも今日においてはとても適切なものとは言えないと思いますが、それにしてもまだ論理的な筋は通っていますので、参考までに載せておきます。今回の「業務取扱要領」案は、、この20年近く前のものよりも後退してしまっているように思えます。
まず初めに「前置き」的なことを言っておくと、私は、この「土地家屋調査士業務取扱要領」案というものについて、そもそも賛成しがたいものだと思っています。
それは、この「業務取扱要領」というものが、これまでのように、日調連で作成した「調査測量実施要領」について、全国各会が検討を加えたうえで「会の定める要領」としてきたことを止めにして「全国統一」のものとして作成することにした経緯そのものがおかしい、と思うからです。
それは、土地家屋調査士法の改正がなされて、土地家屋調査士に対する懲戒権者が、それまでの(地方)法務局長から法務大臣に変わったことを受けて、調査士が守るべきものとされている「要領」も全国統一にする必要がある、という形で説明されているものです。
なぜそうなるのか?何の必然性もない話です。
調査士が業務を行うにあたって拠らなければならないものとされているのは、まず「法令」であり、これは全国共通のものです。その上で「本会の制定する要領」に拠るものとして「調査測量実施要領」を定めていた(り、いなかったり)わけで、何もこれが全国共通でないと進められない、というわけではありません。現に、法務大臣の懲戒に関する事務は、各(地方)法務局に委任されて行われることになっているわけで、これまでどおりの形態で不都合が生じるというものではないはずです。
むしろ、「各会が検討して制定する」という自主的な姿をなくしてしまう方が弊害が多い、と言うべきでしょう。(こういうところから今回の意見照会も、108条207頁もあるものに対してわずか1週間の期限、というアリバイ的なものになっています。「検討」するべきものではなく「与えられるもの」になってしまっているのです。)
そしてそれは、具体的な内容へも影響を与えます。
「業務取扱要領」というものが、「懲戒」への対応を主要動機として考えられているので、それは「懲戒に引っかからないように作っておこう」という方向で考えられるようになります。ここから、従来の「義務規定」を「努力規定」に変えちゃおう、というようないじましいことがなされたりもするわけです。情けないことです。
・・・というわけで言いたいことはいっぱいあるのですが、一つだけ、看過しがたいと思うことに絞って本題に入ります。
この「業務取扱要領」は「調査士法改正を受けて」なされているそうですから、「懲戒」に関することだけではなく、第一条の「筆界を明らかにする業務の専門家」として位置づけられたことを受けて、その「筆界を明らかにする業務」の「取扱要領」を明らかにする方向で検討・策定を行うべきものとしてあるのか、と私は思っていました。「第1条 使命」が規定されたわけですから、それを具体化する「業務取扱要領」を作って行こう、と考えるのは、当然の思考回路なのかと思ったからです。しかし、そのような問題意識はおよそ持たれていないようです。不思議なことです。前を向いて考えればいい(「調査士の使命」を果たすこと)のに、後ろ(「懲戒」に引っかからないように!)ばっかり見ているようで、情けないことです。
その「筆界を明らかにする業務」に関係すると思われるのは、次の条項です。
(筆界位置の判断)
第33条 調査士は、本要領第31条及び第32条の調査結果等と併せて、原則として次に掲げる各号によって筆界位置の判断をするものとする。なお、土地の形状及び面積が地図等又は登記記録の地積と相違しているときは、依頼者に対し地図訂正又は地積更正等の必要性があることを助言するものとする。
(1) 現地において境界標又はこれに代わる構築物等(以下「境界標等」という。)により土地の区画が明らかな場合において、地図、地積測量図又はその他の数値資料が存し、位置及び形状がそれぞれの資料の持つ精度に応じた誤差の限度内である場合は、これをもって筆界と判断することができる。ただし、必要に応じて関係者に土地の筆界の認識を確認するものとする。
(2) 現地において境界標等により土地の区画が明らかな場合において、地図、地積測量図又はその他の数値資料が存せず、地図に準ずる図面、関係者の証言等により対象地の位置、形状、周辺地との関係が矛盾なく確認された場合は、これをもって筆界と判断することができる。
(3) 現地において境界標等が存せず土地の区画が明らかでない場合において、地図、地積測量図又はその他の数値資料、地図に準ずる図面、関係者の証言等により復元した位置が対象地の位置、形状、周辺地との関係が矛盾なく確認された場合は、これをもって筆界と判断することができる。この場合、調査士は、本要領第31条及び第32条による調査結果等に基づく見解を関係者に示し、恣意的に筆界が確認されることのないようにしなければならない。
第33条 調査士は、本要領第31条及び第32条の調査結果等と併せて、原則として次に掲げる各号によって筆界位置の判断をするものとする。なお、土地の形状及び面積が地図等又は登記記録の地積と相違しているときは、依頼者に対し地図訂正又は地積更正等の必要性があることを助言するものとする。
(1) 現地において境界標又はこれに代わる構築物等(以下「境界標等」という。)により土地の区画が明らかな場合において、地図、地積測量図又はその他の数値資料が存し、位置及び形状がそれぞれの資料の持つ精度に応じた誤差の限度内である場合は、これをもって筆界と判断することができる。ただし、必要に応じて関係者に土地の筆界の認識を確認するものとする。
(2) 現地において境界標等により土地の区画が明らかな場合において、地図、地積測量図又はその他の数値資料が存せず、地図に準ずる図面、関係者の証言等により対象地の位置、形状、周辺地との関係が矛盾なく確認された場合は、これをもって筆界と判断することができる。
(3) 現地において境界標等が存せず土地の区画が明らかでない場合において、地図、地積測量図又はその他の数値資料、地図に準ずる図面、関係者の証言等により復元した位置が対象地の位置、形状、周辺地との関係が矛盾なく確認された場合は、これをもって筆界と判断することができる。この場合、調査士は、本要領第31条及び第32条による調査結果等に基づく見解を関係者に示し、恣意的に筆界が確認されることのないようにしなければならない。
正直言って全体として何を言っているのかよく理解できないのですが(その意味で「要領」としての役割を果たしているとは言えないと思いますが)、理解しえた範囲で思ったことを書きます。
この「筆界位置の判断」に関する内容には、「筆界を明らかにする業務の専門家」として考える、という姿勢がまったく感じられません。
それを端的に示しているのは、(1)(2)(3)の各項が立てられているわけですが、それがどのようなことで区別されているものとして別項にしているのか、ということが考えられていないことです。
すなわち、それぞれが「どのような場合」のことを考えているのか?ということが問題になるわけですが、(1)も(2)も「現地において境界標等により土地の区画が明らかな場合」のことを言っているようになっています。
このように、同じ「場合」を考えるのであれば、項を分けずに同じ項にまとめる、というのが論理的な考え方だと言えるでしょう。
さらに、この「場合」の上で、(1)は、「地図、地積測量図又はその他の数値資料が存」する「場合」のことを、(2)は「地図、地積測量図又はその他の数値資料が存」しない「場合」のことを考える、という構造になっています。
この初めに来る「場合」と次に来る「場合」とは逆転しても問題がないようです。すなわち、(1)では、「地図、地積測量図又はその他の数値資料が存する場合」において「現地において境界標等により土地の区画が明らかな場合」にはどうか?というように考えるのでもいいようです。むしろ、このように考えた方が(2)「数値資料が存しない場合」との区別がはっきりとついて、わかりやすくなる、と言えるでしょう。そのようなものとして、従来の「調測要領」では、「既存の地積の測量図、登記所備付けの地図及びその他の数値資料が存する場合・・・」(39条(1))、「前項の資料が存しない場合・・・」(同(2))とされて、異なる「場合」に応じて項が立てられていたのでした。(従来の「調測要領」39条の全文は末尾に掲載)
それをわざわざひっくり返しているわけですが、これは「改正」ではなくて「改悪」だと言うべきです。なぜなら、このように規定することは、「筆界の位置の判断」をするときに、まず考えるべきこと(初めの「場合))を「現地において境界標等により土地の区画が明らか」かどうか?ということに置くことにしていることになるからです。これは間違いです。「筆界の公的性格」ということから、公的な資料から「筆界が明らかである」と認められるかどうか、ということをまず第一に考えるべきです。それが、「筆界を明らかにする業務の専門家」としての見方であり、「土地の区画が明らか」かどうか?という現況を考えてしまう、というのは「現況主義」的な「素人の見方」への後退になってしまいます。「筆界を明らかにする業務の専門家」としての「業務取扱要領」を考えるべき時に行うべきことではありません。(もっとも、従来の調測要領では「当事者間でそれらの境界標等を土地の境界として認めているときは」という限定規定を置いていたのを除いていますので、その面では「改正」と言ってもいいのかと思いますが。)
初めの「場合」と次の「場合」をひっくり返した方がいい、というのは(2)でも明らかです。
すなわち、「地図、地積測量図又はその他の数値資料が存」しない場合でも、「現地において境界標等により土地の区画が明らかな場合」にはどうなのか?というように問題は立てられるべきでしょう。その方が論理的につながるからです。
そのようにせずに、最初に「現地において境界標等により土地の区画が明らかな場合」を置いたので、その次は「地図、地積測量図又はその他の数値資料が存せず、地図に準ずる図面、関係者の証言等により対象地の位置、形状、周辺地との関係が矛盾なく確認された場合」というように、否定的な「場合」(数値資料が存在しない)と肯定的な「場合」(矛盾なく確認できた)を並列的に置く、というアクロバチックな形になってしまい、それは一体どういう「場合」なのか?ということがわからなくなってしまっています。
こうしてみてみると、この「案」を作って人たちがどこまで考えてこのようにしたのかはわかりませんが、この条項が示しているのは、「筆界位置の判断」に当たって最も重要なことは「現地において境界標等により土地の区画が明らか」なのかどうなのか?ということなのだ、ということであり、「現地において境界標等により土地の区画が明らか」な場合には、(何を意味するのかよくわからない条件を付けながら結局のところ)「筆界と判断することができる」という結論に結びつく、としている、ということです。これは、「筆界と普段関係しない一般の人々」に理解しやすいことなのかもしれませんが、それは「専門家」が専門分野をわかりやすく説明する、ということではなく、「素人」のレベルにまで落ちて行ってしまう、ということに過ぎません。本当に「専門家」なの?と疑問に思われてしまうところです。
(なお、(3)については、本当に意味不明で、言うべきことがありません。いろいろと推測をめぐらしたのですが、本当にわからん!)
さて、以上「文句ばっかり言ってる!」と思われるかもしれないので、原文の雰囲気を残したままで作り変えるとしたらどうなるだろう?と考えたものを書いておくことにします。あまり出来のいいものではありませんが、この辺のところにしておけば、その後の具体的な展開を期待できるのではないか、と思います。
(1)地図、地積測量図又はその他の数値資料が存する場合には、その指示する点を現地に復元し、地図に準ずる図面等の他の関係資料及び境界標・工作物等の現地の状況との間に、数値資料の正確性を疑わせるような矛盾のないときは、これをもって筆界と判断することができる。
(2)地図、地積測量図又はその他の数値資料が存しない場合には、現地において境界標又はこれに代わる構築物等が存在し、地図に準ずる図面、関係者の証言等により対象地の位置、形状、周辺地との関係が矛盾なく確認されるときは、これをもって筆界と判断することができる。ただし、必要に応じて関係者に土地の筆界の認識を確認するものとする。
(3) 前号、前々号によって筆界の判断をすることのできない場合には、関係者の筆界に関する認識を調査し、関係者間の認識が一致して確認できる場合には、これをもって筆界と判断することができる。この場合、調査士は、本要領第31条及び第32条による調査結果等に基づく見解を関係者に示し、恣意的に筆界が確認されることのないようにしなければならない。
(2)地図、地積測量図又はその他の数値資料が存しない場合には、現地において境界標又はこれに代わる構築物等が存在し、地図に準ずる図面、関係者の証言等により対象地の位置、形状、周辺地との関係が矛盾なく確認されるときは、これをもって筆界と判断することができる。ただし、必要に応じて関係者に土地の筆界の認識を確認するものとする。
(3) 前号、前々号によって筆界の判断をすることのできない場合には、関係者の筆界に関する認識を調査し、関係者間の認識が一致して確認できる場合には、これをもって筆界と判断することができる。この場合、調査士は、本要領第31条及び第32条による調査結果等に基づく見解を関係者に示し、恣意的に筆界が確認されることのないようにしなければならない。
従来の「調測要領」の規定は次のようなものでした。この規定も、少なくとも今日においてはとても適切なものとは言えないと思いますが、それにしてもまだ論理的な筋は通っていますので、参考までに載せておきます。今回の「業務取扱要領」案は、、この20年近く前のものよりも後退してしまっているように思えます。
(筆界の確認)
第39条 筆界の確認は基礎測量又はこれに類する測量の成果を基礎として、次の各号により行うものとする。
(1) 既存の地積の測量図、登記所備付けの地図及びその他の数値資料が存する場合において、現地における境界標又はこれに代わるべき構築物等により土地の区画が明確であって、位置及び形状がそれぞれの資料のもつ精度に応じた誤差の限度内であり、かつ、当事者間でそれらの境界標等を土地の境界として認めているときは、これをもって筆界と判断して差し支えない
(2) 前号の資料が存しない場合において、現地の状況が境界標又はこれに代わるべき構築物等により土地の区画が明確であり、既存資料、現地精通者の証言等により対象地の位置、形状、周辺地との関係が矛盾なく確認され、かつ、当事者間に異議がないときは、その区画をもって筆界と判断して差し支えない
なお、土地の形状及び面積が登記所備付けの地図等又は登記簿上の地積と相違しているときは、委託者に対し地図訂正又は地積更正等の必要性があることを助言するものとする。
(3) 第38条・第40条又は第50条に基づき確認されたものは、筆界として差し支えない
2 前項により筆界が確認されたときは、後日の紛争防止と登記申請書に添付するため別紙11又は12の様式を参考とした確認書を作成する。
(筆界確認の協議)
第40条 土地の筆界が明らかでない場合には、当事者に対して筆界及び所有権の及ぶ範囲の確認を求め、協議をさせるものとする。この場合において、第39条による調査結果及び第50条による復元資料を示し、調査士の見解を利害関係者に示し、恣意的に筆界が定められることのないようにしなければならない。
2 前項の規定により当事者が筆界を確認したとき、又は不調の場合においても、その立会状況、立会者名及び経過を調査記録書等に明記するものとする。
3 前条第2項の規定は、第1項の規定により筆界が確認された場合に準用する。
第39条 筆界の確認は基礎測量又はこれに類する測量の成果を基礎として、次の各号により行うものとする。
(1) 既存の地積の測量図、登記所備付けの地図及びその他の数値資料が存する場合において、現地における境界標又はこれに代わるべき構築物等により土地の区画が明確であって、位置及び形状がそれぞれの資料のもつ精度に応じた誤差の限度内であり、かつ、当事者間でそれらの境界標等を土地の境界として認めているときは、これをもって筆界と判断して差し支えない
(2) 前号の資料が存しない場合において、現地の状況が境界標又はこれに代わるべき構築物等により土地の区画が明確であり、既存資料、現地精通者の証言等により対象地の位置、形状、周辺地との関係が矛盾なく確認され、かつ、当事者間に異議がないときは、その区画をもって筆界と判断して差し支えない
なお、土地の形状及び面積が登記所備付けの地図等又は登記簿上の地積と相違しているときは、委託者に対し地図訂正又は地積更正等の必要性があることを助言するものとする。
(3) 第38条・第40条又は第50条に基づき確認されたものは、筆界として差し支えない
2 前項により筆界が確認されたときは、後日の紛争防止と登記申請書に添付するため別紙11又は12の様式を参考とした確認書を作成する。
(筆界確認の協議)
第40条 土地の筆界が明らかでない場合には、当事者に対して筆界及び所有権の及ぶ範囲の確認を求め、協議をさせるものとする。この場合において、第39条による調査結果及び第50条による復元資料を示し、調査士の見解を利害関係者に示し、恣意的に筆界が定められることのないようにしなければならない。
2 前項の規定により当事者が筆界を確認したとき、又は不調の場合においても、その立会状況、立会者名及び経過を調査記録書等に明記するものとする。
3 前条第2項の規定は、第1項の規定により筆界が確認された場合に準用する。