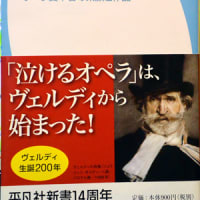北沢方邦の伊豆高原日記【34】
Kitazawa, Masakuni
急に秋が深まった、というより初冬がやってきたため、めずらしく伊豆高原の紅葉が美しい。朝夕の気温差の少ないこの地は、樹々はあまり紅葉することなく、枯葉色のまま落葉する。しかし今年は、雑木類の黄葉が鮮やかに、ハゼやウルシの紅を引き立たせている。
著しい知のレベルの低下
久しぶりに東京にでる都合があったため、輸入楽譜や本の購入のためヤマハ(残念ながら新築中で仮店舗は遠く、山野楽器におもむいた)や日本橋丸善を訪れた。
新築前の丸善では、和書はすでに近隣のビズネスマン向けの本しか並べていなかったので期待はしなかったが、洋書売り場には、まだ私が手にとって読みたいような書籍が、人間科学・自然科学を問わず置いてあった。
ところが新築後の洋書売り場には愕然とせざるをえなかった。ほとんど知的ショックといっていい。つまりここも、ビズネスマン向けの実用書や語学書、あるいはせいぜいメディアで話題となっている(たとえばアル・ゴアの何冊かの環境問題発言書など)本しか置かれていないのだ。思想や哲学書あるいは最新の自然科学の啓蒙書などが棚にないか、店内を数回廻ってみたが、ない!
一九五〇年代から七〇年代にかけての、かつての明るく広々とした洋書売り場の棚を、ぎっしりと埋め尽くしていたハードカヴァーの数々の書籍、平台をこれも埋め尽くしていたペーパーバックスや雑誌類、そしてそれらを手に取り熱心に読みふけるひとびと、あの知的な刺激に溢れた光景はどこへいってしまったのだろうか(フランス書や文芸書などヨーロッパ物を多く並べていた紀伊国屋書店の洋書売り場も、まったく同じ風景であった)。
あの頃、洋書売り場に上がって真っ先に手に取ったペリカン・ブックスの新刊書の多くは、いまもわが家の新書・文庫本専用の棚に収まっている。まだ私の英語力も十分でなかった時代、とにかく知に飢えて辞書を片手に読み漁っていたのだ。
あの時代が懐かしいわけではけっしてない。だがこの風景の変化が、わが国の知的レベルの著しい低下と、内面的文化の荒廃を告げているのではないかと、外の暗い曇り空にもまして暗い日本の未来への不安に、胸を閉ざされたしだいである
いまバルトークが語りかける
アメリカ合衆国打楽器芸術学界世界大会・ヨーロッパ打楽器大会招待演奏凱旋公演と題して、上野信一打楽器リサイタルが11月28日トッパン・ホールで行われた。この公演のための日本人作曲家の委嘱作品をふくめ4曲が演奏された。
彼が輝かしい打楽器技術と、繊細にして的確な音楽的感覚をそなえたひとであることはすでに知っていたが、あらためて感銘を深めることができた。
4組の打楽器セットを楽章毎に変えていくアンドレ・ジョリヴェの「打楽器協奏曲」全曲(ピアノ野平一郎)も興味深かったが、とりわけバルトークの「2台のピアノと打楽器のためのソナタ」(ピアノ:パトリク・シグマノフスキー/池田珠代、打楽器:上野信一/フレデリク・マカレス)が、全体として出色の出来栄えであった。
この曲には個人的な思い出がある。一九五〇年代、作曲家の故柴田南雄と私が、戦後の日本の音楽界にバルトークをはじめて体系的に紹介し(戦前にも断片的な紹介はあったが)、『音楽芸術』誌などに論文や楽曲解説を精力的に書いていた。輸入楽譜がようやく手に入るようになったが、現代音楽の輸入レコード(まだSPであった)はNHKにしかない時代であった。そのNHKラジオの教養番組を担当する第2放送から、ドイツ・グラモフォンの最新レコードで、バルトークの「2台のピアノと打楽器のソナタ」が入ったので、その放送の解説をお願いしたいと依頼された。ところが間際になってどうしてもスタジオが取れないので、録音ではなく生放送だという。生まれてはじめてのラジオ出演が生放送とは、と愕然としたが、あらかじめ原稿を作成し、心理的にあがることもなく無事終了した。
だが私のトーク中に珍事が起こったのだ。マイクロフォンを挟み、男性アナウンサーが私の向かいに対峙していたのだが、急にくしゃみか咳を誘発したらしく、ハンカチで口を蔽ってスタジオの外に飛び出したのはいいが、その拍子に狭い部屋の壁に立てかけてあった折りたたみのパイプ椅子を足に引っ掛け、倒してしまった。一瞬の轟音が生放送中のスタジオに響き渡ったのはいうまでもない。
そのときのレコードの印象(演奏者がだれであったかもはや記憶にないが)も、またその後演奏会で聴いた印象も同じであったが、この曲はあくまで2台のピアノが主役であって、打楽器はいわば伴奏する脇役にすぎないように思われていた。
だが今回はまったくちがう。それは、2人のピアノ奏者と2人の打楽器奏者、合計4人相互のいわば熾烈な決闘であり、そこから第2次世界大戦前夜の緊迫した状況に対する音楽的主張や思想を立ち昇らせようという、バルトーク自身の本来の意図を鮮明にしたものであり、その意味で啓示的な演奏であった。
重苦しい状況とそれに立ち向かう断固とした意志をうたう第1楽章、バルトーク固有の「夜の音楽」様式の深く沈潜する第2楽章、農民舞曲の歓呼に乗せた母なる大地とそこに生きる生命や人間への賛歌である第三楽章、だがそれも祖国を後に亡命する決意のなかで、一場の夢のように消えていく最後の数十小節の重み、それらすべてを浮き彫りにした名演であった。
FM放送よ、おまえもか
夕食後の休息にと、よくNHKのFMにスイッチを入れる。我慢のできない演奏のときには切るが、比較的よく聴くほうである。ところがときどき、わが耳を疑うアナウンスに出くわす。
だいぶ以前だが、リストの「巡礼の年第1集スイス」の「オーベルマンの谷」が演奏された。女性アナウンサーは繰り返しそれを「オーベルマンの旅」と述べ、ご丁寧に「オーベルマンという青年の心の旅を描く作品」と解説するではないか。たしかにこの曲は、ユイスマンスの小説『オーベルマン』の幻想的な一場面に霊感をえたものだが、原題は「ヴァレー・ドーベルマン」であってけっして「ヴォワイヤージュ・ドーベルマン」ではない。
数ヶ月たって別のピアニストが同じ曲を演奏したが、そのときもまた「オーベルマンの旅」とアナウンスし、同じ陳腐な解説を繰り返していた。あきれてものもいえない。
つい最近も、「南仏の古都サント」の修道院でのコンサートというアナウンスに出くわした。たびたびサントというのでそんな町があるのかと思っていると、「ローマ時代の遺跡もある由緒ある町並み」という解説で、はたと「ナントの勅令」で有名なナントであることに思いいたった。それに驚いていると、「次の曲目はベートーヴェンの交響曲第六番田園ハ長調」と語り、解説のあとで「ではベートーヴェンの交響曲第六番田園ハ長調をお聴きください」と繰り返すではないか。たしかに片カナのサとナ、ハとヘは似ているが、これはもはや読み間違いの段階ではない。西欧のクラシック音楽を扱うディレクターやアナウンサーが「田園」がヘ長調であることを知らないとは、世も末というほかはない。
電波メディアだけではない。大新聞にもこれに似た誤りが横行している。もう昔のことでなんの記事であったか忘れたが、朝日新聞のそれに関連したデモンストレーション画面に、Fresh Cake(新鮮なケーキ)のつもりらしいが、Flesh Cake(人肉ケーキ)と表示されているのに思わずわが目を疑った。
また毎日新聞のコラム「余禄」で、ヒトラー暗殺事件にかかわり自決させられたロンメルを、「ナチス親衛隊の将軍」と書いているのに驚いたことがある。ヒトラーへの狂信的な忠誠に凝り固まった親衛隊と、貴族出身者が多く、ヒトラーをひそかに成りあがり者と軽蔑していたドイツ国防軍の高級将校団とは、同じ武装集団であり、同じ戦争を戦ってはいたが、まったく別世界であったのだ。「砂漠の狐」と英軍に恐れられたロンメル将軍も、地下で憮然としたことであろう。最近も似たような誤りにしばしば出会う。新聞社には校閲部という部局があるはずだし、こうした歴史の誤りは、調べればすぐわかることである。
いずれにせよこれらの事例も、わが国の知のレベルの著しい低下を示す徴候にほかならない。