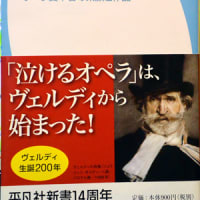北沢方邦の伊豆高原日記⑲
Kitazawa, Masakuni
夕暮れの美しい季節となった。東伊豆では水平線に沈む壮麗な日没はみられないが、日が山影に隠れ、緋色に燃える空も東から紫色に染まり、暮れなずむ頃、遠く濃い大島の島影に、宝石をちりばめたように町々の灯火がきらめき、ゆったりと回る閃光が灯台の位置を知らせ、漁業無線塔のまたたく赤色灯がかすかに識別できる。南の海上に点々と、イカ釣り漁船の集魚灯が、青く、あるいは黄色く、夕闇に光を放ち、そのさらに沖に、もはやさだかにはみえないが、明るい灯火をマストに掲げた大型船舶が、ゆっくりと航行する。恍惚と眺めるひとときである。
この光景はいつもながらだが、今年は年賀状が乱調子である。元日に大半は届くのに、今年は10日頃まで、数十通ずつさみだれのように配達される。私たちの年賀状も、暮の28日に投函したのに、1月10日にいただきましたなどと、電話やeメールではじめて知るしだいである。昨年の10月から、伊豆高原郵便局は集配業務を行わず、伊東の本局が担当します、と通知があったが、それ以来郵便はとどこおりがちで、昨年11月には沖縄からの普通郵便が10日もかかったことがあった。人員も大幅に減り、月曜日など郵便量の多い日には、夜暗くなってから懐中電灯片手の配達で、局員の方にはほんとうに気の毒だ。これが「郵政民営化」「地方切り捨て」の「小泉改革」の成果である。
ホピ語の不思議な世界
昨年秋、テュソンのアリゾナ大学出版局から刊行された『ホピ語辞典』を手にいれた。A4版の900ページに約30,000語がぎっしりと詰まり、英語による逆引きとホピ語文法を付録とするその分量と内容に圧倒された。アメリカという国(国家ではない)のすごさを改めて実感したしだいである。わが国で、これに相当するような大アイヌ語辞典や大琉球語辞典が刊行されるだろうか。
ホピの協力者48名の名簿に、故シドニー・ナミンハの名を見つけ、思いを新たにした。彼は、私たちの最初の長期滞在に下宿を提供してくれたジュリア・ナミンハの夫であり、薬草など自然についての博学と、思いやりのある誠実な人柄、そしてコーン・ダンス(トウモロコシの最初の収穫祭)の名道化役として、いまなお強烈な思い出をとどめている。
さてそれで、今年こそホピの友人や知人たちにホピ語のグリーティング・カードが書けるぞ、と喜び勇んだのだが、結局挫折し、いつもどおり英語になってしまった。なぜなら英語の逆引きを調べても、ホピ語には挨拶の用語やことばなど一切ないからである。それはなぜか。
その疑問に答えるまえに、すでに他の場所(月刊「言語」など)に書いたが、ホピ語の特色を紹介したい。まずジェンダーである。ホピ語にはインド・ヨーロッパ語(たとえばサンスクリット語、フランス語やスペイン語などロマンス語、ドイツ語や英語などゲルマン語)のような女性・男性・中性など名詞のジェンダーは存在しない。だが重要な語では、女の単語と男の単語がはっきり分かれている。
たとえば「ありがとう」は、女はアスクワリ、男はクァクァイという。「美しい」や「良いこと」の名詞兼形容詞兼副詞では、女はソンワイ、男はロロマという。また日本語はもちろんのこと、英語にさえあるウィメンズ・トーク(フィメイル・トークともいう)、つまり女ことばはホピにもあるし、男ことばより優雅で丁寧だ。だがここは母系社会で、女の権利が世界でももっとも強い社会といわれているのだから、これは性差別の表現ではありえない。
また昔、言語学者のベンジャミン・ワーフが、ホピ語には時制(テンス)がないと断言し、長い間それが信じられてきたが、この辞典の副編集長である北アリゾナ大学のエックハート・マロトキが、ホピ語には標準的平均ヨーロッパ語(SAE)とまったく対称的な時制があることを論じた。つまりSAEでは、過去形と現在形が主で、未来形は英語のwillが典型であるように、意志未来でしかない。ホピは逆で、現在形と未来形が主で、過去形は副詞などで補う弱い過去形でしかない。
マロトキの研究を私なりに補えば、SAEは、人間を主体として表現する言語であり、未来はしたがって「こうしよう」「こうありたい」といった人間の意志に属しているのだ。だがホピでは未来そのものは神々の世界に属し、人間の意志で変えられるものではない。未来形は神々の意志の表現である。現在のみが人間に属し、過去は現在という鏡に映る像でしかないのだ。
こうしたホピ語の深遠な世界を知れば、挨拶ことばがないという事実も了解できるだろう。すなわち、神々や精霊たちが介在しないかぎり、人間は世界や宇宙を、知覚することはできても認識することはできない。その介在のない人間同士の挨拶などは、およそ無益なものなのだ、と(そういえば、私たちに対する村人の挨拶は、いつも英語だった)。
多次元世界の国のアリス
伊豆高原日記⑥で彼女のことを紹介したが、リサ・ランドールの近著『湾曲する通路;宇宙の隠された諸次元の神秘を暴く』(Lisa Randall. Warped Pssages;Unravelling the Mysteries of the Universe’s Hidden Dimensions.Harper Collins,2005)を、必要があって大急ぎで読み終えた。
最初の三分の一ほどは、最近のストリング理論とブレーン(膜)理論の分析で、なかなか魅力的であった。とりわけ、宇宙を10次元として捉える超弦理論(スーパーストリングズ)と、11次元として把握する超重力理論(スーパーグラヴィティ)とが、対立するものではなく、相補的な二元性、つまり同じ現象を異なった視点からみるものであることが、はじめて理解できた。そのうえ各種のブレーン理論が納得のいくかたちで紹介され、それらを統合しようとするエドワード・ウィッテンの野心的なM理論(ミステリー、マトリックスなどのM)の詳細も理解できた。
だが中ほどは「標準モデル」のおさらいと、それと対立するはずのストリング理論との宥和を図るものであり、彼女の学説史上の位置を物語っていた。たしかにストリングズは10のマイナス33乗センチメートルという極微小空間に存在し、逆にその存在をたしかめるためには、10の16乗ギガ(10億)電子ヴォルト(GeV)という途方もないエネルギーを必要とする。それに対して「標準モデル」の素粒子は、せいぜい10のマイナス15乗センチメートル程度の空間、10の3乗GeV程度のエネルギーのレベルにある。この二つのレベルを共存として考えれば、たしかに「標準モデル」が難題とした「階層問題」(微視的世界における重力のほとんどゼロに近い微弱さなどの説明)は解決される。
だがこの二つのレベルを、たんに階層問題の解決として位置づけると、素粒子とストリングズとがどのような関係となるか不明になる。ストリング理論原理主義者たちは「標準モデル」の否定から出発したが、彼女は両者の宥和をはかるストリング理論穏健派といえよう。
最後の三分の一は、彼女がラマン・サンドラムとともに推進した宇宙の5次元説の展開であり、われわれのみている宇宙は、そのなかの4次元時空の局所的なシンクホール(流しの穴、すりばち状湾曲部)であるという論議は、たしかに魅力的である。だがその理論的展開の熱意に比べ、その5次元宇宙が、10次元説や11次元説とどのように折り合っているのか、明確な説明はなかった。
批判はともかく、読んで得るところもたしかに多かった。感謝したい。