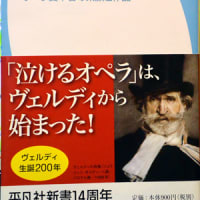北沢方邦の伊豆高原日記【130】
Kitazawa, Masakuni
この夏は各地で猛暑だったようだが、不思議なことに伊豆高原はいつもの夏より涼しく、気温も30度に達する日はついぞなく、とうとうクーラーを一度も使わずに済んだ。こういう夏は晴れていれば海が青く、大島の島影がくっきりとみえ、樹々の間を吹きわたる海風が快く肌をくすぐる。
時代錯誤の「理性」讃歌
この日記でも、60年代に高まった近代理性批判が、新保守主義・新自由主義批判とともに近年ふたたび息を吹き返してきたことにたびたび触れた。だがこうした風潮を真っ向から批判し、近代理性や西欧的近代文明が人類を導く至上の価値体系であるという主張が、きわめて挑戦的・論争的に登場し、反響を呼んでいる。
進化心理学者スティーヴン・ピンカーの『われらの本性なるより良き天使たち;なぜ暴力は没落したか』(Steven Pinker: The Better Angels of Our Nature; Why Violence has Declined. Viking, New York, 2011)という700頁におよぶ大冊である。この春に書きあげた私の本(仮題『世界像の大転換』)へのきびしい知的挑戦でもあるので、ここで批判しておきたい。
すでに年頭に述べたように、今年はジャン・ジャーク・ルソーの生誕300年記念であるが、人類史についての彼の立場は、イギリスの思想家トーマス・ホッブズと真っ向から対立するものであった。ホッブズは人類の原初の「自然状態」は「ヒトはヒトにとって狼である」(Homo homini lupus)ような、個々人が利害を争う闘争の世界であり、それは法と秩序をひとびとに強制的に課するリヴァイアサン(怪物)つまり国家の出現によってはじめて文明状態に転換されたのだ、と説く。
それに対してルソーは、フランスの植民地開拓にともなってアフリカや北米から送られてきた「未開人」についての多くの報告や観察にもとづいて、「自然状態」は逆に、人間が自由で平等で友愛に満ちた社会であって、その後のいわゆる新石器革命(もちろんルソーはこの用語を知らなかったが)による富の蓄積と偏在が文明を生みだし、権力を創りだし、人類に抑圧や強制や暴力をもたらしたのだ、と説いた。
ピンカーはルソーが誤っており、ホッブズが正しいことを、暴力に関する種々の膨大な統計を論拠に執拗に展開する。つまり現在の「未開」諸社会やいわゆる発展途上国などの「殺人率」は、現在の先進文明諸社会に比べ、非常に高く、かつての人類の自然状態がいかに恐ろしい闘争社会であったかを実証している。20世紀の二つの世界大戦の恐るべき数の犠牲者にしても、人口10万人当たりの殺人率に換算すれば、「未開」よりはるかに低いというのだ。
さらに彼は無数の文献を引用して、古代文明や中世文明にあっても、宗教的迷信から風俗習慣にいたるすべてのレベルで、無知にもとづく人身供儀や戦争による殺戮、捕虜や奴隷の拷問や虐待など恐るべき人権侵害がいかにひろくおこなわれていたかと、これでもかこれでもかと提示する。
こうした「野蛮」から人類を救ったのは、第1に18世紀啓蒙思想による近代理性の確立、彼の用語によれば「人道革命」(The Humanitarian Revolution)であり、第2には、人種、マイノリティ、性、同性愛などすべてにわたる人権の確立を求めた20世紀の「権利革命」(The Rights Revolution)であるという。その結果人類は、20世紀後半から世界史上類のない暴力の没落にともなう「長期平和(ロング・ピース)」の時代を実現したのだという。これはまたダーウィンのいう自然選択にもとづく人類の生物学的進化にも沿う現象でもあるとして、自称無神論者ピンカーは、かつてカトリック司祭でもある古生物学者テイヤール・ド・シャルダンが唱えた、ヒトの進化の軸は西欧を通り、西欧近代文明は生物進化の頂点となったという説と、奇妙な同盟を結ぶ。
近代的論理または「理性」の破綻
だがこれらの主張には論理的破綻がある。まず経験論に立つ論客がかならず依拠する統計の問題である。近代戦争とまったく異なる文化である部族間・部族内戦争を、その意味や質とは切り離して統計の問題として考えてもよい。たとえば彼のいう「殺人率」(murder rate)は、人口10万人当たり殺人何人で計算するが、たとえば人口100の小部族がそういった戦争で1人を失うとしよう。だが人口10万人に換算すると殺人1,000人という途方もない率になり、それで「未開」の殺人率は異常に高いと断定されることとなる。こうした単純な統計的比較こそ異常というべきだろう。
この意味での殺人率の急激な低下を彼は理性による上記の「諸革命」、あるいは近代文明の政治形態である近代民主主義、経済形態である自由市場がもたらす「豊かさ」やテクノロジーの進展のせいにしているが、たとえば国連麻薬・犯罪局の作成した2004年の「世界における殺人地図」(p.88に引用)を見てみよう。そこでは10万人当たり殺人0から3人という世界で最も安全な地帯がもっとも薄い色で表示されている。それはカナダ、オーストラリアを含みヨーロッパ、北アフリカと中近東(戦争渦中であったイラクは例外だが)、中国と韓国と日本である。
心ある読者はすぐ理解するであろうが、これはまさしくキリスト教・イスラーム・仏教(および道教)という世界宗教が歴史的にもっとも浸透し、大衆化された地域である。無神論者ピンカーは無意識にあるいは意図的にこの事実を無視している。
彼はこの地図を、近代文明的であれ、集権的であれ、リヴァイアサン(怪物としての国家)がもっとも有効に統治している地域としているが、むしろ宗教やその影響下に育った文化の問題であること、いいかえれば人間のもっとも深い内面性の問題にまったく無知であることをおのずから告白している。
この本の読書中、苛立ちどころか怒りさえ覚え、読み進めることが大きなストレスでさえあったが、最後にはたと思い当たった。すなわちこれは、現在合衆国で再起を伺う近代理性至上の新保守主義・新自由主義イデオロギー──現在共和党を牛耳っているティー・パーティー(茶会党)はキリスト教原理主義である──の強力な知的援軍なのではないか。
ハンティントンの『文明の衝突』が、主としてイスラームという「近代文明の敵」との衝突の不可避性を分析し、その弟子フランシス・フクヤマが、その衝突を克服する処方箋として、近代民主主義と自由市場経済というグローバリズムの世界制覇が、衝突や葛藤を終わらせ、『歴史の終焉』を導くのだ、としたが、スティーヴン・ピンカーは、世界を近代文明という普遍的な「文明化の過程」に巻き込むことがカントのいう「永久平和」を保障する唯一の道である(カントも地下で苦笑しているだろう)として、これらの主張を補強し、脱近代文明論者たちに一撃をあたえたと信じているようだ。
だがこの大冊を読み終えた後でも、ホッブズではなく、ルソーの人類史的洞察が正しいという確信はまったくゆらぐことはなかった。なぜなら、私のこの確信の根底にはつねにホピがあるからだ。