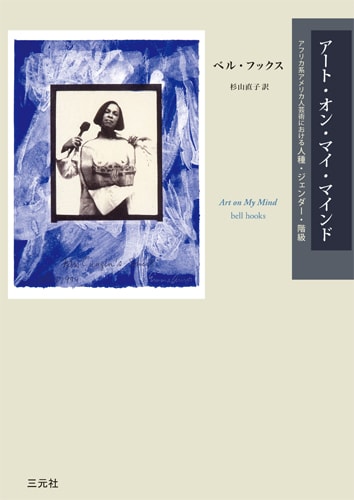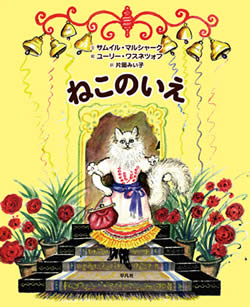『シモーヌ・ヴェーユ回想録
―――20世紀フランス、欧州と運命をともにした女性政治家の半生』
シモーヌ・ヴェーユ著 石田久仁子訳
(パド・ウィンメンズ・オフィス 3000円 2011年7月15日刊行)

本書は、フランスで2007年12月に出版され、発売と同時にベストセラーとなった、フランスのユダヤ系女性政治家シモーヌ・ヴェーユ(1927-)の回想録である。ヴェーユは高校生であった1944年に強制送還されたアウシュビッツ=ビルケナウ収容所を生き抜き、戦後は、保健大臣としてフランスに人工妊娠中絶の自由化を実現し、欧州議会の初代議長として欧州統合に尽力した、国民の信頼厚く、国際的にも評価の高いフランスの良心を代表する政治家である。
18才でビルケナウから奇跡の生還を果たしたヴェーユは、ホロコーストで失われた家族にかわる新しい家族を自ら作り上げた後、夫を説得し、戦後新たに女性にもひらかれた司法官養成制度を利用して自らのキャリアを築いていく。法務官僚だった1974年に保健大臣に抜擢され、数ヶ月後には当時のフランス女性の切実な願いだった人工妊娠中絶の自由化を3日間に及ぶ国民議会本会議の審議を経て実現、一躍女性の自由の象徴的存在となる。その後30年近く政治家として国内および欧州を中心とする国際舞台で活躍、政界引退後は憲法院判事やショア記念財団理事長を務め、一貫して人間の尊厳や人権の擁護、とりわけ女性の人権や自由の擁護に取り組んできた、国民の尊敬を集める女性である。
一読して感じるのは、彼女の偉大さと謙虚さ、そして、人間への信頼と愛、誠実さである。アウシュビッツ=ビルケナウで地獄を経験し、家族を失い、生還後もなお生き抜いた者に向けられる二重三重の差別に直面したにもかかわらず、彼女は人間や社会への信頼を失わない。司法官時代の刑務所改革、保健大臣時代の中絶の自由化、欧州議会議員(議長時代を含む)時代の欧州統合への情熱(それは二度とホロコーストを起こさないためには必要不可欠だった)、ホロコースト以後に起きた大虐殺への糾弾。数々の仕事の局面で、社会の回復力を信じ、人間の尊厳、人権の尊重、正義の擁護のために闘い続けている。
その姿勢は、彼女自身の資質や育った家庭環境、ホロコーストを生き抜いた証人としての使命感にもよるが、彼女自身が突き止めたとおり、フランスが在住ユダヤ人全体に占める強制移送されたユダヤ人の割合がもっとも低い国だったことと無縁ではなかっただろう。ヴェーユは長い年月の間に歴史の真実を執拗なまでに追求し、戦時中のユダヤ人強制移送におけるフランス国の責任を認める大統領の謝罪の実現(1995年)へ働きかけると同時に、占領時代のフランス政府に一定の理解を見せ、占領時の市民生活を批判的に描いた映画を批判し、2007年には、ショア記念財団理事長として、「正義の人々」―大戦中にユダヤ人を匿い、支援した多くのフランス国民―に感謝の言葉を捧げている。
これほど有能で、「女性の大義のために闘うフェミニスト」であることを自認し、女性のチャンスが偶然に支配されすぎており、「法律やもう少し一般的な社会的ルールから生まれることが少なすぎるのだ。女性の被っている不平等が改善すれば、社会に利するだけだ」と確信しているヴェーユが、ポジティブ・アクションやクォータ制について説くのは、声高にそれを要求したり保守層を刺激したりするような論争を行うのではなく、実践してしまうことである。それは、1974年の人工妊娠中絶の自由化の審議をはかる国民議会の演説で、生命についての哲学的論争や保守層を刺激するような女性の身体の自己決定権としての中絶の権利の主張を行うことを注意深く避け、子育てを社会全体でサポートするための家族政策の推進を約束しながら、中絶問題をもっぱら母として子どもを育てられるかどうかの責任の問題として提示し勝利した彼女の、「政治家」としての長年の経験と智恵が言わせたものであろう。夫婦別姓等、日本における女性問題を考える際にも、政治家/実務家のスタンスとして実に参考になるのではないだろうか。
(本書は知と文明のフォーラム評議員の石田久仁子さんの訳書である。このすぐれた女性の人生を知る機会を与えてくれた石田さんに感謝の意を表します。)
katakata