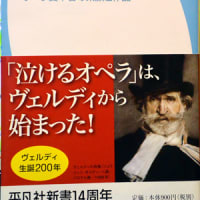楽しい映画と美しいオペラ――その34
現代に息づくバッハとモーツァルト
―アーノンクール最後の日本公演
現在の古楽隆盛の礎を築いたのは、オランダのグスタフ・レオンハルトとオーストリアのニコラウス・アーノンクールである。この二人は、200曲近くもあるバッハの教会カンタータを、18年かけて全曲録音するという偉業を成し遂げた。1970年から88年にかけてのことであり、古楽器の全集としては最初のものであろう。我が家には全曲揃っているわけではないが、彼らの指揮するカンタータは比較的よく聴くCDのうちのひとつである。
レオンハルトはこの20年間たびたび来日し、私も2度、その端正なチェンバロ演奏に接することができた。フォルクレ、ベーム、クープランなど普段あまり耳にすることのない作曲家の音楽を愉しむことができたのも、レオンハルトのおかげである。しかしアーノンクールは来日の回数が極端に少なく(1980年と2006年のみ)、いままで実演を聴く機会はなかった。その彼が最後の日本公演を行うというので、これは何としても聴かねばなるまいと、バッハの『ミサ曲ロ短調』を聴きに出掛けた。
カトリック教会のミサの式文をもとにしているミサ曲は、どの作曲家のものであっても内容は同じである。すなわち、〈キリエ〉( あわれみの賛歌) , 〈グロリア〉( 栄光の賛歌) , 〈クレド〉 (信仰宣言) ,〈サンクトゥス〉(感謝の賛歌) ,〈アニュス・デイ〉(平和の賛歌)の5曲一組で構成されている。歴史をさかのぼると、その嚆矢は14世紀フランスのギヨーム・ド・マショーの『ノートルダム・ミサ』であるという。15世紀のギヨーム・デュファイ、16世紀のジョスカン・デ・プレ(いずれもフランドル)、パレストリーナ(イタリア)などが名曲を残している。
バッハの『ミサ曲ロ短調』はその伝統に連なるものだが、先行の作品群とは一線を画している。オーケストラが加わって規模が大きくなり、アリアや重唱が合唱とともにミサの式文を歌う。そのような楽曲構成上の差異もさることながら、表現そのものがはるかに多様になっている。例えばジョスカン・デ・プレの多声の扱い方はギヨーム・ド・マショーに比べると複雑で、ア・カペラの合唱の響きは天国的な美しさである。しかし式文間の差異はそれほどなく、現代人の耳にはどうしても単調に聴こえてしまう。それから200年を経たバッハ作品の豊穣さには、これが同じジャンルの曲なのかという驚きすら覚える。17世紀以降、オペラという新しい分野の出現もあり、西洋音楽のあり方に大きな変化が生じたであろうことも実感させられる。
バッハの音楽の豊穣さは、神への強い信仰心と、普通人としての日常生活の哀歓とが、稀有なかたちでひとつになったところから生まれたものではないだろうか。弦楽器や管楽器のソロを伴って歌われるアリアや重唱の透明感極まりない美しさも、人間、それも心優しい人間の高い香りがする。オペラを指揮して聴く人の心を惑乱させるアーノンクールは、人間の心をよくとらえている。神を賛美する人の心の表現も、聴く者が容易に納得できるものである。平常でありながら崇高。心は高揚し、またしみじみと慰められる。
もう30年以上も前のこと、モーツァルトの『レクイエム』がFMラジオから流れてきたことがあった。聴きなれているものとは異なった素朴な響きとともに、声楽の扱い方に強い印象を受けた。声をまるで楽器のように操っている、と感じたのだ。古楽器について、またアーノンクールという名前についても、そのときはじめて知ったのだった。「声を楽器のように操る」とは、声とオーケストラが一体であるということである。実演を聴いて、私は、遥か昔の第一印象をまざまざと思い出した。ソプラノのレッシュマンもテノールのシャーデも、現代有数のオペラ歌手である。彼らソリストも合唱団も、完璧にアーノンクールの手の内にあった。しかも表現意欲にあふれた歌いぶりである。類い稀なこの均衡こそ、アーノンクールの音楽の真骨頂であろう。
〈グロリア〉のあとの休憩時間、私は会場でモーツァルト・プログラムのチケットを購入した。『ミサ曲』の前半を聴いてすでに深い感動を覚えた私は、アーノンクールのモーツァルトを是非この耳で聴いてみたくなったのだ。CDに録音された彼のモーツァルトにはいささか違和感を持っていた。ブルーノ・ワルターの流麗なモーツァルトを聴き慣れていた耳には、刺激的な音が多すぎたようだ。80歳を過ぎて、彼のモーツァルトはどのように変貌を遂げているのか、興味は尽きなかった。
それは衝撃的なモーツァルトだった。とりわけ後半の『ハフナー交響曲』には心底圧倒された。まさにアーノンクール節満開で、円熟という言葉を軽やかに吹き飛ばしてくれた。例えばCDでは恣意的と感じられた第3楽章メヌエットの冒頭部分は、実演ではさらに強調されたものとなったが、不自然さは微塵もない。そこは確かにそう演奏されなければならないと、大いに共感したものだった。リズムはまことにしなやかで、数え切れないほど演奏を重ねているだろうこの曲を、どうしてこのように新鮮に響かせることができるのだろうと、驚嘆するしかなかった。
2つの音楽会を通して、アーノンクールは、CDやDVDなどの小さな枠には収まりきれない、真に偉大な音楽家であることを強く認識させられた。そして、その彼がもっとも敬愛する音楽家がバッハとモーツァルトであることを知り、彼への共感の思いはさらに深まったのであった。
2010年10月26日 サントリーホール
バッハ『ミサ曲ロ短調』
ソプラノ:ドロテア・レッシュマン
メゾ・ソプラノ:エリーザベト・フォン・マグヌス
メゾ・ソプラノ:ベルナルダ・フィンク
テノール:ミヒャエル・シャーデ
バリトン:フローリアン・ベッシュ
アーノルト・シェーンベルク合唱団
ウィーン・コンチェントゥス・ムジクス
2010年11月2日 東京オペラシティコンサートホール
モーツァルト『セレナード第9番ニ長調K.320〈ポストホルン〉』
『交響曲第35番ニ長調K.385〈ハフナー〉』
ウィーン・コンチェントゥス・ムジクス
2010年11月29日 j-mosa