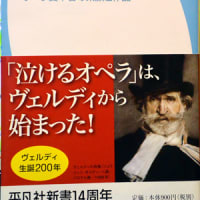楽しい映画と美しいオペラ―その39
文楽、この誇るべき日本のオペラ
このところ大阪維新の会の躍進が目覚ましい。その影響は大阪という地域を越えて、全国的な規模になりつつある。社会が停滞の度を深めると、勇ましく、メリハリの効いた発言をする人間に注目が集まる。橋下大阪市長はその典型で、思想の中味は小泉元首相の新自由主義的発想と何ら異なるところはない。表現の仕方、問題の立て方まで似ている。小泉政権時代の6年間が私たちの生活に何をもたらしたのか、冷静に考えてみるべきだろう。そして民主主義について、思考を深めるべきである。
さてその橋下市長だが、教育への政治介入を目論む一方、文化政策にも大鉈をふるおうとしている。日本の古典芸能のひとつで、大阪を発祥とする文楽(人形浄瑠璃)への補助金を見直すという。財政難に陥るとまっ先に削減されるのは文化予算であるのは世の常だが、こと文楽に関しては慎重を要する。
芸術をどう支えていくかは、難しい問題である。芸術と助成金、昔でいえば芸術家とパトロンの問題である。そもそも支えるという発想がおかしい、芸術は自由なものであり、いかなる庇護も受けるべきではない、という考え方ももちろんある。そうでなければ権力の批判などできない、というわけだ。
ところで人形浄瑠璃の発祥は1700年前後の大阪。この頃、私の大好きな作曲家バッハとヘンデルがドイツで生まれている(共に1685年生まれ)。この二人の対照的な生涯は、芸術家と経済の問題を考える上で大変興味深い。バッハは青年時代、ヴァイマルやケーテンの宮廷に仕え、38歳から65歳で亡くなるまでは聖トーマス教会に属した。教会のカントル(楽長職)であり、ライプツィヒ市の音楽監督も歴任した。生涯組織に属し、組織のために曲を作り、その階梯を上り詰めたのだ。一方ヘンデルは、20歳代早々にイタリアで名声を得、ロンドンでは王室礼拝堂作曲家の任にありながら自らオペラ団を主宰した。その経営に苦悶しながらも、大衆に向けてオペラを書き続けたのである。そしてこの二人の残した作品は、互いに異質な部分を含みながら、いずれも人類の遺産と呼ぶにふさわしい。現代の音楽は彼らの存在なしには考えられもしないだろう。
どうやら偉大な芸術家は、どのような環境下に置かれても、偉大な作品を生み出すものであるようだ。そしてその作品は残っていく。このことは十分承知した上でしかし、ありとあらゆる文化が乱立する現代の文化状況下では、芸術助成の問題は熟慮を重ねる必要があると思う。また文楽に欠かせない義太夫や三味線についていえば、それらが庶民の手慰みであった時代はとうに終わっているのだ。規制緩和し、あらゆるものを自然の淘汰に委ねるという新自由主義的発想では、本当に大切な日本の文化が廃れてしまいかねない。
さて私は、このところ何度か、文楽を観に国立劇場へ出掛けた。その面白さに引かれて、1月には大阪の国立文楽劇場へまで足を延ばした。この歳になるまでどうして文楽と真剣に向き合うことがなかったのだろうと、臍を噛む思いに苛まれながら。文楽は、音楽と演劇が一体となった、まさに日本のオペラなのである。その質の高さに、私は日本人であることに喜びをさえ覚えたものだ。
文楽の中心は、何といっても義太夫を唄う大夫だろう。オペラでいうなら歌手、いやそれを超えた存在である。登場するすべての役柄を一人で唄い、演じなければならない。おまけに筋書きをも語る。そしてオーケストラに相当するのが三味線である。これは単なる大夫の伴奏であってはならない。彼に拮抗する力を持つ必要がある。オペラ歌手に対してのオーケストラと同じである。しかし指揮者は存在しない。音楽は、大夫と三味線奏者二人の手で作り上げられる。その音楽を視覚的に表現するのが人形なのだ。
人形は、三人の男によって操られる。頭と右手を操る主遣いがいて、あとは左手と足の操作にそれぞれ一人。1月に『七福神宝の入舩』という演目を観たが、人形7体のこの舞台に、何と大の男が21人も登場していたことになる。三人で操る人形だけに、眉、目、口と顔の表情は細やかで、動作のしなやかなことも筆舌に尽くし難い。
大夫、三味線、人形と、この三者が混然一体となることで、時に白熱の名舞台が生まれる。昨年12月9日の『奥州安達原』である。中でも「環の宮明御殿の段(たまきのみやあきごてんのだん)」の〈前〉の場面、大夫は竹本千歳大夫、三味線豊澤富助。勘当された袖萩が娘を連れて武家である実家に帰って来る所である。零落して盲目になった娘を主人の平仗(たいらのけんじょう)は赦すことができない。母親は間に立っておろおろするばかり。武士の体面の愚かしさと、どうにもやるせない親娘の情。
千歳大夫は声涙ともに下るかとばかりに唄い上げ、富助の嫋々たる三味線がずしりと心に響く。袖萩の哀れさは桐竹勘十郎がまた余すところなく演じた。人形は人間の感情の上澄を掬いとる。生の感情が抽象化されることで、一層哀れさが身に泌みる。人形の動きひとつひとつに私は涙を禁じ得ず、周りを見れば、ハンケチを取り出して皆泣いている。悲哀の情が会場に充ちていた。舞台と観衆とがこれほど一体となった瞬間も珍しい。
文楽というこの貴重な文化遺産を、どのようして後世に伝えていくのか。国、自治体、文楽協会、そして私たちも、真剣に考えなければならない。
2012年2月26日 j-mosa