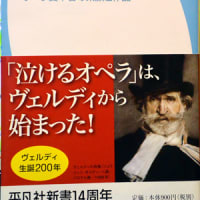北沢方邦の伊豆高原日記【53】
Kitazawa,Masakuni
各地この冬一番の冷え込みとのこと、わが家北側の日蔭に、この冬はじめて霜柱が立つ。しかし陽射しは日々まばゆさを増し、早咲きの白梅の小さな花々がもう五分咲きとなり、メジロたちが逆さになって蜜を吸っている。
ガザの大量殺戮
イスラエル軍の空爆と侵攻で、学校やモスクや国連施設を含む多くの建物は廃墟となり、女性や子供約400人や多くの男性民間人を含む1105人が死亡し、負傷者は5130人となる(1月16日現在アル・ジャズィーラによる)。またすべての検問所の封鎖のうえ、国連の食料・医薬品など援助物資の倉庫も炎上し、ガザ全土は飢餓状態にあり、医薬品も底をつき、負傷者の多くは放置されるという悲惨な状況にある。
停戦期限の終了後、ハマースその他の組織の一部軍事部門がロケット弾をイスラエル領内に撃ち込んだとはいえ、あまりにも過剰な反撃であり、国際法や国連決議(すでにこの数十年、イスラエルは多くの国連決議を黙殺してきた)など、すべてを無視した暴虐な行為である。それが、3月に行われるイスラエル総選挙のための政党カディマの人気取りだとあれば、もはや言語道断ということばさえ甘くひびく。かつてナチスがユダヤ人に行ってきた人種差別にもとづくホロコーストを、いまやイスラエルのユダヤ人がパレスティナ人に行っているのだ(イスラエル内にももちろん平和主義者や人種差別反対者たちがいるが、あまりにも少数派である)。
われわれの政府や諸政党が党利党略の国会対策にかまけ、このパレスティナの窮状に目をそむけているのも許しがたい。総理大臣や外務大臣は、ガザのひとびとの痛みにまったく無感覚なのか。与野党を問わず、アラブやイスラーム諸国に石油資源の多くを依存しているという「わが国の国益」を考える政治家さえもいないのか。わが国には、国際的人権感覚をもつ政党は皆無なのか。だれか、ひとりでも声を挙げる政治家はいないのか。
ロックとはなんであったか
先週、BBCのドキュメンタリーSeven Years of Rockが、10数回に分けてNHKBS1で放映された。仕事のあいまに断片的に見ただけだが、いろいろな意味で面白かった。
1971年、ハード・ロックの全盛期にアメリカを訪れたとき、ワシントンDCで見た当時大流行のロック・ミュージカル『ヘア』、サンフランシスコで立ち会ったザ・フーのロック・オペラ『トミー』の上演など、いくつかのロック・シーンにかかわった新鮮な記憶がよみがえる瞬間であった。とりわけサンフランシスコのある短期大学の体育館での『トミー』の公演では、私たちの席のすぐ隣がザ・フーの演奏者たちのピットであり、伝説のギター奏者ピート・タウンセンドが、阿修羅のごとく演奏しているのをまじかにした。
またシカゴでは、偶然泊まったヒルトン・ホテルが、1968年の大統領選挙で民主党の党本部となり、予備選で選出された反戦候補ユージン・マッカシーを退け、ハンフリーを大統領候補とした決定に対する嵐のような抗議デモが襲った当のホテルであることを知り、窓の外にひろがる流血の舞台となった緑の公園ともども、感銘深く眺めたものである。いうまでもなくその8月29日にザ・シカゴが結成され、あの記念碑的なロック『解放(リベレーション)』3部作(プローローグ、ある日、解放)を抗議集会で奏でたのだ。
ザ・グレイトフル・デッド、ピンク・フロイド、ローリング・ストーンズ、あるいは異色のアフリカン・ロック、オシビサなどはレコードやテープで知ったにすぎないが、それでもそれらの身体をゆさぶるハード・ロックの大音響に、魂までゆさぶられる思いをした。アフリカのトーキング・ドラムのポリリズムを基底にしたオシビサはもちろんのこと、これらハード・ロックには明かに近代を超える音の世界があった。なぜなら、ほんとうの人間本性(ヒューマン・ネイチャー)である身体性、とりわけ大自然のリズムである心臓の鼓動を2分割した8ビート・リズムのもつ身体性は、魂まで躍動させる力をもっているからである。
このドキュメンタリーで私にとって興味深かったのは、その後追跡しなかったハード・ロック以後のロックの歩みであった。おどろおどろしいメイキャップや衣裳で鬼面ひとを驚かすパンクやグラムのアーティストたちは、かつてロックの頽廃期としか思えなかったが、それらにすら強烈な反体制のメッセージがあるのにむしろ感動した。
また、かつて洗車場のアルバイトをしていたというブル-ス・スプリングスティーンは、そう思わせるような下層労働者の身なりで奏で、唄うが、そこにも恐るべき反体制のメッセージが込められていた。たとえば彼を有名にしたBorn in the U.S.A.である。レーガン大統領がこれを愛国歌と勘違いして、彼の議会演説で称揚したが、インタヴューに応じたザ・ストリート・バンド(スプリングスティーンのバック・バンド)のメンバーが、そのテレビを見て、「みんなで笑うしかなかったよ」と語っていた。
ふつう国名には定冠詞theをつけることはないが、そこがミソである。当世の若者風に翻訳すれば「アメリカ合衆国とかに生まれちゃってよお」となるだろう。歌詞は、合衆国に生まれたがゆえに、ライフルを手渡され、ヴェトナムにアジア人を殺しに行かされて……とつづく。つまり反戦歌なのだ。これを聴いたヴェトナム帰還兵たちが涙したというのも当然である。
スプリングスティーンが前回の大統領選挙で、同じヴェトナム帰還兵(メコン河の海軍高速艇の艇長ではあったが)で反戦主義者であったケリー候補の応援キャンペーンを張り、今回はオバマ候補を徹底して支持したのもゆえなしとしない。 U2のボノがアフリカの貧困支援に情熱を燃やすなど、ロック・スターには政治的・社会的行動にのめりこむものが多いが、それはつねにロックの歴史を流れるこの反体制・反戦の反骨からきている。
ボブ・マリーがはじめたジャマイカのレゲエもそうであったが、ロックのこの強烈なメッセージは、わが国ではつねに濾過され、大会場で熱狂するだけのたんなるファッションとなって終ってしまうのはなぜだろう。言語の問題だけではない。おそらく戦後63年の、ほとんど惰性とさえいえる「平和」(それが悪いとはいえないが)がなせる業であろう。ガザの状況に対する危機意識の欠如も、まさにそれである。