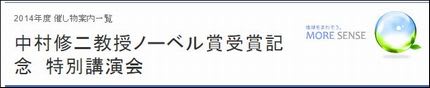先日、日本でのこれからのロボット実用化・製品化を語るパネル・ディスカッションを拝聴しました。
そのパネリストのお一人は、日本のロボット系ベンチャー企業の草分けとなるフラワー ロボティクス(Flower Robotics、東京都港区)の代表取締役社長を務める松井龍哉さんでした。

日本の既存の大手企業が革新的な製品開発の実用化に苦悩している現在、「当社は家庭用ロボットのプラットフォームを提供することで、いくつかの企業群と互いの技術や知恵を持ち寄って、新しい家庭用ロボットを製品化していきたい」と、これからの製品開発の手法を語ります。
松井さんは、文部科学省系の科学技術振興機構(JST)が実施した大型研究開発プロジェクトのデザイナー系研究者として研究開発を続けた後に、2001年にフラワー ロボティクスを創業し、2005年2月に同社を株式会社組織にしたそうです。
フラワー ロボティクスは、2014年9月18日に「機能拡張型 家庭用ロボット『Patin』(パタン)を開発中で、2016年に製品化する」と発表し、注目を集めました。Patinとは、フランス語で「スケート」を意味するそうです。このロボットは“スケート靴”として移動し、その上に載せた家電製品・生活用具・家具などを移動させることで、新しい家庭用ロボットが誕生すると提案します。

このPatinは、AI(Artificial Intelligence、人工知能)搭載の自走式ロボットです。例えば、Patinの上に照明器具ユニットを載せると、自宅の中を人間が移動した時に、最適な位置まで移動し、最適な明るさの照明を与えるなどの働きをします。Patinは3次元カメラを搭載し、空間認識機能を持っているからできる“芸当”です。そして人工知能によって、学習機能を発揮します。
「これからは自宅で働く在宅勤務者が増え、その仕事や生活をサポートする家庭用ロボットのニーズが高まる」と解説します。同社は、2016年でのPatinの製品化を目指しています。
各種のサービス機能を実現するために、ソフトウエア開発キット(Software Development Kit、SDK)を公開し、共同開発体制を整えています。こうしたやり方は、従来のパソコンなどのアプリケーション開発のやり方そのものです。フラワー ロボティクスは、主にアプリケーションなどのソフトウエア系の技術開発に力を入れています。
松井さんは、ベンチャー企業がロボットのプラットフォームを提供し、それに既存の企業が自社向けのアプリケーションを開発し、製品化していくやり方を提案します。これによって、各用途向けのアプリケーションを実用化していく態勢です。
このロボット実用化・製品化を語るパネル・ディスカッションでは、あるパネリストは「昔の大企業の研究開発部門には、何を研究開発しているか分からない先輩などがいたが、最近は研究開発計画や事業化計画が明確でない研究開発テーマはさせてもらいない時代になった」と語ります。「本業の既存の事業が時代の流れに合わなくなった時に、次の新規事業のタネがなく、経営が行き詰まる傾向が、現在の大手企業は多い」と指摘します。
もう一人のパネリストは「これからのロボットは、サービス産業として、アプリケーション使用料を月当たりなどの時間単位で徴収するサービス型を目指すことが賢い」とビジョンを語りました。新しい改良したアプリケーションをネットサービスで提供し、その使用料をもらう、現在のパソコンのアプリケーションやスマートフォンの利用料のような概念です。
これからは、生産支援型や介護支援型などの様々なロボット(姿はさまざま)が登場します。その事業形態に対する示唆に富むパネル・ディスカッションでした。
そのパネリストのお一人は、日本のロボット系ベンチャー企業の草分けとなるフラワー ロボティクス(Flower Robotics、東京都港区)の代表取締役社長を務める松井龍哉さんでした。

日本の既存の大手企業が革新的な製品開発の実用化に苦悩している現在、「当社は家庭用ロボットのプラットフォームを提供することで、いくつかの企業群と互いの技術や知恵を持ち寄って、新しい家庭用ロボットを製品化していきたい」と、これからの製品開発の手法を語ります。
松井さんは、文部科学省系の科学技術振興機構(JST)が実施した大型研究開発プロジェクトのデザイナー系研究者として研究開発を続けた後に、2001年にフラワー ロボティクスを創業し、2005年2月に同社を株式会社組織にしたそうです。
フラワー ロボティクスは、2014年9月18日に「機能拡張型 家庭用ロボット『Patin』(パタン)を開発中で、2016年に製品化する」と発表し、注目を集めました。Patinとは、フランス語で「スケート」を意味するそうです。このロボットは“スケート靴”として移動し、その上に載せた家電製品・生活用具・家具などを移動させることで、新しい家庭用ロボットが誕生すると提案します。

このPatinは、AI(Artificial Intelligence、人工知能)搭載の自走式ロボットです。例えば、Patinの上に照明器具ユニットを載せると、自宅の中を人間が移動した時に、最適な位置まで移動し、最適な明るさの照明を与えるなどの働きをします。Patinは3次元カメラを搭載し、空間認識機能を持っているからできる“芸当”です。そして人工知能によって、学習機能を発揮します。
「これからは自宅で働く在宅勤務者が増え、その仕事や生活をサポートする家庭用ロボットのニーズが高まる」と解説します。同社は、2016年でのPatinの製品化を目指しています。
各種のサービス機能を実現するために、ソフトウエア開発キット(Software Development Kit、SDK)を公開し、共同開発体制を整えています。こうしたやり方は、従来のパソコンなどのアプリケーション開発のやり方そのものです。フラワー ロボティクスは、主にアプリケーションなどのソフトウエア系の技術開発に力を入れています。
松井さんは、ベンチャー企業がロボットのプラットフォームを提供し、それに既存の企業が自社向けのアプリケーションを開発し、製品化していくやり方を提案します。これによって、各用途向けのアプリケーションを実用化していく態勢です。
このロボット実用化・製品化を語るパネル・ディスカッションでは、あるパネリストは「昔の大企業の研究開発部門には、何を研究開発しているか分からない先輩などがいたが、最近は研究開発計画や事業化計画が明確でない研究開発テーマはさせてもらいない時代になった」と語ります。「本業の既存の事業が時代の流れに合わなくなった時に、次の新規事業のタネがなく、経営が行き詰まる傾向が、現在の大手企業は多い」と指摘します。
もう一人のパネリストは「これからのロボットは、サービス産業として、アプリケーション使用料を月当たりなどの時間単位で徴収するサービス型を目指すことが賢い」とビジョンを語りました。新しい改良したアプリケーションをネットサービスで提供し、その使用料をもらう、現在のパソコンのアプリケーションやスマートフォンの利用料のような概念です。
これからは、生産支援型や介護支援型などの様々なロボット(姿はさまざま)が登場します。その事業形態に対する示唆に富むパネル・ディスカッションでした。