映画における作りの上手さとは。
私は今まで様々な映画を観てきた。
音楽もそうだが、趣向とするのは「ノンジャンル」
ジャンルにとらわれては良い映画、良い音楽と巡りあうことはない。
その様々な映画を観て思ったことがある、名作映画とは何か?
名作映画とは多くの人々に作品を印象付け、感銘等を与えるものである。
昔フランスの「アレクサンドル・アストリュック」が「カメラ=万年筆」を提唱した。
これが全てとは言わないが、私は正論であると思っている。
カメラが物語りを書いて行く、その下層に脚本がある。
フランス派生した「ヌーベルバーグ」が台頭した頃、初めに脚本あらず、現場にて脚本ありと言う映画の製作方法が一部主流になった。
古い映画フアンで当時若かった人々はその斬新さに驚いたと側聞したことがある。
しかし最近では派手なSFXや凝った脚本中心の映画が多いと思う。
私は昔の映画をもっと観て欲しいと思っている。
残念ながら今観ると「ヌーベルバーグ」作品などはどうしても古さや作りの身勝手さが鼻につくかもしれない。
しかしそれ以前の映画で名作は沢山ある。
カメラ、脚本それそれが素晴らしく一体になった映画では「第三の男」が挙げられるだろう。
私はこの映画を最初に観たとき、その作りの斬新さに驚嘆したものだ。
この映画は音楽も秀逸でまさに隙のない見事な映画である。
見た目の派手さや、脚本だのみになっている映画は感心できない。
最近では以前このブログで紹介したタルベーラー監督の「ニーチェの馬」などが「カメラ=万年筆」として傑作だろう。
今一度カメラの持つ、観客に訴えかける可能性を見直すべきではないだろうか。
私は今まで様々な映画を観てきた。
音楽もそうだが、趣向とするのは「ノンジャンル」
ジャンルにとらわれては良い映画、良い音楽と巡りあうことはない。
その様々な映画を観て思ったことがある、名作映画とは何か?
名作映画とは多くの人々に作品を印象付け、感銘等を与えるものである。
昔フランスの「アレクサンドル・アストリュック」が「カメラ=万年筆」を提唱した。
これが全てとは言わないが、私は正論であると思っている。
カメラが物語りを書いて行く、その下層に脚本がある。
フランス派生した「ヌーベルバーグ」が台頭した頃、初めに脚本あらず、現場にて脚本ありと言う映画の製作方法が一部主流になった。
古い映画フアンで当時若かった人々はその斬新さに驚いたと側聞したことがある。
しかし最近では派手なSFXや凝った脚本中心の映画が多いと思う。
私は昔の映画をもっと観て欲しいと思っている。
残念ながら今観ると「ヌーベルバーグ」作品などはどうしても古さや作りの身勝手さが鼻につくかもしれない。
しかしそれ以前の映画で名作は沢山ある。
カメラ、脚本それそれが素晴らしく一体になった映画では「第三の男」が挙げられるだろう。
私はこの映画を最初に観たとき、その作りの斬新さに驚嘆したものだ。
この映画は音楽も秀逸でまさに隙のない見事な映画である。
見た目の派手さや、脚本だのみになっている映画は感心できない。
最近では以前このブログで紹介したタルベーラー監督の「ニーチェの馬」などが「カメラ=万年筆」として傑作だろう。
今一度カメラの持つ、観客に訴えかける可能性を見直すべきではないだろうか。










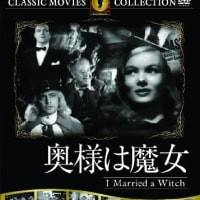
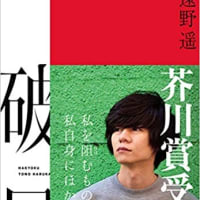

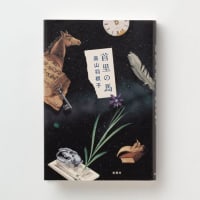


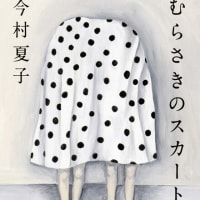
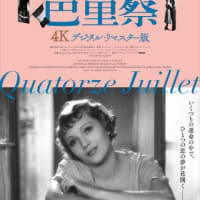


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます