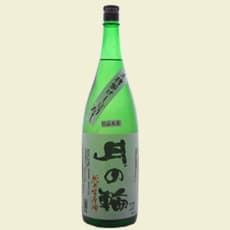最近、上さんが友人に誘われてこんにゃく作りに2回ほど行った。
こんにゃく芋から作る本格的こんにゃくである。
以前は、私も何度か作ったことがあって、それほど難しいことはない。
ただ手がかかるのは間違いない。
今回のこんにゃくは前回に比べて出来が悪い。
しっかり形が取れていないというか、若干型崩れの部分がある。
しかし、売り物ではないのでそれで十分なのだ。
さて、手作りこんにゃくのいいところは、まず新しいので刺身にできる。
できたてをきっちり冷やして、薄く切って、酢味噌で食べると美味い。
さっぱりしているので、淡麗な酒に合いそうである。
次に、市販品に比べて空気が入りやすく、身に隙間が多い。これは素人だから仕方ない。
隙間が多い分、調理したときに味が染みこむという利点がある。
その調理したこんにゃくの話。
まず最初の日は、こんにゃくをサイコロより少し大きめに切って、
少量のごま油で炒めて、酒・みりん・濃口醤油・砂糖を加えて煮込む。
鷹の爪を1本刻んで入れ、もう少し煮込んで、味が染みこんだところでできあがり。
と、これを食べたときに、勿論美味しかったのだが、思い付いたのが、
鶏皮を一緒に煮込んだらもっと美味いのではないか。
早速、翌日スーパーで鶏皮が安かったので手に入れて、作ったのが次の料理。
油で、ニンニクを2欠け入れ、こんにゃくを一緒に炒める。
こんにゃくを炒めるのは水分を飛ばすためで、
その後、調味料を入れたときに、ひたひたになるくらいに水を入れ、
同時に鶏皮も適当な大きさに切って入れる。
調味料は前回と同じ。味を見ながら量を調整していく。
煮立ったら弱火で20分ほど煮込み、最後に大きなスプーン1杯くらいの味噌を隠し味で投入。
その後また10分ほど弱火で煮込んで終了。
鶏皮の脂が適当にこんにゃくに絡んで、予想通りの美味さ。
これだから料理は止められない。
次は、牛すじ肉で試してみよう。
さてこれに合う酒はと、ちと難しいが、
滋賀県の北島酒造が醸す、純米吟醸玉栄55%の「Motto GO GO」という変わった名前の酒である。
酒蔵によると、以下の説明がある。
「生酛でもない、山廃でもない、速醸でもない。その名は「さんきおあまざけもと」。明治の世に編み出されたが、管理の難しさから幻となった酒母の製法。 米、水、麹を高温糖化し甘酒を造る。キモト仕込みの酒母から取り出した乳酸菌を投入し、酒母による醗酵を促す。」
難しい!さっぱり分からないが、
生酛造りでさえ手間がかかるのにそれ以上にややこしいとは。
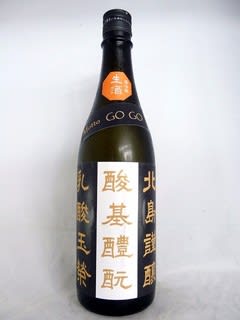
それより味だ。
純米吟醸にしては、香りはかなり控えめだ。
最初飲み口は若干甘く感じられるが、喉を通るときは日本酒度+9.5に違わぬ辛口で切れる。
アルコール度数は18.3度で、普通より2,3度高めである。
甘辛く煮込んだこんにゃくによく合って美味い。
このコラボは止められなくなりそうな感じになってきた。ヤバいぞ。
こんにゃく芋から作る本格的こんにゃくである。
以前は、私も何度か作ったことがあって、それほど難しいことはない。
ただ手がかかるのは間違いない。
今回のこんにゃくは前回に比べて出来が悪い。
しっかり形が取れていないというか、若干型崩れの部分がある。
しかし、売り物ではないのでそれで十分なのだ。
さて、手作りこんにゃくのいいところは、まず新しいので刺身にできる。
できたてをきっちり冷やして、薄く切って、酢味噌で食べると美味い。
さっぱりしているので、淡麗な酒に合いそうである。
次に、市販品に比べて空気が入りやすく、身に隙間が多い。これは素人だから仕方ない。
隙間が多い分、調理したときに味が染みこむという利点がある。
その調理したこんにゃくの話。
まず最初の日は、こんにゃくをサイコロより少し大きめに切って、
少量のごま油で炒めて、酒・みりん・濃口醤油・砂糖を加えて煮込む。
鷹の爪を1本刻んで入れ、もう少し煮込んで、味が染みこんだところでできあがり。
と、これを食べたときに、勿論美味しかったのだが、思い付いたのが、
鶏皮を一緒に煮込んだらもっと美味いのではないか。
早速、翌日スーパーで鶏皮が安かったので手に入れて、作ったのが次の料理。
油で、ニンニクを2欠け入れ、こんにゃくを一緒に炒める。
こんにゃくを炒めるのは水分を飛ばすためで、
その後、調味料を入れたときに、ひたひたになるくらいに水を入れ、
同時に鶏皮も適当な大きさに切って入れる。
調味料は前回と同じ。味を見ながら量を調整していく。
煮立ったら弱火で20分ほど煮込み、最後に大きなスプーン1杯くらいの味噌を隠し味で投入。
その後また10分ほど弱火で煮込んで終了。
鶏皮の脂が適当にこんにゃくに絡んで、予想通りの美味さ。
これだから料理は止められない。
次は、牛すじ肉で試してみよう。
さてこれに合う酒はと、ちと難しいが、
滋賀県の北島酒造が醸す、純米吟醸玉栄55%の「Motto GO GO」という変わった名前の酒である。
酒蔵によると、以下の説明がある。
「生酛でもない、山廃でもない、速醸でもない。その名は「さんきおあまざけもと」。明治の世に編み出されたが、管理の難しさから幻となった酒母の製法。 米、水、麹を高温糖化し甘酒を造る。キモト仕込みの酒母から取り出した乳酸菌を投入し、酒母による醗酵を促す。」
難しい!さっぱり分からないが、
生酛造りでさえ手間がかかるのにそれ以上にややこしいとは。
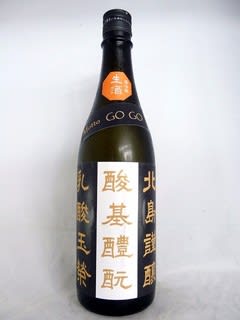
それより味だ。
純米吟醸にしては、香りはかなり控えめだ。
最初飲み口は若干甘く感じられるが、喉を通るときは日本酒度+9.5に違わぬ辛口で切れる。
アルコール度数は18.3度で、普通より2,3度高めである。
甘辛く煮込んだこんにゃくによく合って美味い。
このコラボは止められなくなりそうな感じになってきた。ヤバいぞ。