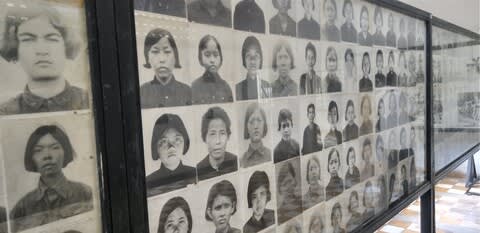実はこれは本ではないし、まだ読み上げてもいない。
だから最近読んだ本というジャンルの中で語ることはできないのだが、
それでも、これが一冊の本として世の中に出ることを願って・・・。
沢木耕太郎と言えば、「深夜特急」という本を一番先に思い浮かべることができる。
バックパッカーのバイブルとまで言われたこの本は、1970年に作者がインドのデリーからロンドンまでをバスで行くという、
今の時代でも二の足を踏むような体験を元に書かれている。
1970年という年は日本では大阪万博が開催された年で、70年安保で学生運動が再燃した年でもある。
この年私はまだ学生でありながら、所属サークルの関係でアフリカのタンザニアに1年間滞在することになった。
沢木耕太郎ほどの冒険心はなかったものの、結果的には私の10ヶ月に及ぶアフリカ滞在はハプニングの連続で、
図らずも当時では冒険とも呼べる体験をして、翌年の1971年2月に帰国したときは、
日本を出る前の自分が嘘のように逞しくなっていたように思う。
それ故にか、「深夜特急」が後年発刊されて読んだとき、私は既に若いという年齢ではなかったものの、
作者と同年にアフリカに渡った自分の体験を重ね合わせて、大いなる共感を持って読んだことを覚えている。
当時「深夜特急」の一節にいたく共感を覚えた文章があったことを思い出して、
それがどんな内容だったかを図書館で改めて調べてみたその一節は、
「さて、これからどうしよう……
そう思った瞬間、ふっと体が軽くなったような気がした。
今日一日、予定は一切なかった。
せねばならぬ仕事もなければ、人に会う約束もない。すべてが自由だった。
そのことは妙に手応えのない頼りなさを感じさせなくもなかったが、それ以上に、自分が縛られている何かから解き放たれていくという快感の方が強かった。
今日だけでなく、これから毎日、朝起きれば、さてこれからどうしよう、と考えて決めることができるのだ。
それだけでも旅に出てきた甲斐があるように思えた。」
そして後年、私はこの一節のような目的がないことを目的とした旅に何度も出かけることになる。
閑話休題
さて、「暦のしずく」は2022年から朝日新聞の土曜版におよそ2年にわたって連載されたもので、
その新聞を私の友人がそれこそ2年に渡って保存していてくれたのを先日、
「読んでみませんか」といって渡してくれた。
作者には珍しい時代物で、江戸時代の講釈師とそれを取り巻く人々との物語と言えばあまりに簡単すぎるが、
この講釈師が、その内容によって罪に問われ処刑されるというのが序章において語られ、
これは推理小説では倒叙ミステリーといわれるジャンルによく似ており、
最初に結果が示され、あとはそこに至るまでの経過を物語っていく手法である。
私は最近時代物を読むことが多く、このブログでもいくつか書いているが、
それらに勝るとも劣らぬくらい「暦のしずく」は面白い。
まだ読み上げてはいないものの、2年間の新聞の束を次々に捲ることになる。
私はこの連載を欠かさず保存しておいてくれた友人に深く感謝したい。
そしていつかこの物語が本になって多くの人の目に触れることを願うものである。
だから最近読んだ本というジャンルの中で語ることはできないのだが、
それでも、これが一冊の本として世の中に出ることを願って・・・。
沢木耕太郎と言えば、「深夜特急」という本を一番先に思い浮かべることができる。
バックパッカーのバイブルとまで言われたこの本は、1970年に作者がインドのデリーからロンドンまでをバスで行くという、
今の時代でも二の足を踏むような体験を元に書かれている。
1970年という年は日本では大阪万博が開催された年で、70年安保で学生運動が再燃した年でもある。
この年私はまだ学生でありながら、所属サークルの関係でアフリカのタンザニアに1年間滞在することになった。
沢木耕太郎ほどの冒険心はなかったものの、結果的には私の10ヶ月に及ぶアフリカ滞在はハプニングの連続で、
図らずも当時では冒険とも呼べる体験をして、翌年の1971年2月に帰国したときは、
日本を出る前の自分が嘘のように逞しくなっていたように思う。
それ故にか、「深夜特急」が後年発刊されて読んだとき、私は既に若いという年齢ではなかったものの、
作者と同年にアフリカに渡った自分の体験を重ね合わせて、大いなる共感を持って読んだことを覚えている。
当時「深夜特急」の一節にいたく共感を覚えた文章があったことを思い出して、
それがどんな内容だったかを図書館で改めて調べてみたその一節は、
「さて、これからどうしよう……
そう思った瞬間、ふっと体が軽くなったような気がした。
今日一日、予定は一切なかった。
せねばならぬ仕事もなければ、人に会う約束もない。すべてが自由だった。
そのことは妙に手応えのない頼りなさを感じさせなくもなかったが、それ以上に、自分が縛られている何かから解き放たれていくという快感の方が強かった。
今日だけでなく、これから毎日、朝起きれば、さてこれからどうしよう、と考えて決めることができるのだ。
それだけでも旅に出てきた甲斐があるように思えた。」
そして後年、私はこの一節のような目的がないことを目的とした旅に何度も出かけることになる。
閑話休題
さて、「暦のしずく」は2022年から朝日新聞の土曜版におよそ2年にわたって連載されたもので、
その新聞を私の友人がそれこそ2年に渡って保存していてくれたのを先日、
「読んでみませんか」といって渡してくれた。
作者には珍しい時代物で、江戸時代の講釈師とそれを取り巻く人々との物語と言えばあまりに簡単すぎるが、
この講釈師が、その内容によって罪に問われ処刑されるというのが序章において語られ、
これは推理小説では倒叙ミステリーといわれるジャンルによく似ており、
最初に結果が示され、あとはそこに至るまでの経過を物語っていく手法である。
私は最近時代物を読むことが多く、このブログでもいくつか書いているが、
それらに勝るとも劣らぬくらい「暦のしずく」は面白い。
まだ読み上げてはいないものの、2年間の新聞の束を次々に捲ることになる。
私はこの連載を欠かさず保存しておいてくれた友人に深く感謝したい。
そしていつかこの物語が本になって多くの人の目に触れることを願うものである。