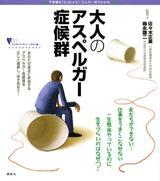星槎教育研究所フリースクール・支援センターのスタッフGENです
今回も本の紹介です
『子どもがぐんぐん伸びる目のトレーニングBOOK』

先日私たちが受講したかわばた眼科さんの「視覚発達支援講習」で、
講師をされた米国認定オプトメトリストの内藤貴雄先生の本です。
ご存知のように、私たちが普段キャッチしている情報の約80%は
目からの情報といわれています。つまり、視覚情報を適切に
処理することは、環境に適応するためにとても重要なことと
いえるでしょう。
LDやADHD、アスペルガー症候群といった発達障害
のあるお子さんのなかには、新しいことを覚えること、
体を動かすこと、集中すること、イメージすること、など
が苦手なことがあります。
内藤先生いわく、こうした発達障害のお子さんにありがちな問題が、
「視機能と関連していることがある」、とのこと。
この『子どもがぐんぐん伸びる目のトレーニングBOOK』では、
こうした発達障害のあるお子さんの抱えがちな問題に対して、
視機能からの要因を分析し、対応策をビジョン・トレーニング、
というかたちで提案しています。
すごく分かりやすく、普段子どもたちと関わる人にとってはとても
ありがたい、実践に役立つ具体的な手立てが多数紹介されています。
現在、星槎教育研究所ではビジョン・トレーニングの研究しています。
近々フリースクールや支援センターでも導入を目指していこうと思っています
ふわっとサポートできるクラスに
みんなが居心地のよいクラスに
イジメのないクラスに
U_SST ソーシャルスキルワーク
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

年間指導計画実例・1年~6年までのプログラム一覧・紙面見本・パンフレットはこちらをご覧ください

今回も本の紹介です

『子どもがぐんぐん伸びる目のトレーニングBOOK』

先日私たちが受講したかわばた眼科さんの「視覚発達支援講習」で、
講師をされた米国認定オプトメトリストの内藤貴雄先生の本です。
ご存知のように、私たちが普段キャッチしている情報の約80%は
目からの情報といわれています。つまり、視覚情報を適切に
処理することは、環境に適応するためにとても重要なことと
いえるでしょう。
LDやADHD、アスペルガー症候群といった発達障害
のあるお子さんのなかには、新しいことを覚えること、
体を動かすこと、集中すること、イメージすること、など
が苦手なことがあります。
内藤先生いわく、こうした発達障害のお子さんにありがちな問題が、
「視機能と関連していることがある」、とのこと。
この『子どもがぐんぐん伸びる目のトレーニングBOOK』では、
こうした発達障害のあるお子さんの抱えがちな問題に対して、
視機能からの要因を分析し、対応策をビジョン・トレーニング、
というかたちで提案しています。
すごく分かりやすく、普段子どもたちと関わる人にとってはとても
ありがたい、実践に役立つ具体的な手立てが多数紹介されています。
現在、星槎教育研究所ではビジョン・トレーニングの研究しています。
近々フリースクールや支援センターでも導入を目指していこうと思っています

ふわっとサポートできるクラスに
みんなが居心地のよいクラスに
イジメのないクラスに
U_SST ソーシャルスキルワーク
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


年間指導計画実例・1年~6年までのプログラム一覧・紙面見本・パンフレットはこちらをご覧ください












 の本紹介です!
の本紹介です!