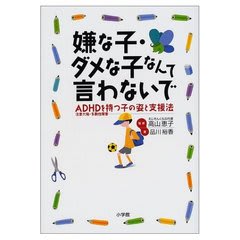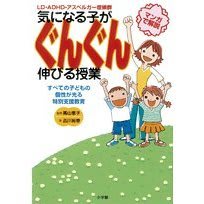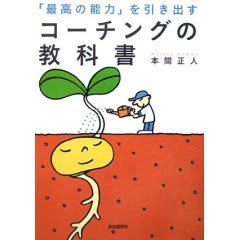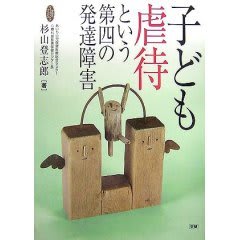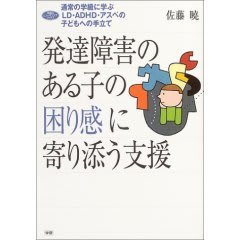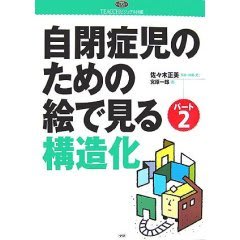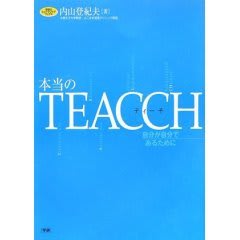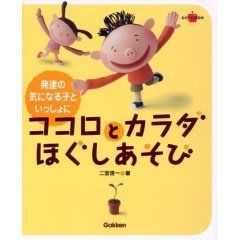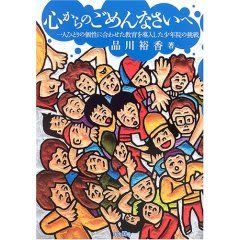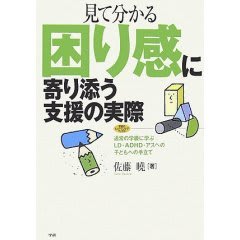研究員 (Mae)の本紹介です
(Mae)の本紹介です
上野 一彦 著 講談社〈1,300円税別〉
『LD教授(パパ)の贈り物
ふつうであるよりも個性的に生きたいあなたへ』
御自身の性向を「LD・ADHDの特徴と類似している」と自覚され
つつ、LD(Learning Disabilities=学習障がい)と関わってきた
ご経験の中で、考えられたことをエッセイ形式でまとめてくださって
います。
机に向かいかしこまって読むよりも、楽しく文字を追いリラックスしながら
読むことを、本書には求められているような気がして、わたしは時に横に
なりつつ、そして時には机に向かって、読みすすめていきました。
LD教授(パパ)と自称して、「徒然日記(1)(2)」「教育論」「雑学考」
「短編」「夢」とそれぞれが章立てで分けられています。
特に、「徒然日記(1)(2)」には、手に汗握るLD教授(パパ)ならではの
失敗談を多く紹介くださっています。
このLD教授(パパ)の失敗談は、例えば、物をなくす、大いなる勘違い
をする、片づけができない、字が汚い、ノートが上手くとれないなどの
子どもは、LD・ADHDがそうさせているという可能性があることを
示唆してくれます。
その子本人は十分すぎるほど気を付けているのですが、なぜかそう
なってしまうのですよね。
LD教授(パパ)はそういった失敗談を気軽(?)に告白くださって、
「たいへんなんだ」と思わせつつ、私たちを笑わせてくれています。
「教育論」では、LD、ADHD、広汎性発達障害を含め、そのお子
さんの親として、教師として、関わっていく側の大人が心と頭に留めて
おくべき内容として残ります。
「徒然日記(1)(2)」で笑わされ、「教育論」では頭を垂れ、思わず
背筋を伸ばして読んでしまう、そんなバラエティに富んだメリハリのある
エッセイが一冊の本にまとめられています。
~本書の一節より~
LDやディスレクシアと呼ばれる人々は、これまでの一般的な学習法
では成果が上がりにくいが、「いったんコツをつかめばより早く、より
多くのスキルやテクニックを身につけることができる力」をもつ。まさ
に学び方のちがう、LD(learning difference)と呼ぶべき人々なの
である。
彼らは障がいを克服して、成功したのではなく、他の人とはちがった
考え方、発想法に長けていたから成功した。いいかえると、障がいがあ
るのに成功したのではなく、障がいがあったから、他の領域がより強く、
より広く発達し、異なる解決法を採り入れる力が伸びて成功したのだと
LD教授(パパ)は確信する。
・・・この一節は、「LD教授の夢」の章立て中の「LD偉人伝 こぼ
ればなし」にある文章です。
発達障害は「克服」するものではなく、自分の個性として受け入れる
ものだということを考えます。
自分の「コツ」をつかむことがとても大切で、特別支援教育は、この
「コツ」を自覚させることが求められているのだと感じます。
「ふつう」ではないということが、世の中を進歩させていきます。
障害の名のもとにくくられてしまってはいますが、発達障害を持つ
人たちこそ、世の中(それは思想・技術・芸術のどの分野でも)
すべてにわたり、進歩・変革させる力を持っているのだと思うのです。
 (Mae)の本紹介です
(Mae)の本紹介です上野 一彦 著 講談社〈1,300円税別〉
『LD教授(パパ)の贈り物
ふつうであるよりも個性的に生きたいあなたへ』
御自身の性向を「LD・ADHDの特徴と類似している」と自覚され
つつ、LD(Learning Disabilities=学習障がい)と関わってきた
ご経験の中で、考えられたことをエッセイ形式でまとめてくださって
います。
机に向かいかしこまって読むよりも、楽しく文字を追いリラックスしながら
読むことを、本書には求められているような気がして、わたしは時に横に
なりつつ、そして時には机に向かって、読みすすめていきました。
LD教授(パパ)と自称して、「徒然日記(1)(2)」「教育論」「雑学考」
「短編」「夢」とそれぞれが章立てで分けられています。
特に、「徒然日記(1)(2)」には、手に汗握るLD教授(パパ)ならではの
失敗談を多く紹介くださっています。
このLD教授(パパ)の失敗談は、例えば、物をなくす、大いなる勘違い
をする、片づけができない、字が汚い、ノートが上手くとれないなどの
子どもは、LD・ADHDがそうさせているという可能性があることを
示唆してくれます。
その子本人は十分すぎるほど気を付けているのですが、なぜかそう
なってしまうのですよね。
LD教授(パパ)はそういった失敗談を気軽(?)に告白くださって、
「たいへんなんだ」と思わせつつ、私たちを笑わせてくれています。
「教育論」では、LD、ADHD、広汎性発達障害を含め、そのお子
さんの親として、教師として、関わっていく側の大人が心と頭に留めて
おくべき内容として残ります。
「徒然日記(1)(2)」で笑わされ、「教育論」では頭を垂れ、思わず
背筋を伸ばして読んでしまう、そんなバラエティに富んだメリハリのある
エッセイが一冊の本にまとめられています。
~本書の一節より~
LDやディスレクシアと呼ばれる人々は、これまでの一般的な学習法
では成果が上がりにくいが、「いったんコツをつかめばより早く、より
多くのスキルやテクニックを身につけることができる力」をもつ。まさ
に学び方のちがう、LD(learning difference)と呼ぶべき人々なの
である。
彼らは障がいを克服して、成功したのではなく、他の人とはちがった
考え方、発想法に長けていたから成功した。いいかえると、障がいがあ
るのに成功したのではなく、障がいがあったから、他の領域がより強く、
より広く発達し、異なる解決法を採り入れる力が伸びて成功したのだと
LD教授(パパ)は確信する。
・・・この一節は、「LD教授の夢」の章立て中の「LD偉人伝 こぼ
ればなし」にある文章です。
発達障害は「克服」するものではなく、自分の個性として受け入れる
ものだということを考えます。
自分の「コツ」をつかむことがとても大切で、特別支援教育は、この
「コツ」を自覚させることが求められているのだと感じます。
「ふつう」ではないということが、世の中を進歩させていきます。
障害の名のもとにくくられてしまってはいますが、発達障害を持つ
人たちこそ、世の中(それは思想・技術・芸術のどの分野でも)
すべてにわたり、進歩・変革させる力を持っているのだと思うのです。