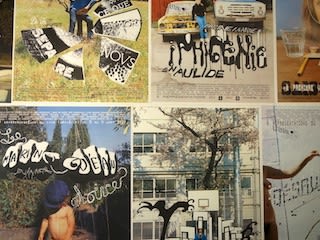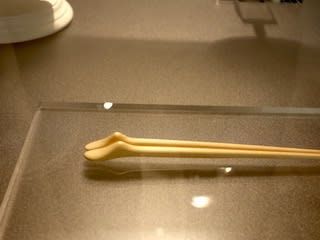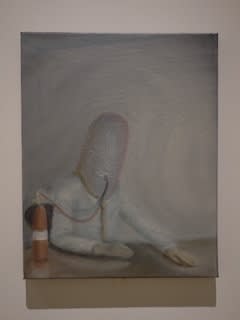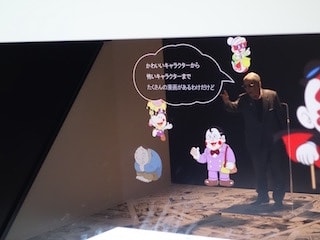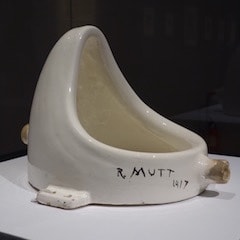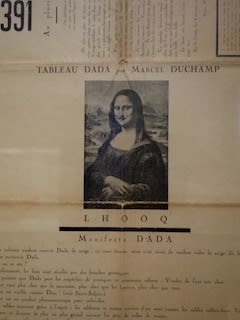世間一般のGWを少しでも満喫すべく、連休最終日にお台場へ行ってきました。もうそこまで混雑していないであろう...という予測はまあまあ当たったかと思います。チケットブースも入場口も待ち行列はありません。
日本科学未来館で開催中の企画展「工事中!」では、ショベルカーやブルドーザといった重機がいろいろ展示してあるそうで。こんなのは工事現場でしかまじまじと見られませんし、それが展示物になっている展覧会ってのも非常に気になります。

会場入口では四脚クローラ方式双腕型重機がお出迎え。操縦席はコクピットのよう...ガンタンクのような足回り。


国産初の油圧ショベルカーユンボY-35。なぜ銀色なのかわからず。


キャタピラーの314F油圧ショベル。まあ普通ならここまで近寄れません。


会場内はどこを見ても現場。



「都市」再・工事中!―解体の美学
油圧ショベルの先っちょを付け替えて解体作業。鉄筋コンクリなんでもぶち壊すデストロイヤー。

深海で獲物を狙うかのようなお姿。

看板並べると絵になる光景。


日本科学未来館で開催中の企画展「工事中!」では、ショベルカーやブルドーザといった重機がいろいろ展示してあるそうで。こんなのは工事現場でしかまじまじと見られませんし、それが展示物になっている展覧会ってのも非常に気になります。

会場入口では四脚クローラ方式双腕型重機がお出迎え。操縦席はコクピットのよう...ガンタンクのような足回り。


国産初の油圧ショベルカーユンボY-35。なぜ銀色なのかわからず。


キャタピラーの314F油圧ショベル。まあ普通ならここまで近寄れません。


会場内はどこを見ても現場。



「都市」再・工事中!―解体の美学
油圧ショベルの先っちょを付け替えて解体作業。鉄筋コンクリなんでもぶち壊すデストロイヤー。

深海で獲物を狙うかのようなお姿。

看板並べると絵になる光景。