
我々の仕事は、必ず第三者の評価、究極的には顧客からの評価を受けます。
上司や会社からの評価もまた、顧客からの視点を基にされるのが通常です。
しかし、自分の仕事は、一義的には、自分自身で評価をします。
自分が良かれと思って仕事をするのです。
つまり、最初の評価は、主観的な自分自身の評価であり、次に客観的な第三者の評価を受けることになります。
問題なのは、自分自身の評価が非常に高かったのに関わらず、顧客からの評価が低いケースです。
例えば、プロ受けする文学作品を書いたけれど、
商業出版としてはサッパリ売れない。
良い本の定義は売れなくともプロ受けすることか、
それとも、売れる本が良い本なのか?
岩波書店が危機的状況にあります。
素晴らしい本を作っても売れなかったからです。
プロフェッショナルとしては、顧客に受け入れられなければ、自己満足と考えなければいけません。
どんなに良いものも、顧客に受けなければ自己満足に過ぎない。
くれぐれも、評価者である顧客を否定してはいけない。
岩波書店の本が売れないのは、日本人がバカになったからだ。
もっと、国民は勉強すべきだ!!!と分析しても意味はありません。
売れないとは、一つの時代の終焉と捉えるべきなのです。
Anything that does not meet the customer's needs is nothing more than self-gratification.
Our works are always evaluated by the third party e.g.the clients.
Evaluating of boss or company is also based on the viewpoint of clients.
However,at first, our works are evaluated by ourselves.
Subjectively, we do good jobs!
Hence, at first, evaluation is subjective, then it will be objective.
In spite of high self evaluation, clients aren't satisfied. This is an issue.
For instance, I write a novel that is accepted by professional but not sold well.
The difinition of good book is whether specialized or sold well?
However good it may be, it is just complacent if it is not sold well.
We should not deny clients that assess our job.
One of Japanese book publisher Iwanami that is famous for eminent faces a fanancal difficulty.
The reason Iwanami books are not sold well is whether Japanese are stupid or not?
We should analyze that it is the end of the social role of it.










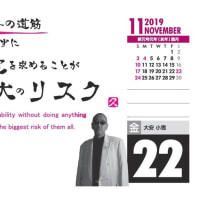
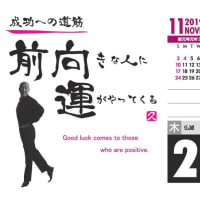
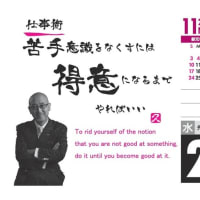
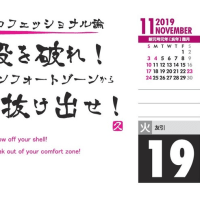
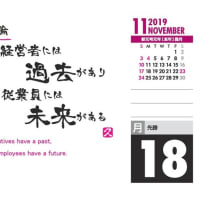
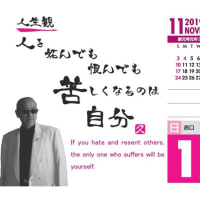
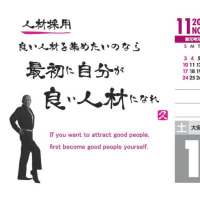
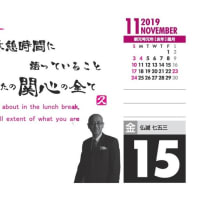
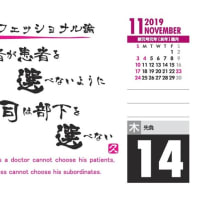
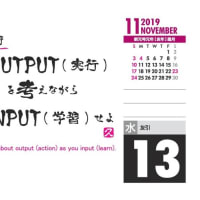
① 自分による評価
② 相手による評価
①の場合、主観的な見方をしてしまうし、②の場合は客観視によるもの。
①と②のギャップが小さいとWIN - WIN の関係となるが、逆に大きくなればなるほど関係は悪化する。
私達の仕事は相手あってこそ、存在意義がある。
相手が満足できなければ、どんなに高度な知識や技術を使っても意味がない。
例えば、集計表をマクロを使っても顧客が使えなければ(メンテナンス含む)、不要の産物となる。
一般的な関数式を組み込んだ集計表の方が喜ばれる。
仕事は自分を「ひけらかす」場ではなく、相手を「満足」させる場と考える。
エゴを捨て、満足させる為の取捨選択が必要。
「自分のやり方を貫くためには、自己評価が一番厳しいものでないといけないでしょうね。誰の評価よりも自分の評価、自分に対する客観的な評価が一番厳しいものでないといけない、これはもう絶対です。」
よく若い人は自分のやり方でやろうとしますが(私もそうですが)、それをやるのであれば、自己評価が上司や顧客の評価よりも厳しいものでないと当然ですが許されません。
また、その評価が自分よがりの評価であっても意味はなく、あらゆる面から評価されたとしても、自己評価が最も厳しくないと、自分のスタイルを貫くことはできません。
未熟なうちは、自己評価をする力も未熟なので、まずは滅私で、言い訳せず、とことん言われたことを学ぶ姿勢が大事だと私は思います。
そうならない様にするには、PDCを回すこと。評価者である相手の反応を見て、次工程のプランにフィードバックし、改善されなければ、どんな努力も自己満足だと思います。
大切なことは、相手の反応を見て、相手が変わることを望むのではなく、自分がどう変わらなければならないのかを考えることだと思います。
自分に成功体験があると、そのときの顧客の満足したポイントやニーズがわかり、いつしかそれがいいものだと思い込む。
そうすると、同じような仕事方法をとり、ニーズを探らず、いいものだと勘違いしたことを顧客へ押し付けてしまう。そして傲慢となる。
ビジネスであれば、常に謙虚で探求し続けることが重要である。
マーケットはすごい勢いで変化しています。今のニーズではなく、先のニーズに常にアンテナを広げて行動しないと、すぐ価格競争に陥ります。もし過去の成功に囚われれば完全にニーズとマッチせずマーケットに参加することもできません。次のニーズを先取りする行動が必要です。
その中で自己満足に陥った人は「成長」を考えていかなくなります。
すると変化に対応できず、マイナスになり「衰退」していくのです。「現状維持」ということばかり考えて行動していると「マイナス」になっていきます。プラスになることはありえません。
現状維持という捉え方はやめ、常に新しいことにチャレンジし、成長するとこをやめない思考を持っていこうと感じました。
まず、最低限の生活を保証する「衣食住」に力を入れると思います。とは言え、今の僕には、無人島で水や食糧、衣服や安全な寝床を確保するための術はありません。当然、道具を作ったり、島を探索して地形を把握したりするでしょう。こうした、衣食住は、今の我々の生活では当たり前になっていますが、無人島での生活となると、大きな試練になるのは必至です。況んや、独りぼっちの生活ですから、人との繋がりに悩める段階ではないと思います。
しかし、無人島など、自然に触れ合いながら育っていく人は、我々以上にコミュニケーション能力が高いのではないかと考えます。ある時は野生の動物を殺し、ある時は戯れ、常に自然に心を開き続けることで、動物や自然の気持ちが理解できると想定しても不自然ではありません。現に、動物と生活を共にしている未開人が時折、報道されています。今、相手が何を考えているのか、何を望んでいるのか、雰囲気や表情だけで判断できるのであれば、人のニーズも的確に把握できるのではないかと思います。つまり、コミュニケーションの継続といった付き合いが、今の我々には求められているのではないかと考えます。