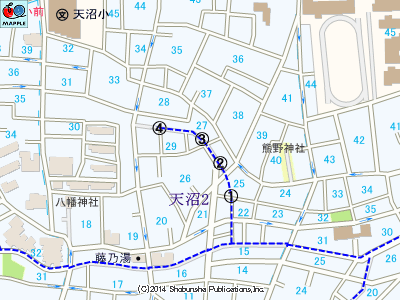「阿佐ヶ谷村は、郡の東の方にあり、郷庄の唱を伝えず、江戸日本橋には三里半の行程なり、村名の起りを詳にせず、『小田原北条家人所領役帳』に、太田新六郎知行八十四貫文中野内阿佐ヶ谷分とあり、・・・・されば古き村なる事は疑ひなけれど、その詳なるころを伝へず、江戸麹町山王の神領に附せらる、村内はすべて平地にして土性は野土なり、陸田多く水田少なし、民家九十四軒、村の広さ東西七町、南北十一町、東は馬橋村にとなり、南は青梅街道に界ひ、又田端、成宗の二村にも続けり、西は天沼村に接し、北は下鷺ノ宮村に及ぶ」(「新編武蔵風土記稿」)

・ 「東京近傍図 / 板橋駅」(参謀本部測量局 明治14年測量)及び「同 / 内藤新宿」(明治13年測量)を合成、その一部を加工したもので、本来の縮尺は1/20000、パソコン上では1/12000ほどです。オレンジ線は区境、細線は杉並村当時の大字境です。
阿佐ヶ谷の地名が文献上最初に現れるのは、応永27年(1420年)作成の古文書(熊野那智大社「米良文書」)で、檀家であった江戸氏の一族を列記したなかに、「中野殿」と並んで「あさかやとの」とあります。さらに、冒頭の引用文にもある「小田原衆所領役帳」(永祿2年 1559年)は、「中野内阿佐ヶ谷」と、現行と同じ漢字表記です。地名由来としては、桃園川流域の浅い谷筋の意と解するのが一般で、泥が浅く耕作しやすい、麻の生い茂る、葦の生い茂るなどもありますが、いずれにしても谷筋にある地形由来は間違いないところです。「新編武蔵風土記稿」に記載された小名は、向、小山、原、本村で、神明宮や世尊院のある本村を中心に、桃園川流域を開発したのが最初と思われます。

・ 神明宮 阿佐ヶ谷村の鎮守で、桃園川を東に望む右岸段丘斜面にあります。西隣の世尊院は江戸時代別当でしたが、中杉通りに面して→ 山門が建っています。
「神明宮 除地、百五十坪、小名本村にあり、村内の鎮守なり、・・・・右の五社共に村内世尊院の持ちなり」(「新編武蔵風土記稿」) 「江戸名所図会」本文にも記載があり、日本武尊の東征に際し当地に立ち寄った後、地元民がその武功を慕って神明宮を勧請したこと、源頼義の奥州遠征に随行し、病気となって土着した者が、伊勢神宮に参拝して霊石を得、これをご神体としたこと、当初の社地は「七八町東の方にあり、土人これを元伊勢と称」したことなど、神明宮にまつわる伝承を紹介しています。なお旧地は今もお伊勢の森と呼ばれています。