
奥書によると、全国各地16の新聞に連載された小説に加筆・修正されて、2020年2月に単行本として出版された。
カバーには、「Sen no Rikyu」と名前が付記されている。その名の通り、茶の湯を究め佗茶の境地を確立したとされる千利休の人生を織田信長並びに豊臣秀吉との関係を主軸にしながら描き出した歴史小説である。
「茶聖」という言葉は、本書のp416に古田織部が利休に語る言葉として出てくる。
「何を仰せか。この世に二人といない茶聖の名が廃れることなどありましょうか」と。本書のタイトルは、この個所に由来するのだろう。
その織部の発言に対し、利休は心の内で語る。「茶の湯は『聖俗一如』なのだ」と。つまり、利休は己がどれだけ俗にまみれているかを明晰に自覚していたと著者は捕らえている。この続きに著者は記す。
”利休には「異常なまでの美意識」という聖の部分と、「世の静謐を実現するためには権力者の懐にも飛び込む」という俗の部分があった。この水と油のような二種類の茶が混淆され、利休という人間が形成されていた。” (p436)
この一文がこの小説のテーマになっている。利休という人間を形成した聖と俗の二面を併せて、その姿を具体的に描き出す。特に、俗の部分に比重を置きながら、千利休の生き様を描き切っていると感じた。
それは同時に、コインの反面として、織田信長が茶の湯を政治の道具として有用とみた視点・発想と行動、及びそれを継承しある時点までは茶の湯に深く傾倒して行った豊臣秀吉の視点・発想と行動をそれぞれ描き出していくことになる。ただし、比重は秀吉の方に傾く。信長を描くのは、秀吉が茶の湯と関わるための必然的な前提であり、秀吉の考えの背景を明確にするために欠かせない部分という印象を受けた。その比重の差は、宗易(利休)がそれぞれの茶頭となった時の序列の違いにも関係していると思う。
プロローグは、天正19年(1591)2月28日、利休の聚楽屋敷にある不審庵での今生最後の手前から始まる。そして検使役蒔田淡路守に遺偈の書かれた折り紙を手渡し、利休が切腹する場面を簡潔に描く。「人世七十 力囲希咄(りきいきとつ) ・・・・・ 今此時ぞ天に抛(なげう)つ」という有名になった遺偈である。
このプロローグで、著者は利休の内奥の言葉として「わしは茶の湯と共に永劫の命を得るのだ」という一文を記す。ここに、著者の千利休観の一端が出ていると思う。
この小説はプロローグに続き5つの章で構成され、独立したエピローグはない。第5章の末尾がエピローグを兼ねている。2月28日当日の場面描写に回帰してこのストーリーが終わる。
「第1章 覇者」は、天正10年6月10日、本能寺の変後、信長落命の事実が堺に届く場面から始まる。信長と茶の湯との関わり及び「御茶湯御政道」の視点が回想的に描かれるとともに、山崎での合戦を経て、秀吉が覇者の立場を確立するまでの要所が描き込まれていく。いわば、この小説構成の「序」である。
「聖」の視点では、利休が長次郎に和物の今焼茶碗を作れという場面。それは村田珠光の考案した「冷凍寂枯」思想を踏襲した茶碗を作れという示唆である。山崎宝寺城の山麓に造られた妙喜庵を秀吉に見せる場面。「名物がなければ、名物を作るまで。・・・・・羽柴様が天下を取り、私の威権を高めていただければできます。」(p55)利休が俗にまみれる決意の始まりである。大坂城築城において、利休が山里曲輪という佗茶の異空間を創造する場面も織り込まれていく。
最も、キーポイントになるのは、宗易が23歳で娶った妻・稲との間の子・紹安と宗易との会話場面である。父・宗易が秀吉に近づいていくことを、紹安は父・宗易が茶の湯に求めるものと矛盾すると批判する。それに対し、宗易は「この世に静謐をもたらし、人々が自由に行き来できる世を作るためだ」と言う。紹安はこの言すら、詭弁と断じる。だが、宗易は俗にまみれる己の行為はこの大義の実現のためとして突き進んで行く。これは宗易と紹安の関わり方の「序」となる。
この大義が利休と秀吉との関わりの一つの柱になり、この小説の主題になっていく。
「第2章 蜜月」は、山崎合戦後、秀吉が勢力範囲を拡大していく展開期である。天正12年の小牧・長久手の戦い、四国の長宗我部との戦いの広がり、天正13年(1585)3月の雑賀・根来一党の討伐が進展する。宗易は茶事を手段としつつ、秀吉の懐深くに入って行く。宗易は堺の商人としての情報、茶の湯の人間関係を介しての情報を武器に、秀吉の知恵袋、参謀的機能を担い始める。その一方で、禁中茶会を催す企画の根回しを宗易が進める。「蜜月」という見出しが二人の関係を暗示する。「承」の段階といえる。
禁中茶会(正式には献茶式)の前、9月8日に宗易は朝廷から「利休」居士号を勅賜された。著者はこの号について、”「利を(追求することを)休む」、すなわち商人としての宗易と決別し、茶人としての道を歩んでいくという覚悟”を込めたものと言い、「この号は、宗易自身が考案し、朝廷が追認という形で下されたもの」(p146)という解釈をしている点は興味深い。
10月7日の小御所菊見の間での献茶は利休がその趣向を考えた。だが、秀吉はその趣向に満足できなかった。茶の湯で帝を驚かせたかったのだ。そこで、利休は2回目の禁中茶会を提案し、秀吉自身がその趣向を考えるべきと言う。秀吉自身が己の侘をみつけるべき時だと。それが2回目の禁中茶会となる。このとき、秀吉は「黄金の座敷」を使う。これはたぶん通常「黄金の茶室」と称されるものをさすのだろう。これが秀吉の作意としての侘だという。著者は、利休が一切関知しないところでこの黄金の座敷が制作されたとして描き出していく。
ここには重要な視点が含まれている。秀吉は利休の言を「胸中にわき立つ作意を現のものにすることこそ侘だ」と受けとめていた。
「寂びた茶室で古びた茶道具を使って茶事を行うことだけが、侘ではない」(p163)ここに、既に形式化しつつある侘に対する侘の本質論がクローズアップされている。黄金の座敷に対する評価意識が転換する視点が描かれている。利休はこの秀吉の作意に「殿下は・・・己の侘を見つけられた」と答える。著者はここに利休と秀吉の関係性の転換点を見出していると言える。
「第3章 相克」は、構成的にも「起」「承」を受けた「転」に入って行く。「第4章 聖俗」と合わせて、時間軸の長い「転」の部分が進展していくように思う。
第3章は、堺の屋敷で、利休とりきが黄金の座敷他について語り合う場面から始まる。ここでも利休は「しょせん侘とは、見る者の心のあり方がすべてなのだ」(p171)と語る。さらに「孤高にいる者の侘」だと言う一方で、「現世の王に心の内まで支配されては、これほど息苦しいことはない」(p173)とりきに語る。
利休を軸にしながら、様々な相克が並存する状況が進展する。まず、茶の湯における利休と秀吉の相克がある。キリスト教をめぐる高山右近と秀吉の相克、秀吉の勢力拡大に関しては、秀吉と徳川家康の相克、秀吉と島津義久の相克がある。「世の静謐を実現するためには権力者の懐にも飛び込む」という利休の大義が、俗の中での関わりを利休が広げて行く様を描いて織り込んで描いて行くことになる。
「第4章 聖俗」は、美意識としての聖なる茶の湯を、俗の中に持ち込む。世の静謐のために茶事として利用するという局面が大きく動き出す様を描いて行く。北野の大茶湯の提案と実行。利休の大義に対し己への災厄回避のために利休から離れていく堺の商人たちの思惑。秀吉の小田原攻めとそれに対して民の苦しみをミニマムにしようと画策する利休の献策と行動。利休は茶事を手段にして小田原城に赴き開城交渉をする使者となる。また、山上宗二の処刑がリアルに描き込まれていく。伊達正宗と利休の関係の始まり、対話が加わる。
小田原征伐の決着は秀吉を名実共に天下人にしたが、利休にとっては新たな戦いの始まりとなる。
第4章には、興味深いことがいくつか書き込まれている。その要点は、
*山上宗二は「働きのある茶人」。利休の教えを修得し、忠実に再現した。だが、そこから逸脱できなかった。 p164
*利休は茶人を二種類に分ける。一つは利休の教えに忠実である茶人。
もう一つは利休の教えを消化した上で独自の境地に達し、茶の湯の可能性を押し広げて行ける茶人である。 p164
*茶人が最後にたどり着くのは茶杓と花入。この二つは手ずから作れる。自らの考えを具現化することで侘は生まれる。 p382
「第5章 静謐」は、構成として起・承・転の先、最後の「結」となる。
天正18年9月23日に聚楽第で天下平定を祝す大寄せが行われた。四畳半茶室での茶事では、秀吉が作意により、利休に試しを仕掛ける。利休も又、黒を嫌う秀吉に無言で黒楽茶碗を使うという行動を取る。「天下人は・・・・苦きものも飲み下さねばなりません」と。さらに、茶葉には宗二が好んで使った「極無」を使って。それは、利休の終わりへの始まりとなる。
秀吉は朝鮮出兵、大明国討伐という夢に走り始める。勿論、利休の大義はそれをできるだけ穏便に阻止することにある。石田三成は利休を茶事に招き、利休を取り込もうと画策する挙に出る。天正19年正月22日、豊臣秀長が死ぬ。秀吉の行動を押さえることのできた秀長の死の影響は大きい。それは利休を屈伏させたい秀吉の思いを助長する。26日に利休の大坂屋敷を突然秀吉が訪れる。二畳茶室で、秀吉は「そなたの負けだ。もはや茶の湯に力はない」と言い切る。
利休が切腹する直前の半年余の状況、利休の最後の心理戦が描かれて行く。
ストーリーとしての第5章は、第19節、利休が堺に蟄居謹慎の沙汰を受け、罪人扱いの駕籠のまま舟に乗せられ淀川を下るところで終わる。第20節は、上記の通り、エピローグに相当する描写であり、このストーリーが完結する。
第5章に、著者は利休が排除される一因を説明している。要点を記す。
*死を恐れぬ武辺者ほど権力に弱く従順である。茶の湯は武士の魂を鎮める薬になる。だが、茶室において皆同格という意味の「一視同仁」思想は、武士の序を突き崩す毒でもある。 p406
*秀吉と武将の間の関係は武家社会の制度的主従関係であり、御恩と奉公を基本とする。
一方、利休と弟子である武将との間には人格的主従関係が築かれる。利休を中心に結束し、世の静謐を保つために利休を助けようとする。
つまり、制度的主従関係にとっては、組織内組織として邪魔な存在に成長しすぎた。 p428
また、歴史を眺めると、桃山時代には豪華絢爛たる文化が花開いた。様々な道楽の流行・浸透の中で、「政治と密着したことで、茶の湯が桃山文化を代表するものとなり、上は天皇から下は民衆まで、あらゆる人々が熱中するまでになった。」(p461)とも言える。
新たな千利休像が歴史時代小説としてここに紡ぎだされた。
千利休の語る言葉として「侘」の意味、本質論に言及されている。また茶人を二種類に分けている。この視点は、一面で現代社会の茶道に投げかけられた一石と読むこともできる。本書の言及を前提にした場合、現在の茶道はどういう位置づけになるのだろうか。
そういう面から、過去のストーリーに留まらず、現存する茶道に対する考察課題を提起していているとも読め、興味深い。
ご一読ありがとうございます。
本書に関連してネット検索した事項を一覧にしておきたい。
千利休 :ウィキペディア
【 あの人の人生を知ろう ~ 千 利休 】
千利休という戦国時代のカリスマの正体 こばみほ :「note」
山上宗二 :ウィキペディア
山上宗二 :「コトバンク」
山上宗二を想う :「武士道美術館」
千道安 :ウィキペディア
千紹安 :「コトバンク」
古田重然 :ウィキペディア
国宝茶室 待庵 :「豊興山 妙喜善庵」
黄金の茶室 :「MOA美術館」
黄金の茶室と北野の大茶会 :「インターネット公開文化講座」(愛知県共済生活協同組合)
武者小路千家 官休庵 公式ページ
茶の湯 こころと美 表千家ホームページ
裏千家今日庵 ホームページ
茶道 式正織部流(しきせいおりべりゅう) :「市川市」
茶道扶桑織部 扶桑庵 ホームページ
天下の茶人・古田織部が確立した茶の湯「織部流」 :「鳥影社」
遠州流茶道 綺麗さびの世界 遠州茶道宗家公式サイト
古田織部美術館 ホームページ
桃山時代の織部焼美術館 ホームページ
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
こちらもお読みいただけると、うれしいかぎりです。
『天下人の茶』 文藝春秋
『国を蹴った男』 講談社
『決戦! 本能寺』 伊東・矢野・天野・宮本・木下・葉室・冲方 講談社
『決戦! 大坂城』 葉室・木下・富樫・乾・天野・冲方・伊東 講談社
『決戦! 関ヶ原』 作家7人の競作集 講談社
伊東 潤 の短編作品「人を致して」が収録されています。
カバーには、「Sen no Rikyu」と名前が付記されている。その名の通り、茶の湯を究め佗茶の境地を確立したとされる千利休の人生を織田信長並びに豊臣秀吉との関係を主軸にしながら描き出した歴史小説である。
「茶聖」という言葉は、本書のp416に古田織部が利休に語る言葉として出てくる。
「何を仰せか。この世に二人といない茶聖の名が廃れることなどありましょうか」と。本書のタイトルは、この個所に由来するのだろう。
その織部の発言に対し、利休は心の内で語る。「茶の湯は『聖俗一如』なのだ」と。つまり、利休は己がどれだけ俗にまみれているかを明晰に自覚していたと著者は捕らえている。この続きに著者は記す。
”利休には「異常なまでの美意識」という聖の部分と、「世の静謐を実現するためには権力者の懐にも飛び込む」という俗の部分があった。この水と油のような二種類の茶が混淆され、利休という人間が形成されていた。” (p436)
この一文がこの小説のテーマになっている。利休という人間を形成した聖と俗の二面を併せて、その姿を具体的に描き出す。特に、俗の部分に比重を置きながら、千利休の生き様を描き切っていると感じた。
それは同時に、コインの反面として、織田信長が茶の湯を政治の道具として有用とみた視点・発想と行動、及びそれを継承しある時点までは茶の湯に深く傾倒して行った豊臣秀吉の視点・発想と行動をそれぞれ描き出していくことになる。ただし、比重は秀吉の方に傾く。信長を描くのは、秀吉が茶の湯と関わるための必然的な前提であり、秀吉の考えの背景を明確にするために欠かせない部分という印象を受けた。その比重の差は、宗易(利休)がそれぞれの茶頭となった時の序列の違いにも関係していると思う。
プロローグは、天正19年(1591)2月28日、利休の聚楽屋敷にある不審庵での今生最後の手前から始まる。そして検使役蒔田淡路守に遺偈の書かれた折り紙を手渡し、利休が切腹する場面を簡潔に描く。「人世七十 力囲希咄(りきいきとつ) ・・・・・ 今此時ぞ天に抛(なげう)つ」という有名になった遺偈である。
このプロローグで、著者は利休の内奥の言葉として「わしは茶の湯と共に永劫の命を得るのだ」という一文を記す。ここに、著者の千利休観の一端が出ていると思う。
この小説はプロローグに続き5つの章で構成され、独立したエピローグはない。第5章の末尾がエピローグを兼ねている。2月28日当日の場面描写に回帰してこのストーリーが終わる。
「第1章 覇者」は、天正10年6月10日、本能寺の変後、信長落命の事実が堺に届く場面から始まる。信長と茶の湯との関わり及び「御茶湯御政道」の視点が回想的に描かれるとともに、山崎での合戦を経て、秀吉が覇者の立場を確立するまでの要所が描き込まれていく。いわば、この小説構成の「序」である。
「聖」の視点では、利休が長次郎に和物の今焼茶碗を作れという場面。それは村田珠光の考案した「冷凍寂枯」思想を踏襲した茶碗を作れという示唆である。山崎宝寺城の山麓に造られた妙喜庵を秀吉に見せる場面。「名物がなければ、名物を作るまで。・・・・・羽柴様が天下を取り、私の威権を高めていただければできます。」(p55)利休が俗にまみれる決意の始まりである。大坂城築城において、利休が山里曲輪という佗茶の異空間を創造する場面も織り込まれていく。
最も、キーポイントになるのは、宗易が23歳で娶った妻・稲との間の子・紹安と宗易との会話場面である。父・宗易が秀吉に近づいていくことを、紹安は父・宗易が茶の湯に求めるものと矛盾すると批判する。それに対し、宗易は「この世に静謐をもたらし、人々が自由に行き来できる世を作るためだ」と言う。紹安はこの言すら、詭弁と断じる。だが、宗易は俗にまみれる己の行為はこの大義の実現のためとして突き進んで行く。これは宗易と紹安の関わり方の「序」となる。
この大義が利休と秀吉との関わりの一つの柱になり、この小説の主題になっていく。
「第2章 蜜月」は、山崎合戦後、秀吉が勢力範囲を拡大していく展開期である。天正12年の小牧・長久手の戦い、四国の長宗我部との戦いの広がり、天正13年(1585)3月の雑賀・根来一党の討伐が進展する。宗易は茶事を手段としつつ、秀吉の懐深くに入って行く。宗易は堺の商人としての情報、茶の湯の人間関係を介しての情報を武器に、秀吉の知恵袋、参謀的機能を担い始める。その一方で、禁中茶会を催す企画の根回しを宗易が進める。「蜜月」という見出しが二人の関係を暗示する。「承」の段階といえる。
禁中茶会(正式には献茶式)の前、9月8日に宗易は朝廷から「利休」居士号を勅賜された。著者はこの号について、”「利を(追求することを)休む」、すなわち商人としての宗易と決別し、茶人としての道を歩んでいくという覚悟”を込めたものと言い、「この号は、宗易自身が考案し、朝廷が追認という形で下されたもの」(p146)という解釈をしている点は興味深い。
10月7日の小御所菊見の間での献茶は利休がその趣向を考えた。だが、秀吉はその趣向に満足できなかった。茶の湯で帝を驚かせたかったのだ。そこで、利休は2回目の禁中茶会を提案し、秀吉自身がその趣向を考えるべきと言う。秀吉自身が己の侘をみつけるべき時だと。それが2回目の禁中茶会となる。このとき、秀吉は「黄金の座敷」を使う。これはたぶん通常「黄金の茶室」と称されるものをさすのだろう。これが秀吉の作意としての侘だという。著者は、利休が一切関知しないところでこの黄金の座敷が制作されたとして描き出していく。
ここには重要な視点が含まれている。秀吉は利休の言を「胸中にわき立つ作意を現のものにすることこそ侘だ」と受けとめていた。
「寂びた茶室で古びた茶道具を使って茶事を行うことだけが、侘ではない」(p163)ここに、既に形式化しつつある侘に対する侘の本質論がクローズアップされている。黄金の座敷に対する評価意識が転換する視点が描かれている。利休はこの秀吉の作意に「殿下は・・・己の侘を見つけられた」と答える。著者はここに利休と秀吉の関係性の転換点を見出していると言える。
「第3章 相克」は、構成的にも「起」「承」を受けた「転」に入って行く。「第4章 聖俗」と合わせて、時間軸の長い「転」の部分が進展していくように思う。
第3章は、堺の屋敷で、利休とりきが黄金の座敷他について語り合う場面から始まる。ここでも利休は「しょせん侘とは、見る者の心のあり方がすべてなのだ」(p171)と語る。さらに「孤高にいる者の侘」だと言う一方で、「現世の王に心の内まで支配されては、これほど息苦しいことはない」(p173)とりきに語る。
利休を軸にしながら、様々な相克が並存する状況が進展する。まず、茶の湯における利休と秀吉の相克がある。キリスト教をめぐる高山右近と秀吉の相克、秀吉の勢力拡大に関しては、秀吉と徳川家康の相克、秀吉と島津義久の相克がある。「世の静謐を実現するためには権力者の懐にも飛び込む」という利休の大義が、俗の中での関わりを利休が広げて行く様を描いて織り込んで描いて行くことになる。
「第4章 聖俗」は、美意識としての聖なる茶の湯を、俗の中に持ち込む。世の静謐のために茶事として利用するという局面が大きく動き出す様を描いて行く。北野の大茶湯の提案と実行。利休の大義に対し己への災厄回避のために利休から離れていく堺の商人たちの思惑。秀吉の小田原攻めとそれに対して民の苦しみをミニマムにしようと画策する利休の献策と行動。利休は茶事を手段にして小田原城に赴き開城交渉をする使者となる。また、山上宗二の処刑がリアルに描き込まれていく。伊達正宗と利休の関係の始まり、対話が加わる。
小田原征伐の決着は秀吉を名実共に天下人にしたが、利休にとっては新たな戦いの始まりとなる。
第4章には、興味深いことがいくつか書き込まれている。その要点は、
*山上宗二は「働きのある茶人」。利休の教えを修得し、忠実に再現した。だが、そこから逸脱できなかった。 p164
*利休は茶人を二種類に分ける。一つは利休の教えに忠実である茶人。
もう一つは利休の教えを消化した上で独自の境地に達し、茶の湯の可能性を押し広げて行ける茶人である。 p164
*茶人が最後にたどり着くのは茶杓と花入。この二つは手ずから作れる。自らの考えを具現化することで侘は生まれる。 p382
「第5章 静謐」は、構成として起・承・転の先、最後の「結」となる。
天正18年9月23日に聚楽第で天下平定を祝す大寄せが行われた。四畳半茶室での茶事では、秀吉が作意により、利休に試しを仕掛ける。利休も又、黒を嫌う秀吉に無言で黒楽茶碗を使うという行動を取る。「天下人は・・・・苦きものも飲み下さねばなりません」と。さらに、茶葉には宗二が好んで使った「極無」を使って。それは、利休の終わりへの始まりとなる。
秀吉は朝鮮出兵、大明国討伐という夢に走り始める。勿論、利休の大義はそれをできるだけ穏便に阻止することにある。石田三成は利休を茶事に招き、利休を取り込もうと画策する挙に出る。天正19年正月22日、豊臣秀長が死ぬ。秀吉の行動を押さえることのできた秀長の死の影響は大きい。それは利休を屈伏させたい秀吉の思いを助長する。26日に利休の大坂屋敷を突然秀吉が訪れる。二畳茶室で、秀吉は「そなたの負けだ。もはや茶の湯に力はない」と言い切る。
利休が切腹する直前の半年余の状況、利休の最後の心理戦が描かれて行く。
ストーリーとしての第5章は、第19節、利休が堺に蟄居謹慎の沙汰を受け、罪人扱いの駕籠のまま舟に乗せられ淀川を下るところで終わる。第20節は、上記の通り、エピローグに相当する描写であり、このストーリーが完結する。
第5章に、著者は利休が排除される一因を説明している。要点を記す。
*死を恐れぬ武辺者ほど権力に弱く従順である。茶の湯は武士の魂を鎮める薬になる。だが、茶室において皆同格という意味の「一視同仁」思想は、武士の序を突き崩す毒でもある。 p406
*秀吉と武将の間の関係は武家社会の制度的主従関係であり、御恩と奉公を基本とする。
一方、利休と弟子である武将との間には人格的主従関係が築かれる。利休を中心に結束し、世の静謐を保つために利休を助けようとする。
つまり、制度的主従関係にとっては、組織内組織として邪魔な存在に成長しすぎた。 p428
また、歴史を眺めると、桃山時代には豪華絢爛たる文化が花開いた。様々な道楽の流行・浸透の中で、「政治と密着したことで、茶の湯が桃山文化を代表するものとなり、上は天皇から下は民衆まで、あらゆる人々が熱中するまでになった。」(p461)とも言える。
新たな千利休像が歴史時代小説としてここに紡ぎだされた。
千利休の語る言葉として「侘」の意味、本質論に言及されている。また茶人を二種類に分けている。この視点は、一面で現代社会の茶道に投げかけられた一石と読むこともできる。本書の言及を前提にした場合、現在の茶道はどういう位置づけになるのだろうか。
そういう面から、過去のストーリーに留まらず、現存する茶道に対する考察課題を提起していているとも読め、興味深い。
ご一読ありがとうございます。
本書に関連してネット検索した事項を一覧にしておきたい。
千利休 :ウィキペディア
【 あの人の人生を知ろう ~ 千 利休 】
千利休という戦国時代のカリスマの正体 こばみほ :「note」
山上宗二 :ウィキペディア
山上宗二 :「コトバンク」
山上宗二を想う :「武士道美術館」
千道安 :ウィキペディア
千紹安 :「コトバンク」
古田重然 :ウィキペディア
国宝茶室 待庵 :「豊興山 妙喜善庵」
黄金の茶室 :「MOA美術館」
黄金の茶室と北野の大茶会 :「インターネット公開文化講座」(愛知県共済生活協同組合)
武者小路千家 官休庵 公式ページ
茶の湯 こころと美 表千家ホームページ
裏千家今日庵 ホームページ
茶道 式正織部流(しきせいおりべりゅう) :「市川市」
茶道扶桑織部 扶桑庵 ホームページ
天下の茶人・古田織部が確立した茶の湯「織部流」 :「鳥影社」
遠州流茶道 綺麗さびの世界 遠州茶道宗家公式サイト
古田織部美術館 ホームページ
桃山時代の織部焼美術館 ホームページ
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
こちらもお読みいただけると、うれしいかぎりです。
『天下人の茶』 文藝春秋
『国を蹴った男』 講談社
『決戦! 本能寺』 伊東・矢野・天野・宮本・木下・葉室・冲方 講談社
『決戦! 大坂城』 葉室・木下・富樫・乾・天野・冲方・伊東 講談社
『決戦! 関ヶ原』 作家7人の競作集 講談社
伊東 潤 の短編作品「人を致して」が収録されています。















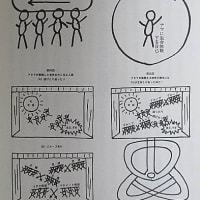




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます