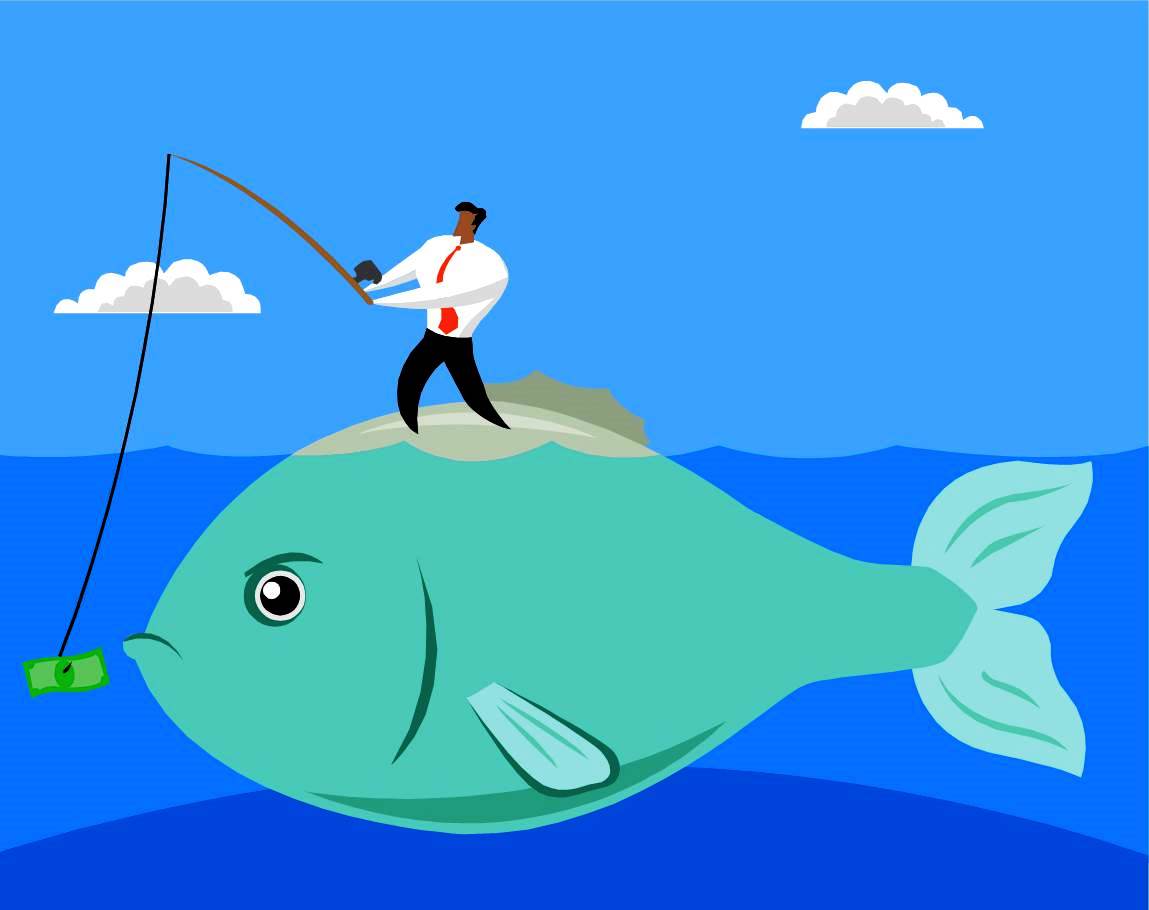前回のブログ「プライベート時間の過ごし方」で読書をお奨めしたところ、何人かの方から「お奨めの本はあるの?」「本屋に行くと本の量に圧倒されて、どれにしたらよいのか迷ってしまう・・・」といった感想をいただきました。
そこで、私は「まず目に入った本を手に取って、相性がよさそうだったらその本を読むことをお奨めします」とお答えしました。
一見、何の役に立つのかイメージできないような本であっても、後日何らかの役に立つことはよくあることです。沢山並んでいる中でそれを手にとったということは潜在的な自分のアンテナに引っかかったということで、その「出会い」を無駄にする手はないと思うからです。
そんなことを考えていたところ、ふと昨年読んだ「『自己啓発』は私を啓発しない」(マイナビ新書)の著書の齋藤正明氏のことを思い出しました。
齋藤氏は、大学卒業後に入社したバイオ系企業で上司のパワーハラスメントにあい、上司との関係を何とか良くしたいと考えコーチングやディベートやコミュニケーションなど、数々の自己啓発やセミナーを受講したのだそうです。自己啓発にかけた額は数年後には何と600万円にもなったそうです。
しかし、自己啓発に勤しんだ甲斐もなく上司との関係は改善されない中、ある日業務命令によりマグロ船に乗せられることになりました。しかし、このマグロ船で出会った漁師たちのコミュニケーション術に感銘を受けて、その後大きな転身をはかったのです。
バイオ系企業を退職した後、コミュニケーションの勉強会でたまたま講師役になったことがきっかけとなり、自身がセミナー講師になることを決めて、現在は年間200回もの講演活動を行っているそうです。
セミナーを受講しまくっていた人が、今はセミナーの講師になっているとは何か不思議な気もしますが、セミナーなどを受講したことで何らかの影響を受けたことは言うまでありません。これはキャリアで言うジョン・D・クランボルツ教授の「プランドハプンスタンス」(計画された偶発性)の一つの例かもしれません。
さて、齋藤氏の本のタイトルの意味ですが、セミナーで習ったことを受動的にそのまま自分にあてはめて使おうとすると効果はない。主体的に自分のスタイルに置きかえて考えることで、初めて意味があると斎藤氏は本の中でおっしゃっています。
研修も受講したらそれで終わりということではなく、自分で咀嚼して応用していくことが大事ということだと思います。
研修の中で、そのことを受講者にあわせてお伝えすることも講師の大切な役割なのだと、あらためて感じました。
(人材育成社)