 | 狂気の巡礼 |
| クリエーター情報なし | |
| 国書刊行会 |
ちょっと前ですが、やっとこさ後半を読み終えました。
本書『狂気の巡礼』は、グラビンスキ生前に発表された二つの短編集(『薔薇の丘にて』『狂気の巡礼』)からの訳出ということですが、後半は『狂気の巡礼』からの8編。
一つ目の『灰色の部屋』は、本書に通底している、場所が孕む魔という主題を根幹にもつ代表作。
前に住んでいたところがどうにもいたたまれなくなった主人公が転居したのだが、どうも新居もなんともやばい感じがしてきた。。と思ったらなんとその新居は・・・・!?
というお話(要約しすぎ)なんですが、話の展開もさることながら、
テーマに関する著者の見解がさりげなく書かれているのではないかしらというような箇所があって、
本文と注釈がごっちゃになっているような印象があるのが面白いです。
長期に住んだ家などに、人間の精神の残滓のようなものが残るということは
比喩としてのみ受け取るべきではない、とか急に書いてある。
場所、というのはつまり家や家具などの無生物なわけで、
無生物に精神エネルギーが浸透して、家主が去った後も残り、
周囲に影響を及ぼす、というのがこの短編集の基調となる薄気味悪さですね。
日本だと地縛霊というニュアンスになりそうですが、
ここではあくまで物に染みこんだ精神なので、
物を撤去してしまうと、精神エネルギーにも居場所がなくなるようです。
2つ目「夜の宿り」もまた、精神の残滓が人の夢に影響を与えるという主題ですが、
この短編の面白さは、全編ほぼ暗闇の描写であることですね。
闇の描写とはすなわち主観のみの世界というか、自分の感覚が生起するイメージだけの世界で、
その描写から夢の描写へのつながりが地続きなところが上手いと思う。
3つ目「兆し」は趣の違う作品。
どうやら恐ろしい事件が起きたのだが、誰もその現場を見ておらず、
読者にもその内容が伝えられないという面白いホラー。
傍観者というか(観ていないから違うか・・)第三者の抱く恐怖心もまた
主題になりうるという、手法的なかっこよさ。
4つ目「チェラヴァの問題」はジキルとハイド風の対照的な人格の話だけど
二重人格ものではない。いや、そうとも言えるけどちょっと違う。
面白いのは、この人格の対照性をネタにしてチェラヴァ氏が稼いでいること。
記憶や思考が両者で共有されていること。
劇的な終焉ののちもそれをネタにするチェラヴァ氏はちょっとしたたか。
精神分析医という存在が神秘と最先端の感覚を人々に与えた時代のもの。
5つ目「サトゥルニン・セクトル」
主に時間をめぐる哲学的な考察、それに精神の交流もしくは分身というテーマが絡んでいる。
繰り返し読みたい小編。やはりどこか埴谷雄高風。ウェルズへのちょっとしたアンサー。
6つ目「大鴉」これも人間の強い思い(というか妄執というか怨念というか)が
事物にとりついているお話。
グラビンスキの好きな、植物が繁茂する負の力場のような裏庭的空間の描写が冴えている。
そういう場所に心惹かれる主人公も定番。
7つ目「煙の集落」は、毛色の違う辺境探検モノ。舞台も北米。
着想がとても奇妙。異文化との出会いがお互い不幸なパターン。
謎の集落の描写が細部にこだわった病的な感じがする。
ドイツの冒険作家カール・マイの影響下にあるという話ですが、
カール・マイといえばあれですよ、シーバーベルクの1976年の映画「カール・マイ」。
そして8つ目「領域」。タイトルは「領域」なのか。う~む???
ワタシはこれが一番怖かった。映画にしたい。トラウマ映画になるだろう。
夜になると敵意を持ってこちらを見つめる人影が・・しかもだんだん増えてくるって。。
そんでもってラストに生まれ出るあれはいったいなに??
後半戦はわりと理知的な怖さを書いているという印象ですが、
最後の「領域」でまた理屈を超えた異様を表現しています。
また、ストーリーの奇想もさることながら、人物の性格設定であるとか、
ちょっとしたシーンの描写が細かく具体的に織り込まれており、
一話ごとの世界を立体的に立ち上らせる感じです。
「チェラヴァ氏の問題」はテレビドラマ化されてるということですが、
確かに映画のカットを想起させる描写にあふれています。
というわけで、グラビンスキ邦訳2冊目でした。
他のものも読みたいので、興味がわいた方はぜひこの「奇跡の巡礼」を購入して、
次の作品への機運を盛り上げてくださるとよいかと思います。
装丁と装画もすばらしいです。









































 amazon
amazon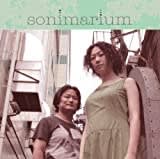 amazon
amazon