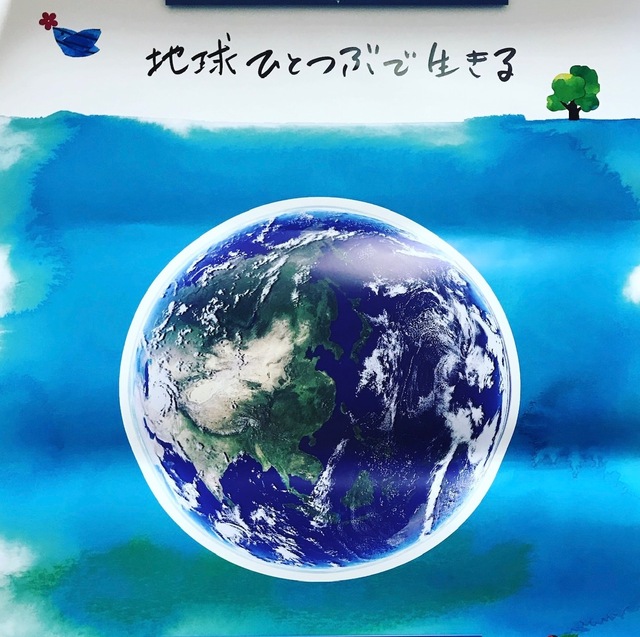討論(抄)
**********
虹とみどりの会として、
本3月定例会に提出されました議案の内
議案第27号 平成30年度郡山市一般会計予算
議案第30号 平成30年度郡山市介護保険特別会計
議案第78号 郡山市介護保険条例の一部を改正する条例
議案第95号 郡山市立美術館条例の一部を改正する条例
議案4件に反対の立場で、
常任委員会で不採択となりました
請願第61号 生活保護基準引き下げの撤回を求める請願
請願第62号 生活保護世帯の子どもたちの大学等への進学に関する意見書提出に
ついての請願
請願第63号 「若い人も高齢者も安心できる年金制度」を国の責任で創設するための意見書提出の請願
請願3件に賛成の立場で、討論を行います。
はじめに、議案第27号、95号、議案2件は、関連していますので一括して反対する理由を申し上げます。
平成30年度郡山市一般会計予算中、原子力災害に伴う家屋の評価額減額補正の解除と郡山市美術館の条例を改正する件に反対します。
まず、固定資産税と都市計画税の減額補正の解除についてですが、その理由を一般住宅や道路除染が完了したことを上げています。しかし、一般住宅除去土壌等の搬出作業は、事業もまだ完了していない地区が多く残されています。各家庭の土地や庭等に除染物が残されたままの状況で、一律に減額補正の解除をして、固定資産税、都市計画税が元に戻ることなど、原発事故の影響で事業や生活再建など苦労している市民も多く、到底納得できるものではありません。広く市民の意見を聞くべきです。
また、今回提案の美術館条例の改正は、近年65歳以上の増加とともに美術館企画展観覧者数も増えており、優れた文化芸術鑑賞の恩恵を受けていた高齢者の愉しみが減ることになってしまう懸念があります。高齢者間の経済格差の課題もあり、料金を払える方は影響ないでしょうが、払うのが厳しい方にとっては、今まで以上に外出の機会が奪われ、増々自宅に閉じこもる傾向になってしまわないか、健康長寿をめざす本市としてどうなのかと危惧します。(観覧料を払える方には、無料招待状の廃止や寄付金等と募るとともに、)払えない方を排除する方向ではなく、憂いなく足を運べる配慮等が求められていると考えます。
次に
議案第30号、議案第78号は、平成30年度から平成32年度までの介護保険料を定めるもので、第6次計画の保険料基準月額5027円から、第7次計画の保険料を介護給付費準備基金から8億円取り崩し、基準月額5573円に引き上げる提案です。平成12年第1次計画基準月額2739円と比較すると約2倍の引き上げになります。一方、サービス利用の負担増、利用の制限に対する苦情等も聞かれ、わずかな年金からの介護保険料支払いには困難で、これ以上の値上げは本当にキツイとの悲鳴も届いています。準備基金を取り崩し負担増をできるだけ回避し、国の責任で、介護を含む社会保障の充実が望まれています。
次に、
請願第61号 生活保護基準引き下げの撤回を求める請願
請願第62号 生活保護世帯の子どもたちの大学等の進学に関する意見書提出についての請願
請願第63号 「若い人も高齢者も安心できる年金制度」を国の責任で創設するための意見書提出の請願
請願3件について、貧困の連鎖と格差解消の観点で、一括して賛成する意見を申し上げます。
厚生労働省社会保障審議会生活保護基準部会は、昨年12月に、5年に1度実施される全国消費実態調査のデータ等を用いた生活扶助基準の検証に関する報告書をとりまとめました。それらを受けた政府は、生活保護政策内容を2018年10月から3年かけて段階的5%削減する方針です。2004年からの老齢加算の段階的廃止、2013年からの生活扶助費3年で6.5%引き下げ、2015年冬季加算の削減とこの間続いてきました。そして、現在もなお全国29都道府県で千名近くの原告が、憲法第25条に反する「生きさせろ」と違憲訴訟中です。
日本の相対的貧困率(可処分所得が中央値の半分未満の人の割合)は、1985年の12.0%から上昇しており、生活保護を受ける世帯の割合(被保護率)は、母子世帯やその他の世帯(主に勤労世帯)で上昇し、高齢世帯の被保護率も2000年代以降上昇しています。そして、特に70歳代以降の女性の相対的貧困率は、3割弱と極めて高い特徴があります。背景は、所得なし又は少ない、低年金、子からの支援がないなどです。貯蓄余力が少なく、年金収入も少ない非正規労働者が現役世代で増加し、予想される「高齢期貧困者」の拡大も懸念されており、その対策は不十分です。
また、親の収入により、子どもの成績、進路、1日1人あたりの食費などに格差があり、両親の年収1000万円超の子の4年生大学進学率62%に対し、年収400万円以下の場合は30%という調査報告もあります(みずほ総合研究所)。年収500万以下世帯が増加し、中間層の所得分布が低い方にシフトしており、我が国の格差を巡る、雇用・賃金・年金・子どもの貧困の課題に対しては、それぞれ1、失業時の公的支援の拡充 2、最低賃金引き上げ 3、将来の低年金者の抑制 4、教育支援と所得保障の実現が重要と提言されています。しかし、現実は、生活保護基準以下の所得で厳しい生活を強いられている国民が増大していても生活保護捕捉率は、わずか2割程度で、先進諸国の中でも著しく低い状態です。厚生労働省社会保障審議会生活保護基準部会が比較検討した低所得階層の消費実態には、本来生活保護を受給すべき階層の8割が含まれており、そもそも比較対象として不適切と指摘する研究者も多くいます。
今回の削減方針は、継続的な消費者物価指数の上昇の下、経済的弱者である子どもや高齢者がさらに追い詰められ、貧困格差が拡大する恐れがあります。本市の標準家族等モデル試算では、0.7%から1.0%のプラスになると説明されていますが、1日当たりでは約30円から約46円の金額です。大学等進学時の一時金の給付は歓迎しつつも、教育の機会均等を充実させる子どもの貧困対策は、待ったなしです。生活費や授業料等に充てるためアルバイトを重ねて心身を壊し残念ながら途中で自死された方もいます。少子化の中、未来を担う子どもたちの貧困の連鎖を止めるべく、抜本的有効な政策を今こそ手厚く実行しなければなりません。
世論調査では、格差が広がっている、格差対策として再分配を強化すべきという見方が多く、富裕層から税金を多くとって貧しい層との所得格差を減らす政策を今より進めるべきとの意見が62%、そうは思わないは31%です。(朝日新聞2015.5.2)
政府がやるべきことは、生活保護制度の目的をふまえ、基準以下の収入で生活している国民に生活保護費を支払うなど制度の拡充見直しと、最低保障年金制度の実現で若い人も高齢者も安心できる年金制度を早急に創設することであり、本市から意見書を提出することは大変有意義です。
「誰一人取り残さない」は、政府が推進している持続可能な開発目標(SDGs)2030アジェンダのキーワードにもなっています。
地域経済の好循環をめざし、「誰一人取り残されないため」にも強く国に働きかけていきましょう。
**********
虹とみどりの会として、
本3月定例会に提出されました議案の内
議案第27号 平成30年度郡山市一般会計予算
議案第30号 平成30年度郡山市介護保険特別会計
議案第78号 郡山市介護保険条例の一部を改正する条例
議案第95号 郡山市立美術館条例の一部を改正する条例
議案4件に反対の立場で、
常任委員会で不採択となりました
請願第61号 生活保護基準引き下げの撤回を求める請願
請願第62号 生活保護世帯の子どもたちの大学等への進学に関する意見書提出に
ついての請願
請願第63号 「若い人も高齢者も安心できる年金制度」を国の責任で創設するための意見書提出の請願
請願3件に賛成の立場で、討論を行います。
はじめに、議案第27号、95号、議案2件は、関連していますので一括して反対する理由を申し上げます。
平成30年度郡山市一般会計予算中、原子力災害に伴う家屋の評価額減額補正の解除と郡山市美術館の条例を改正する件に反対します。
まず、固定資産税と都市計画税の減額補正の解除についてですが、その理由を一般住宅や道路除染が完了したことを上げています。しかし、一般住宅除去土壌等の搬出作業は、事業もまだ完了していない地区が多く残されています。各家庭の土地や庭等に除染物が残されたままの状況で、一律に減額補正の解除をして、固定資産税、都市計画税が元に戻ることなど、原発事故の影響で事業や生活再建など苦労している市民も多く、到底納得できるものではありません。広く市民の意見を聞くべきです。
また、今回提案の美術館条例の改正は、近年65歳以上の増加とともに美術館企画展観覧者数も増えており、優れた文化芸術鑑賞の恩恵を受けていた高齢者の愉しみが減ることになってしまう懸念があります。高齢者間の経済格差の課題もあり、料金を払える方は影響ないでしょうが、払うのが厳しい方にとっては、今まで以上に外出の機会が奪われ、増々自宅に閉じこもる傾向になってしまわないか、健康長寿をめざす本市としてどうなのかと危惧します。(観覧料を払える方には、無料招待状の廃止や寄付金等と募るとともに、)払えない方を排除する方向ではなく、憂いなく足を運べる配慮等が求められていると考えます。
次に
議案第30号、議案第78号は、平成30年度から平成32年度までの介護保険料を定めるもので、第6次計画の保険料基準月額5027円から、第7次計画の保険料を介護給付費準備基金から8億円取り崩し、基準月額5573円に引き上げる提案です。平成12年第1次計画基準月額2739円と比較すると約2倍の引き上げになります。一方、サービス利用の負担増、利用の制限に対する苦情等も聞かれ、わずかな年金からの介護保険料支払いには困難で、これ以上の値上げは本当にキツイとの悲鳴も届いています。準備基金を取り崩し負担増をできるだけ回避し、国の責任で、介護を含む社会保障の充実が望まれています。
次に、
請願第61号 生活保護基準引き下げの撤回を求める請願
請願第62号 生活保護世帯の子どもたちの大学等の進学に関する意見書提出についての請願
請願第63号 「若い人も高齢者も安心できる年金制度」を国の責任で創設するための意見書提出の請願
請願3件について、貧困の連鎖と格差解消の観点で、一括して賛成する意見を申し上げます。
厚生労働省社会保障審議会生活保護基準部会は、昨年12月に、5年に1度実施される全国消費実態調査のデータ等を用いた生活扶助基準の検証に関する報告書をとりまとめました。それらを受けた政府は、生活保護政策内容を2018年10月から3年かけて段階的5%削減する方針です。2004年からの老齢加算の段階的廃止、2013年からの生活扶助費3年で6.5%引き下げ、2015年冬季加算の削減とこの間続いてきました。そして、現在もなお全国29都道府県で千名近くの原告が、憲法第25条に反する「生きさせろ」と違憲訴訟中です。
日本の相対的貧困率(可処分所得が中央値の半分未満の人の割合)は、1985年の12.0%から上昇しており、生活保護を受ける世帯の割合(被保護率)は、母子世帯やその他の世帯(主に勤労世帯)で上昇し、高齢世帯の被保護率も2000年代以降上昇しています。そして、特に70歳代以降の女性の相対的貧困率は、3割弱と極めて高い特徴があります。背景は、所得なし又は少ない、低年金、子からの支援がないなどです。貯蓄余力が少なく、年金収入も少ない非正規労働者が現役世代で増加し、予想される「高齢期貧困者」の拡大も懸念されており、その対策は不十分です。
また、親の収入により、子どもの成績、進路、1日1人あたりの食費などに格差があり、両親の年収1000万円超の子の4年生大学進学率62%に対し、年収400万円以下の場合は30%という調査報告もあります(みずほ総合研究所)。年収500万以下世帯が増加し、中間層の所得分布が低い方にシフトしており、我が国の格差を巡る、雇用・賃金・年金・子どもの貧困の課題に対しては、それぞれ1、失業時の公的支援の拡充 2、最低賃金引き上げ 3、将来の低年金者の抑制 4、教育支援と所得保障の実現が重要と提言されています。しかし、現実は、生活保護基準以下の所得で厳しい生活を強いられている国民が増大していても生活保護捕捉率は、わずか2割程度で、先進諸国の中でも著しく低い状態です。厚生労働省社会保障審議会生活保護基準部会が比較検討した低所得階層の消費実態には、本来生活保護を受給すべき階層の8割が含まれており、そもそも比較対象として不適切と指摘する研究者も多くいます。
今回の削減方針は、継続的な消費者物価指数の上昇の下、経済的弱者である子どもや高齢者がさらに追い詰められ、貧困格差が拡大する恐れがあります。本市の標準家族等モデル試算では、0.7%から1.0%のプラスになると説明されていますが、1日当たりでは約30円から約46円の金額です。大学等進学時の一時金の給付は歓迎しつつも、教育の機会均等を充実させる子どもの貧困対策は、待ったなしです。生活費や授業料等に充てるためアルバイトを重ねて心身を壊し残念ながら途中で自死された方もいます。少子化の中、未来を担う子どもたちの貧困の連鎖を止めるべく、抜本的有効な政策を今こそ手厚く実行しなければなりません。
世論調査では、格差が広がっている、格差対策として再分配を強化すべきという見方が多く、富裕層から税金を多くとって貧しい層との所得格差を減らす政策を今より進めるべきとの意見が62%、そうは思わないは31%です。(朝日新聞2015.5.2)
政府がやるべきことは、生活保護制度の目的をふまえ、基準以下の収入で生活している国民に生活保護費を支払うなど制度の拡充見直しと、最低保障年金制度の実現で若い人も高齢者も安心できる年金制度を早急に創設することであり、本市から意見書を提出することは大変有意義です。
「誰一人取り残さない」は、政府が推進している持続可能な開発目標(SDGs)2030アジェンダのキーワードにもなっています。
地域経済の好循環をめざし、「誰一人取り残されないため」にも強く国に働きかけていきましょう。