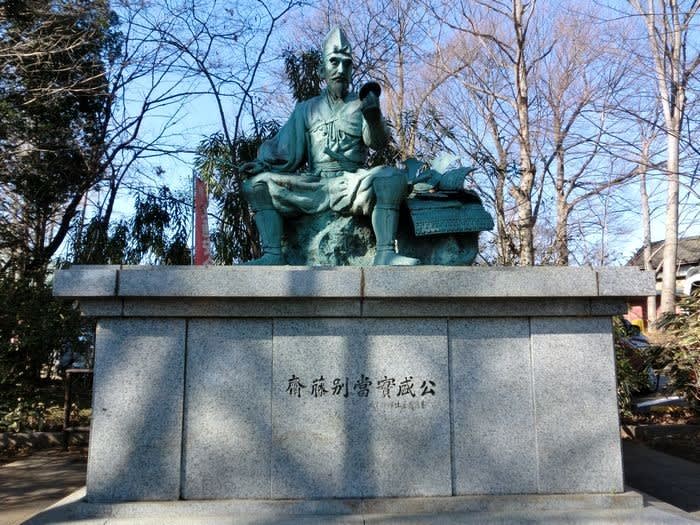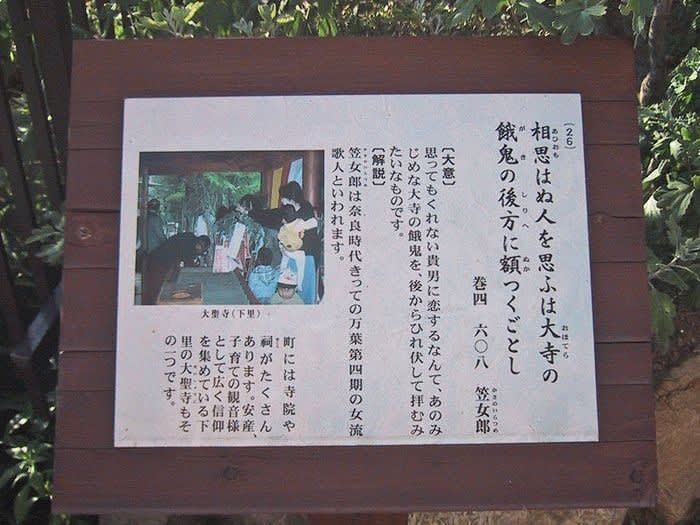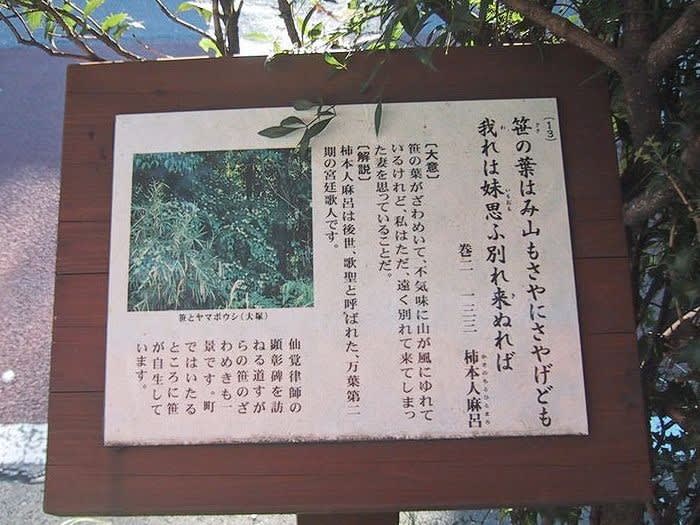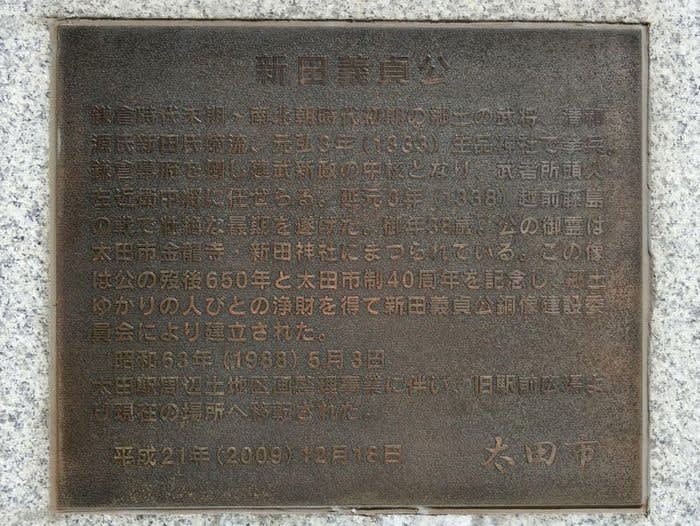『長楽用水路』散策記その②です

前回同様地図に番号を入れて紹介します

地蔵尊から東方へ少し行ったところに架かっている橋の左岸に板碑が見えます (地図⑦)
道路が嵩上げされているので板碑は下3分の1くらいが隠れた状態です ※左側が上流

『阿弥陀一尊図板碑』のようです

背面を見ると近世に供養塔として再利用されたようで
天長 享保十一丙午 長楽村 横田茂太夫
梵字 奉納大乗經本朝回國一千部供養所
地久 三月日 法名権大僧都常楽印勝寛
とあります

京塚樋管 長楽用水路右岸に設置 (地図⑧)

左岸から京塚樋管の正面を
当然ながら樋管の裏側が堤の向こう側にあるのですが写真は失念

音羽橋 左が上流 (地図⑨)
右岸の橋のたもと上流・下流両側に庚申塔が建立されている
左岸側・・・川島町大字正直 右岸側・・・大字戸守

上流側の庚申塔(青面金剛)
左側面に 【顧主 戸守村 七人 正直村 三人】とあり
右側面には建立日があると思われるが判読に難あり

下流側の庚申塔(青面金剛)
右側面に 【安永十辛丑 二月十七日】(1781年)とあり
左側面 判読に難あり

六地蔵橋と石仏 長楽用水路左岸から (地図⑩)
左岸側・・・川島町大字正直 右岸側・・・大字戸守

上流側側面に 【六地蔵橋】 と刻まれている

下流側側面に 【大正十三年十一月竣工】(1924年) と刻まれている

右岸の石仏群 下流から

庚申塔(青面金剛) 【寛政五 癸丑 三月吉日】(1793年) と刻まれている

石橋供養塔 【大乗妙典六十六郡日本廻國橋供養】 宝暦6年(1756年)建立

石幢六地蔵 【正徳四年 甲午講中 ・・・北戸守村】(1714年) と刻まれている

川店(かわだな) 川棚とも (地図⑪)
馬や農具、野菜を洗うために、水路の脇に設けられた場所
洗濯所に使われることもあったようです

サイクリング道路下の長楽用水路 左側が上流 (地図⑫)
埼玉県道158号・川島こども動物自然公園自転車道線の北側を流れる長楽用水路
水路の北側は日枝神社の社叢

ここにも分岐点が 左側が上流 (地図⑫)の付近

山王樋管 (地図⑬)
山王樋管のある場所と日枝神社方向とを行き来できるよう木製の橋が架けられています

黄色の枠の所に『山王樋管』と刻まれた石製の銘板がはめ込まれていますが、この時はゲートの扉
が上がっていて銘板を隠してしまっていました。
堤防の反対側に山王樋管の吐口がありますが、写真は失念

長楽用水路は更に東方に向けて流れ国道254号線の下を通り進んでいきます 上流から

山王樋管のすぐ南側に日枝神社の鳥居があります

日枝神社の鳥居の斜め前にある庚申塔群
右端の庚申塔は 右側面に「文化十二年 乙亥」(1815) 左側面に「三月吉日」と刻まれている
散策日:令和2年(2020)7月16日(木)・19日(日)