先日、「日本ホタルの会」の臨時役員会が開かれた。ホームページを通じて広報宣伝活動するIT委員として出席した。内容の詳細は話せないが、今後の「日本ホタルの会」のあり方、理念、会員の方々へのサービスを見直す時期に来ており、より良い会へ発展させるために1つ1つ問題を解決していこうということになった。全国には、沢山のホタルの会がある。歴史も古く、私がホタルを始めた時にはすでにあった会もあるが、ホタル飼育屋さんの集まりで、会合では、「私は、こうしたらホタルを沢山羽化させることができた・・・」という自慢話に終始するというものもけして少なくない。
「日本ホタルの会」の目的・理念・方向性は、そういうものではない。
「日本ホタルの会」に期待することや具体的に行って欲しいサービス等あれば、遠慮なくご意見を頂戴したい。会員の方はもちろん、ホタル関係者、ホタルに関わっていない方からのご意見も大歓迎である。
「日本ホタルの会」の目的・理念・方向性は、そういうものではない。
「日本ホタルの会」に期待することや具体的に行って欲しいサービス等あれば、遠慮なくご意見を頂戴したい。会員の方はもちろん、ホタル関係者、ホタルに関わっていない方からのご意見も大歓迎である。













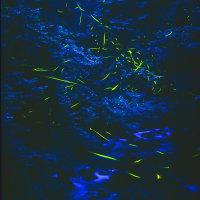






とても美しいサイトをつくり、維持されていることに敬意を表したいと思います。
私の専門は海洋生物で、現在はハマグリ類の資源と環境の問題に取り組んでいます。海辺の自然環境の破壊要因の中で特に大きい要素であり、海の現場では解決できない問題として河川から海に流出してくる汚染物質があります。これについて、カワニナとホタルを軸にすえた水辺と水質環境の保全に注目しています。ハマグリ資源の復活には河川環境の建て直しが不可欠であると考えています。
この環境問題を解決しなければ、いくら海で水産資源生物の種苗放流をやっても無駄な努力に終わる場合があります。海で作り育てる漁業が標榜されてから長い年月がたっていて、無数の稚魚、稚貝などが放流されてきました。新聞やテレビなどマスコミはこのような行為をたたえますが、遺伝子かく乱、病原体の移動、などの問題だけでなく、稚仔魚などの生育環境の改善をバイパスした放流では、肝心の水産資源が持っている持続的な生産能力を忘れてしまい、悪い場合では放流しないと漁獲が維持できないような依存性まで作ってしまいます。特にハマグリの場合は、稚貝時代を河口部の浅瀬で数年間過ごすので、そこに流出してくる汚染物質に高濃度で直接さらされることになります。
水に溶けにくい生物濃縮する農薬が使われなくなってから、水に溶けて流出しやすい化学物質が代替されてきてから、また合成洗剤が普及してから、干潟の貝類などが急速に消えました。
さて、全国ホタル研究会について批判的なコメントを拝見しました。幼虫放流については、指摘されたとおりであると思います。しかし、全国研究会のホームページを見ているかぎり、最近の動向は科学的な合理性を基にして、ホタルとその環境を守りたいという意識があると思われます(まだ放流シンドロームは残っているようですが)。
日本ホタルの会はどうかというと、環境原理主義的なにおいが少し漂っている気がします。ホタルをたくさん飛ばして、それを愉しむという行為は経済行為の一つとして見てもよいと思います。
地域おこし、環境教育の一環としてそのツールとして使うことは(目的と手段が混同されないかぎり)よいことでしょう。営利行為を悪とすれば、たとえて言えば、観賞用の園芸作物やペットなどを育成、生産、販売することが悪いことのように言っているように聞こえます。
人々、団体、それぞれ理念や思想の違いがありますが、ホタルが好きということは一致していると思います。ホタルは豊かな自然と生態系あってこその存在です。また、それにホタルの生息環境が整っていなければ生息できません。もちろん、ホタルがたくさん飛ぶ姿を見たいのは誰しもの思いです。しかし、一部の人々は、ホタルを飛ばしたいという願いだけから、ホタルの生態系を考えず、それを復元・再生することなしに、手っ取り早い方法としてホタルの終齢幼虫を放流するということを続けています。生息環境が整っていなくても、放流すればある程度はホタルは飛ぶのです。果たして、それがホタルの保護や自然環境の再生と言えるのでしょうか。私は、自然環境のことなどどうでもよく、ただホタルを飛ばして喜んでいるだけの人が多いことを悲しく思います。
終令幼虫を大量に生産することには相当な時間と費用と努力を伴うと思います。つまり、この行為は相当強い意志で目的を達成するということでしょう。
生態系の保全の点ですが、遊馬さんたちが指摘されているように、ホタルと里山の生態系というものは人為的に維持されているからこそ存在する系ですね。この系の場合、ただ懐古的に昔の姿を取り戻すことを目指すのでなく、今の時代に合った持続的に存在しうる新たな姿の系を構築する必要もあると思います。
生態学について世間でよく誤解されていることは、生態系とは安定しているものではなく、ダイナミックに変化し続けている系であるという事実です。農耕でも林業でも、それらの系をある特定の状態に維持するためには大きなエネルギーを必要とします。里山生態系でも同様です。
自然環境や生態系などについて「本来の姿」を狭く規定して、それに合わないことを非難したりすることは「原理主義」となりますね。たとえば、実験室の観察と野外生態観察はお互いに補完して、いろいろな事実を教えてくれます。野外でいくら熱心に見ていてもわからないことがあり、また実験室だけでも同様です。
ホタルをたくさん飛ばして、それを愉しむという行為は経済行為の一つ・・・地域おこし、環境教育の一環としてそのツールとして使う・・・反対は致しません。
終令幼虫を大量に生産することには相当な時間と費用と努力を伴うと思います・・・。確かにその通りだと思います。ただ、私が思うのは、その相当な時間と費用と努力をホタルが一生通じて暮らせる(放流等しなくても毎年自然発生する)環境の再生に、まず使うべきだと言うことです。それをせずに終齢幼虫まで大量に養殖して放流するという行為が一部で行われています。ホタルは約9ヶ月~2年9ヶ月間水中生活しますが、放された幼虫は、カワニナをほとんど食べることなく、わずか一ヶ月で上陸して蛹になります。ホタルの生態や生息環境について「本来の姿」を過大解釈して、人が見るため、楽しむために都合の良いようにコントロールすることが、今の時代に合った人為的に維持された、持続的に存在しうる新たな系の姿なのでしょうか?
本来の姿というものがそもそも存在するのかどうか、それが過去の姿と同じであるべきものかどうか、という点を明確にしないと、永久に論理がすれ違います。
たとえば、多くの田んぼの姿は機械化に対応するように変革されていますので、それを昔のような姿に戻すことでホタルがたくさん飛べるようにしたい、と望んでも無理があります。田んぼに一年中水を張っておくことや、畦や水路の土手をホタルの幼虫のさなぎつくりに適合するようにしたいといっても農業生産者はとまどうしかないでしょう。現在のシステムには安定的に作物を生産する目的で工夫された結果、ホタルのライフサイクルを維持させるためには具合が悪いところが多いようです。それについて、ホタル中心主義(その周辺の里山環境の復元を夢見ていたとしても)は農業生産との不整合が起こるでしょう。
私の意見としては、ホタルよりもむしろカワニナが大量に生育できる水辺環境を維持管理することで、間接的にホタルが多く飛べるようにする工夫が大切だろうと思います(もちろん、産卵場所や土まゆを作る場所も用意しておくべきです)。現在の稲作農業と軋轢を生じないようにしながら、新しい姿として、ホタルを愉しむために都合のよいシステムを構築するべきではないでしょうか。そのために、終令幼虫を大量に飼育して放流するやり方は費用と労力ばかりかかって、持続的な方法ではないでしょう。(水産関係でも同じ過ちをやっていると考えています)自然の力を最大限利用して、生物の本来持っている旺盛な生産能力を引き出す工夫を考えるべきです。
自然のなすがままに任せていてもホタルが多く飛ぶ場所もまれにはあるようですが、人々の身近な場所、つまり里山の環境では人為的に維持管理システムを構築しないとたくさんのホタルは飛んでくれないでしょう。それを昔ながらのシステムで今の時代の社会環境で実行できるとは考えにくいと思います。
究極的には、蛍狩りをしてもホタル資源の再生産に支障がおきないようなシステムを維持することも可能であろうと思います。(ただし、そのためのコストを負担するために、持続的な経済行為として認められるべきであるという前提です)
本来の姿というものがそもそも存在するのかどうか、それが過去の姿と同じであるべきものかどうか、という点を明確にしないと・・・
ホタルの自然発生する生息条件を考えますと「本来の姿」は存在しますが、「本来の姿」が崩れてしまった場所において、人々との共存も考えますと、「本来の姿」に戻すことはたいへん難しいことだと思います。
過去の姿に戻すということも難しいでしょう。また、過去の姿と同じでなくても良いと思います。
福島県鮫川村の里山再生と農業生産システム・流通システムをご存じだと思います。行政と住民が一体となって改革し、すばらしい成果を上げています。
この理念や手法は理想ではありますが、残念ながら都市部では通用しません。
日本ホタルの会のホームページでもうたっていますが、
ホタルや身近な生き物を通じて環境問題に注目し、どうしたらそれを守り私たちと共存できるかを調べる、
そしてそのあるべき姿を提案することを目的に活動しています。
今後とも、ご意見をお願い申し上げます。
そこで、ちょっとした工夫をすれば、何かよい方策が見つかるのではないかと思います。
例えば、治水を損なわない範囲の施しをするとか、植物が育つようなコンクリート護岸にすることはできないものでしょうか。
素人の考えでは及びもつきませんが、専門の学者ならそのへんのことくらい分かりそうな気がします。
分かっていて出来ないのか、それとも分からないから出来ないのか、そのどちらでしょうか。はがゆくてなりません。
私は地域に密着した自然環境保全活動をしています。
ここで色々な意見を聞かせていただきましたが、私は基本的に管理人さんの意見に賛成です。
経済活動を最優先にしたり、ホタルを飛ばすことだけを目的にしているかのような活動には強く疑問を持ちます。
申し訳ありませんが、ここには色々な人が出入りしているようなので、具体的な意見は差し控えたいと思います。
確かにこのブログは色々な人にご覧いただいているようです。心より感謝致しております。コメントも随分といただきますが、内容とはまったく関係のない単なる宣伝は削除しておりますが、それ以外は、例えいやがらせであっても削除せずに、そのまま掲載しております。知っていながら知らない振りをして、ちょっと言葉が足らないだけでも、それについて避難する人もいますが・・・。
所詮、ブログのコメント欄です。会議室での議論のようにはいきません。個人や場所の特定をされないような書き方であれば、どのようなご意見でもお書き下さって結構だと思います。