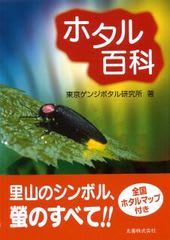日本ホタルの会主催のシンポジウムが開かれる。
第16回 日本ホタルの会シンポジウム
-発光生物を支える水環境を考える-
今年のシンポジウムは、ホタルをはじめとする発光生物を支えている水環境について考るという内容である。興味ある方はご参加を。
日 時 2008年9月6日(土) 午後2時より
場 所 JAM金属労働会館
東京都渋谷区桜丘町6-2,JR渋谷駅西口より徒歩7分
基調講演 稲村 修(魚津水族館) 「蛍烏賊が照らす富山湾」
その他 総合討論
参加費 無料
お問い合わせ
日本ホタルの会事務局 メールアドレス : mail@nihon-hotaru.com
電話・ファックス : 042-530-2111
第16回 日本ホタルの会シンポジウム
-発光生物を支える水環境を考える-
今年のシンポジウムは、ホタルをはじめとする発光生物を支えている水環境について考るという内容である。興味ある方はご参加を。
日 時 2008年9月6日(土) 午後2時より
場 所 JAM金属労働会館
東京都渋谷区桜丘町6-2,JR渋谷駅西口より徒歩7分
基調講演 稲村 修(魚津水族館) 「蛍烏賊が照らす富山湾」
その他 総合討論
参加費 無料
お問い合わせ
日本ホタルの会事務局 メールアドレス : mail@nihon-hotaru.com
電話・ファックス : 042-530-2111