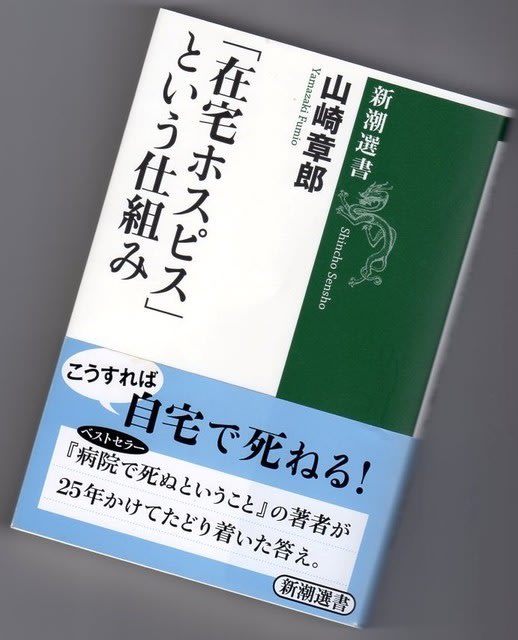
(株)新潮社発行 定価 1300円(税別)
ホスピスケアの第一人者で小平ケアタウンクリニック院長の山崎章郎(ふみお)先生から、3月20日に発行されたばかりの本を恵送いただきました。
山崎先生は小金井市にある聖ヨハネ会桜町病院ホスピスで14年間勤務の後、2005年小平市御幸町に「ケアタウン小平」を創設されました。
ケアタウン小平は一つの建物の中に24時間対応の在宅診療専門診療所、訪問看護ステーション、デイサービスセンター、2階にはアパートもある複合施設。
地域の中でホスピスケアを!を目指し、ケアタウン小平チームとして一貫した事業を行っています。
緑の中庭が美しく、訪れると気持ちが清々しくなる場所です。
多くのボランティアさんが活動し、子どもたちにも遊びの場を提供する子育て支援へも取り組んでいます。
2025年問題から生じるもの
この本の中でまず触れられているのが、2025年には団塊の世代が75歳を超え、死亡者数が年間約153万人に増加すると推計されていること。
2014年には死亡者数は約127万人だったそうですが。
そのため現状のままの病院のベッド数では不足し、入院できない「死に場所難民」の出現が予測される。
かといって新たに医療施設を整備しても、団塊の世代があの世へ旅立ってしまった後は、使われない無用の箱ものになってしまう。
子孫に新たな「負の遺産」を残すことになるからです。
私は「死に場所難民」という言葉を初めて目にしてギョッとしました。
大学への入学難、就職難など「難」がつきまとってきた団塊の世代の私たち。
友人たちと冗談で、「私たちが死ぬ頃はどこも満杯で、葬儀も出してもらえないだろう」と言っていましたが、
それより前の「死に場所」にも「難」がつくのですね。
冗談が現実としてやってくることを否応なく知らされました。
私たちが住み慣れた地域で、できれば自宅を「死に場所」に、自分の意志で、人としての尊厳をもってこの世とおさらばしたい。
無機質な病室の中で延命のチューブや医療装置に囲まれ、人生の最期を迎えたいと思う人は数少ないことでしょう。
そのためには私たちが周囲にはっきりとした意思表示をしておくことが必要だと書かれています。
「在宅ホスピス」ということ
山崎先生はこれまで25年にわたるホスピスケアを通して、現在の在宅ホスピスににたどり着くまでの取り組みをこの本の中で詳述されています。
ホスピス病院では入院患者にしかケアは提供できませんが、ホスピスチームが住まいに“出向くこと”で「最期まで家に居たかった」という患者さんの思いに応えることができる。
そのことが命の危機に瀕しているすべての人にホスピスケアは必要であるという、ホスピス本来の理念にも適うものでした。
実際、山崎先生はケアタウン小平を立ち上げてからも850人以上の方々を在宅で看取られています。
患者さんの状況や家族の思い、それぞれが辛く、重い中で先生は一人ひとりの最終章に相対していらっしゃいます。
「一人でも多くのがん患者さんが、自分らしく生きることができるような支援(緩和ケア)の在り方は、延命を目指した治療の継続以上に重大な課題ではないだろうか」と
書かれているように、現場での実践に基づく緩和ケアの在り方に私自身の行く道を照らし合わせてしまいました。
在宅ホスピスについて何を知り、何が課題なのか。
先生はその教科書として書いたと記されていました。
けれどもそこから浮かび上がるのは、先生の深く温かい人間性です。
「死にゆく人はみな師匠である。私がお会いしたすべての故人のご冥福を祈りたい」とあとがきの最後にありました。
山崎先生が生涯をかけてつくられた、ケアタウン小平がある街に住んでいることを改めて誇りに思います。
地域の中でいかに生きて逝くか。
団塊の世代はいうに及ばず、誰にでも分け隔てなくやってくる死について多くの人たちに読んでほしい。
山崎先生でなければ書けない本です。
思い出すこと
この本の中にも触れられていましたが、4年前に小平の中心地のマンションにホームホスピス「楪(ゆずりは)」が開設されました。
マンションの1室を借りて、自宅にいるように最期まで安心して暮らせる定員5人のホームホスピスです。
この取り組みを立ち上げたSさんを取材したことがあります。
Sさんは聖ヨハネ桜町病院ホスピスでお母さんを山崎先生に看取ってもらい、そのご縁で後にケアタウン小平でボランティアを経験された方。
「楪」を訪ねた時、有料老人ホームとは異なる全く普通の家庭の雰囲気に驚かされました。
その折は90代の女性が穏やかな表情で、リビングのソファで休んでいらっしゃいました。
そこは生活の音や匂いがする場所でした。
開設に至るまでのSさんの熱意と奮闘に感動したものです。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます