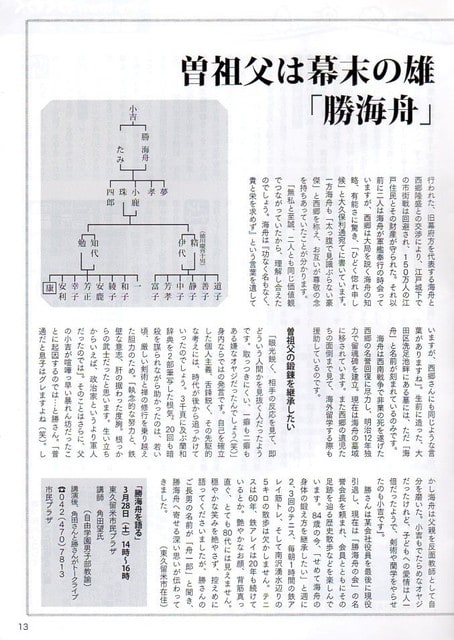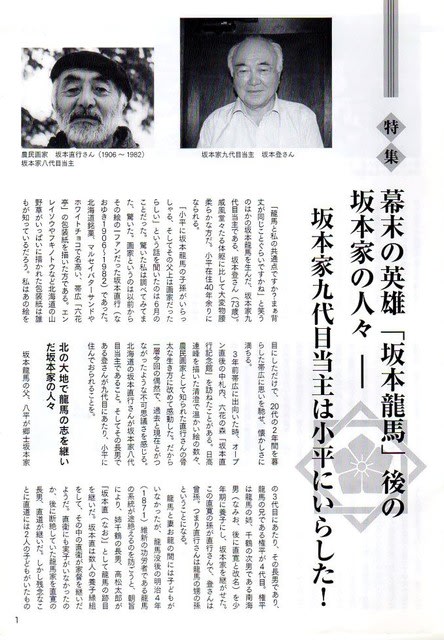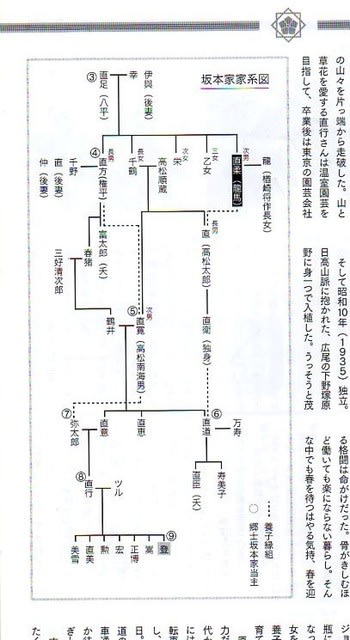今日で東日本大震災から10年ですね。
津波で親を失った子どもたちの10年の成長を映像で見るにつけ、彼らの生きる逞しさ、
周りの人々の温かい支援に心動かされています。
小平在住の演出家・作曲家の寺本建雄さんとプロデューサーの祖父江真奈さんご夫婦が9年前に作った、100人以上の被災者が出演したミュージカル「とびだす100通りのありがとう」が今日、震災の起こった時間14時45分からYouTubedeで公開されます(3月31日まで)
祖父江さんが東京新聞に掲載されたとラインで知らせてきました。

動画サイトはこちらから
https://www.youtube.com/channel/UCaBIlQlsjw7qexi7tMFPslw
思えば、このミュージカルの出発点に私は居合わせたのでした。
寺本さん宅に東松島市から避難してきたバンド仲間の友だちが「世界中からの支援にお礼を言いたい被災者が多いはずだから、何かやりたい」と言ったところ、確か寺本さんが入浴中に「そうだ、ミュージカルでありがとうを発信しよう」と思い立ち決めたのだそう。
このエピソードを寺本さんのアトリエで発足の集まりがあった時聞きました。
2011年春、当時まだ小平市に計画停電が実施されていた時のこと。
途中で電気が消え、ろうそくの灯りの中で話し合ったことが懐かしく思い出されます。
それからの寺本さんと祖父江さんの東松島通いが始まったのです。
出演する被災者を募り、現地で震災体験を取材し、脚本を書き、作詞作曲をしていきました。
こうして2歳から80代の素人の被災者が出演するミュージカル「とびだす100通りのありがとう」
が震災の1年後、3月18日に銀座ブロッサムで公演されたのです。
出演者は大型バスで銀座にやってきました。
あの時のステージから発するエネルギー、観客の熱気は今も忘れられません。
「私たちは負けない、世界中の人々にありがとう!」フィナーレは皆が涙、涙でした。
祖父江さんは「コロナ禍の今、元気のない人も励ますことができると思います。ぜひぜひ一人でも多くの方々にみてほしい」とメッセージしています。
10年の節目にこのミュージカルを見ていただければうれしいです!