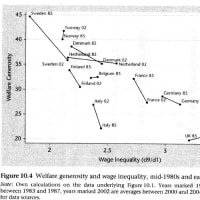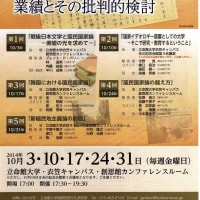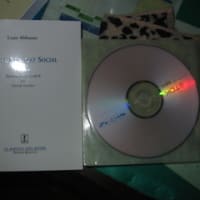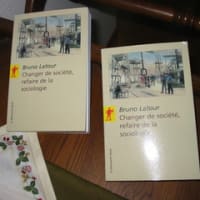最近更新が滞っていた。書くことがないわけではないけれど、なかなか時間がなかったり、あまり書く気が起きなかったり。
その間、本だけでもかなり出ていて、ネグリとハートの本の翻訳、
それからバデュの翻訳も出ていたりする。
両方とも長原先生の翻訳。
それから、仏語の本では、Marx 1845 : Les « thèses » sur Feuerbach (traduction et commentaire) が出ていたりする。この本はまだ手に取っていないけど。
が出ていたりする。この本はまだ手に取っていないけど。
でも、実のところ、今日は、最近はまっているpodcastsのある番組について話をしようと思う。
最近電車の中で過ごす時間が増えてしまったのだが、その時間を有効に使おうと、podcastで様々な番組を拾ってきては、電車の中で聞いている。初めは、米の大学の公開されている講義や講演など、あるいは仏語の教養ラジオ局の書評番組、あるいは思想系その他の本の番組を聞いていたのだが、最近は疲れてしまい、もっと楽に聞けるものにしている。要は、バラエティー番組なのだが……。
で、おもわず吹き出すようなギャグが耳に入ってしまい、電車の中で思わず笑ってしまってあわてて顔を隠そうとしたりする。私の今のおすすめは、"never not funny"というコメディー番組。つい最近笑い出しそうになったのは下のような話題。
大統領が演説で「誰もが大統領になれるような国は、この国以外にあり得ない」と言っていたけれど、、お前のような奴が大統領になれる国は、このアメリカ以外にあり得ないんだよ、ブッシュ大統領! このバカが!!
と、聞いた時点で大爆笑。そのときは、電車の中ではなく、外を歩いていたので、周囲の人から怪しがられることはなかったんですが(笑)。
こうやって常日頃から英語なり仏語なりに触れていることは、確かに大事なことだと思う。
が、そうした方法の限界も、実はあったりすると思う。昔はイングリッシュマラソンという英語教材があって、「耳に入る」程度でいいので常に英語に触れることが役に立つ、というコンセプトだったと思うが。
でも、私自身は、こうした方法では、「わかるものしかわからない」状態はかわらない、と考えている。耳にしているだけでは、複雑な構文がわかるようになるわけではないし、ボキャブラリーが増えるわけでもない。文法的な蓄積も、それほど伸びないと思う。
やはり、机に座って、文法書とにらめっこしながら、あれこれ細かな知識を積み上げてゆく作業も、上達には必要ではないかというのが、「文法主義」の私の考え。って、それはすごく時間けれど。
その間、本だけでもかなり出ていて、ネグリとハートの本の翻訳、
| ディオニュソスの労働―国家形態批判 アントニオ・ネグリ,マイケル・ハート 人文書院 このアイテムの詳細を見る |
それからバデュの翻訳も出ていたりする。
 | 世紀 アラン・バディウ 藤原書店 このアイテムの詳細を見る |
両方とも長原先生の翻訳。
それから、仏語の本では、Marx 1845 : Les « thèses » sur Feuerbach (traduction et commentaire)
でも、実のところ、今日は、最近はまっているpodcastsのある番組について話をしようと思う。
最近電車の中で過ごす時間が増えてしまったのだが、その時間を有効に使おうと、podcastで様々な番組を拾ってきては、電車の中で聞いている。初めは、米の大学の公開されている講義や講演など、あるいは仏語の教養ラジオ局の書評番組、あるいは思想系その他の本の番組を聞いていたのだが、最近は疲れてしまい、もっと楽に聞けるものにしている。要は、バラエティー番組なのだが……。
で、おもわず吹き出すようなギャグが耳に入ってしまい、電車の中で思わず笑ってしまってあわてて顔を隠そうとしたりする。私の今のおすすめは、"never not funny"というコメディー番組。つい最近笑い出しそうになったのは下のような話題。
大統領が演説で「誰もが大統領になれるような国は、この国以外にあり得ない」と言っていたけれど、、お前のような奴が大統領になれる国は、このアメリカ以外にあり得ないんだよ、ブッシュ大統領! このバカが!!
と、聞いた時点で大爆笑。そのときは、電車の中ではなく、外を歩いていたので、周囲の人から怪しがられることはなかったんですが(笑)。
こうやって常日頃から英語なり仏語なりに触れていることは、確かに大事なことだと思う。
が、そうした方法の限界も、実はあったりすると思う。昔はイングリッシュマラソンという英語教材があって、「耳に入る」程度でいいので常に英語に触れることが役に立つ、というコンセプトだったと思うが。
でも、私自身は、こうした方法では、「わかるものしかわからない」状態はかわらない、と考えている。耳にしているだけでは、複雑な構文がわかるようになるわけではないし、ボキャブラリーが増えるわけでもない。文法的な蓄積も、それほど伸びないと思う。
やはり、机に座って、文法書とにらめっこしながら、あれこれ細かな知識を積み上げてゆく作業も、上達には必要ではないかというのが、「文法主義」の私の考え。って、それはすごく時間けれど。