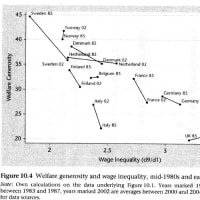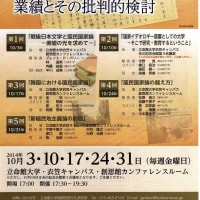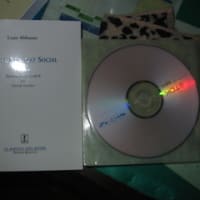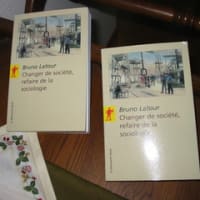電子辞書には、一長一短があるだろうと思う。とりわけ、その検索の速度には。以前新聞記事で、電子辞書の普及で高校生が英語の予習をしなくなったという旨の記事を読んだことがある。それによると、授業で単語の意味を質問されて、その場で電子辞書で調べてしまえば済むため、予習をしなくても答えられるからだとか。
マルクスの生産様式を出すまでもないが、道具等の手段(ここでは「生活手段」あるいは「勉強手段」と呼ぶべき?)に規定されつつ我々の生活様式も変化するのは当然のことであり、パソコンにしても電子辞書にしても、それに適した学習様式がそのうち確立されてゆくだろうと思う。
ただ、今のところ私は、電子辞書に少し距離をとる必要を感じている。少なくとも今のところは、電子辞書に全面的に頼ることは避けようと思っている(と言っても、仏語型の電子辞書は初級辞典止まりなので、大辞典などを使う時には当然紙の本を使わねばならないのだが)。
というのも……。
これについては、私が電子辞書の購入を決めた理由の説明から話したいのだが……、
ある時私は、パリで知り合った仏人の友人と、彼女がある雑誌で書いた日本のロックグループについて書いた記事を和訳するのを手伝ったことがあった(記事が載った雑誌というのは、かなりマイナーな雑誌なよう)。それは、彼女が日本に滞在していた時のことなのだが、的確な日本語の訳語が見つからない時は、二人で辞書を調べてあれこれ議論をしていた。で、彼女は日本で購入した仏和付きの電子辞書を使っていた。私は、帰国して数ヶ月後だったこともあり、滞仏時に辞書を引きまくっていたため、辞書を引く速さには自信があった。で、彼女と競争(彼女は電子辞書の仏和で、私は紙の辞書で、仏単語の意味を調べる)をしたのだが、ことごとく相手にならなかったのだった。私が単語の頭文字のページをおえた時には、彼女はすでに単語を入力し終えて、訳語の候補を見つけていた。
まあ、後に気付いたのだが、彼女が入力していたのは母語の単語。その時点で私には勝てる余地などあるわけがない(たとえ紙の辞書でも 笑)。あとから、あるところで小耳に挟んだのだが(それ故に確かな情報ではないが)、欧米圏で最も優秀な秘書というのは、一分間でタイプできる能力が100ワード以上だという(・〇・;)グェッ。そこまでの能力が、私の友人にあるとは思えないが、1/3程度だとしても一分間で30ワード、つまり二秒ほどで一つの単語が入力できることになる。
それでは、私がかなうわけがない(爆笑)。
で、そのスピードに驚き、自分も電子辞書を購入しようと思い立ったわけである。ただし、購入後に気付いたのは、上のように、彼女は母語を入力していたので、私が実際に電子辞書を使っても、その時に感じたほど(驚いたほど)のスピードは出せなかったのは、言うまでもないが(;^_^A アセアセ…。
長くなったので、また続く
マルクスの生産様式を出すまでもないが、道具等の手段(ここでは「生活手段」あるいは「勉強手段」と呼ぶべき?)に規定されつつ我々の生活様式も変化するのは当然のことであり、パソコンにしても電子辞書にしても、それに適した学習様式がそのうち確立されてゆくだろうと思う。
ただ、今のところ私は、電子辞書に少し距離をとる必要を感じている。少なくとも今のところは、電子辞書に全面的に頼ることは避けようと思っている(と言っても、仏語型の電子辞書は初級辞典止まりなので、大辞典などを使う時には当然紙の本を使わねばならないのだが)。
というのも……。
これについては、私が電子辞書の購入を決めた理由の説明から話したいのだが……、
ある時私は、パリで知り合った仏人の友人と、彼女がある雑誌で書いた日本のロックグループについて書いた記事を和訳するのを手伝ったことがあった(記事が載った雑誌というのは、かなりマイナーな雑誌なよう)。それは、彼女が日本に滞在していた時のことなのだが、的確な日本語の訳語が見つからない時は、二人で辞書を調べてあれこれ議論をしていた。で、彼女は日本で購入した仏和付きの電子辞書を使っていた。私は、帰国して数ヶ月後だったこともあり、滞仏時に辞書を引きまくっていたため、辞書を引く速さには自信があった。で、彼女と競争(彼女は電子辞書の仏和で、私は紙の辞書で、仏単語の意味を調べる)をしたのだが、ことごとく相手にならなかったのだった。私が単語の頭文字のページをおえた時には、彼女はすでに単語を入力し終えて、訳語の候補を見つけていた。
まあ、後に気付いたのだが、彼女が入力していたのは母語の単語。その時点で私には勝てる余地などあるわけがない(たとえ紙の辞書でも 笑)。あとから、あるところで小耳に挟んだのだが(それ故に確かな情報ではないが)、欧米圏で最も優秀な秘書というのは、一分間でタイプできる能力が100ワード以上だという(・〇・;)グェッ。そこまでの能力が、私の友人にあるとは思えないが、1/3程度だとしても一分間で30ワード、つまり二秒ほどで一つの単語が入力できることになる。
それでは、私がかなうわけがない(爆笑)。
で、そのスピードに驚き、自分も電子辞書を購入しようと思い立ったわけである。ただし、購入後に気付いたのは、上のように、彼女は母語を入力していたので、私が実際に電子辞書を使っても、その時に感じたほど(驚いたほど)のスピードは出せなかったのは、言うまでもないが(;^_^A アセアセ…。
長くなったので、また続く