源頼朝は鎌倉で初めての武家政権の樹立に於いて,都の朝廷に対し又武家政権内部の武将たちに対しても,神経をすり減らす毎日であったことでしょう。そのような時 明るい三浦の海を訪れ開放感を味わうために三つの別業(別荘)を儲けました。
それは【桃の御所】・・・見桃寺(けんとうじ)。 【桜の御所】・・・本瑞寺(ほんずいじ)。 【椿の御所】・・・大椿寺(だいちんじ)。
その三寺を軸に周辺を訪れました。
★ 三崎の歴史 ★
源頼朝の別業の時代。
戦国時代には,三浦氏により新井城の出城として三崎城ガ構えられました。三浦氏を滅ぼした後北条氏は房総の里見氏に備え,三崎城を強化しました。
天正18年(1615),徳川家康は関東入府に伴い,三浦郡の直轄領を支配するため,長谷川長綱を三浦領代官に命じます。一方江戸湾口のおさえとして,三崎に向井・間宮・小浜・千賀氏の4名のお船手奉行をおきました。
1615年豊臣氏が滅亡すると,4氏のうち向井氏だけが残り御船手奉行として,元禄期まで長く三崎に足跡を残します。
1618年向井将監忠勝によって船改めが開始され,海の関所として「出船・入船}の検査が行われたのです。1696年にはそれも廃止され下田奉行所に引き継がれました。
欧米の外国船が接近するようになった19世紀には,会津藩主松平容衆が幕府から任命され,その後 川越 小田原 熊本 佐倉藩等が沿岸防備に着きました。
★ 見桃寺 ★

【山号寺号】紫陽山見桃寺。 【宗派】臨済宗妙心寺派。 【開基】向井正綱。
源頼朝の三崎・三御所の一つ「桃の御所」跡。 能救寺と城ケ島の神宮寺が見桃寺に合併され,秘仏の薬師如来は三浦市の指定文化財。境内には北原白秋の歌碑があり,三崎の名を天下に知らしめた「城ヶ島の雨」はここで出来たとされます。
★ 本瑞寺 ★
【山号寺号】海光山本瑞寺。 【宗派】曹洞宗。 【開基】三浦荒次郎義意
源頼朝の三崎・三御所の一つ「桜の御所」跡。

境内には彫刻家北村四海の胴型の墓があり,その傍らには彼の愛児桜子の像が彫られています。御所に相応しいお名前ですね。
★ 大椿寺 ★
【山号寺号】金剛山大椿寺。 【宗派】臨済宗妙心寺派。 【創建】正治元年頃(1200)
源頼朝の三崎御所の一つ「椿の御所」跡。ここには頼朝の愛妾がいて,頼朝亡き後髪を下して妙悟尼と称し大椿寺の開基となったといわれています。
本尊は秘仏の十一面観音菩薩坐像。右脇間には椿の杉戸絵があり「椿御所」の掲額があります。
久々の「鎌倉史跡めぐり」に参加して,三崎に頼朝の別荘があったことも初めて知ることが出来ましたし,いつもはお弁当のところをお食事処で海の幸を味わうことが出来て楽しい旅になりました。














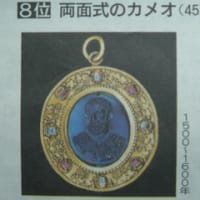







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます