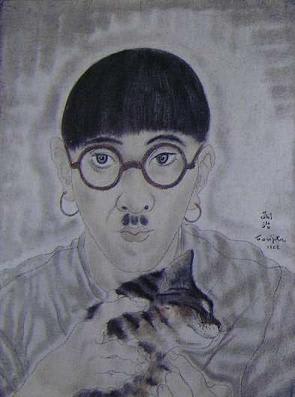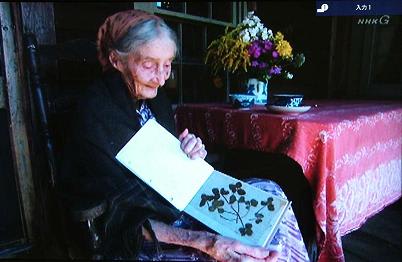鎌倉歴史散策「桔梗の会」には 二年前に入会いたしましたが、色々な角度から何度お聞ききしても魅力的です。今回は《タイトルを辿る》でした。
【中世鎌倉の幕開け】
頼朝は鎌倉の街造りの第一歩として、鶴岡八幡宮の社頭から由比ノ浦へ一直線に延びる大路を造り、平安京の朱雀大路を模して若宮大路と名付けました。
【段葛と鳥居】
同時に妻政子が懐妊した慶事は、頼朝の歓びも大きく安産を祈願しての特別の参詣道「段葛」が造られました。
「吾妻鏡」に治承4年(1180)12月16日、鶴岡若宮に鳥居立てられるとあります。
由比ガ浜に近いところに一の鳥居 段葛の南端に二の鳥居 八幡宮入り口が三の鳥居と称されています。

境内入口近くに、源平池という瓢箪型の蓮池が有りますが、北条政子が造らせたもので、東側には白い蓮を植えて源氏池とし、西側は赤い蓮で平氏池。
そこに朱塗りの橋が架けられました。
【源平池と赤橋】

文治2年(1186)4月頼朝と政子達が見物した静御前の舞は、現在の舞殿ではなく若宮の回廊だったと言われています。
「吾妻鏡」に依れば 当日工藤祐経が鼓を、畠山重忠が銅拍子を打ち「それはまことにこの神社での壮観であり、身分の上下を問わず皆全てが感嘆を催した」とその感動振りを描写しています。
舞殿左奥の大銀杏は樹齢千年といわれ 県の天然記念物ですが、承久元年(1219)正月 この樹に隠れた公暁(頼家の子)は三代将軍源実朝を襲い殺したとあります。
【舞殿と大銀杏】

舞殿の後方の石段を上り詰めた所に本宮がありますが、1063年頼朝の5代前の先祖 源頼義が奥州鎮圧をして鎌倉由比郷の鶴ヶ岡に、石清水八幡宮を勧請して鶴岡若宮としてより約100年後、治承4年(1180)12月頼朝は鎌倉入場2ヶ月後に鶴岡の名前を冠したまま若宮の地に遷宮しています。
建久2年(1191)大火で類焼したため、新社殿を現在地に建て改めて石清水八幡宮を勧請し、頼朝自身の鶴岡八幡宮を創建しました。
現在境内には、流鏑馬馬場・舞殿・大銀杏・丸山稲荷社・白旗神社の外に、県立美術館・市立国宝館等があります。
【鶴岡八幡宮寺式内社:延喜式神名帳に記載された神社であり、朝廷から認識されていました】

本宮を降りて東側へ向かうと静かな雰囲気の中に、本宮とは対照的な黒漆の美しい神社が佇んでいます。
二代将軍頼家が父頼朝を祭神として建立しました。
木立の中に石柱があります。
「歌あわれ その人あわれ 実朝忌」
後に実朝もこの神社に祀られました。
踵をかえして南に向かうと、左手に校倉風の国宝館がありその庭に実朝の歌碑が建っています。
「山はさけ 海はあせなん世なりとも 君にふた心 わがあらめやも」
【白旗神社】

【鎌倉幕府の成立】
鎌倉幕府の成立については諸説ありますが、主な説として
①智承4年(1180)鎌倉に入り武家政権を樹立した時。
②壽永2年(1183)「十月宣旨」を獲得し東国諸国の支配権を確立した時。
③元暦元年(1184)公文所・門柱所を設置した時。
④文治元年(1185)「守護・地頭」の設置権限を獲得した時。
⑤建久元年(1190)右近衛大将となった時。
⑥建久3年(1192)征夷大将軍に任命された時。
等々で⑥説が従来の定説になっています。
現在の宝戒寺は、鎌倉時代北条得宗家一族の居住した「小町亭」跡で元弘3年(1333)鎌倉幕府滅亡後、一族慰霊の為建武2年(1365)足利尊氏が創建した寺院です。
萩の寺で知られていますが 銘木「ムクロジ」の大木が聳えていました。
【無患子】

元弘3年(1333)5月22日新田義貞の鎌倉攻めで、北条得宗家最後の執権北条高時は菩提寺である東勝寺に遁れて、寺に火を放ち自害して鎌倉幕府は滅亡しました。その時高時と一緒に死んだ人々は総勢870余人だったそうです。その後寺は再建されましたが戦国期に完全に廃絶しました。
その跡地に佇んで・・・広大な敷地は金網で隔離され鎌倉市の管轄になっていました。最奥に腹きりやぐらが・・・卒塔婆も新しく花が手向けられていました。
【東勝寺跡 腹きりやぐら】