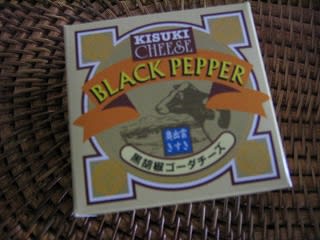あけましておめでとうございます。
年内もう一度更新!と宣言?してたわりに、あっさりこう言うことになってしまった。。
大晦日の夜。皆さんどう過ごしましたか?
紅白をちらちら見ましたが、あまりのつまらなさに・・・というより、民放頼りの企画の連発に情けなさを禁じえず、
早々に「ダイナマイト!」に切りかえた。
民放の番組企画のスタッフとして参加していた経歴があるワタシとしては、
NHKがおいしいところだけ持っていくのはどうにも疑問を感じざるを得ない。
ダイナマイトも、あれだけ引っ張ったわりには永ちゃん1曲かよ!!
・・・というようなものたりなさはあるが、
「格闘技で燃える大晦日」ってのが紅白に代わるニッポンの風物詩として定着するかもしれない。
話は変わるが、
沖縄では、年越しそばも当然「沖縄そば」だ。
厳密にいえば、沖縄そばはそば粉が使われていないので、「そば」ではない。
それをとやかくいう人もいるにはいたらしいが、それで定着しているので「そば」ということになったらしい。
パパイヤだって、沖縄では「野菜」だ。
食品成分表には「果実」のところに載っていようがなんだろうが、とにかく「野菜」なのだ。
先月、沖縄そばの名店に行く機会を得た。
前から行きたいと思っていた国際通り近くの「大東そば」
じつは南大東島のそばなので、いわゆる沖縄そばとは少しちがう
麺は南大東島で作ってその日のうちに空輸しているらしい
私は、八重山そば(石垣島・与那国島)、宮古そば(宮古島)など、離島のそばが好きだが、
この「大東そば」は絶品。
きしめんのような、うどんのようなシコシコ麺がスープに絶妙にからむ
あまりにもおいしくて、はじめてスープを全部飲みほしてしまった
あ~、もう一度食べたい。。
☆今年も1クリックの応援をよろしくお願いします!
人気Blogランキング















 「沖縄タイムス」のホームページに豚料理のことがでています。
「沖縄タイムス」のホームページに豚料理のことがでています。