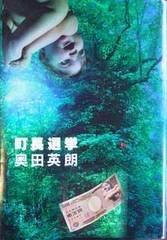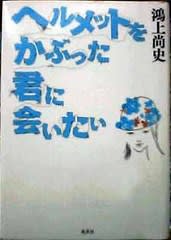本格的に写真を撮りはじめた頃手にしたカメラが今回紹介するNicca33。
父親が写真好きであったためか、小学校低学年の頃には120フィルム(フィルム幅:61.5mm, 長さ:830mm でパーフォレーション[フィルム送りの穴]無しのフィルム)を使ったロクロク版(56ミリ×56ミリ)の「
フジペット」で「写真」を撮っていた記憶がある。
その後、今は手元に無くメーカーも忘れたが、上から覗き込む
二眼レフを貰ったり、35ミリレンズシャッター式の
コニカSⅡを買ってもらったりしながら、徐々に写真へのめりこんでいった。
そこで今回登場するカメラだが、ニッカという戦後の一時期
ライカ・コピーを生産し、その後ヤシカに合併されたメーカーの最後のカメラがこの「33」。父親から譲り受けた。
通称の39ミリのスクリューマウント=通称「ライカマウント」と、写真では見えないが距離計が別になった「2眼式」のファインダー、シャッターダイヤルがボディ上面の軍艦部の高速側と前面の低速の2軸に別れ且つ高速側はシャッターを切ると回転する「2軸回転式シャッターダイヤル」、それと今の銀塩カメラ(新しい「M型ライカ」を除く)のほぼ100%が裏蓋を開けてフィルムを装填するのに対し、
底蓋を開けて「職人技」でフィルムを装填するのが古いタイプのカメラに共通の特徴。
本家「バルナック・ライカ」や日本製のコピーは巻上げがノブ式なのに対し、このニッカ33はレバー式(小刻み巻上げOK)という優れもの!また、シャッターボタンの位置が「本家」やコピーの多くがボディ後端よりの、巻上げスプロケットの上部と異なり、前寄りの自然な位置にあるのも特徴の一つ。残念ながらシャッターの最高速度は1/500秒止まり。
父親から譲り受けた当初は「銀梨子地」のいわゆる「
白ボディ」であったが、高校時代に、今は名前が思い出せないプロの写真家がカメラを目立たなくするため、ブラックボディを使った上にメーカーのロゴにまでブラックテープを貼っていたという記事を読んで、自分で分解してブラック塗装を施した。