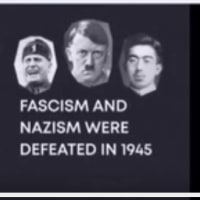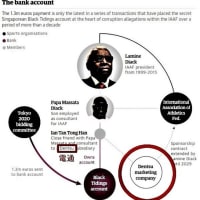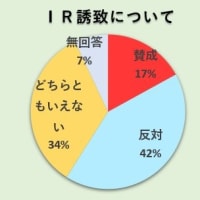休日に職場から離れた場所で「しんぶん赤旗」号外を配布した公務員が、また1人有罪になった。勿論、「自由民主」や「公明新聞」を配っても逮捕されることはない。ところが、19日、東京地裁・小池勝雅裁判長は、ビラ配布が「公務員の政治的中立性に抵触する、強い違法性を有する行為」だとして、求刑通り罰金十万円の実刑判決を言い渡した。政治的中立性をいうなら、各省庁が財界から各種諮問委員会や審議会などに代表を受け入れ、派遣された委員と相談しながら財界の意向を政策立案に反映させていることの方がよほど政治的中立性に抵触している。残念なことに「しんぶん赤旗」を配る一般公務員には、政治的中立性に影響するような力がないからこそ、国民の利益にもならない、国民を苦しめる、碌でもない施策が次々と出てくるのだ。
国公法世田谷事件で、東京地裁は19日、宇治橋眞一氏にたいして、罰金十万円の有罪判決を言い渡した。世田谷事件は、厚生労働省職員の宇治橋氏が、2005年総選挙の最終日に、世田谷区内の警察官官舎に「しんぶん赤旗」号外を配布したもので、配布場所では住居侵入という別の容疑で検挙したが、宇治橋氏が国家公務員だと判明すると、住居侵入は不問に付して国家公務員法違反(政治的行為)で起訴していたものである。政党や政治団体の構成員や支持者などが、集合住宅や一戸建て住宅の郵便受けにビラを配ったり、駅頭や街頭でビラを配布したりすることは、日本中で普通に行われている政治活動である。ビラ配布は、まわりから見て配っている人がどんな職業なのかなどは、全く関係ないし、なんの問題にもならない。ところが、ふつうの人が配れば何でもないことが一般の国家公務員が配れば犯罪だというのが、今回の東京地裁が言い渡した判決の論理である(「しんぶん赤旗」2008年9月20日)。
犯罪というからには当然、その根拠が必要だ。公判で検察側は、郵便局職員の選挙活動を違法とした34年前の猿払事件最高裁判決(1974年)に全面的に依拠して、宇治橋さんの行為の違法性を主張していたが、判決は検察の言い分をそのまま受けいれた。
猿払判決とは、一人の国家公務員の私的な場面での職務と関連しない態様での政治的行為が直ちに行政の中立性を侵害することはないとしても、それを許してしまうとその公務員がいずれは公務においても政治的偏向をもたらす危険もあれば、あるいは他の公務員に伝播して他の公務員が政治的偏向ある人間になるやもしれず、ひいては公務全体において政治的偏向が生じ、行政の中立性に対する国民の信頼が損なわれる、というものである(余りに評判が悪く、その後長らく援用されるようなことはなかった)。
弁護士の石井逸郎さんは、これを「不合理な校則を正当化するときの教師の言い分と同じ」レベルという。「何故、靴下は白でなければいけないのか?長髪は何故だめか?こうした問いに対し、教師から、確かに色の付いた靴下を履いたからといって直ちに不良少年になるわけではない、しかし一旦それを許すといつしかファッションにばかり気にする子どもになり、あるいは一人に許すとみんながファッションにばかり気にするようになり、ひいては学校全体の学問の気風が損なわれ、学校が荒れる、などという、よく聞かされた理不尽な理由」となんら変わらない。「この論理は、単に中学生を押さえつけるためのものでしかない、と多くの中学生が思っている。猿仏判決の論理も、単に、国家公務員を中学生と同じように、荒れないように、がんじがらめに拘束する必要があると考えたに過ぎない」(石井逸郎「堀越事件第一審判決の論理の幼稚性」)。
いま、ビラ配りへの規制・公務員への弾圧を強めているのには、明白な政治目的がある。はじまりは2004年2月の立川自衛隊官舎への「イラク派兵反対」のビラ配布であったが、その後の一連の事件には注目すべき共通点がある。第1に、これらの事件はいずれもビラの配布に焦点を合わせ、これを弾圧しようとしている点である。第2は、取締りの対象が共産党か、立川テント村のように長年市民運動を継続している組織をねらったものであること、つまり組織の運動をねらったものである点である。第3は、これら逮捕・起訴がいずれも組織的、計画的に実行されていること、第4は弾圧のたびに取り締まり対象が拡大している点である。すなわち取り締まりは、まず国家公務員から市民へと拡大し、またビラ配布でもマンションの各戸のポストへの配布から、集合ポストへの配布にまで拡大しているなどである。
こうした特徴を見ると、これらの一連の弾圧事件が、この間の改憲や構造改革にたいする政党や市民の運動の活発化に冷水を浴びせようという意図の下に行われているのは明らかである。さらに、注目すべきことは、これが現在、新憲法制定議員同盟の掲げる九条の会運動への対抗、九条の会への規制というねらいに収斂しつつある点である(渡辺治・一橋大学大学院教授「憲法をめぐる現局面と海外派兵恒久法」(月刊『全労連』2008・9 No.140)。
国公法世田谷事件で、東京地裁は19日、宇治橋眞一氏にたいして、罰金十万円の有罪判決を言い渡した。世田谷事件は、厚生労働省職員の宇治橋氏が、2005年総選挙の最終日に、世田谷区内の警察官官舎に「しんぶん赤旗」号外を配布したもので、配布場所では住居侵入という別の容疑で検挙したが、宇治橋氏が国家公務員だと判明すると、住居侵入は不問に付して国家公務員法違反(政治的行為)で起訴していたものである。政党や政治団体の構成員や支持者などが、集合住宅や一戸建て住宅の郵便受けにビラを配ったり、駅頭や街頭でビラを配布したりすることは、日本中で普通に行われている政治活動である。ビラ配布は、まわりから見て配っている人がどんな職業なのかなどは、全く関係ないし、なんの問題にもならない。ところが、ふつうの人が配れば何でもないことが一般の国家公務員が配れば犯罪だというのが、今回の東京地裁が言い渡した判決の論理である(「しんぶん赤旗」2008年9月20日)。
犯罪というからには当然、その根拠が必要だ。公判で検察側は、郵便局職員の選挙活動を違法とした34年前の猿払事件最高裁判決(1974年)に全面的に依拠して、宇治橋さんの行為の違法性を主張していたが、判決は検察の言い分をそのまま受けいれた。
猿払判決とは、一人の国家公務員の私的な場面での職務と関連しない態様での政治的行為が直ちに行政の中立性を侵害することはないとしても、それを許してしまうとその公務員がいずれは公務においても政治的偏向をもたらす危険もあれば、あるいは他の公務員に伝播して他の公務員が政治的偏向ある人間になるやもしれず、ひいては公務全体において政治的偏向が生じ、行政の中立性に対する国民の信頼が損なわれる、というものである(余りに評判が悪く、その後長らく援用されるようなことはなかった)。
弁護士の石井逸郎さんは、これを「不合理な校則を正当化するときの教師の言い分と同じ」レベルという。「何故、靴下は白でなければいけないのか?長髪は何故だめか?こうした問いに対し、教師から、確かに色の付いた靴下を履いたからといって直ちに不良少年になるわけではない、しかし一旦それを許すといつしかファッションにばかり気にする子どもになり、あるいは一人に許すとみんながファッションにばかり気にするようになり、ひいては学校全体の学問の気風が損なわれ、学校が荒れる、などという、よく聞かされた理不尽な理由」となんら変わらない。「この論理は、単に中学生を押さえつけるためのものでしかない、と多くの中学生が思っている。猿仏判決の論理も、単に、国家公務員を中学生と同じように、荒れないように、がんじがらめに拘束する必要があると考えたに過ぎない」(石井逸郎「堀越事件第一審判決の論理の幼稚性」)。
いま、ビラ配りへの規制・公務員への弾圧を強めているのには、明白な政治目的がある。はじまりは2004年2月の立川自衛隊官舎への「イラク派兵反対」のビラ配布であったが、その後の一連の事件には注目すべき共通点がある。第1に、これらの事件はいずれもビラの配布に焦点を合わせ、これを弾圧しようとしている点である。第2は、取締りの対象が共産党か、立川テント村のように長年市民運動を継続している組織をねらったものであること、つまり組織の運動をねらったものである点である。第3は、これら逮捕・起訴がいずれも組織的、計画的に実行されていること、第4は弾圧のたびに取り締まり対象が拡大している点である。すなわち取り締まりは、まず国家公務員から市民へと拡大し、またビラ配布でもマンションの各戸のポストへの配布から、集合ポストへの配布にまで拡大しているなどである。
こうした特徴を見ると、これらの一連の弾圧事件が、この間の改憲や構造改革にたいする政党や市民の運動の活発化に冷水を浴びせようという意図の下に行われているのは明らかである。さらに、注目すべきことは、これが現在、新憲法制定議員同盟の掲げる九条の会運動への対抗、九条の会への規制というねらいに収斂しつつある点である(渡辺治・一橋大学大学院教授「憲法をめぐる現局面と海外派兵恒久法」(月刊『全労連』2008・9 No.140)。