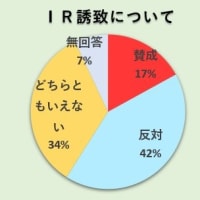2005年に集合住宅(警視庁職員官舎)で共産党機関紙「しんぶん赤旗」の号外を配布したとして、国家公務員法違反(政治的行為)の罪に問われた厚生労働省の元課長補佐宇治橋真一被告(62)の控訴審判決で、東京高裁の出田孝一裁判長は13日、「政治的行為を制限する規定と罰則の適用は合憲」と判断、罰金10万円とした一審判決を支持、被告側の控訴を棄却した(「東京」2010年5月13日 )。
国家公務員法(110条1項19号)は同法第102条第1項に規定する政治的行為の制限に違反した者に対して3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することを定めている。そして、第102条第1項に規定する政治的行為は具体的には、人事院規則14-7(政治的行為)の第6項で17に及ぶ政治的行為として規定されている。
憲法は「平等で自由な個人」を第一義的原理としているが、個別の公務員は、職種・職務権限・勤務時間の内外を問わず、また行為の行われる場所のいかんを区別することなく、一律広範囲に「政治的行為」について規制を受ける。なぜこんなことになったのか。
占領軍の時代、労働運動の高揚を恐れる連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーの指示で1948年(昭和23年)、第102条第1項に「人事院規則で定める政治的行為」を禁止する旨の規定が導入され、第110条第1項第19号の罰則規定も定められた(なお、同時に労働基本権に対しても大幅な制約が加えられた。)。
公務員政治的行為規制システムは、世界標準からかけ離れた、まさに旧体制(アンシャン・レジーム)の遺物なのだ(奥平康弘「『堀越事件』東京高裁無罪判決の意味」『世界』2010・6/no.805)。
国家公務員法第102条第1項、人事院規則14-7は、一般職の国家公務員の政治活動を一律広範囲に制限していること、その政治的行為の具体的な定めを包括的に人事院規則に委任していること(その違反行為が刑事罰の対象となることから、犯罪の構成要件の委任であり、罪刑法定主義との関係でも問題となる)、またその制定が連合国軍総司令部の意向によってなされたものであることなどから、制定当初より、これを違憲とする学説が根強い。しかし、当初、最高裁判所や下級裁判所は、これらの規定を違憲と判断したことはなかった。
ところが、その後、北海道宗谷郡猿払村の郵便局に勤務する郵政事務官が、1967年(昭和42年)の衆議院議員総選挙に際し、日本社会党を支持するポスターを掲示し又は配布したという事実で起訴された事件(猿払事件)があり、旭川地裁は、国家公務員法の政治的行為の制限規定を日本国憲法第21条第1項が保障する表現の自由との関係からはじめて検討し、被告人の当該行為に適用される限度において、行為に対する制裁としては合理的にして必要最小限度の域を超えるものであり、日本国憲法第21条、第31条(適正手続の保障)に違反する、として無罪判決を出した(1968年3月25日判決)。
法令違憲・全面違憲ではないが、個別・具体的な本件に適用するのは違憲(いわゆる適用違憲論)というわけだ。
旭川地裁判決の影響は大きく、その後、全国の裁判所に係属していた同種の事件につき、下級審で同法、同規則の規定を違憲と判断するか、あるいは同法、同規則を違憲とまでは判断しないものの、公務員の政治的行為に可罰的違法性がないなどとして、無罪とする事例が続出した。このような動きを真っ向から抑えにかかったのが、1974年(昭和49年)の猿払事件最高裁大法廷判決である。
猿払事件大法廷判決は、「平等で自由な個人」の上に「国民の共同の利益」なる抽象的・情緒的概念をおき、公務員の自由制限=禁止を全面的に正当化した。こうして、公務員の一律規制がなければ、「行政の中立的運用は保てない」、したがって一律規制が不可欠であるという理屈が、司法最高機関により留保なしに語られ、いささかの修正もなされず、アンシャン・レジームの遺物が今日まで残ることになった。
ところが、最近同じような政党ビラ配布事件で、審理が別々に行われ、元社会保険庁職員の堀越明男さんは逆転無罪の判決を受けた。 どうして同じ東京高裁の二つの判決で、こういう正反対の結果がでるのか。
無罪とした中山隆夫裁判長は、表現の自由には政治活動の自由も含まれると指摘したうえで、この程度の行為で行政全体の中立性に対する国民の信頼が失われる危険があるとはいえず、刑罰を科すのは憲法に反するとした。猿払事件大法廷判決に逆らって再び適用違憲論の立場から、公務員の個人の基本的人権を擁護した。しかし、中山裁判長の内心はわからないが、やはり法令違憲・全面違憲の判断をだすことはできなかった。最高裁判決の全面否定となってしまうからである。
一方、有罪の出田孝一裁判長は、最高裁猿払事件判決を金科玉条のようにあつかい、表現の自由について正面から論じないまま、機関紙の配布は政治的偏向が強い行為で「放任すると行政の中立的運営が損なわれ、党派による不当な介入や干渉を招く恐れがある」とした。
裁判官の人事評価の元締めは最高裁事務総局である。民間会社でも、自分の仕事に誇りをもち、相対的に上司から独立する人間と上司にひたすら迎合することが自己の出世の道と考える人物がいるものだ。無罪とした中山裁判長や有罪判決の出田裁判長がそれぞれ、今後どのような出世の道を歩むのか見てみたいものだ。
国家公務員法(110条1項19号)は同法第102条第1項に規定する政治的行為の制限に違反した者に対して3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することを定めている。そして、第102条第1項に規定する政治的行為は具体的には、人事院規則14-7(政治的行為)の第6項で17に及ぶ政治的行為として規定されている。
憲法は「平等で自由な個人」を第一義的原理としているが、個別の公務員は、職種・職務権限・勤務時間の内外を問わず、また行為の行われる場所のいかんを区別することなく、一律広範囲に「政治的行為」について規制を受ける。なぜこんなことになったのか。
占領軍の時代、労働運動の高揚を恐れる連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーの指示で1948年(昭和23年)、第102条第1項に「人事院規則で定める政治的行為」を禁止する旨の規定が導入され、第110条第1項第19号の罰則規定も定められた(なお、同時に労働基本権に対しても大幅な制約が加えられた。)。
公務員政治的行為規制システムは、世界標準からかけ離れた、まさに旧体制(アンシャン・レジーム)の遺物なのだ(奥平康弘「『堀越事件』東京高裁無罪判決の意味」『世界』2010・6/no.805)。
国家公務員法第102条第1項、人事院規則14-7は、一般職の国家公務員の政治活動を一律広範囲に制限していること、その政治的行為の具体的な定めを包括的に人事院規則に委任していること(その違反行為が刑事罰の対象となることから、犯罪の構成要件の委任であり、罪刑法定主義との関係でも問題となる)、またその制定が連合国軍総司令部の意向によってなされたものであることなどから、制定当初より、これを違憲とする学説が根強い。しかし、当初、最高裁判所や下級裁判所は、これらの規定を違憲と判断したことはなかった。
ところが、その後、北海道宗谷郡猿払村の郵便局に勤務する郵政事務官が、1967年(昭和42年)の衆議院議員総選挙に際し、日本社会党を支持するポスターを掲示し又は配布したという事実で起訴された事件(猿払事件)があり、旭川地裁は、国家公務員法の政治的行為の制限規定を日本国憲法第21条第1項が保障する表現の自由との関係からはじめて検討し、被告人の当該行為に適用される限度において、行為に対する制裁としては合理的にして必要最小限度の域を超えるものであり、日本国憲法第21条、第31条(適正手続の保障)に違反する、として無罪判決を出した(1968年3月25日判決)。
法令違憲・全面違憲ではないが、個別・具体的な本件に適用するのは違憲(いわゆる適用違憲論)というわけだ。
旭川地裁判決の影響は大きく、その後、全国の裁判所に係属していた同種の事件につき、下級審で同法、同規則の規定を違憲と判断するか、あるいは同法、同規則を違憲とまでは判断しないものの、公務員の政治的行為に可罰的違法性がないなどとして、無罪とする事例が続出した。このような動きを真っ向から抑えにかかったのが、1974年(昭和49年)の猿払事件最高裁大法廷判決である。
猿払事件大法廷判決は、「平等で自由な個人」の上に「国民の共同の利益」なる抽象的・情緒的概念をおき、公務員の自由制限=禁止を全面的に正当化した。こうして、公務員の一律規制がなければ、「行政の中立的運用は保てない」、したがって一律規制が不可欠であるという理屈が、司法最高機関により留保なしに語られ、いささかの修正もなされず、アンシャン・レジームの遺物が今日まで残ることになった。
ところが、最近同じような政党ビラ配布事件で、審理が別々に行われ、元社会保険庁職員の堀越明男さんは逆転無罪の判決を受けた。 どうして同じ東京高裁の二つの判決で、こういう正反対の結果がでるのか。
無罪とした中山隆夫裁判長は、表現の自由には政治活動の自由も含まれると指摘したうえで、この程度の行為で行政全体の中立性に対する国民の信頼が失われる危険があるとはいえず、刑罰を科すのは憲法に反するとした。猿払事件大法廷判決に逆らって再び適用違憲論の立場から、公務員の個人の基本的人権を擁護した。しかし、中山裁判長の内心はわからないが、やはり法令違憲・全面違憲の判断をだすことはできなかった。最高裁判決の全面否定となってしまうからである。
一方、有罪の出田孝一裁判長は、最高裁猿払事件判決を金科玉条のようにあつかい、表現の自由について正面から論じないまま、機関紙の配布は政治的偏向が強い行為で「放任すると行政の中立的運営が損なわれ、党派による不当な介入や干渉を招く恐れがある」とした。
裁判官の人事評価の元締めは最高裁事務総局である。民間会社でも、自分の仕事に誇りをもち、相対的に上司から独立する人間と上司にひたすら迎合することが自己の出世の道と考える人物がいるものだ。無罪とした中山裁判長や有罪判決の出田裁判長がそれぞれ、今後どのような出世の道を歩むのか見てみたいものだ。