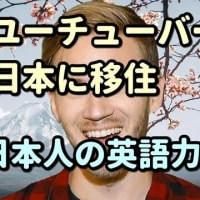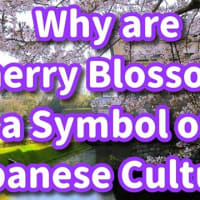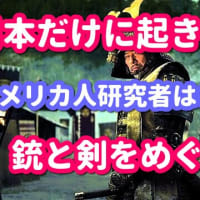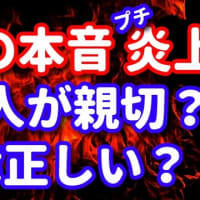◆『神話と日本人の心 』
』
この本を読んで印象深いのは、すでに日本神話の中に、その後に展開する日本文化や日本社会の特徴が色濃く現れているということであった。その一つが、「①男性原理とのバランスを取りながらの女性原理」であった。引き続きこの特徴を見ていこう。今回は、これと関係し「③文明の原始的な根から切り離されず、連続性を保っている」という特徴にも触れる。
イザナギは、死んだイザナミを追って黄泉の国へいったが、逆にイザナミに追われてこの世に逃げ帰る。イザナギは、禊(みそぎ)をして黄泉の国の穢れを払い、自ら三柱の神を産む。左目を洗った時にアマテラス、右目からはツクミヨ、鼻からはスサノオが産まれる。アマテラスとツクヨミは、父の命令のままに、それぞれ天井と夜の国を治めた。ところが、海を治めろと命じられたスサノオは、命に服さず泣き叫ぶ。
イザナギが理由を尋ねると、母に会いに根の堅洲の国に行きたいという。アマテラスが「父の娘」であるのに対し、スサノオは父から生まれたにもかかわらず「母の息子」である。イザナギは、怒ってスサノオを高天原から追放しようとする。スサノオは、それならと姉アマテラスのところへ挨拶に行くが、アマテラスはそれを自分の国を奪おうとして来たと誤解、武装して待ち構える。
スサノオは、来訪の真意を説明するが、アマテラスは信じない。つまり日本神話では、アマテラスは最高神でありながら間違いを犯すこともある神として描かれている。次の誓約の場面ではスサノオが勝つのだが、今度はスサノオが勝利に有頂天になりすぎて失敗する。つまり、日本神話では誰かが絶対的優位に立つことはできず、優位にあると思った間もなくすぐに転落する。では中心はないのかと言えば、実は何もせずにただそこにいるだけのツクヨミこそが真の中心なのである。これが前回挙げた「⑦明確なリーダー的存在なしでことが運ばれていく。中心に強力な存在があってその力で全体が統一されるのではなく、中心が空でも全体のバランスでことが運ばれるといいう『中空構造』」そのものであるが、詳しくは追って触れることになるだろう。
ところで、スサノオが勝利した誓約とは、スサノオの身の潔白を証明するため各々が子を産むという提案だった。スサノオはアマテラスの勾玉によって五柱の男神を産み、アマテラスはスサノオの剣によって三柱の女神を産んだ。アマテラスは、産まれた子はその材料の持ち主のものと判断し、スサノオは女神を産んだことを理由に潔白を宣言した。男女どちらを産んだら勝ちとあらかじめ決めていたわけではないので、女を産んだから潔癖だと宣言するのは、背景に女性優位の立場があるからだと著者はいう。
以上は古事記による物語だが、日本書紀ではこの話に多くのバリエーションがあるという。ただ日本書紀では、本文と付記されたバリエーションとのすべてで、古事記とは逆に男子を産んだことで清い心が証明されたとされている。その上で、互いの持ち物を交換し相手の所有物から子を産むという状況で、どちらをどちらの子にするかという判断が混淆する。
この日本書紀の記述に対する著者の結論は、母性原理と父性原理のどちらに優位を置くかに混乱ないし迷いがあったのだろうといことである。が、どちらかと言えば古事記は、母性原理優位でほぼ一貫しており、おそらくこれが古代日本の姿で、日本書紀は中国などへの対外的な意識から父性優位になっているが、父性原理だけで整合性を保つことにかなり難しさがあったということである。
この本で著者は、神話と歴史的な事実や背景との関係についてはほとんど全く触れていない。ユング派の心理療法家として、あくまでも神話と深層心理との関係という観点から論を深めている。著者は歴史家ではないから、それは当然の態度であろう。一方私としては、これまでのこのブログの流れからも、縄文文化と弥生文化との関係という視点から、母性原理・父性原理の問題に簡単に触れておきたい。
以前この問題については、日本文化のユニークさ34:縄文の蛇信仰(3)で論じたことがある。これをかんたんに振り返りながら進めよう。
紀元前1500年ごろから、シリア北西部で天候神バールの信仰が盛んになった。バール神は太陽の力をもち、嵐と雨の神、豊穣と多産の神でもあった。この天候神バールが、大地の女神のシンボルである蛇を殺す。シリアに残るバール神の彫刻は口ひげをはやした男神で、右手に斧を振り上げて、左手に握った蛇を殺そうとしている。
バール神は、ヘブライ人(ユダヤ人)の一部も信仰していた。やがてヤハウェのみを神とする一神教を確立するが、ヤハウェとバールはどちらも、これまでの蛇をシンボルとしする大地の豊穣の女神とは対決する性格をもつ男神であった。
日本の稲作技術は、気候の寒冷化をきっかけとして大陸からやってきた環境難民によって最初にもたらされ、弥生時代以降も、大陸から大量の人々が渡来した。こうして新たにやってきた人々は、蛇殺しの信仰をもっていた。こうした神話は、稲作と鉄器文化が結びついて伝播した可能性が高いというのが著者の推論だ。
日本神話でその蛇殺しの神話を代表するのがヤマタノオロチの伝説だ。スサノオが、オロチに酒を飲ませ、酔って寝込んだすきに、剣を抜いて一気にオロチの八つの首を切り落とする。この物語は、バール神が海竜ヤムを退治した物語によく似ている。スサノオノ命は荒れ狂う暴風の神であり、この点でもバール神を思い起こさせる。
バール神の蛇殺しもスサノオの蛇殺しも、ともに新たな武器であった鉄器の登場を物語っている。バール神がシリアで大発展した紀元前1200年頃は、鉄器の使用が広く普及した時代でもある。日本の弥生時代も鉄器が使用されはじめた頃だ。こうしてみると、蛇を殺す神々の登場の背景には、鉄器文化の誕生と拡散とが深く関わっており、殺される大蛇たちは、それ以前の文化のシンボルだったのだと著者はいう。
しかし、日本神話に関してはスサノオが大蛇を退治したから、それ以前の文化を葬り去った新時代の神だと言えるほど単純ではない。アマテラスが縄文以来の地母神を受継ぎ、スサノオが稲作と鉄器をもたらした新時代の神だとは割り切れないのが日本神話の興味深いところだ。スサノオは、女神を産んだことで身の潔白を宣言し、勝ち誇って大暴れをする。アマテラスの田の畔を壊したり、機織場の屋根を破って血だらけの馬を投げ入れ、驚いて逃げた機織女が、機織に御陰を刺して死んでしまう。
アマテラスが住まう稲作の地を破壊するのがスサノオなのだ。しかも大暴れをしたスサノオは、「根の国」に追放されてしまう。つまり男神が女神に敗北しているのだ。女神や蛇に象徴される古い文化が、鉄器をもった男神によって葬り去られるという単純な図式では整理できないのが、スサノオの物語だ。
ではどう考えればよいのか。母性原理と男性原理とのバランスが働く構造、アマテラスとスサノオのどちらが圧倒的な優位に立つわけではないという構造、そしてアマテラスは縄文時代以来の地母神を受け継ぐと見えながら一方で稲作に携わり、スサノオはアマテラスに追放されながら、大蛇を退治し新時代を代表するとも見える。
この単純に割り切れない構造をどのように理解すればよいのか。
私は、ここに日本人の原体験のひとつが反映していると考える。世界の多くの地域では農耕の広がりとともに農耕以前の文化は消えていく傾向にあった。男神による蛇殺しがそれを象徴した。おそらくそれは、古い文化を担う人々の抑圧や消滅を伴っていた。ヨーロッパでは、キリスト教が支配的になるとそれ以前のケルト文化はほとんど抹殺された。新しい文化が古い文化を完膚なきまでに葬り去ってしまうことが多いのだ。
西アジアの大草原で人類が農耕を開始したころ、東アジアの日本列島では、ブナやナラの落葉広葉樹の森で、狩猟・漁撈採集民としての生活を開始していた。日本列島の森の中は食べ物が豊富だったので、本格的な農耕を伴わない高度な新石器文化を形成し、一万年を超えて洗練することができた。そこへ大陸の人々が、稲作や鉄器を携えて渡来したとしても、一度に多人数が渡来できたわけではないから、人数の上でも縄文人を圧倒するほどの勢力にはなり得なかった。
つまり弥生人は、縄文人を一方的に追放したり、ましてや抹殺したりしたのではなく、せめぎ合いながらも、他方で和合したり協力したりして、縄文的な要素を大幅に取り入れながら最終的には溶け合っていったのである。その過程では様々な配慮や調整が必要な場面もあっただろう。異質なものを互いに受け入れ、配慮しあいながら融和していく。これが日本人の原体験になったのではないか。そして日本神話は、その原体験を反映する特質を持つに至ったのではないか。日本神話が、構造的に調和やバランスの感覚を大切にする(後に詳述)のも、この原体験に根ざしているといえよう。
以上からも、日本神話が「③文明の原始的な根から切り離されず、連続性を保っている」という特徴をもっていることも納得できるだろう。日本人の原体験は、「文明の原始的な根」を断ち切るところにあったのではなく、「原始的な根」と調和し、バランスを取り、受入れていくところにあったのだ。それは、「文明の原始的な根」に生き続ける母性原理を受け入れることでもあった。同時に、父性原理的な行為によって根を断ち切るのではなく、母性原理的な行為によってそれそれを受け入れることでもあった。
《関連記事》
日本文化のユニークさ27:なぜ縄文文化は消えなかった?
日本文化のユニークさ28:縄文人は稲作を選んだ
日本文化のユニークさ29:母性原理の意味
日本文化のユニークさ30:縄文人と森の恵み
日本文化のユニークさ31:平等社会の基盤
日本文化のユニークさ32:縄文の蛇信仰(1)
日本文化のユニークさ33:縄文の蛇信仰(2)
日本文化のユニークさ34:縄文の蛇信仰(3)
日本文化のユニークさ35:寄生文明と共生文明(1)
日本文化のユニークさ36:母性原理と父性原理
《関連図書》
☆文明の環境史観 (中公叢書)
☆対論 文明の原理を問う
☆一神教の闇―アニミズムの復権 (ちくま新書)
☆環境と文明の世界史―人類史20万年の興亡を環境史から学ぶ (新書y)
☆環境考古学事始―日本列島2万年の自然環境史 (洋泉社MC新書)
☆蛇と十字架
この本を読んで印象深いのは、すでに日本神話の中に、その後に展開する日本文化や日本社会の特徴が色濃く現れているということであった。その一つが、「①男性原理とのバランスを取りながらの女性原理」であった。引き続きこの特徴を見ていこう。今回は、これと関係し「③文明の原始的な根から切り離されず、連続性を保っている」という特徴にも触れる。
イザナギは、死んだイザナミを追って黄泉の国へいったが、逆にイザナミに追われてこの世に逃げ帰る。イザナギは、禊(みそぎ)をして黄泉の国の穢れを払い、自ら三柱の神を産む。左目を洗った時にアマテラス、右目からはツクミヨ、鼻からはスサノオが産まれる。アマテラスとツクヨミは、父の命令のままに、それぞれ天井と夜の国を治めた。ところが、海を治めろと命じられたスサノオは、命に服さず泣き叫ぶ。
イザナギが理由を尋ねると、母に会いに根の堅洲の国に行きたいという。アマテラスが「父の娘」であるのに対し、スサノオは父から生まれたにもかかわらず「母の息子」である。イザナギは、怒ってスサノオを高天原から追放しようとする。スサノオは、それならと姉アマテラスのところへ挨拶に行くが、アマテラスはそれを自分の国を奪おうとして来たと誤解、武装して待ち構える。
スサノオは、来訪の真意を説明するが、アマテラスは信じない。つまり日本神話では、アマテラスは最高神でありながら間違いを犯すこともある神として描かれている。次の誓約の場面ではスサノオが勝つのだが、今度はスサノオが勝利に有頂天になりすぎて失敗する。つまり、日本神話では誰かが絶対的優位に立つことはできず、優位にあると思った間もなくすぐに転落する。では中心はないのかと言えば、実は何もせずにただそこにいるだけのツクヨミこそが真の中心なのである。これが前回挙げた「⑦明確なリーダー的存在なしでことが運ばれていく。中心に強力な存在があってその力で全体が統一されるのではなく、中心が空でも全体のバランスでことが運ばれるといいう『中空構造』」そのものであるが、詳しくは追って触れることになるだろう。
ところで、スサノオが勝利した誓約とは、スサノオの身の潔白を証明するため各々が子を産むという提案だった。スサノオはアマテラスの勾玉によって五柱の男神を産み、アマテラスはスサノオの剣によって三柱の女神を産んだ。アマテラスは、産まれた子はその材料の持ち主のものと判断し、スサノオは女神を産んだことを理由に潔白を宣言した。男女どちらを産んだら勝ちとあらかじめ決めていたわけではないので、女を産んだから潔癖だと宣言するのは、背景に女性優位の立場があるからだと著者はいう。
以上は古事記による物語だが、日本書紀ではこの話に多くのバリエーションがあるという。ただ日本書紀では、本文と付記されたバリエーションとのすべてで、古事記とは逆に男子を産んだことで清い心が証明されたとされている。その上で、互いの持ち物を交換し相手の所有物から子を産むという状況で、どちらをどちらの子にするかという判断が混淆する。
この日本書紀の記述に対する著者の結論は、母性原理と父性原理のどちらに優位を置くかに混乱ないし迷いがあったのだろうといことである。が、どちらかと言えば古事記は、母性原理優位でほぼ一貫しており、おそらくこれが古代日本の姿で、日本書紀は中国などへの対外的な意識から父性優位になっているが、父性原理だけで整合性を保つことにかなり難しさがあったということである。
この本で著者は、神話と歴史的な事実や背景との関係についてはほとんど全く触れていない。ユング派の心理療法家として、あくまでも神話と深層心理との関係という観点から論を深めている。著者は歴史家ではないから、それは当然の態度であろう。一方私としては、これまでのこのブログの流れからも、縄文文化と弥生文化との関係という視点から、母性原理・父性原理の問題に簡単に触れておきたい。
以前この問題については、日本文化のユニークさ34:縄文の蛇信仰(3)で論じたことがある。これをかんたんに振り返りながら進めよう。
紀元前1500年ごろから、シリア北西部で天候神バールの信仰が盛んになった。バール神は太陽の力をもち、嵐と雨の神、豊穣と多産の神でもあった。この天候神バールが、大地の女神のシンボルである蛇を殺す。シリアに残るバール神の彫刻は口ひげをはやした男神で、右手に斧を振り上げて、左手に握った蛇を殺そうとしている。
バール神は、ヘブライ人(ユダヤ人)の一部も信仰していた。やがてヤハウェのみを神とする一神教を確立するが、ヤハウェとバールはどちらも、これまでの蛇をシンボルとしする大地の豊穣の女神とは対決する性格をもつ男神であった。
日本の稲作技術は、気候の寒冷化をきっかけとして大陸からやってきた環境難民によって最初にもたらされ、弥生時代以降も、大陸から大量の人々が渡来した。こうして新たにやってきた人々は、蛇殺しの信仰をもっていた。こうした神話は、稲作と鉄器文化が結びついて伝播した可能性が高いというのが著者の推論だ。
日本神話でその蛇殺しの神話を代表するのがヤマタノオロチの伝説だ。スサノオが、オロチに酒を飲ませ、酔って寝込んだすきに、剣を抜いて一気にオロチの八つの首を切り落とする。この物語は、バール神が海竜ヤムを退治した物語によく似ている。スサノオノ命は荒れ狂う暴風の神であり、この点でもバール神を思い起こさせる。
バール神の蛇殺しもスサノオの蛇殺しも、ともに新たな武器であった鉄器の登場を物語っている。バール神がシリアで大発展した紀元前1200年頃は、鉄器の使用が広く普及した時代でもある。日本の弥生時代も鉄器が使用されはじめた頃だ。こうしてみると、蛇を殺す神々の登場の背景には、鉄器文化の誕生と拡散とが深く関わっており、殺される大蛇たちは、それ以前の文化のシンボルだったのだと著者はいう。
しかし、日本神話に関してはスサノオが大蛇を退治したから、それ以前の文化を葬り去った新時代の神だと言えるほど単純ではない。アマテラスが縄文以来の地母神を受継ぎ、スサノオが稲作と鉄器をもたらした新時代の神だとは割り切れないのが日本神話の興味深いところだ。スサノオは、女神を産んだことで身の潔白を宣言し、勝ち誇って大暴れをする。アマテラスの田の畔を壊したり、機織場の屋根を破って血だらけの馬を投げ入れ、驚いて逃げた機織女が、機織に御陰を刺して死んでしまう。
アマテラスが住まう稲作の地を破壊するのがスサノオなのだ。しかも大暴れをしたスサノオは、「根の国」に追放されてしまう。つまり男神が女神に敗北しているのだ。女神や蛇に象徴される古い文化が、鉄器をもった男神によって葬り去られるという単純な図式では整理できないのが、スサノオの物語だ。
ではどう考えればよいのか。母性原理と男性原理とのバランスが働く構造、アマテラスとスサノオのどちらが圧倒的な優位に立つわけではないという構造、そしてアマテラスは縄文時代以来の地母神を受け継ぐと見えながら一方で稲作に携わり、スサノオはアマテラスに追放されながら、大蛇を退治し新時代を代表するとも見える。
この単純に割り切れない構造をどのように理解すればよいのか。
私は、ここに日本人の原体験のひとつが反映していると考える。世界の多くの地域では農耕の広がりとともに農耕以前の文化は消えていく傾向にあった。男神による蛇殺しがそれを象徴した。おそらくそれは、古い文化を担う人々の抑圧や消滅を伴っていた。ヨーロッパでは、キリスト教が支配的になるとそれ以前のケルト文化はほとんど抹殺された。新しい文化が古い文化を完膚なきまでに葬り去ってしまうことが多いのだ。
西アジアの大草原で人類が農耕を開始したころ、東アジアの日本列島では、ブナやナラの落葉広葉樹の森で、狩猟・漁撈採集民としての生活を開始していた。日本列島の森の中は食べ物が豊富だったので、本格的な農耕を伴わない高度な新石器文化を形成し、一万年を超えて洗練することができた。そこへ大陸の人々が、稲作や鉄器を携えて渡来したとしても、一度に多人数が渡来できたわけではないから、人数の上でも縄文人を圧倒するほどの勢力にはなり得なかった。
つまり弥生人は、縄文人を一方的に追放したり、ましてや抹殺したりしたのではなく、せめぎ合いながらも、他方で和合したり協力したりして、縄文的な要素を大幅に取り入れながら最終的には溶け合っていったのである。その過程では様々な配慮や調整が必要な場面もあっただろう。異質なものを互いに受け入れ、配慮しあいながら融和していく。これが日本人の原体験になったのではないか。そして日本神話は、その原体験を反映する特質を持つに至ったのではないか。日本神話が、構造的に調和やバランスの感覚を大切にする(後に詳述)のも、この原体験に根ざしているといえよう。
以上からも、日本神話が「③文明の原始的な根から切り離されず、連続性を保っている」という特徴をもっていることも納得できるだろう。日本人の原体験は、「文明の原始的な根」を断ち切るところにあったのではなく、「原始的な根」と調和し、バランスを取り、受入れていくところにあったのだ。それは、「文明の原始的な根」に生き続ける母性原理を受け入れることでもあった。同時に、父性原理的な行為によって根を断ち切るのではなく、母性原理的な行為によってそれそれを受け入れることでもあった。
《関連記事》
日本文化のユニークさ27:なぜ縄文文化は消えなかった?
日本文化のユニークさ28:縄文人は稲作を選んだ
日本文化のユニークさ29:母性原理の意味
日本文化のユニークさ30:縄文人と森の恵み
日本文化のユニークさ31:平等社会の基盤
日本文化のユニークさ32:縄文の蛇信仰(1)
日本文化のユニークさ33:縄文の蛇信仰(2)
日本文化のユニークさ34:縄文の蛇信仰(3)
日本文化のユニークさ35:寄生文明と共生文明(1)
日本文化のユニークさ36:母性原理と父性原理
《関連図書》
☆文明の環境史観 (中公叢書)
☆対論 文明の原理を問う
☆一神教の闇―アニミズムの復権 (ちくま新書)
☆環境と文明の世界史―人類史20万年の興亡を環境史から学ぶ (新書y)
☆環境考古学事始―日本列島2万年の自然環境史 (洋泉社MC新書)
☆蛇と十字架