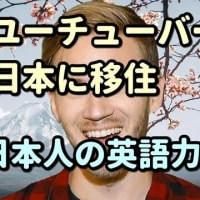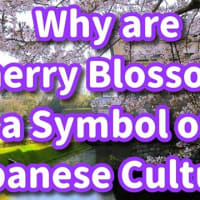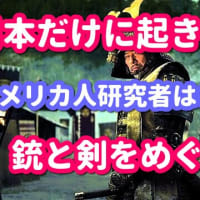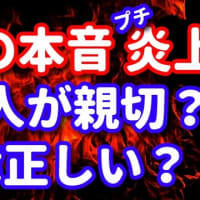今回は、日本文化のユニークさ5項目のうち(2)、(3)、(4)についてさらに追及していきたい。そのさい参考にするのは、『森から生まれた日本の文明―共生の日本文明と寄生の中国文明 (アマゾン文庫) 』と『奇跡の日本史―「花づな列島」の恵みを言祝ぐ
』と『奇跡の日本史―「花づな列島」の恵みを言祝ぐ 』である。
』である。
(2)ユーラシアの穀物・牧畜文化にたいして、日本は穀物・魚貝型とで言うべき文化を形成し、それが大陸とは違うユニークさを生み出した。
(3)大陸から海で適度に隔てられた日本は、異民族(とくに遊牧民族)による侵略、強奪、虐殺な体験をもたず、また自文化が抹殺されることもたなかった。一方、地震・津波・台風などの自然災害は何度も繰り返され、それが日本人独特の自然観・人間観を作った。
(4)宗教などのイデオロギーによる社会と文化の一元的な支配がほとんどなかった。
『森から生まれた日本の文明』では、ユーラシア大陸の文明を「寄生文明」と呼び、日本の文明を「共生文明」と呼ぶ。「寄生」という言葉自体は、かなり批判的なニュアンスが強く、刺激的だが、要するに自然に「寄生」するという意味だ。
乾燥した大草原を舞台とした麦栽培、羊や山羊などの家畜を飼育する草原農耕文明は、早くから階級分化と支配がはじまり、都市文明が生まれた、人間中心の文化は、森林を破壊しながら自然に寄生する文明として成熟していく。
森林を破壊した文明は、メソポタミア文明に端を発し、地中海地域からヨーロッパ、アジア、アフリカ、アメリカやオーストラリアにまで拡散したという。黄土高原で生まれた黄河文明もまた、一方的な略奪と地力の搾取によって、その文明を支えた母なる大地を荒廃させ、森林を食いつぶした。
草原の資源が枯渇すると森に依存し、森が枯れれば森を捨てる。この人間中心の自然征服型文明は、わずか1万年あまりの間に地球を支配してしまった。
一方、日本列島は周囲を海に囲まれていることもあり、大陸の諸勢力が侵入することもなく、縄文時代から弥生時代にかけて、森林と共存しながら稲作が成立した。日本では、水田耕作社会を維持するためには、背後の山や丘陵の森林が不可欠とされた。これこそが、森林・自然との「共生」を維持しつづけた日本の複合農業文化であった。
日本文化の基層には、縄文時代以来の森の文化の伝統が流れている。弥生文化がはじまったとき、日本は稲作を受け入れたが、羊や山羊などの肉食用の家畜は受け入れなかった。その理由の一つは、日本の稲作が、羊や山羊などの家畜を持たない長江流域から伝播したからだという。もう一つの理由は、森の文化にとって家畜は天敵であり、それを知っていた縄文人が、家畜の受け入れを拒んだ可能性だ。
家畜は、森の若芽や樹皮を食べつくして森を破壊する。家畜を伴わない稲作文明だったからこそ、日本は豊かな森を維持することができた。また、肉食用の家畜を伴わなかったからこそ、ユーラシア大陸とは違って、人間と他の生物を厳然と区別しないユニークな人間観・生命観を維持することができた。
(2)ユーラシアの穀物・牧畜文化にたいして、日本は穀物・魚貝型とで言うべき文化を形成し、それが大陸とは違うユニークさを生み出した。
(3)大陸から海で適度に隔てられた日本は、異民族(とくに遊牧民族)による侵略、強奪、虐殺な体験をもたず、また自文化が抹殺されることもたなかった。一方、地震・津波・台風などの自然災害は何度も繰り返され、それが日本人独特の自然観・人間観を作った。
(4)宗教などのイデオロギーによる社会と文化の一元的な支配がほとんどなかった。
『森から生まれた日本の文明』では、ユーラシア大陸の文明を「寄生文明」と呼び、日本の文明を「共生文明」と呼ぶ。「寄生」という言葉自体は、かなり批判的なニュアンスが強く、刺激的だが、要するに自然に「寄生」するという意味だ。
乾燥した大草原を舞台とした麦栽培、羊や山羊などの家畜を飼育する草原農耕文明は、早くから階級分化と支配がはじまり、都市文明が生まれた、人間中心の文化は、森林を破壊しながら自然に寄生する文明として成熟していく。
森林を破壊した文明は、メソポタミア文明に端を発し、地中海地域からヨーロッパ、アジア、アフリカ、アメリカやオーストラリアにまで拡散したという。黄土高原で生まれた黄河文明もまた、一方的な略奪と地力の搾取によって、その文明を支えた母なる大地を荒廃させ、森林を食いつぶした。
草原の資源が枯渇すると森に依存し、森が枯れれば森を捨てる。この人間中心の自然征服型文明は、わずか1万年あまりの間に地球を支配してしまった。
一方、日本列島は周囲を海に囲まれていることもあり、大陸の諸勢力が侵入することもなく、縄文時代から弥生時代にかけて、森林と共存しながら稲作が成立した。日本では、水田耕作社会を維持するためには、背後の山や丘陵の森林が不可欠とされた。これこそが、森林・自然との「共生」を維持しつづけた日本の複合農業文化であった。
日本文化の基層には、縄文時代以来の森の文化の伝統が流れている。弥生文化がはじまったとき、日本は稲作を受け入れたが、羊や山羊などの肉食用の家畜は受け入れなかった。その理由の一つは、日本の稲作が、羊や山羊などの家畜を持たない長江流域から伝播したからだという。もう一つの理由は、森の文化にとって家畜は天敵であり、それを知っていた縄文人が、家畜の受け入れを拒んだ可能性だ。
家畜は、森の若芽や樹皮を食べつくして森を破壊する。家畜を伴わない稲作文明だったからこそ、日本は豊かな森を維持することができた。また、肉食用の家畜を伴わなかったからこそ、ユーラシア大陸とは違って、人間と他の生物を厳然と区別しないユニークな人間観・生命観を維持することができた。