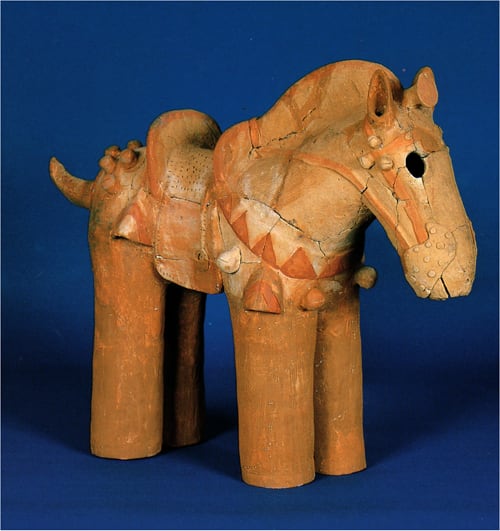飛び散る火花に走る湯玉ぁ~~
というわけで、某所で刀づくり体験をしてきましたぁ!!
まずは細長い板状の鉄棒を叩いて伸ばし、先を尖らせていきます。

手動式のふいごを左で操作しながら、右手で鉄の棒を炉の中に突っ込みます。
鉄が赤くなったら(といっても、それは火の中なので見えません)引き出して、
叩いて鍛えます。その温度はおよそ900~1000℃ほどにもなるといいます。
叩いてのばして、叩いて整えて、叩いて尖らせて、の繰り返しですが
そう上手くは行きません。曲がったり、うすくならなかったり、デコボコだったり・・・
ちなみに、途中で水を打ちながら鍛えると、鉄の表面にできた酸化鉄の
皮膜がはがれて奇麗になり、仕上げがらくになります。その水を打つときに
焼けた鉄の上を水が玉になって転がる様子が「走る湯玉」だそうです。
結局、大まかな形をつくったら、あとはヤスリでけずって形を整え、
ある程度刃のほうを薄くします。ま、小刀一本と言えど2時間程度では
到底作り上げられませんので、そこんとこはご愛嬌。
以上が私が体験した刀づくりです。ここから先は素人ではむりなので
講師の方々が少しずつやっていくそうです。
なので、ここからは刀匠のデモを見ました。
その後、焼き入れから研ぎ出しとなります。で、今回のお話のメインはここから。
日本刀は極めて鋭利な刃物です。しかも、鋼自体に適度な粘りと堅さを併せ持った
希有な刀なのです。刃物は堅くすればするほど切れるようになりますが、
粘りが無いと欠けやすくなります。両者は相反する性質なのです。
そして、その相反する性質を併せ持った刀を可能にするのが
粘土を使った焼き入れの技術なのです。
まず、粘土です。まるでごますり団子のごま餡のような黒くてつややかな粘土。
これは粘土と炭粉と砥石の粉を配合したものだそうです。

おいしそうですね!
それを、竹のヘラで刀に盛っていきます。

一見、無造作に見えますが実はこののせかたも出来不出来を決める重要なポイントです。
というのは、

はい、わかりますでしょうか。粘土は刃先のほうが薄く峰のほうが厚く盛られています。
焼き入れとは加熱した鉄を急激に冷やして硬度を増す技法です。ゆっくり冷やすと軟鉄となり
粘りが出ます。つまり、冷却速度の違いで堅くなったり軟らかくなったりするのです。
ということは、同じように加熱した状態でも、水につけて冷却したときに、
粘土の薄い部分は早く冷え、粘土の厚い部分は冷えるのにそれよりも時間がかかる、というわけです。
それによって、刀身の部分には粘りを持ち、刃先の部分は切れ味鋭い刀が出来るわけです。
その厚さとあんばいは、経験なのでしょう。

粘土をぬった刀をもう一度炉で加熱します。これも真っ赤になるまでです。
炉から引き出した瞬間には粘土も真っ赤になっており、非常に奇麗です。
ちなみに、刀の切れ味はこの焼き入れにかかっているのですが、
その温度は非常に微妙で、長年の経験と勘に頼って具合を見ながら
温度を微調整していました。
実際には夜になって暗いところで、加熱された刀の発光の具合で判断するのため、
昼間はやりたくないのだそうで、今回は体験学習のため特別の実演だそうです。

さて、冷却の速度が切れ味を決めるため、本当は刀をつける水の温度も
重要なのだという話を聞いたことがあります。弟子がその水に手をいれて
温度を測ったところが、その場で師匠にその腕を切り落とされたという話を
何かで読んだ覚えがあります。

そして、研ぎだしです。時間がなかったので大まかに研ぎをかけて、
実際には刃をつけるところまでは行きませんでしたが、それでも

切れそうじゃぁありませんか。焼きの入った部分と入らなかった部分の境にできる
刃紋を「におい」といって、これも鑑賞のポイントです。
私の打った小刀もこうなるのかしら??
ちなみにこの日使った鉄は、以前たたらで作ったものだそうです。
というわけで、某所で刀づくり体験をしてきましたぁ!!
まずは細長い板状の鉄棒を叩いて伸ばし、先を尖らせていきます。

手動式のふいごを左で操作しながら、右手で鉄の棒を炉の中に突っ込みます。
鉄が赤くなったら(といっても、それは火の中なので見えません)引き出して、
叩いて鍛えます。その温度はおよそ900~1000℃ほどにもなるといいます。
叩いてのばして、叩いて整えて、叩いて尖らせて、の繰り返しですが
そう上手くは行きません。曲がったり、うすくならなかったり、デコボコだったり・・・
ちなみに、途中で水を打ちながら鍛えると、鉄の表面にできた酸化鉄の
皮膜がはがれて奇麗になり、仕上げがらくになります。その水を打つときに
焼けた鉄の上を水が玉になって転がる様子が「走る湯玉」だそうです。
結局、大まかな形をつくったら、あとはヤスリでけずって形を整え、
ある程度刃のほうを薄くします。ま、小刀一本と言えど2時間程度では
到底作り上げられませんので、そこんとこはご愛嬌。
以上が私が体験した刀づくりです。ここから先は素人ではむりなので
講師の方々が少しずつやっていくそうです。
なので、ここからは刀匠のデモを見ました。
その後、焼き入れから研ぎ出しとなります。で、今回のお話のメインはここから。
日本刀は極めて鋭利な刃物です。しかも、鋼自体に適度な粘りと堅さを併せ持った
希有な刀なのです。刃物は堅くすればするほど切れるようになりますが、
粘りが無いと欠けやすくなります。両者は相反する性質なのです。
そして、その相反する性質を併せ持った刀を可能にするのが
粘土を使った焼き入れの技術なのです。
まず、粘土です。まるでごますり団子のごま餡のような黒くてつややかな粘土。
これは粘土と炭粉と砥石の粉を配合したものだそうです。

おいしそうですね!
それを、竹のヘラで刀に盛っていきます。

一見、無造作に見えますが実はこののせかたも出来不出来を決める重要なポイントです。
というのは、

はい、わかりますでしょうか。粘土は刃先のほうが薄く峰のほうが厚く盛られています。
焼き入れとは加熱した鉄を急激に冷やして硬度を増す技法です。ゆっくり冷やすと軟鉄となり
粘りが出ます。つまり、冷却速度の違いで堅くなったり軟らかくなったりするのです。
ということは、同じように加熱した状態でも、水につけて冷却したときに、
粘土の薄い部分は早く冷え、粘土の厚い部分は冷えるのにそれよりも時間がかかる、というわけです。
それによって、刀身の部分には粘りを持ち、刃先の部分は切れ味鋭い刀が出来るわけです。
その厚さとあんばいは、経験なのでしょう。

粘土をぬった刀をもう一度炉で加熱します。これも真っ赤になるまでです。
炉から引き出した瞬間には粘土も真っ赤になっており、非常に奇麗です。
ちなみに、刀の切れ味はこの焼き入れにかかっているのですが、
その温度は非常に微妙で、長年の経験と勘に頼って具合を見ながら
温度を微調整していました。
実際には夜になって暗いところで、加熱された刀の発光の具合で判断するのため、
昼間はやりたくないのだそうで、今回は体験学習のため特別の実演だそうです。

さて、冷却の速度が切れ味を決めるため、本当は刀をつける水の温度も
重要なのだという話を聞いたことがあります。弟子がその水に手をいれて
温度を測ったところが、その場で師匠にその腕を切り落とされたという話を
何かで読んだ覚えがあります。

そして、研ぎだしです。時間がなかったので大まかに研ぎをかけて、
実際には刃をつけるところまでは行きませんでしたが、それでも

切れそうじゃぁありませんか。焼きの入った部分と入らなかった部分の境にできる
刃紋を「におい」といって、これも鑑賞のポイントです。
私の打った小刀もこうなるのかしら??
ちなみにこの日使った鉄は、以前たたらで作ったものだそうです。