
引き続き、関裕二氏の「謎の出雲・伽耶王朝」のご紹介を続けます。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
倭=和=日本という観念を外さないと、意味がわからない文章です。
外してみると、また別の世界が現れるように思い、ご紹介したく思います。
*****
(引用ここから)
「伽耶」が小国家連合のまま6世紀まで続いた最大の理由は、彼らの発想がきわめて商人的であったところではないだろうか?
他国との交流・交易によって生き残ろうとするコスモポリタン国家としての「伽耶」は、広い視野と自由な気風で、小国家連合の形を選んだのではあるまいか?
国境の概念がまだ薄かったこの当時、日本と朝鮮半島をめぐる交流は、交易を主体に行われた。
支配・被支配の関係ではなく、共存共栄の道だったということになる。
それでは、もし「伽耶」が日本を半島の死闘に引きずり込んだとしたら、いかなる手段を用い、なぜ日本がこれに乗ったのか?
もともと「伽耶人」と「日本人」は、同じ民族であった可能性が高い。
一般的に朝鮮半島南部と九州北部は、きわめて似通った文化を共有していたとされる。
日本海をはさみ、「伽耶」と九州北部は、一つの文化圏を形成していたと考えられている。
そして文化と共に、「伽耶人」も大挙して移住したということになる。
「日本書紀」の証言に触れよう。
人生の大半を朝鮮半島問題に費やし、滅亡寸前の「伽耶」と密接に関わった欽明天皇は、その死の床で、皇太子の手を取って、次のように懇願したという。
「新羅を討ち、任那(伽耶)を復興しろ。再び任那と〝夫婦″の関係になって旧日のようになれば、死んでも恨むことはない」。
「伽耶」の衰弱に対し、国運を賭して救援しようとした欽明天皇。
一体、彼を突き動かしたのは何だったのか?
「日本書紀」の立場からすれば、「任那(伽耶)」は被支配者であり、その関係は親子・兄弟にたとえてもよかった。
ところが欽明天皇に語らせた言葉は、「夫婦」だったのである。
つまり、〝夫婦″こそ、日本と「伽耶」の本来の関係だったということになる。
日本と「伽耶」を構成する民族の元を辿ってゆくと、どうやら同じ根っこに行きつく。
それが「倭人」だ。
「倭人」といえば、古代日本人を指していると思われがちだが、これとは別に、朝鮮半島南部にも「倭人」が存在していたのである。
たとえば、馬韓(後の百済)の位置について、「後漢書」は、
「その北は楽浪と、南は「倭」に接し、辰韓は東にあり」とし、
また「三国志」には、「南は倭と接する」とある。
また弁韓の地の「伽耶」も同様で、「後漢書」には、
「その南また倭と接す」とあり、「三国志」は「倭と境を接す」と記している。
つまり、朝鮮半島に在った「倭」は、馬韓と「伽耶」の南方に位置する、地続きの国であったらしい。
それだけではない。
「「三国史記」・新羅本紀」のなかに、西暦193年のこととして、
「倭人大いに飢える。来りて、食を求むる者、千人余りなり」。
という記述があり、この時、「倭国」に飢饉が起き、新羅に千人余りの飢えた人々がやってきて、食料を求めたという。
なぜ朝鮮半島に「倭人」が住んでいたのか?
そしてこの「倭人」は、いわゆる日本人の祖先、祖国の住民と同じ民族だったのであろうか?
日本人の血の中に、大きく分けて、2つの種が交わっていることが明らかになっている。
古いモンゴロイドと、新しいモンゴロイドである。
狩猟採集民族・縄文人と稲作民族・弥生人ということになる。
今から二千数百年前、稲作技術を携えた弥生人たちは、九州北部へ上陸した。
彼らは高身長・長顔型の渡来者と、低身長・低顔型の、二つに分けられるという。
前者は北アジア系であり、彼らが朝鮮半島から来たことは間違いないとされる。
一方、後者は、中国江南地方の出身ではないかとされている。
現在稲作伝来のルートとして、最も有力視されているのは、揚子江・わい河地域から、朝鮮半島南部を経由して、九州北部へ伝来したルート。
揚子江河口から九州北部に直接伝到来したルート。
そして江南地域から琉球列島を経由してきたルート。
とするのが今日の一般的な見方である。
そして大量の人たちが、稲作技術と共にやってきた。
この稲作民たちが「倭人」だったらしい。
中国大陸に「倭人」が存在したことは、文献の記述から明らかである。
「周時 天下泰平にして 越襟、白雉を献じ、倭人 ちょうを貢す。
長層は倭より献ず。倭人 ちょうを貢す」。
これらの記事は紀元前1000年頃のことであるため、日本はまだ縄文時代で、「倭人」が日本にはいなかった時のことである。
したがって、中国大陸のどこかに「倭人」はいたらしい。
そしてこの「倭人」が、どうも日本人の祖先らしいのである。
稲作民族「倭人」らが、中国大陸南部の海岸地帯から、日本、あるいは朝鮮半島南部に渡来し、弥生人の祖となったと考え、この集団を「倭族」として捉え直したのは、鳥越憲三郎氏である。
では「越人」あるいは「倭人」と、日本の「倭人」の間に、共通点を見出すことは可能であろうか?
まず、最も重要なことは、彼らがどちらも稲作民族だったということにある。
そしていわゆるジャポニカ米が揚子江周辺からやって来たとされることは、越人(倭人)と日本の「倭人」の接点といっても過言ではない。
さらに「魏志倭人伝」の、邪馬台国に関する記事に描かれた「倭人」と、「越人」の風俗と文化は、瓜二つと言ってもよいほどよく似ている。
稲作民族・弥生人の祖先は、呉から大量に流れこんだ亡命人らしい。
このことは、「徐福」が大挙して蓬莱山を求めて日本へやって来た、という伝承を彷彿とさせる。
日本は大陸南部の人々にとって、漢民族の圧迫あるいは周辺諸国の迫害から逃れるための最後の楽園だった可能性があるのだ。
日本の歴史を大きく左右した地理的条件は、島国であるとともに、黒潮の行き着く先であったことではあるまいか?
稲作民族であると同時に、優れた海洋民族でもあった「倭人」は、大陸から逃れる手段として、舟を選んだ。
そして黒潮に乗れば自然に辿り着く場所が、日本列島と朝鮮半島だったのである。
「伽耶」諸国は、「倭人」に最も近い部類に入ったであろうが、その中でも騎馬民族化してゆく人々、韓人化してゆく人々があれば、また一方で、稲作・海洋民族としての「倭人」の風俗を守った人々があったと考えられる。
このように、「伽耶人」は、「倭族」の末裔の意識を持ち、日本海をはさんで、日本の「倭人」との間に交流を続けたであろう。
しかしその一方で、彼らが多彩な民族文化の集合体であったことも事実だ。
そしてこのことが、「伽耶」の懐の深さを感じさせるのである。
なぜ「伽耶」は「任那」という名で語られたのか?
朝鮮半島南部に渡来した「倭人」は、韓族と混血を繰り返し、やがて「伽耶」を建国した。
また日本の九州に渡来した「倭人」は東進し、大和に王権を打ち立てる。
大和朝廷の誕生だ。
これが天皇家の祖であり、大陸側はこれを「倭人」の国家=「倭国」と呼んだのである。
大和朝廷にとって「伽耶諸国」は、単なる隣国ではなかったはずだ。
「倭族」が呉から亡命し、流民と化して以来の同族として、強い連帯感を持っていたことは間違いない。
だからこそ大和朝廷は、「伽耶」をめぐる半島の紛争に、積極的に参加してゆくことになるのである。
また6世紀、大和朝廷は「伽耶」滅亡に際し、これを阻止すべく必死の努力を試みた。
そしてこれが失敗すると、欽明天皇は恨みを残して世を去った。
大和朝廷がこれほど「伽耶」に固執したのも、「倭国」と「伽耶」の歴史の歴史背景を考えれば、自然のなりゆきだったと考えることができる。
ところが「倭人」王国・「大和」が記した「日本書紀」の中で、「伽耶」は名を「任那」とされた上に、まるで「倭国」の属国であるかのような扱いを受けてしまった。
この大和朝廷の不可解な態度は、一体何が原因だったのであろうか?
また「出雲の国の造(みやつこ)の神賀詞(かむよごと)」の中で、出雲系を代表する4人の神の中に、歴史から抹殺された「カヤナルミ」なる女神が選ばれている。
神話の世界で、天皇家の祖神と敵対していたはずの出雲の神の一人に、なぜ「伽耶」の名を冠した女神がいるのか?
そしてこの女神の存在を、なぜ「日本書紀」「古事記」は抹殺しなければならなかったのか?
結論を言おう。
縄文人は、「倭人」(弥生人)の圧力から身を護るために、「伽耶」の一部と手を組み、7世紀後半に至るまで、一大勢力として存在し続けたのである。
日本を二分する「東国勢力・縄文人系」と「西国勢力・倭・弥生人系)、さらに「伽耶」を組み入れたトライアングルが、大和朝廷を成立させたのであり、このバランスが崩れた時、「伽耶」本国は滅亡に向かったのである。
そしてこのバランスを崩す原因が、天皇家自身であった。
また、東国・縄文人を代表する王朝が、「日本書紀」に言うところの「出雲王朝」であったのである。
そこで「日本書紀」は、「出雲王朝」を神話の世界に閉じ込め、実像を抹殺するだけではなく、出雲と「伽耶」の親密ぶりを抹殺した上で、「伽耶」が「倭国」の属国であったことにしなければならなくなった。
(引用ここまで)
*****
出雲の国譲りという話は、なんとなくのどかで明るみをおびた神話という印象がありますが、スサノオが朝鮮半島からやってきたと「日本書紀」にはっきり書いてあるのですから、国境がなかった古代アジアの世界を、ゆったりとした気持ちで眺めることは、むしろ必要なことであろうと思えます。
 ブログ内関連記事
ブログ内関連記事
「米は麦より歴史が長い・・梅原猛氏の「長江文明の探求」(1)」(5)まであり
「ニニギノミコトは中国からやってきた?・・「長江文明の探求」(5)」
「出雲の謎は日本の謎・・関裕二氏の「消された王権・物部氏の謎」の推理」
「応神天皇の正体(1)・・海の女神・神功皇后」(5)まであり
「梅原猛の「古代出雲王朝のなぞを解く(1)・・アマテラスとスサノオという光と影」(4)まであり
「白=新羅・・荒俣宏氏の〝白いサルタヒコ論(3)」
「牛殺しの風習と、牛の王・・新羅と日本人(2)」
「朝鮮と古代日本(1)・・済州島をめぐる考察」(6)まであり
「新羅と日本(1)・・スサノオノミコトはどこから来たのか?」(5)まであり
「北陸の白山信仰(1)・・菊理(きくり)ひめとは だれなのか?」(4)まであり
「新羅と日本(5)・・アメノヒボコと、角がある人(ツヌガアラシト)の渡来」
 「アジア」カテゴリー全般
「アジア」カテゴリー全般 「日本の不思議」カテゴリー全般
「日本の不思議」カテゴリー全般











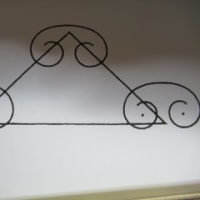


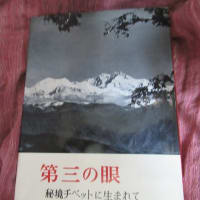







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます